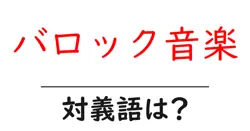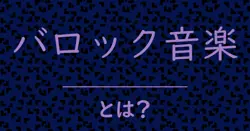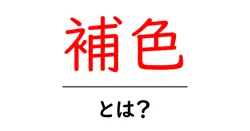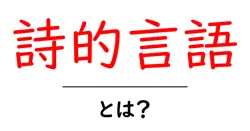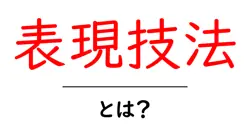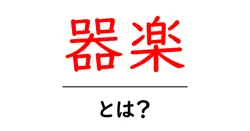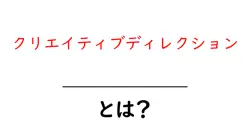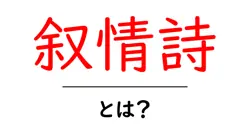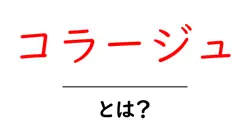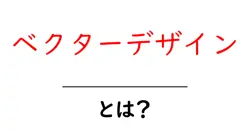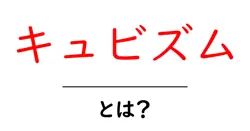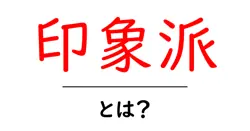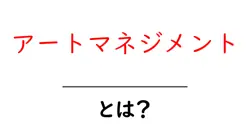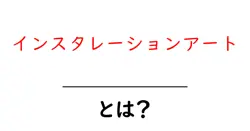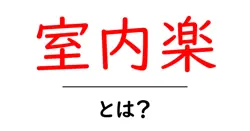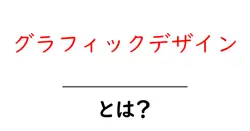バロック音楽とは?
バロック音楽は、16世紀から18世紀初頭にかけてヨーロッパで発展した音楽のスタイルです。この時期には、いくつかの特有の特徴があり、私たちが今聴くクラシック音楽の基盤となりました。
バロック音楽の特徴
バロック音楽にはいくつかの重要な特徴があります。以下の表に主なポイントをまとめました。
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 対位法 | 異なる旋律が同時に進行する技法です。 |
| 装飾音 | メロディに装飾を加えることが一般的でした。 |
| ダイナミクスの変化 | 強弱をつけて演奏することで、感情を表現しました。 |
| 器楽音楽の発展 | 特にバイオリンやチェンバロなどの楽器が使用されました。 |
著名な作曲家
バロック音楽の時代には、多くの著名な作曲家が活躍しました。以下に代表的な作曲家を紹介します。
ヨハン・セバスティアン・バッハ
彼はバロック音楽の巨匠とされ、特に教会音楽や器楽音楽で知られています。
ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル
オペラやオラトリオで有名で、特に「メサイア」が有名です。
アントニオ・ヴィヴァルディ
「四季」というバイオリン協奏曲が特に有名です。
バロック音楽の影響
バロック音楽は、その後のクラシック音楽の発展に大きな影響を与えました。特に、作曲技術や楽器の使い方は現代の音楽にも受け継がれています。
バロック音楽は聴く人々に感動を与え、多くの人々に愛されています。今日でもコンサートや音楽祭で演奏され、私たちの生活の中で色あせることがありません。
バロック音楽 対位法 とは:バロック音楽というのは、1600年代から1750年までの間に広まった音楽のスタイルのことを指します。この時期には、作曲家たちが新しい技法を用いて音楽を作り出しました。その中でも「対位法」は特に重要な技法の一つです。対位法とは、異なるメロディーを同時に演奏することで、音楽に豊かな響きを与える方法です。バロック時代の作曲家たちは、主にバッハやVivaldiなどがこの技法を使い、互いに絡み合うメロディーを作り上げました。彼らの音楽を聴くと、まるで複数のストーリーが同時に語られているかのように感じられます。対位法は、単純なメロディーだけでなく、和音にも工夫をもたらし、音楽の表現力を高めました。この技術を使って作られたバロック音楽は、今でも多くの人に愛され続けています。音楽がどうやって生まれるのか、バロック音楽や対位法に触れてみることで、新たな視点が得られるかもしれません。
バロック:音楽が発展した時代(約1600年〜1750年)、特徴的なスタイルや技術が色々と生まれた。
クラシック音楽:バロック音楽の後に続く音楽ジャンルで、18世紀から19世紀にかけて広まり、より洗練された形式や和声が特徴。
オーケストラ:バロック時代には小規模なオーケストラが存在し、器楽曲やオペラなどで演奏された。
ハープシコード:バロック音楽でよく使用された鍵盤楽器で、弦をはじくことで音を出す独特の音色を持つ。
宗教音楽:バロック時代には宗教的なテーマの音楽が多く作られ、オラトリオやミサ曲が代表的。
オペラ:演劇と音楽が融合したジャンルで、バロック音楽の中で特に人気があった。
ソナタ:器楽のために書かれた曲形式で、バロック音楽で重要なスタイルの一つ。
バッハ:バロック音楽の代表的な作曲家で、宗教音楽や器楽曲で非常に影響力を持つ。
ヘンデル:バロック時代の作曲家で、特にオペラやオラトリオが著名。
対位法:複数のメロディーを組み合わせる技法で、バロック音楽の重要な特徴。
アリア:オペラやオラトリオにおいて、独唱者が感情を表現するための楽曲の一部。
チェンバロ:ハープシコードの一種で、バロック音楽で広く使用されたポピュラーな楽器。
曲式:バロック音楽では、特定の構造や形式(例:フーガ、ダンス型曲式)がよく用いられた。
フィガー:バロック音楽における特定の音型や演奏法を指し、個性的な表現を生み出す要素。
バロック様式:バロック音楽と同じく、17世紀から18世紀初頭にかけての芸術様式を指します。このスタイルは、装飾的で感情的な表現が特徴です。
クラシック音楽:広義にはバロック音楽を含む音楽ジャンルですが、通常はバロック以降の時代の音楽全般を指すため、バロック音楽の一部と考えられます。
バロック時代の音楽:バロック音楽が制作された時代の音楽を示し、具体的には1600年代から1750年代の音楽を意味します。
古典派音楽:バロック音楽の後に続く音楽ジャンルであり、バロック音楽の要素を取り入れつつ、よりシンプルで明確な構造を持っています。
装飾音楽:バロック音楽には装飾的な要素が多く含まれているため、特にその特徴を強調した表現です。
オペラ:バロック音楽の時代に発展した舞台作品で、音楽と演劇が融合した芸術形式。特に、モンテヴェルディが作品を残しています。
協奏曲:ソロ楽器とオーケストラが交互に演奏する音楽の形式。バロック時代にはヴィヴァルディによって多くの協奏曲が作曲されました。
ソナタ:通常、楽器のために書かれた楽曲形式で、バロック時代には特に鍵盤楽器や弦楽器のためのソナタが人気を集めました。
バッハ:バロック音楽を代表する作曲家の一人。特に『マタイ受難曲』や『ブランデンブルク協奏曲』で知られています。
フーガ:バロック音楽に特有の contrapuntal(対位法的)な作曲技法。バッハの作品に多く見られる形式です。
トリオ・ソナタ:通常、二つの楽器と低音楽器(通奏低音)のために書かれたソナタの形式。バロック時代の室内楽で広く用いられました。
通奏低音:楽曲の基礎を成す低音部の上に和音を加えて演奏するスタイル。バロック音楽では非常に重要な手法でした。
ダンス音楽:バロック時代に人気のあった、舞踏のために作曲された楽曲。バロック音楽の中で様々なリズムとスタイルが特徴です。
カンタータ:バロック音楽における宗教音楽の一形式。通常は合唱とオーケストラが組み合わさった作品で、宗教的なテーマが多く扱われます。