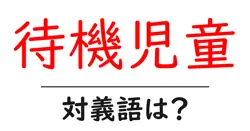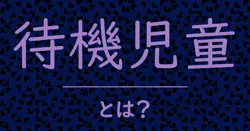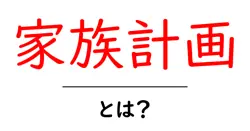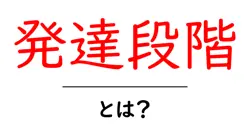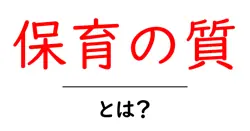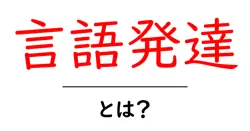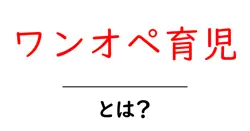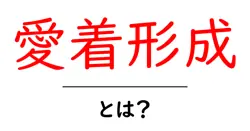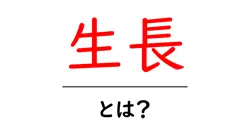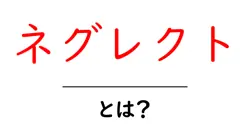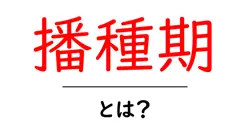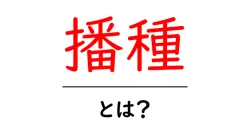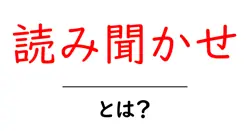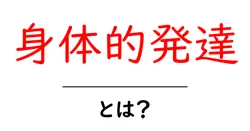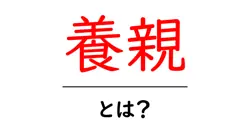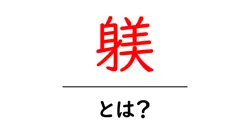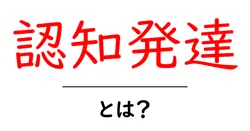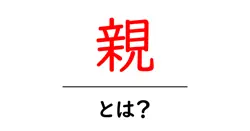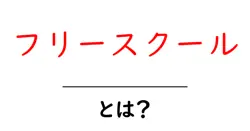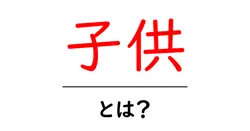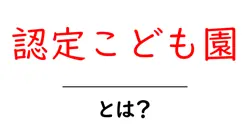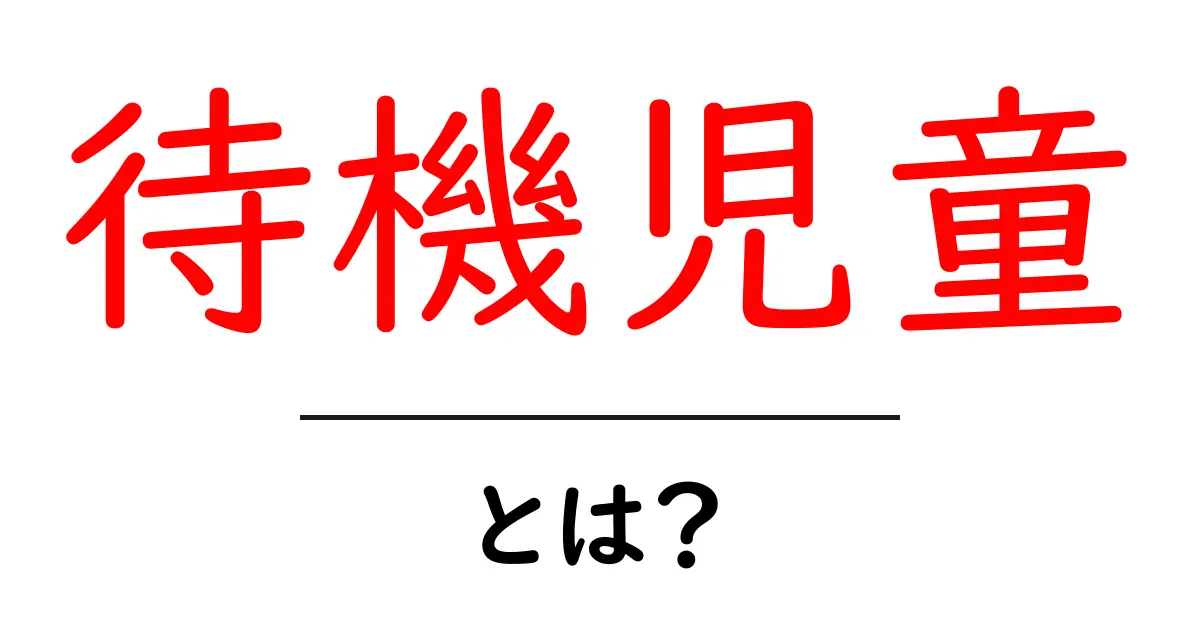
待機児童とは?
待機児童(たいきじどう)とは、保育所や幼稚園などの施設に入るための待機リストに載っている子どもたちのことを指します。保護者が働いている場合、または何らかの理由で保育が必要な場合、子どもを保育所に預けることが求められますが、施設の定員が満たされていると、待機を強いられることになります。
待機児童が問題になる理由
待機児童の問題は、日本の大きな社会問題の一つとされています。特に都市部では、共働き家庭が増加しているため、保育施設の需要が高まっています。しかし、設備や人手の不足から、保育所に入れない子どもが増えてしまっているのです。
待機児童の現状
最新のデータによると、待機児童の数は年々増加しており、特に大都市圏でその傾向が顕著です。以下の表に、都道府県別の待機児童数を示します。
| 都道府県 | 待機児童数 |
|---|---|
| 東京都 | 3000人 |
| 大阪府 | 2500人 |
| 愛知県 | 1800人 |
解決策は?
待機児童の問題を解決するためには、保育所の数を増やすことや、保育士を増やすことが大切です。また、地域での子育て支援の強化も求められています。具体的には、企業と連携した保育所の設立や、地域におけるファミリーサポートセンターの充実が考えられます。
さらに、政府は待機児童対策として、補助金や助成金を用意し、保育所の設立を促進しています。これにより、今後少しでも多くの子どもたちが、安心して保育を受けられる環境が整うことが期待されます。
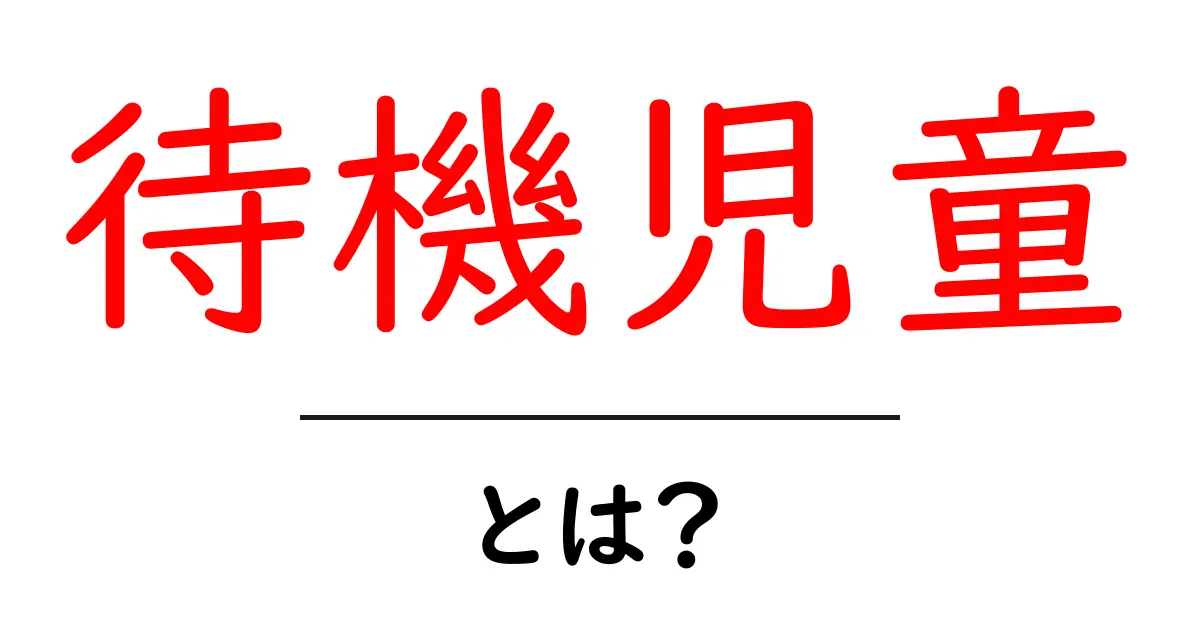
保育園 待機児童 とは:保育園の待機児童とは、保育園に入れない子どもたちのことを指します。日本では、特に都市部で待機児童の問題が深刻です。多くの親が働きに出る中、保育園の定員が足りず、必要な保育施設が整備されていないために、子どもたちが保育園に入れない状態が続いています。これにより、親たちは育児と仕事の両立が難しくなります。現状では、国や地方自治体が保育園の数を増やす取り組みを進めていますが、短期間では解決が難しい問題です。待機児童の解消には多方面からのアプローチが必要で、地域社会や企業との協力も重要です。私たち一人ひとりがこの問題について理解し、考えていくことが大切です。これからの未来のために、子どもたちが安心して育てられる環境を整えることが急務です。
社会問題 待機児童 とは:待機児童とは、保育施設に入れない子どもたちのことです。日本では多くの親にとって、小さな子どもを持つことは仕事を続ける上での大きな課題になっています。特に都市部では、保育園が足りず、申し込んでも入れない子どもが多くなっているのです。この問題は、子どもたちや親の生活に大きな影響を与えるだけでなく、社会全体にも影響を及ぼします。例えば、仕事を持つ親が安心して働ける環境を整えることは、経済活動にとっても重要です。待機児童問題を解決するためには、保育施設を増やしたり、保育士の数を増やして、より多くの子どもたちを受け入れられるようにすることが必要です。また、働く時間や働く場所の選択肢を柔軟にすることも、親をサポートするために大切です。このように、待機児童問題を解決するためには、社会全体が協力し合い、子どもたちが安心して育てられる環境を整えることが求められています。
保育園:子どもを預けるための教育施設。待機児童の問題は、保育園の不足と関係が深い。
幼稚園:子どもが入園する教育機関で、待機児童はここでも問題になることがある。
待機児童問題:待機児童が多く、保育を必要としている子どもが入所できない状況を指す。
保育士:保育園や幼稚園で子どもたちを見る専門職。待機児童の解消には保育士の数を増やすことが鍵となる。
子育て支援:地域や国が行う、育児を支えるためのサービスや政策のこと。待機児童の解決に向けた重要な活動。
地方自治体:各地域の行政サービスを提供する単位。待機児童問題に対して地域ごとに対策を講じる。
少子化:出生率が低下する現象。待機児童と一見関係がないように思えるが、人口の減少は保育園の運営に影響を与える。
需給バランス:保育所の需要と供給の均衡を意味する。待機児童が多い地域では需給バランスが崩れている。
認可保育所:政府によって認可された保育施設。待機児童はこの認可保育所に入所できない場合が多い。
無認可保育施設:認可を受けていない保育施設。待機児童が多い地域では、利用されることもあるが、質が保証されていない場合がある。
保育待機児童:保育所に入ることができず、待機している子どもを指します。保育園の枠が不足しているため、入所を希望する家庭が待たされる状態です。
待機保育児:保育施設に登録しているものの、すぐには受け入れられずに待機している子どもたちのことです。
預けられない子ども:育児をする親が働いているにもかかわらず、保育所に入れず、預けることができない状況にある子どもを指します。
求職中の子ども:親が仕事を探している間に、保育施設に入れないために待機している子どもに対する呼び方です。
育児休業中の子ども:育児休業を取得した親が復職を希望しているが、保育所に入れないために待機する子どもたちのことを指します。
保育園:子どもを預けることができる施設で、主に0歳から就学前の幼児を対象にした教育・保育を提供します。待機児童問題の解決策として保育園の定員を増やすことが求められています。
幼稚園:3歳から6歳までの子どもを対象とする教育機関で、幼児教育を重視しています。保育園とは異なり、主に教育に重点を置いています。
認可保育所:政府の基準を満たしている保育施設で、運営者は subsidies(助成金)を受けることができます。待機児童の多くがこの種類の施設を希望しています。
無認可保育所:政府の基準を満たしていない保育施設で、法律に基づいた運営がされていませんが、柔軟な保育が受けられることから需要があります。
保育士:保育園や幼稚園で子どもを預かり、教育や保育を行う専門職のことです。待機児童問題の解決には、保育士の増員も重要な要素となります。
待機児童数:保育施設に申し込んでいるが、空きがないために預けられない子どもの数を指します。この数が増えることは、地域の保育環境が整っていないことを示す指標です。
子育て支援:親が子どもを育てる上で必要な情報やサービスを提供することです。待機児童を減らすための政策の一環として重要な役割を果たします。
地域子育て支援センター:地域ごとに設置されている子育て支援施設で、親同士の交流や子育てに関する相談などを行う場所です。
就学前教育:子どもが小学校に入学する前に受ける教育のことで、保育園や幼稚園で行われます。待機児童の問題を解決するためには、就学前の教育環境を充実させることが重要です。
待機児童の対義語・反対語
待機児童とは?待機児童問題のいまと原因・対策 - マイナビ保育士
待機児童とは?待機児童問題のいまと原因・対策 - マイナビ保育士