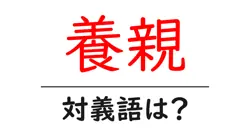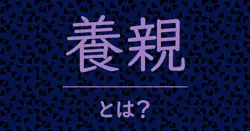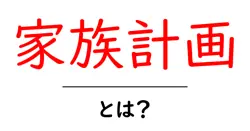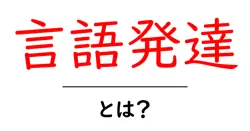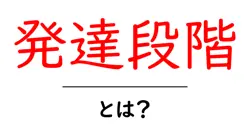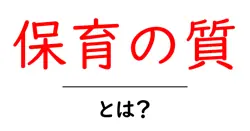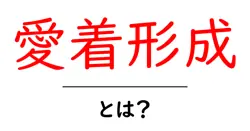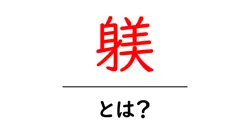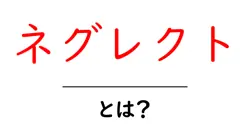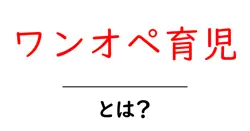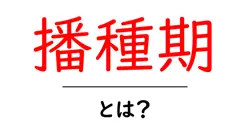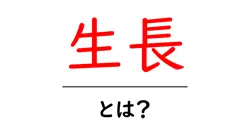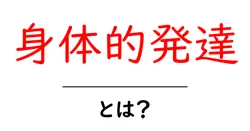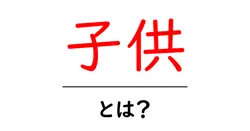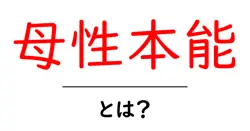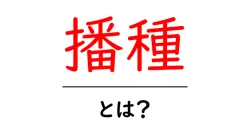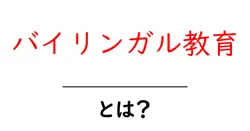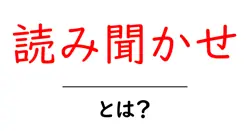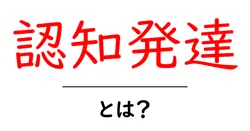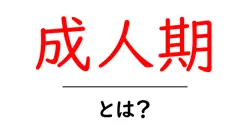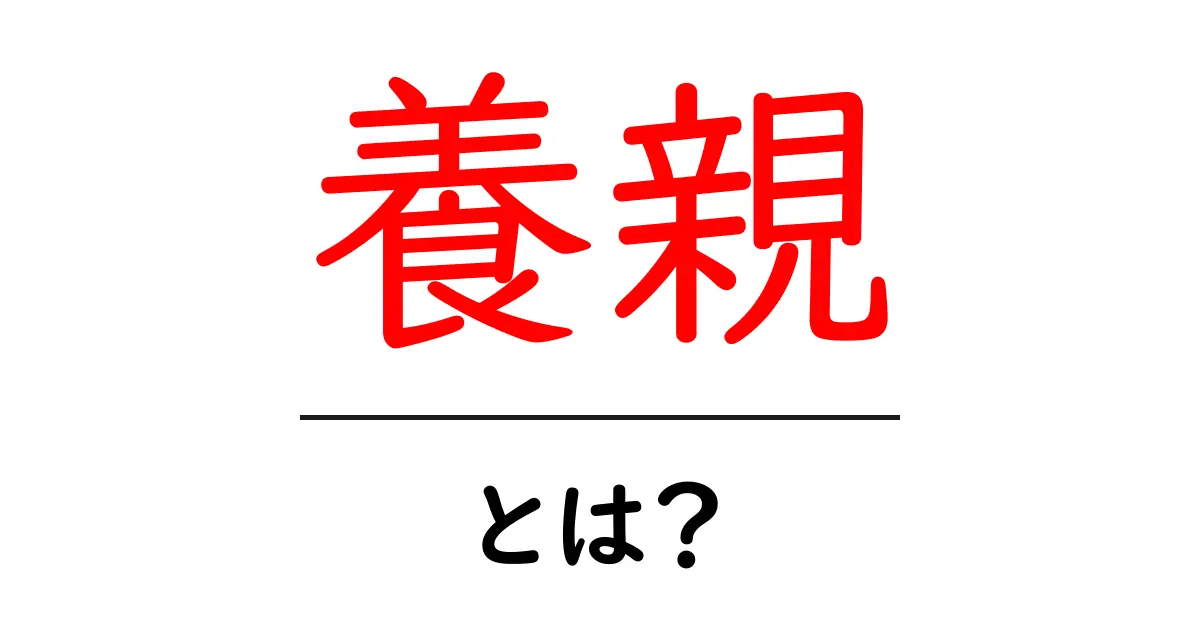
養親とは?
養親という言葉は、特に養子縁組に関係する重要な概念です。養親とは、他人の子供を自分の子供として育てる親のことを指します。つまり、生物学的には親子関係がないけれども、法律上や心のつながりで家族と認識されている関係のことを言います。
養親と養子の関係
養親は養子を迎えることで家族の一員にします。養子とは、養親に育てられる子供のことで、実親とは別の家庭で育てられます。養親と養子の関係は、法律的にも認められることが多く、養子は養親の戸籍に記載され、相続権なども与えられます。
養親になる方法
養親になるためには、まず法的手続きを行う必要があります。以下はその流れです:
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 養子縁組の準備 |
| 2 | 必要書類の提出 |
| 3 | 審査の実施 |
| 4 | 養子縁組成立 |
養親になることのメリット
養親になることには多くのメリットがあります。まず、子供に新しい家族を与えることができ、育てる喜びを感じられます。また、養子は法律上の家族として認められるため、社会的な安定も得られます。さらに、養子との関係を通じて、親としての成長も期待できます。
注意点
一方で、養親になることには責任も伴います。養子に対して無条件の愛情を注ぐことが求められるため、心理的な準備も必要です。また、時には養子とのコミュニケーションの難しさを感じることもあります。そのため、専門家の相談を受けることをお勧めします。
まとめ
養親は、法律的にも心理的にも深い意味を持つ存在です。他人の子供を受け入れることで、家族の形を新たに創造することができます。興味がある方は、ぜひ養子縁組について調べてみてください。
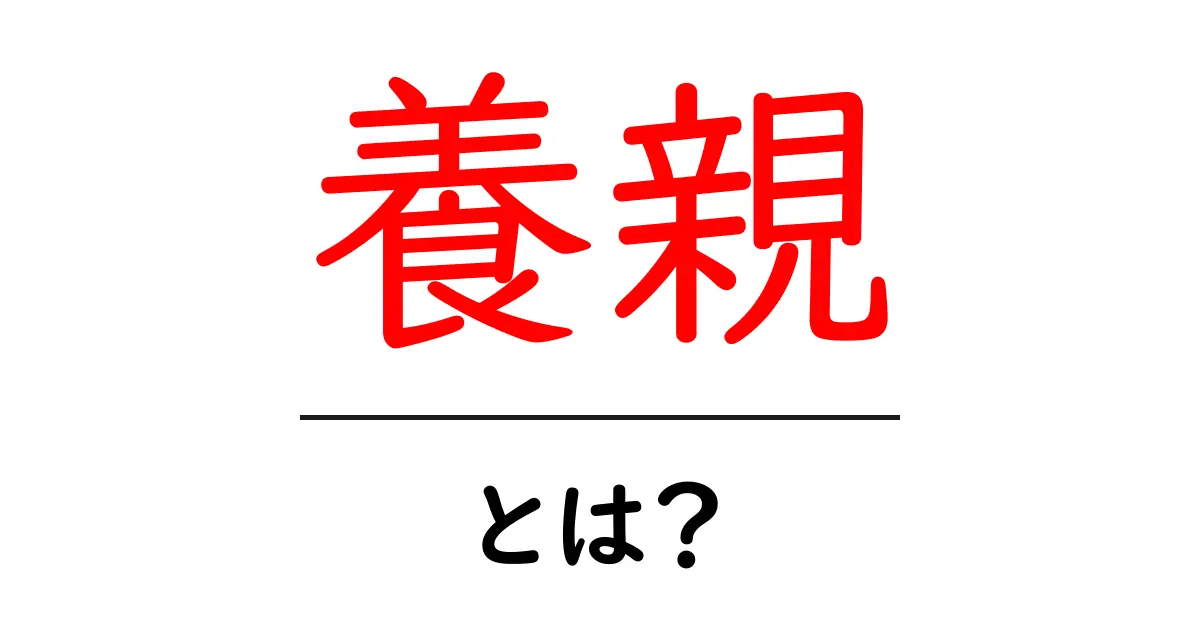
里親:養親と似た意味を持ち、子どもを一時的に自宅に迎え入れ、生活を支える家庭のこと。正式な親子関係は成立しないが、愛情を持って育てる役割を担う。
養育:子どもを育てること全般を指し、経済的・精神的な面で支えることが含まれる。養親が行う主要な責任のひとつ。
支援団体:養親や里親を支援するための非営利団体や自治体など。情報提供や研修支援などを行う。
法律:養親制度に関する法的な規定や法律が関係してきます。子どもと養親の権利や責任について定めている。
子ども居場所:養育が必要な子どもたちが集まり、安全に過ごすことができる場所。多くの場合、養親が支援先となる。
家庭:養親が提供する生活環境。愛情に包まれた家庭を築くことが養親の役割の一つ。
福祉:養親制度や里親制度は、福祉の一環として位置づけられ、困難な状況にある子どもたちを支援するための取り組みが含まれる。
子どもの権利:養親家庭にいる子どもたちが享受すべき権利。愛情や教育、健全な生活環境が含まれる。
養子:法的に親子関係が成立した場合、養親の子どもとなること。養子を迎えることは養親の大きな一歩。
ネットワーク:養親や里親同士が情報を交換し合うためのコミュニティやグループ。支え合いの場となる。
里親:養親と同じように、他人の子供を一時的に受け入れて育てる役割を持つ人のこと。
養育者:子供を育てたり、面倒を見たりする担当者で、養親の役割を持つ場合もある。
育ての親:生みの親ではなく、実際に子供を育てた親のこと。養親としての役割を果たすことも多い。
後見人:子供の法律上の保護者であり、親の代わりに子供を守る役割を持つ人。
保護者:子供を法的に保護する立場の人。養親と同様に、子供の育成に関わる。
養子:養親が育てることになった子どもを指します。生物学的な親とは異なり、法的に養子縁組を結ぶことで親子の関係が成立します。
養子縁組:養親が子どもを自分の子どもとして法律上の関係を結ぶ手続きです。通常、法的な手続きが必要で、養子は養親の権利や義務を持つことになります。
里親:一時的に虐待や育児放棄された子どもを預かり育てる人のことを指します。法律的な親子関係はありませんが、子どもに愛情を持って接する重要な役割です。
適応:養子が養親の家庭にうまく馴染んでいく過程を指します。新しい環境に適応することは、子どもにとっても養親にとっても大切な課題です。
家族制度:家族の構成や役割に関する社会的な枠組みを指します。養子縁組を通じて、養親と養子は新しい家族としての関係を築きます。
親権:親が子どもに対して持つ権利や義務のことを指します。養親は養子に対して法的な親権を持つことになります。
福祉:養親が子どもを育てる際に関与する制度やサービスを指します。養子や里親支援を通じて、子どもの福祉を確保することが目的です。
愛情:養親が養子に対して持つ感情です。愛情をもって接することで、養子の心の安定や成長が促されます。
契約:養子縁組を行う際には、法的な契約が必要になることがあります。この契約により、養親と養子の権利や義務が明確になります。