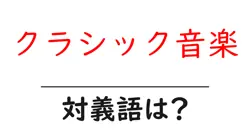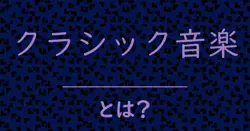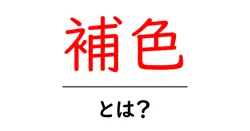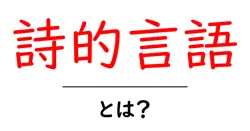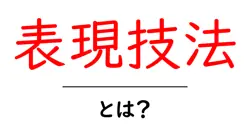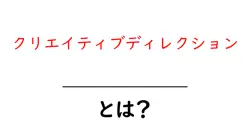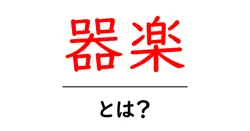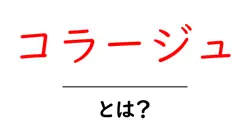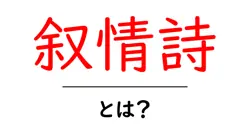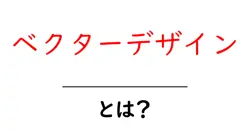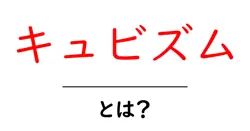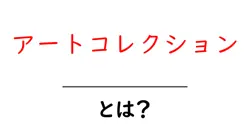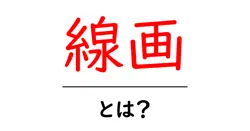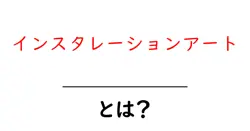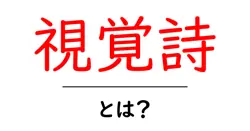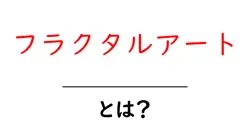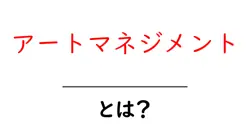クラシック音楽とは?その魅力と歴史を解説!
クラシック音楽という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。音楽にはさまざまなジャンルがありますが、クラシック音楽は特に古くから愛されてきたジャンルの一つです。この記事では、クラシック音楽の基本的な特徴や歴史、そしてその魅力についてお話しします。
クラシック音楽の定義
クラシック音楽とは、おおむね18世紀から19世紀にかけて作曲された音楽を指します。このジャンルには、交響曲や協奏曲、オペラなどの形態があります。特に有名な作曲家には、モーツァルト、ベートーヴェン、バッハなどがいます。
クラシック音楽の歴史
クラシック音楽の起源は古代までさかのぼりますが、特に重要なのはバロック時代(1600-1750年頃)、古典派時代(1750-1820年頃)、ロマン派時代(1820-1900年頃)といった3つの時代です。
| 時代 | 特徴 |
|---|---|
| バロック時代 | 装飾的な音楽が流行し、声楽と器楽の対比が楽しめた。 |
| 古典派時代 | シンプルで洗練されたメロディが特徴。交響曲が多く作られた。 |
| ロマン派時代 | 感情表現を重視し、より自由なスタイルが多く見られた。 |
クラシック音楽の魅力
クラシック音楽の魅力は、その豊かな表現力と深い感情にあります。聴く人の心に響くメロディや、壮大なオーケストラの音色は、リスナーに感動を与えます。また、楽器や声のテクニックも多彩で、演奏者によるアレンジも楽しみの一つです。
クラシック音楽を楽しむ方法
クラシック音楽を楽しむには、コンサートに出かけるのも良いでしょう。多くの都市で定期的にコンサートが開催されており、名曲を生で聴くことができます。また、CDやストリーミングサービスを利用して、自宅で楽しむのもおすすめです。
最後に、クラシック音楽はただの過去のものではなく、今もなお進化し続けています。新しい作曲家が次々と登場し、未来のクラシック音楽がどのように発展していくのか、楽しみです。
クラシック音楽 op とは:クラシック音楽では、作曲家が自分の作品に番号を付けることがあります。この番号は「op」と呼ばれ、「オペス」と読みます。これはラテン語の「opus」の略で、「作品」という意味です。例えば、ベートーヴェンが作曲した「ピアノソナタ第14番」は「Op. 27」と表記されます。この「op」のあとに続く数字が、その作曲家が作った作品の順番を示しています。つまり、番号が小さいものは早く作られた作品で、数字が大きくなるにつれて後に作られた作品なのです。これにより、リスナーはその曲がどのくらい新しいのか、あるいは古いのかを簡単に理解することができます。作曲家によっては「op」を付けない作品もありますが、多くの有名な作品にはこの番号が付いているので、クラシック音楽を聴くときはぜひ注目してみてください。音楽を聴きながら「op」の番号を考えることで、その作品がどのような背景を持っているのかを学ぶ興味も増えるかもしれません。
オーケストラ:多くの楽器や演奏者が一緒に演奏するための音楽団体。クラシック音楽の演奏でよく見られる形式。
ソリスト:独奏を行う音楽家のこと。例えば、ピアノソリストやバイオリンソリストなどがいる。
交響曲:オーケストラのために作曲された大規模な楽曲の形式。通常、複数の楽章から成り立っている。
室内楽:少人数の楽器編成による演奏スタイル。通常、アンサンブルとして親しまれている。
アリア:オペラやオラトリオなどで、ソロの歌手が歌う楽曲のこと。感情や物語を表現する重要な部分。
協奏曲:ソリストとオーケストラが対話する形で演奏される楽曲の形式。特にピアノ協奏曲が有名。
楽譜:音楽の演奏方法が記された書類。楽器や声のための音符、指示が含まれている。
指揮者:オーケストラや合唱などの演奏を指揮する人。音楽の解釈やテンポを調整する役割を担う。
オペラ:音楽と演劇が組み合わさった演目。歌と演技が融合した形で物語を語る。
バロック:17世紀から18世紀の西洋音楽のスタイルを指す。装飾的で複雑な音楽が特徴。
ロマン派:19世紀の音楽スタイルで、感情や個人的な表現を重視する。ショパンやブラームスが代表的。
クラシカル:クラシック音楽のスタイルや時代を指す言葉で、伝統的な形式や手法が重視される。
古典音楽:18世紀から19世紀初頭にかけて作られた音楽のことを指し、特にモーツァルトやベートーヴェンなどの作品が有名です。
西洋音楽:西洋で発展した音楽全般を指し、特にクラシック音楽はその中で重要なジャンルです。
伝統音楽:長い歴史を持つ音楽スタイルを指し、クラシック音楽もその一部として考えられることがあります。
室内楽:少人数で演奏するためのクラシック音楽の一形態で、弦楽四重奏やピアノトリオなどが含まれます。
オーケストラ音楽:オーケストラによって演奏される音楽で、クラシック音楽の中でも特に大規模な編成が特徴です。
交響楽:オーケストラによって演奏される主要な作品の一形態で、特に特定の楽章を持つ大規模な音楽です。
オーケストラ:複数の楽器奏者が集まって演奏する音楽の集団で、クラシック音楽の演奏において重要な役割を果たします。
交響曲:オーケストラのために書かれた大規模な楽曲で、通常は数楽章から構成されています。代表的なクラシック音楽の形式の一つです。
室内楽:少人数の演奏者によって演奏されるクラシック音楽のジャンルで、弦楽四重奏やピアノトリオがよく知られています。
バロック音楽:1600年代から1750年代にかけての音楽スタイルで、装飾的なメロディーや対位法が特徴です。バッハやヘンデルなどの作曲家が活動しました。
ロマン派音楽:19世紀に発展した音楽スタイルで、感情表現や個人主義が重視されました。ショパンやリストが代表的な作曲家です。
協奏曲:ソロ楽器とオーケストラが共演するために書かれた楽曲の形式で、ソリストの技術や表現力が際立つ作品が多いです。
オペラ:歌と演技が組み合わさった舞台芸術で、クラシック音楽の重要なジャンルの一つです。ウェーバーやヴェルディなどの作曲家が有名です。
楽譜:音楽を視覚的に表現するための記号の集合で、演奏者が音楽を演奏する際のガイドとなります。
指揮者:オーケストラや合唱団を指揮して音楽の演奏を統率する役割を持つ人物で、音楽の解釈や演奏のクオリティに大きな影響を与えます。
クラシック音楽の時代:主にバロック、古典派、ロマン派の三つの時代に分かれるクラシック音楽の歴史のことで、それぞれに特有のスタイルや作曲家が存在します。