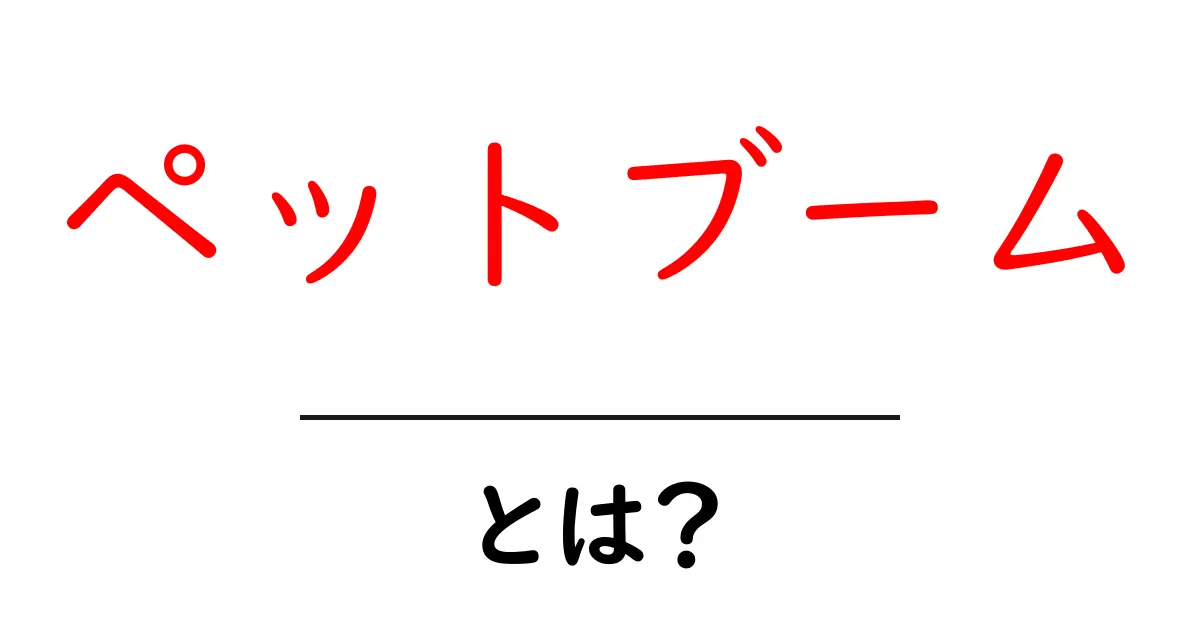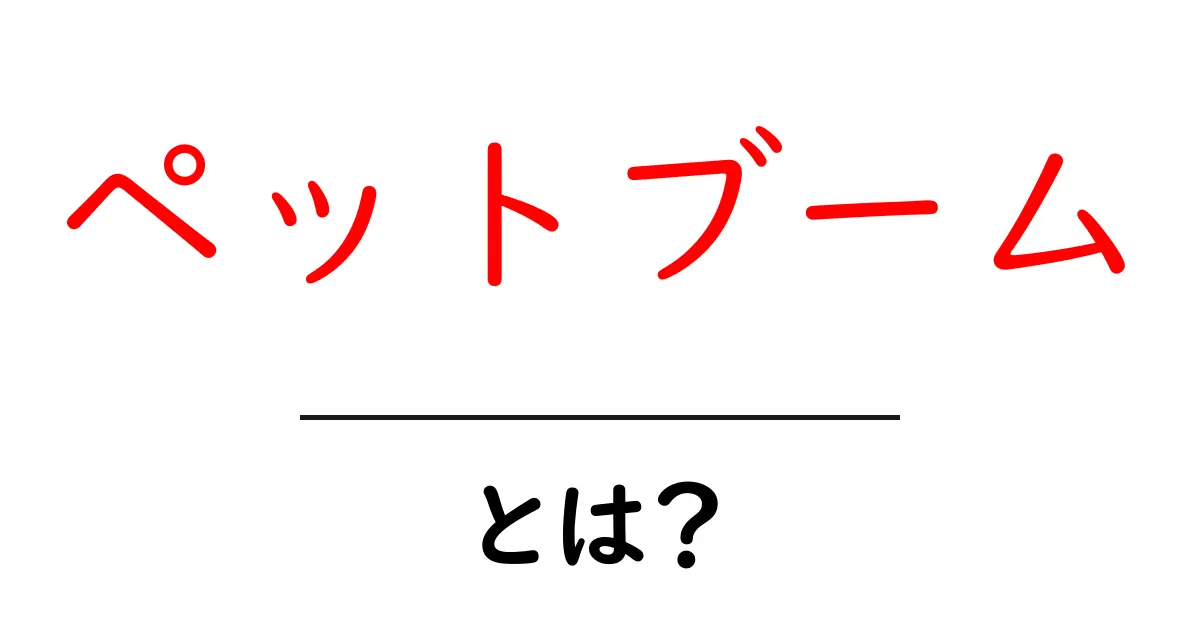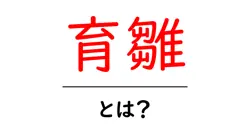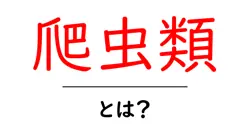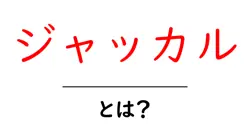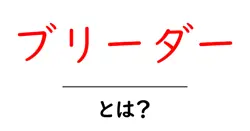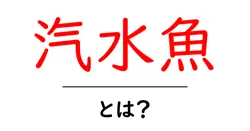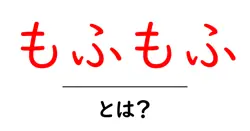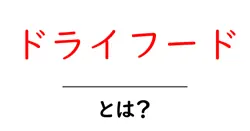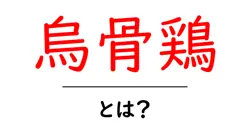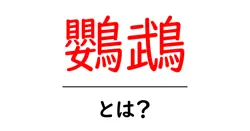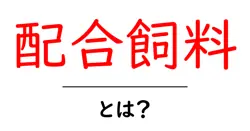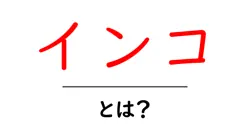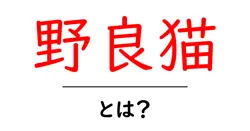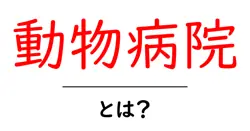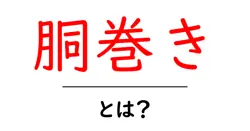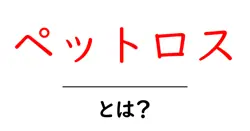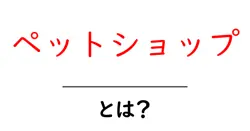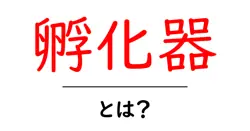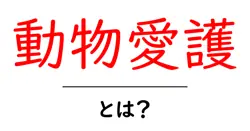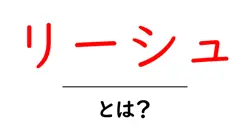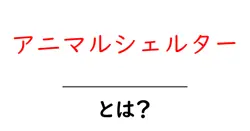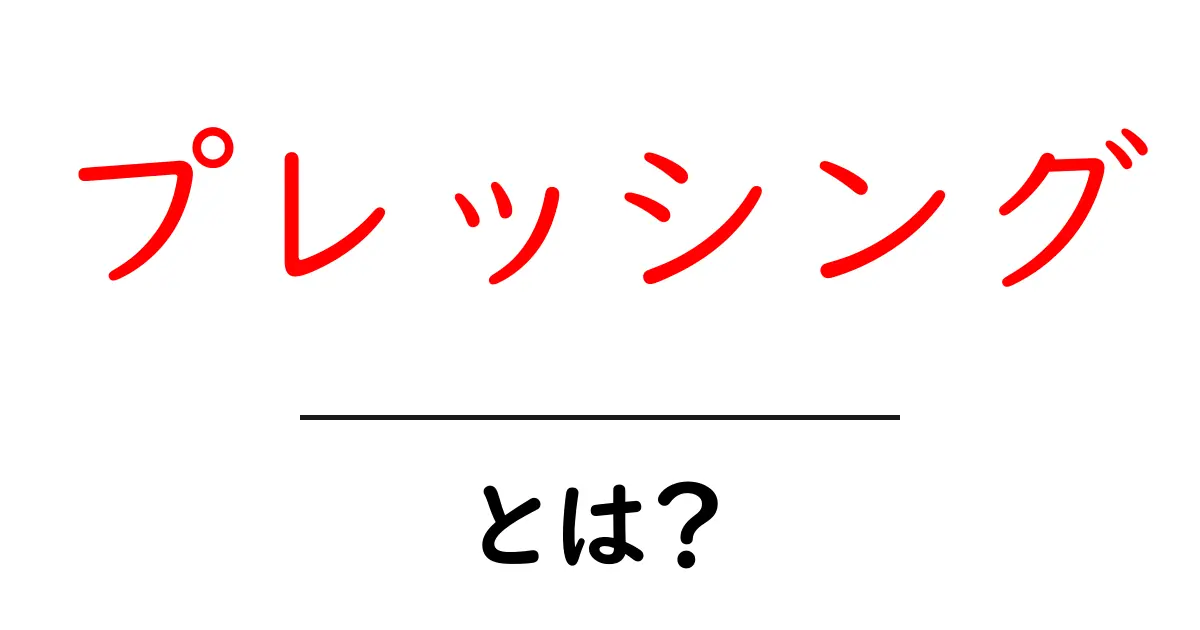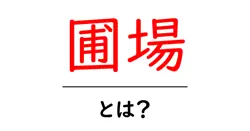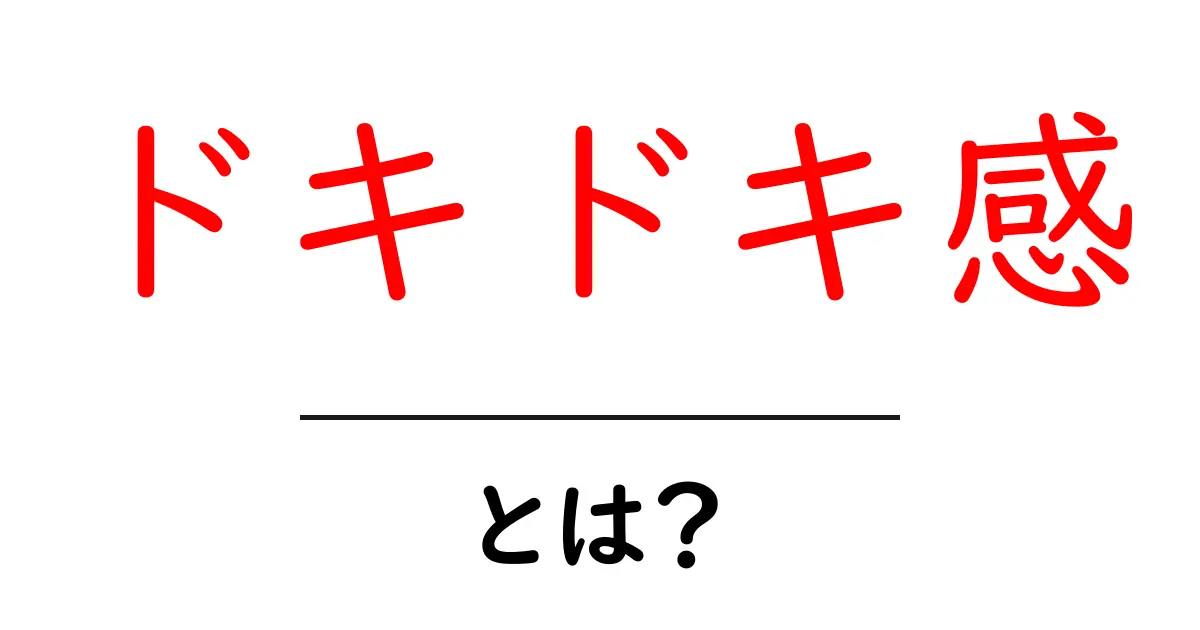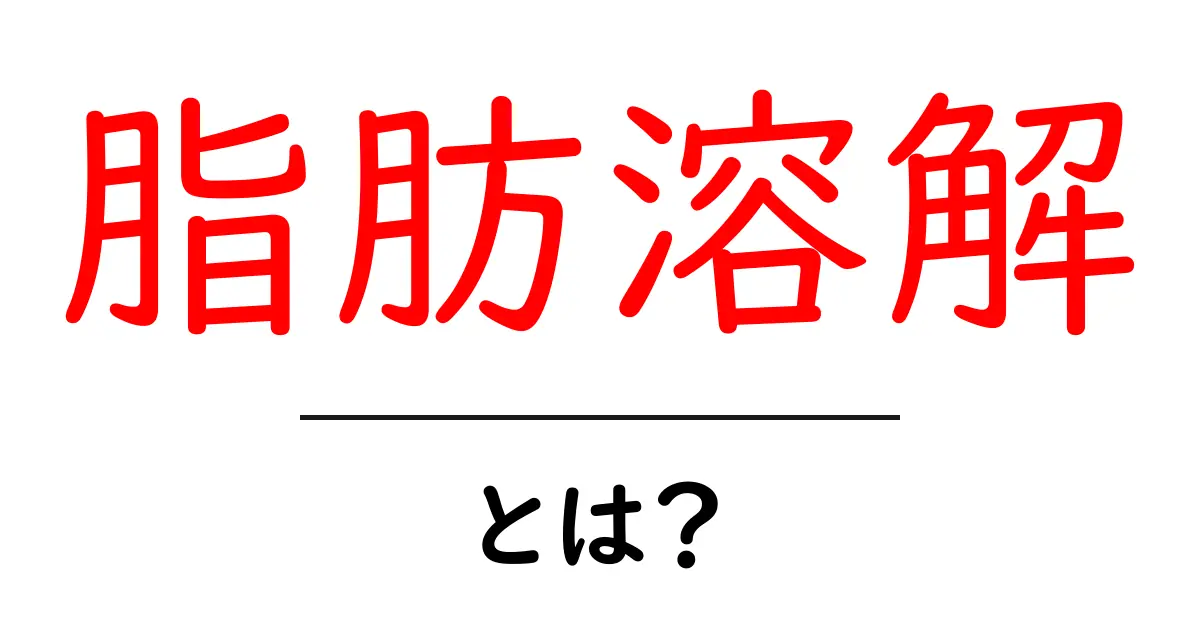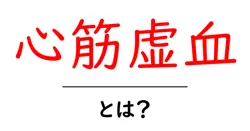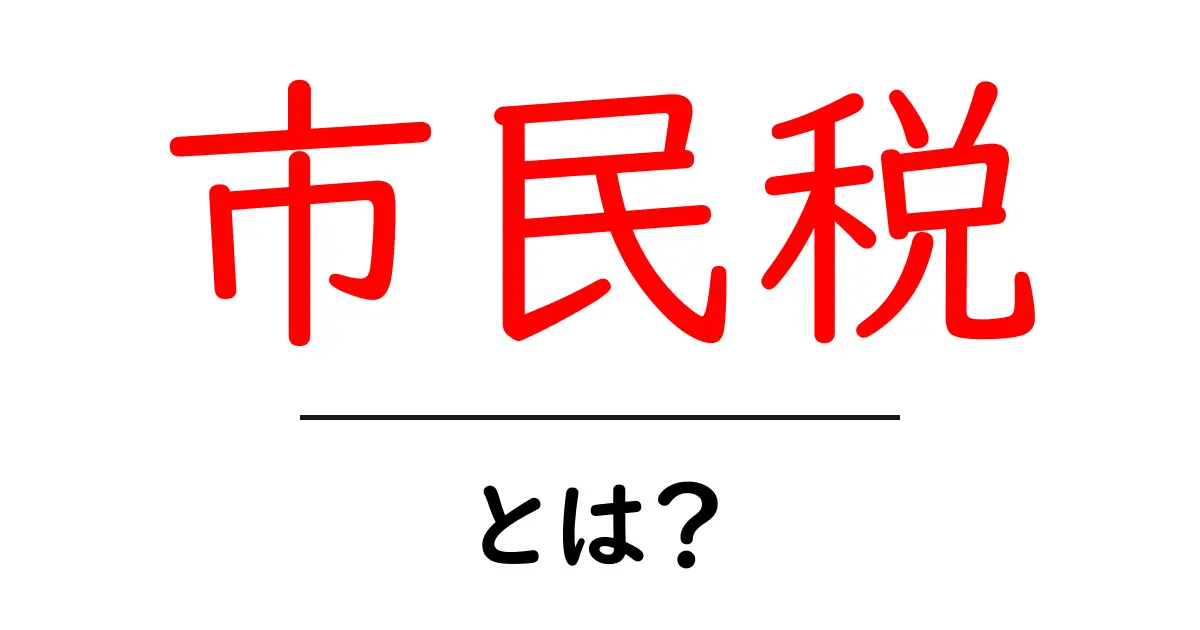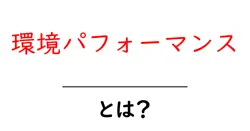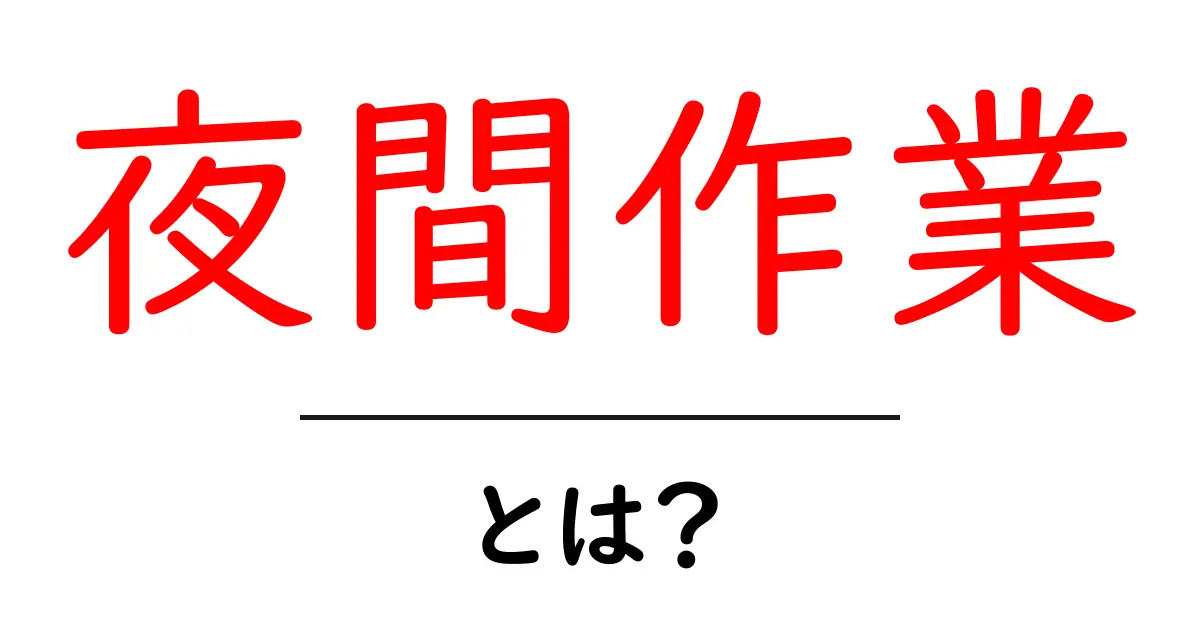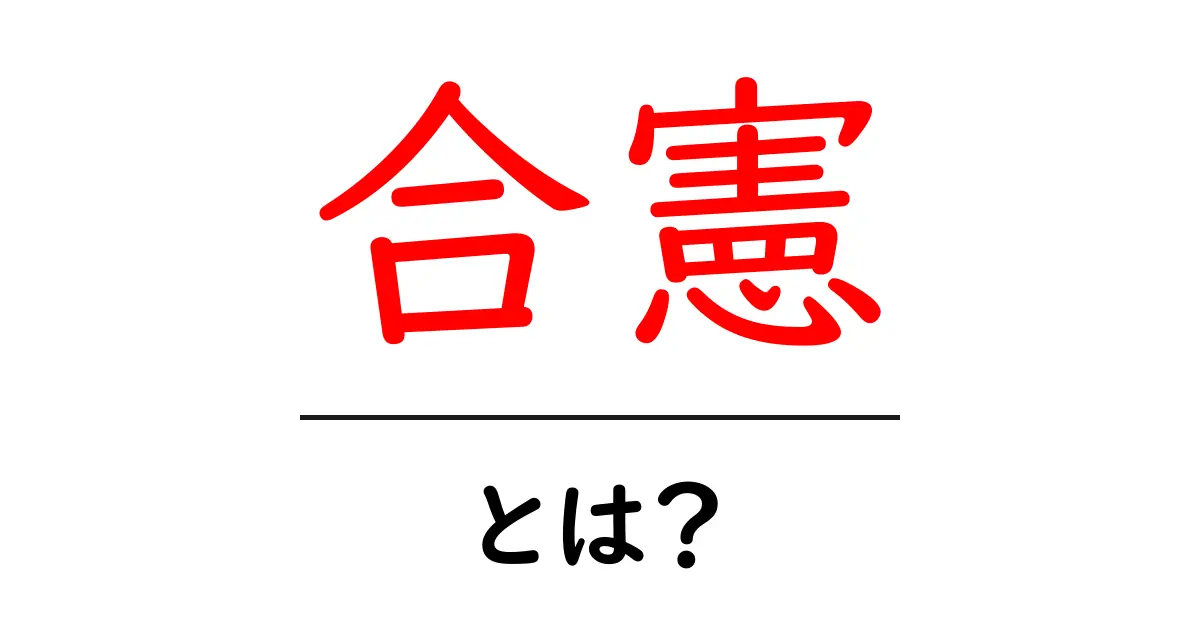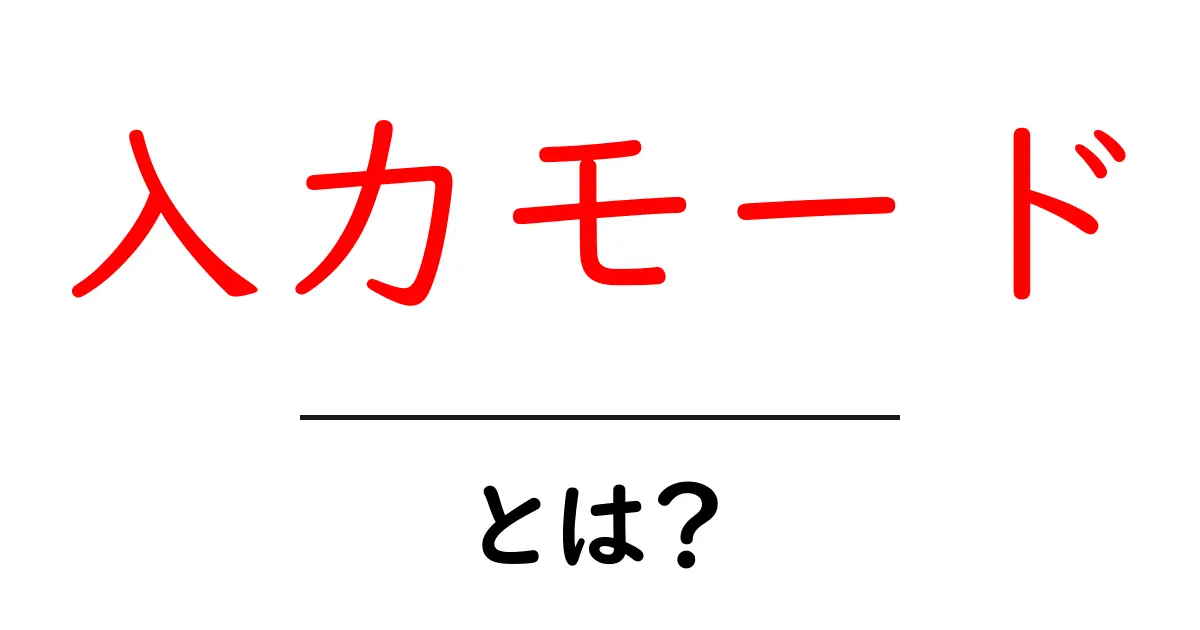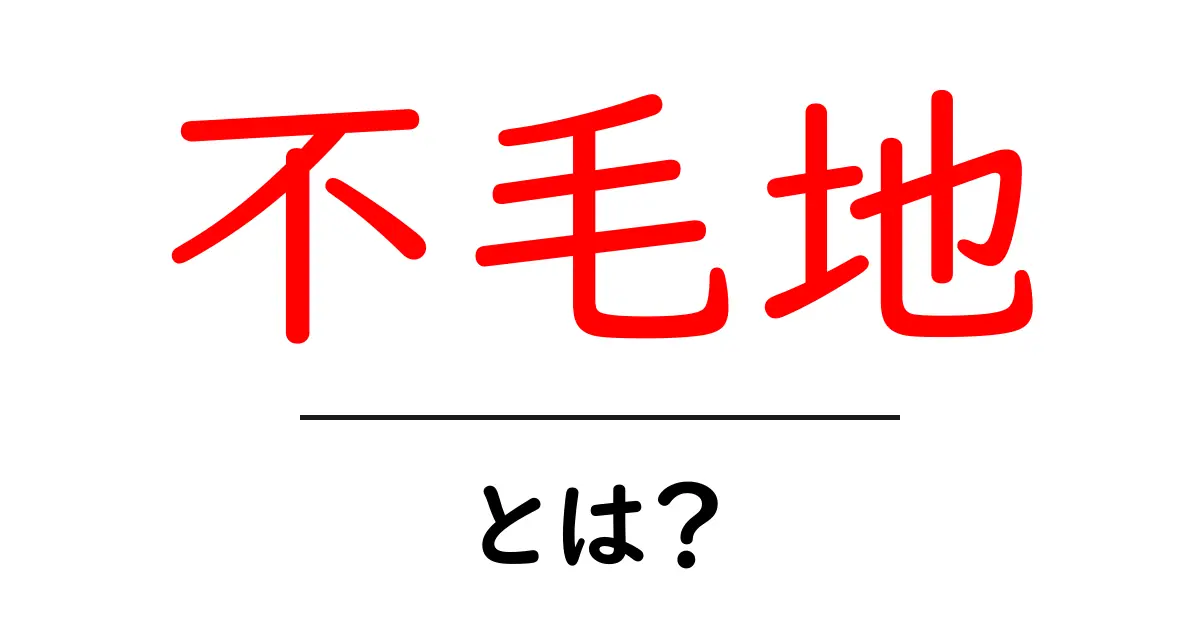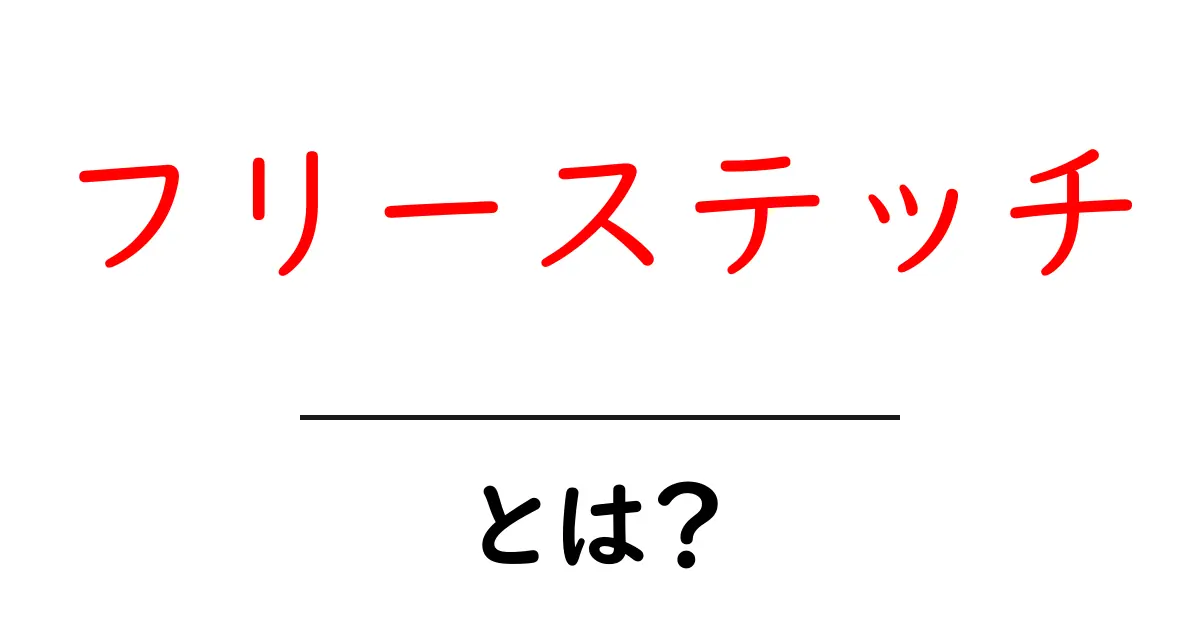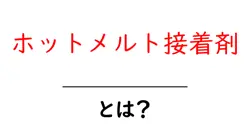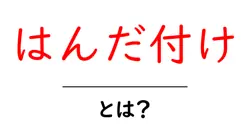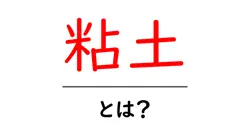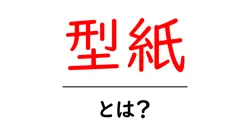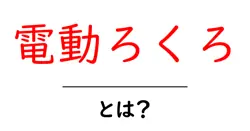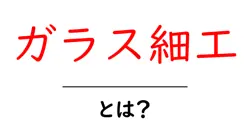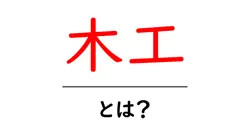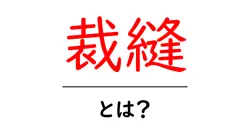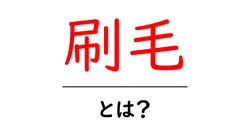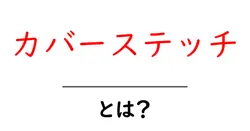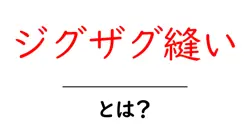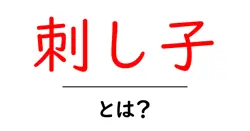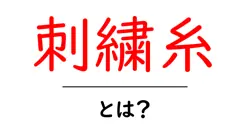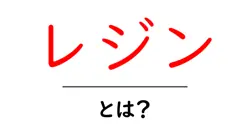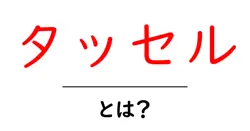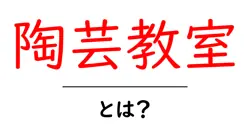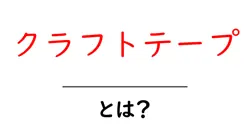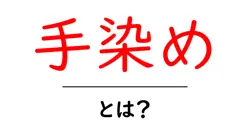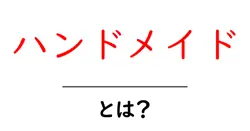市民税とは?
市民税は、私たちが住んでいる市町村に対して支払う税金のひとつです。この税金は、主に地方公共団体が行う様々なサービスや事業に使われます。たとえば、道路の維持管理や学校の運営、福祉サービスなどに利用されています。
市民税の種類
市民税は大きく分けて「均等割」と「所得割」の2つの種類があります。
| 種類 |
説明 |
| 均等割 |
市民税の基本的な部分で、全ての住民が同じ金額を支払います。 |
| 所得割 |
その人の所得に応じて金額が変わる部分で、収入が多いほど支払う金額も増えます。 |
市民税が必要な理由
市民税は、市町村が地域の住民に提供するサービスを支えるために欠かせないものです。税金を通じて、私たちは教育や福祉、交通などの充実した生活基盤を享受しています。
市民税の支払い方法
市民税の支払いは、年に一度の一括払いや、分割払いなどがあります。また、住民票のある市町村から、納税通知書が送られてきますので、それに従って支払います。
まとめ
市民税について理解することは非常に大切です。私たちの生活を支えるための重要な資源であり、地域に住む人々同士の助け合いの一部です。市民税を通じて、より良い地域環境を築いていくことが私たちの役割でもあります。
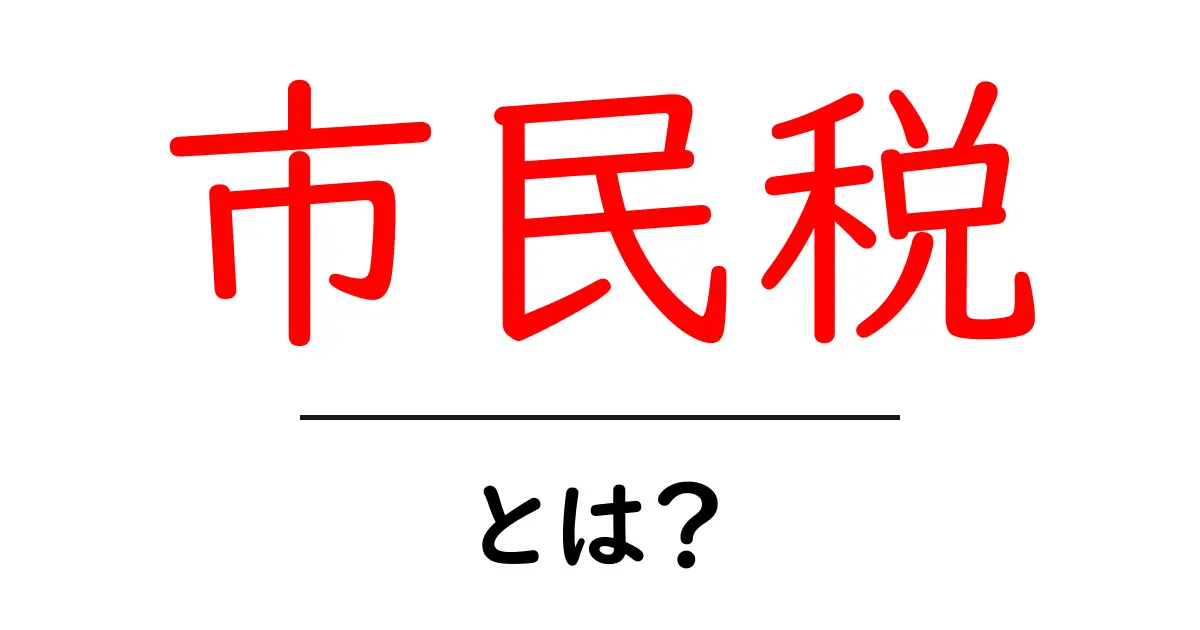
市民税のサジェストワード解説市民税 とは 学生:市民税とは、地方自治体が住民から集める税金の一つで、自分が住んでいる地域の公共サービスを支えるために使われます。例えば、道路の整備や公園の管理、教育や福祉の充実などに使われます。この税金は、ほとんどの住民に課されますが、学生の場合は特別なルールがあります。学生は、アルバイトをしていると収入が発生しますが、その収入が一定の金額を超えない限り、市民税を支払わなくても良い場合があります。しかし、もしアルバイトでしっかりと収入を得ている場合や、生活のために税金を払う必要があると判断された場合は、市民税を支払う必要があります。また、各自治体ごとに税率や免除の条件が異なるため、自分の住む地域のルールを確認することが大切です。税金についての知識をもっておくことで、無駄な出費を避け、賢いお金の使い方ができるようになるでしょう。
市民税 とは 退職:市民税というのは、地方自治体が住民から徴収する税金の一つです。退職した場合、収入が減るので市民税も変わる可能性があります。市民税は、前年の所得を元に計算されるため、退職した年の収入が少なければ、翌年度の市民税も少なくなります。ただし、忘れがちなことは、退職後でも市民税の支払いが必要なことです。市民税の額は住んでいる地域によって異なりますし、納付期限にも注意が必要です。通常、市民税は年に1回の一括納付か、数回に分けて納付することができます。退職後すぐに手続きを行わないと、税金の支払いが滞る場合がありますので、注意が必要です。また、退職後にアルバイトやパートをする予定がある場合は、その分も市民税に影響します。退職したら、収入の変化に応じて市民税のアドバイスを受けると良いでしょう。必要であれば、役所に相談してみるのも一つの手です。
市民税 とは住民税:市民税(しみんぜい)とは、私たちが住んでいる市町村に支払う税金のことです。住民税(じゅうみんぜい)とも呼ばれることがありますが、厳密には少し違います。市民税は、住民税の中の一部で、通常は市区町村に納める税金を指します。市民税は、私たちの暮らしに必要な公共サービスの資金源となります。これには、学校、病院、公園、道路の整備などが含まれます。つまり、市民税を支払うことで、私たちの住んでいる地域がよくなり、みんなが快適に暮らせる環境が整えられるのです。また、住民税には市民税のほかに、県民税(けんみんぜい)もあります。県民税は、県に支払う税金で、県が提供するサービスのために使われます。これらを合わせて、住民税と言われることが多いです。市民税や住民税は所得や住んでいる場所によって異なるお金の額が決まりますので、この点についても理解を深めることが大切です。税金の仕組みを知ることで、将来の生活設計にも役立つかもしれません。
市民税 均等割 とは:市民税均等割は、地方自治体が住民に課税する税金の一つです。市民税は住んでいる市町村の自助融資として使われ、地域のサービスやインフラの整備に充てられます。均等割は、その名の通り、すべての住民に均等に課される部分のことです。具体的には、収入や資産に関係なく、住んでいる市町村によって定められた金額を一律に支払うことになります。このため、金額は市町村によって異なりますが、通常は数千円程度です。均等割の目的は、地域住民が平等に地域のサービスを利用できるようにするためです。例えば、道路や公園、学校の整備などは、市民税をもとに運営されています。すべての住民が税金を支払うことで、地域社会が豊かになり、より良い生活環境が提供されるのです。これが、市民税均等割の重要な役割です。
市民税 所得割額 とは:市民税の所得割額という言葉を聞いたことがありますか?市民税は、私たちが住んでいる市区町村に対して支払う税金の一種です。市民税は主に、住民の生活を支えるために使われます。所得割額は、その市民税の中の一部分で、私たちの所得に応じて決まる税金のことを指します。具体的には、その年の所得に基づいて課税される額を計算します。たとえば、働いて得たお金や、株や不動産から得た利益などが対象です。この所得に対して、決められた税率をかけて計算されるため、収入が多い人は多めの所得割額を支払わなければなりません。また、所得割額には控除制度もあり、特定の条件を満たすと、税金を減らすことができます。市民税は地域社会に貢献する重要な役割を持っているため、私たちの生活にとって大切なものです。市民税の所得割額についてきちんと理解しておくことは、自分の税金を適切に管理するためにも有意義です。
市民税 特別徴収 とは:市民税特別徴収(しみんぜいとくべつちょうしゅう)とは、会社や団体が社員の市民税を一定期間ごとに自動的に徴収し、税務署に納める制度です。この制度は、税金を正確に支払い、納税を楽にするためのものです。通常、私たちが支払う税金は自分で管理しなければならないですが、特別徴収を利用すると、会社がその手続きをしてくれます。
例えば、あなたが働いている会社で特別徴収がされていると、毎月の給料から自動的に市民税が引かれます。そのため、税金を自分で計算したり、納めたりする手間が省けます。この制度を利用する最大のメリットは、税金の支払いが簡単になることと、納め忘れを防ぐことができる点です。また、企業側も、従業員が安心して仕事に集中できる環境を提供することができます。
市民税特別徴収は、特にサラリーマンや組織に所属する人々にとってメリットが大きい制度です。自分の税金がどう扱われているのかを理解して、上手に税金との付き合いをしていきましょう。
市民税 非課税 とは:市民税の非課税という言葉を聞いたことがあるでしょうか?市民税は、町や市で住んでいる人が支払う税金の一種ですが、全ての人が支払うわけではありません。非課税とは、税金を支払う必要がない状態を指します。市民税が非課税になるのは、主に収入が一定以下である場合です。特に低所得の家庭や、学生、年金受給者などが対象になります。収入が少ないと、生活に必要なお金をカバーするのが大変です。そのため、税金を少なくすることで、少しでも生活が楽になるようにしています。ただし、非課税の基準は地域によって異なることがありますので、自分の住んでいるところの市役所や役場で確認することが重要です。また、非課税の制度を利用するためには、申請が必要な場合がありますので、手続きも忘れずに行いましょう。市民税の非課税制度を理解することで、税負担を軽くする手助けになります。
府民税 市民税 とは:府民税と市民税は、地方自治体が住民から集める税金です。府民税は都道府県が課税する税金、一方で市民税は市町村が課税します。例えば、あなたが住んでいる町では、市民税が取られますが、その町は府の一部でもあるので、府民税も支払うことになります。これらの税金は、地域の行政サービスや公共施設の維持、教育や福祉などに使われています。
府民税は、都道府県に住んでいる人たちが負担します。一般的に所得や住民の数によって変わるため、税額も人それぞれです。市民税は、あなたが住んでいる市町村に直接関係があります。引っ越しをすると、市民税が変わることがあります。
このように、府民税と市民税は、私たちの生活にとても大切な税金です。地域を支えるためにも、正しく理解しておくことが大切ですね。税金がどう使われているかを考えると、より地域への愛着が深まります。日々の生活にどのように影響するのか、少しでも知っておくと良いでしょう。
県民税 市民税 とは:県民税と市民税は、私たちの住む地域に関わる大切なお金で、これをまとめて住民税と呼びます。県民税は、都道府県に納める税金で、その地域で暮らす人全体が影響を受けます。一方、市民税は、市町村に納める税金で、地元の行政サービスや公共施設の運営に使われます。この2つの税金は、私たちが生活する上で重要で、どちらも地域の発展を支える役割があります。たとえば、学校や公園、道路の整備などに使われているため、私たちの身近な生活に深く関わっています。税金を納めることで、地域が良くなる手助けをしていることを理解してほしいです。税金は一見難しそうですが、自分の住む地域が元気になるためのお金だと考えると、身近に感じられるかもしれません。
市民税の共起語住民税:住民税は、地域に居住する人々がその地域の行政サービスを受けるために支払う税金です。市民税は住民税の一部を指します。
所得税:所得税は、個人や企業が得た所得に基づいて課税される税金です。市民税は所得の一部として計算されることがあります。
地方税:地方税は、政府が地方自治体に課せられる税金で、ここには市民税や県民税も含まれます。
税率:税率は、税金の計算に用いる割合を指します。市民税の税率は地域によって異なることがあります。
課税基準:課税基準は、税金が計算される際の基準となる金額や条件です。市民税の場合は、総所得や居住地に基づいて決まります。
減免:減免とは、特定の理由により税金が減額または免除されることです。市民税にも、低所得者層などに対しての減免制度があります。
納税義務:納税義務は、税金を支払う法的な責任です。市民税は、市区町村の住人に課せられる納税義務があります。
申告:申告は、自分の所得や税金を正しく報告する手続きです。市民税を支払う場合、所得の申告が必要になります。
税務署:税務署は、税金の管理や徴収を行う国の機関です。市民税に関する問い合わせや申告も税務署で行われます。
納付:納付は、税金を実際に支払うことを指します。市民税の納付は通常、年に1回または分割して行われます。
市民税の同意語住民税:市民税は、地方自治体が住民から徴収する税金の一種で、住民の権利やサービスに対する対価の意味を持つ。
地方税:市民税は地方自治体が課す税金であり、地方税というカテゴリに含まれる。日本では、地方政府が独自に設定する税として、地域の財源を支えている。
所得税:市民税とは異なるが、所得に対して課される税金で、必ずしも同じではないが、市民税と一緒に考えられることもある。
市税:市民税は広義に市税と呼ばれることがあり、特定の市がその住民に対して課すさまざまな税金を指すことがある。
固定資産税:市民税とは異なるが、地方自治体が固定資産に対して課す税金で、地方の公共サービスの財源の一つとして位置付けられている。
市民税の関連ワード住民税:市民税は、住民税の一部であり、特に市町村が課税する税金を指します。住民税は、住んでいる地域の公共サービスの財源となります。
地方税:市民税は地方税の一環です。地方税は国税と対照的に、市町村や都道府県が独自に課税する税金で、地域に根ざしたサービスに使われます。
所得税:所得税は、個人や法人が得た所得に対して課税される国税です。市民税は所得税と関連がありますが、住民が住む市町村のための税金という点で異なります。
固定資産税:固定資産税は、不動産や設備などの資産に対して課税される税金です。市民税とは違いますが、同じく地方自治体の収入源となります。
納税義務:市民税を支払う義務があるのは、その市町村に住む人です。納税義務は各個人に課されており、居住している人口に応じた公共のサービスを受ける対価として捉えられます。
税率:市民税の税率は、住んでいる市町村によって異なります。市民税はその税率に基づいて計算され、住民の収入や資産に応じて支払いが決まります。
税務署:税務署は、税金の徴収や管理を行う機関です。市民税の申告や納付は、税務署を通じて行われることが一般的です。
税金控除:市民税には、特定の条件を満たすと受けられる税金控除が存在します。これにより、実際に納付する市民税の額が軽減される場合があります。
市町村:市民税を課税する主体である市町村は、地域住民に対するサービスを提供するための重要な役割を担っています。市町村の財政は市民税によって支えられています。
公共サービス:市民税は、地域で提供される公共サービスの財源となります。これには、教育、福祉、警察、消防などが含まれます。
市民税の対義語・反対語
該当なし
社会・経済の人気記事

8826viws

4459viws

4680viws

5101viws

6654viws

6373viws

4415viws

7874viws

5561viws

8494viws

6056viws

6358viws

5648viws
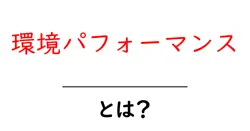
1165viws

6336viws

4989viws

5261viws

6361viws

8435viws

9056viws