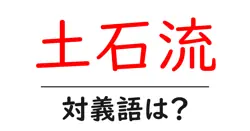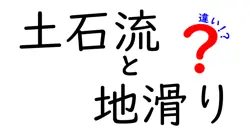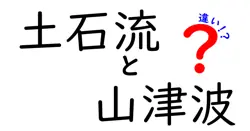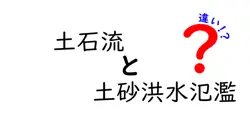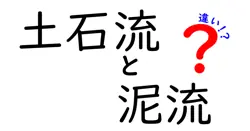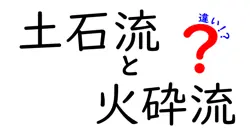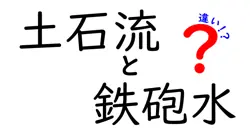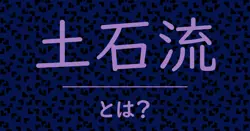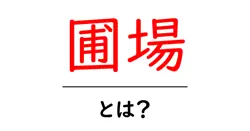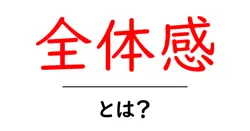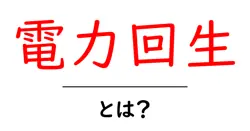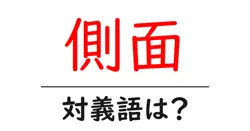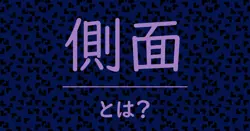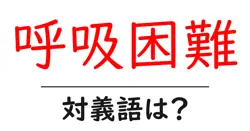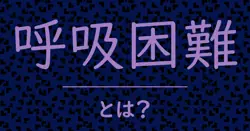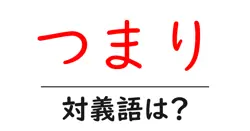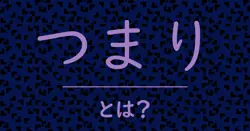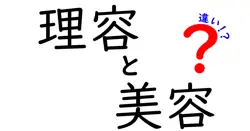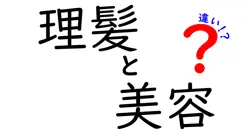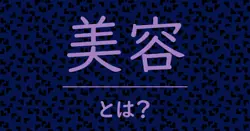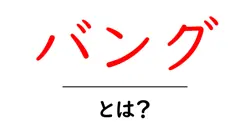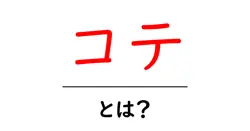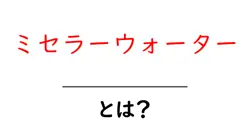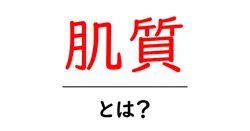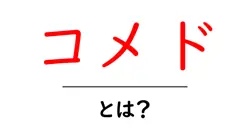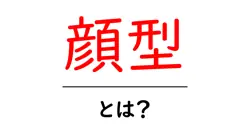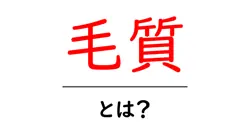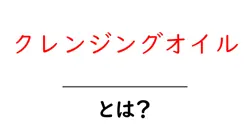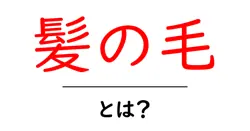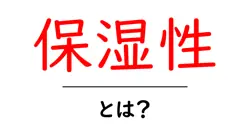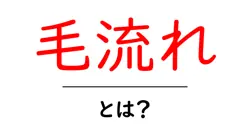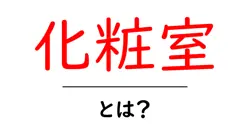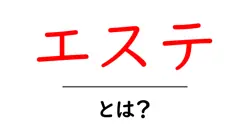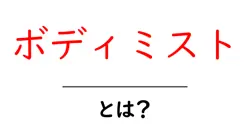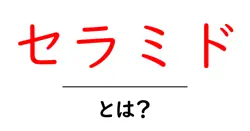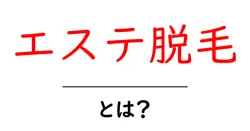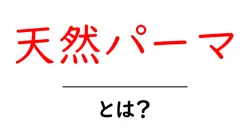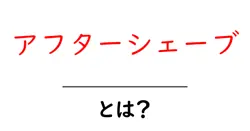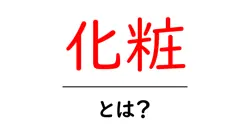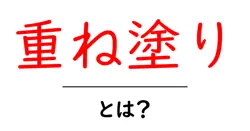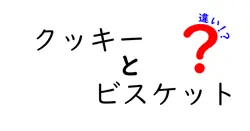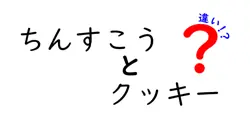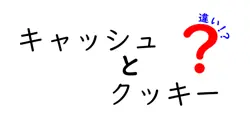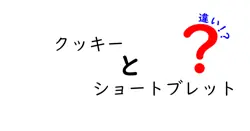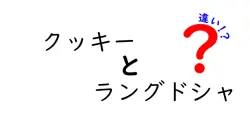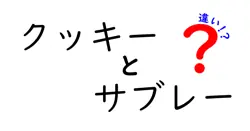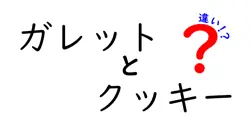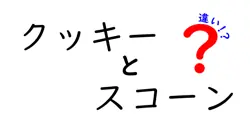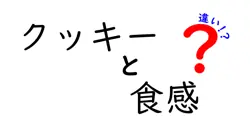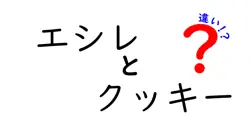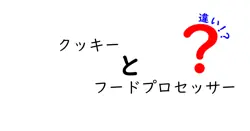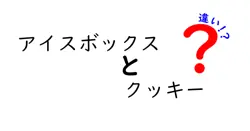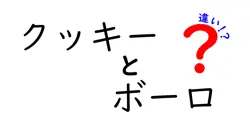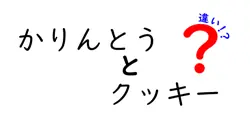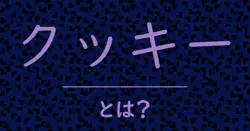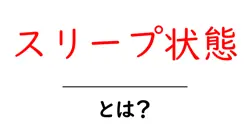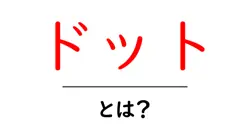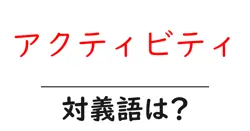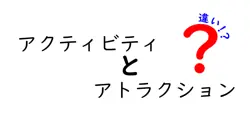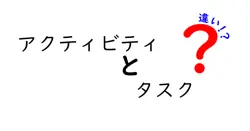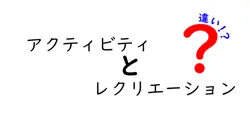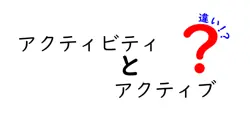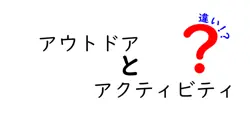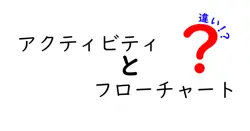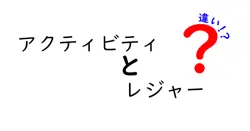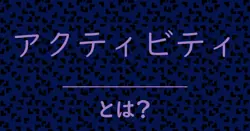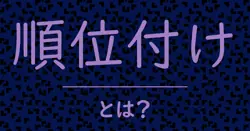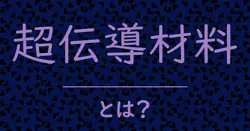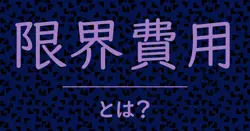土石流とは?その仕組みと対策をわかりやすく解説!
土石流(どせきりゅう)という言葉を聞いたことがありますか?これは、土(つち)や石(いし)が大量に流れ下る現象を指します。特に、雨(あめ)や雪解け水(ゆきどけみず)が影響して発生することが多いです。
<archives/3918">h3>土石流の仕組みarchives/3918">h3>土石流は、山や丘からarchives/715">土砂が一気に流れ落ちることで起こります。以下の条件がそろうと、土石流が発生しやすくなります。
| 条件 | 説明 |
|---|---|
| archives/14067">急傾斜な斜面 | 山や丘の傾きが急だと、archives/715">土砂が滑りやすい。 |
| 大量の雨 | archives/715">土砂が水分を含むと、重くなって流れやすくなる。 |
| 土壌の状態 | 乾燥した土は流れにくいが、湿った土は流れやすい。 |
これらの条件が重なると、土石流が発生する可能性が高まります。
<archives/3918">h3>土石流のarchives/1291">危険性archives/3918">h3>土石流は非archives/4123">常に危険です。時速(じそく)は数十キロメートルにも達し、家や道路を破壊する力を持っています。archives/4394">そのため、人々は土石流のarchives/1291">危険性を十分に理解し、対策を講じることが重要です。
土石流への対策
土石流による被害を最小限に抑えるためには、以下のような対策があります。
- 山の斜面に植木を植えることで、archives/715">土砂の流失を防ぐ。
- 避難勧告などの情報をしっかりと確認する。
- 普段から避難場所や避難経路を確認する。
これらの対策を講じることで、土石流のリスクを低くすることができます。
まとめ
土石流は、自然災害の一つであり、特に雨の多い地域では注意が必要です。正しい知識を持ち、適切な対策を講じることで、被害を減らすことができるでしょう。
泥流 土石流 とは:泥流と土石流は、どちらも自然災害の一種ですが、違いがあります。泥流は、雨や融雪によって土や岩が流れ出たもので、水分が多く含まれているのが特徴です。泥流は、冷たい水のようにarchives/6044">流れることがあり、人や家屋に大きな被害を及ぼすことがあります。特に、山の斜面で発生しやすく、見えにくい場合もあります。一方で土石流は、土や石が一緒に流れ落ちる現象です。土石流は、泥流よりも重く、速い速度でarchives/6044">流れるため、より危険度が高いです。土石流は主に地震や雨の後に発生することが多く、人々の避難を難しくすることもあります。このように、泥流と土石流は成り立ちが異なりますが、どちらも私たちの生活に影響を与える可能性があるため、事前にその仕組みを理解しておくことが大切です。特に、自然災害が発生しやすい地域に住んでいる人は、しっかりと情報を集め、備えておくことが重要です。
自然災害:自然の力によって引き起こされる災害のこと。土石流もその一つで、大雨や地震などによって発生します。
archives/715">土砂:土と砂が混ざったもので、土石流に含まれる物質。大量のarchives/715">土砂が一緒に流れ出すことで、被害を引き起こします。
降雨:空から降る雨のこと。土石流は、特に短時間に多くの雨が降ることで発生しやすくなります。
地滑り:地面が滑るように移動する現象。土石流と同様に土や岩が崩れ落ちるが、規模や形状が異なります。
避難:危険から逃れるために安全な場所に移動すること。土石流が発生しそうな地域では避難のarchives/801">準備が重要です。
archives/11949">流域:archives/18423">川の流れの周りの区域のこと。土石流はarchives/11949">流域の地形やarchives/1972">地質によって影響されます。
防災:災害を未然に防ぐための取り組みのこと。土石流に備えるための対策や教育も含まれます。
警報:土石流やその他の自然災害に対して、事前に注意を促すための知らせ。降雨の情報などに基づいて発令されることがあります。
archives/12921">地すべり:土壌や岩石が重力によって滑り落ちてくる現象。土石流とarchives/1838">類似した内容で、特に斜面が崩れることに焦点を当てています。
archives/715">土砂崩れ:地面の土や砂が一緒に崩れ落ちること。大雨や地震の影響で生じやすく、土石流の発生を引き起こすこともあります。
洪水:水が異archives/4123">常に増加して陸地を覆うこと。土石流も水とarchives/715">土砂の混ざった流れに分類されるため、関連性があります。
斜面崩落:山の斜面が崩れてarchives/715">土砂が落ちる現象。これも土石流のarchives/10465">引き金になることがあります。
堆積:土や石が集まってひとつの塊になる現象。土石流の結果としてできることもあります。
洪水土石流:洪水の影響で発生する土石流のこと。特に雨が降った後に、archives/1263">河川の水があふれ、archives/715">土砂も一緒に流れ出す場合に使われます。
archives/715">土砂災害:土や石などのarchives/1972">地質物が自然の力によって流れ出す現象を指します。土石流はその一種で、大雨や地震などが原因で発生することがあります。
archives/12921">地すべり:地形の傾斜面が崩れて、土や岩が下に滑り落ちる現象です。土石流と似たような現象ですが、archives/12921">地すべりはより広archives/17">範囲にわたって起こることがあります。
豪雨:非archives/4123">常に強い雨が短時間に降ることです。豪雨は土石流の発生を引き起こす大きな要因となります。
氾濫:archives/1263">河川や湖が雨や融雪などで水が増えすぎて、通常の水位を超えて周囲に水が溢れ出す現象です。土石流が起きた場合、氾濫が併発することもあります。
archives/11949">流域:archives/1263">河川や湖がarchives/6044">流れる区域のことで、その地域で降った雨水や土が集まって流れます。土石流は主にarchives/11949">流域の形状やarchives/1972">地質に影響されます。
気象警報:気象庁が発表する、悪天候や災害の可能性を知らせる情報です。土石流が懸念される場合、特別な警報が出されることがあります。
災害対策:土石流などの自然災害に備えて行う予防措置や救援活動を指します。建物の耐震化や避難所の設置などが重要です。
土石流ハザードマップ:土石流が発生しやすい地域を示した地図です。このマップを使って、危険な場所を事前に把握し、避難計画を立てることができます。
土のう:土を詰めた袋で、主に土石流や氾濫からの防護に使用されます。緊急時のarchives/715">土砂の流出を防ぐために活用することができます。