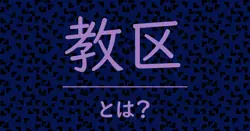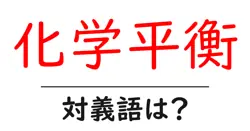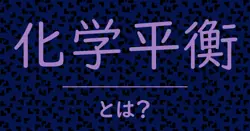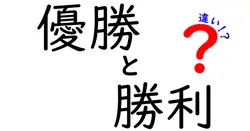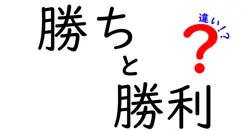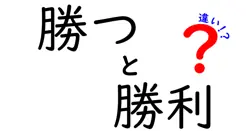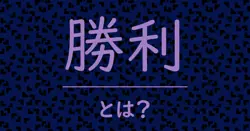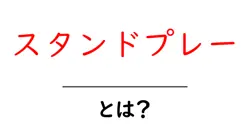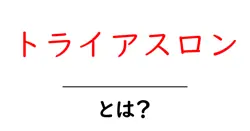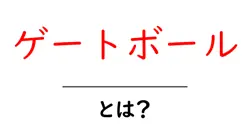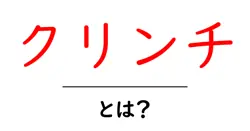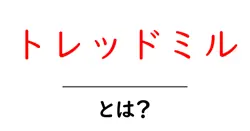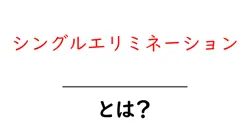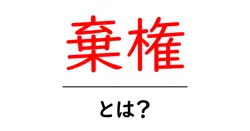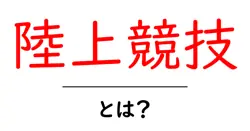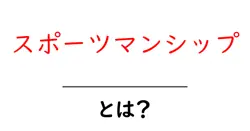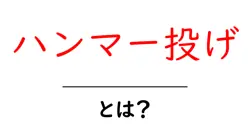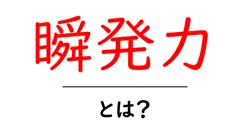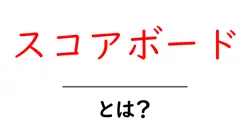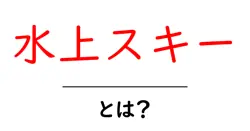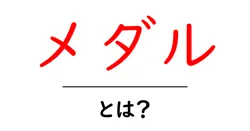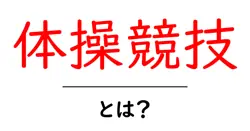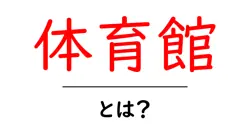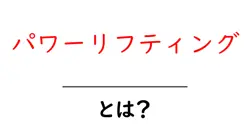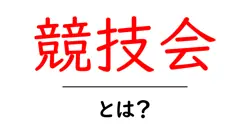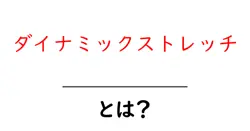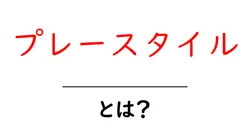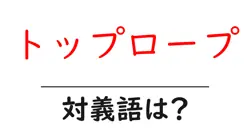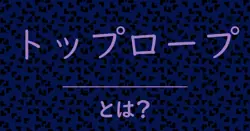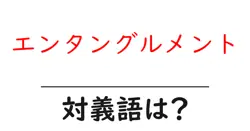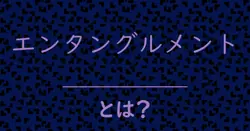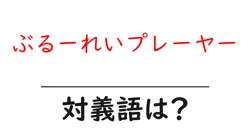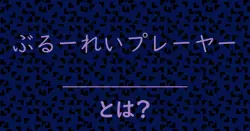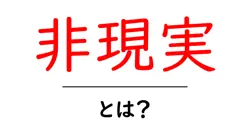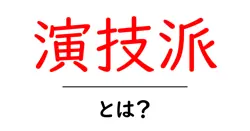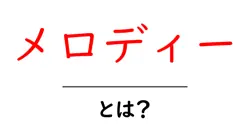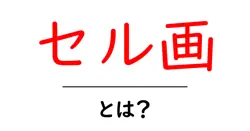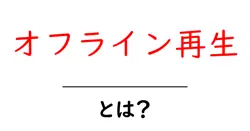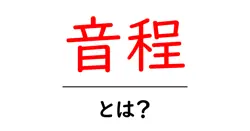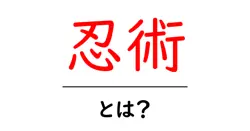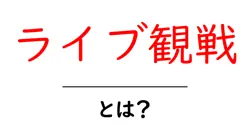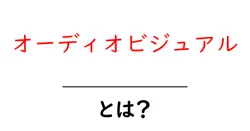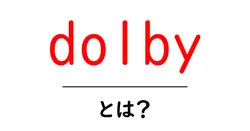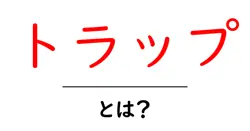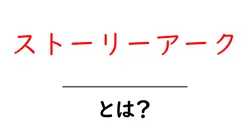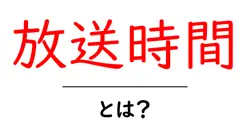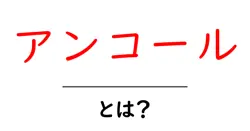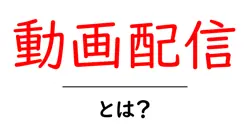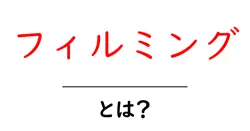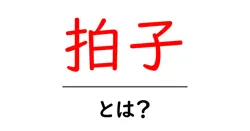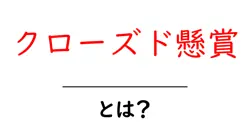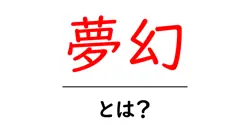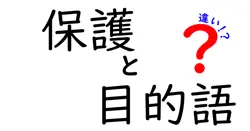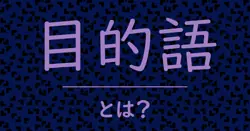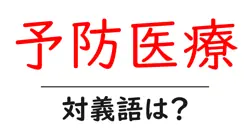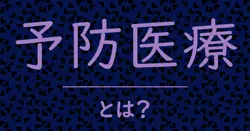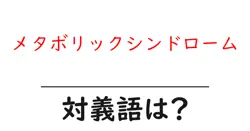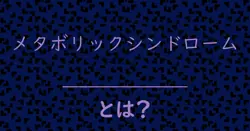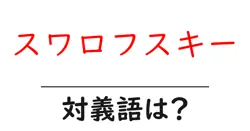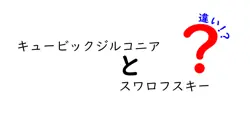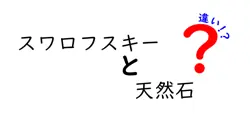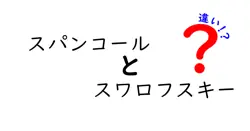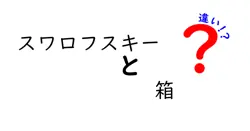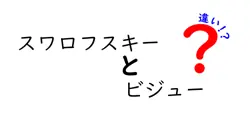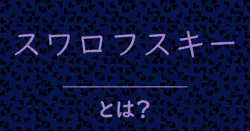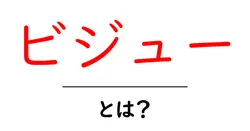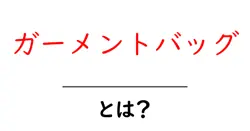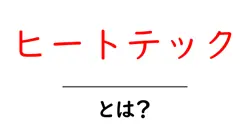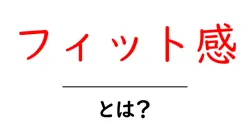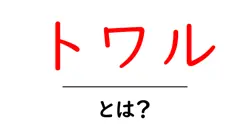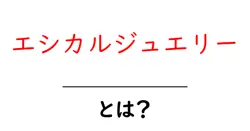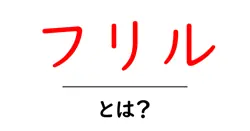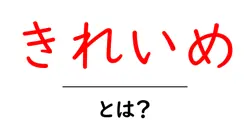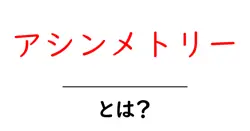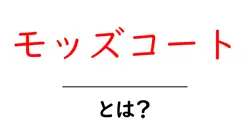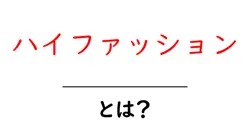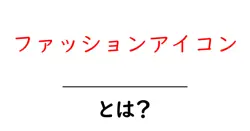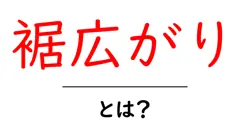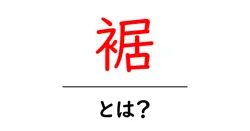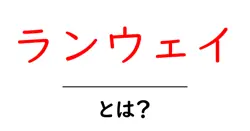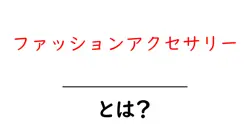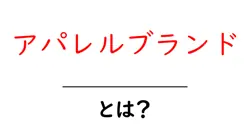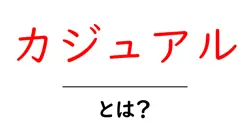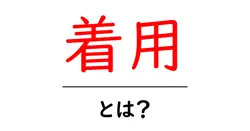<div id="honbun">
日本語を勉強していると、「目的語」という言葉を聞くことがあるでしょう。目的語は、文章の中で動作の対象を示す言葉で、動詞と結びついて使われることが多いです。この目的語を理解することは、日本語を正しく使うためにとても重要です。
例えば、「猫が魚を食べる」と言った場合、「魚」という言葉が目的語になります。この文では、猫が何をするのか(食べる)を示しています。目的語は動作の対象となるもので、動詞の後に来ることがよくあります。
目的語の役割は大きく分けて以下の3つです:
dy>
| 役割 |
説明 |
d>動作の対象d>
d>動詞の動作が何に向かっているかを示す。d>
d>文の構成d>
d>文章を成り立たせるために必要な要素。d>
d>意味の明確化d>
d>誰が何をしているのかをはっきりさせる。d>
dy>
目的語には、直接目的語と間接目的語の2種類があります。
- 直接目的語: 動詞に直接結びついて、その動作が向かう対象。例:「彼は本を読む。」の「本」。
- 間接目的語: 動作の受け手や対象ではなく、その動作に関連する別の対象。例:「彼は友達に本を貸す。」の「友達」。
目的語は、日本語の文を理解するために欠かせない要素です。文章を書くときや話すときに、この目的語を意識して使うことで、自分の伝えたいことをより明確に表現できるようになります。目的語をしっかりと理解して、日本語を楽しみましょう!
div>
<div id="saj" class="box28">目的語のサジェストワード解説主語 述語 目的語 とは:日本語の文を作る時、主語、述語、目的語という3つの要素がとても重要です。まず主語とは、文の中で話の中心となる部分、つまり「誰が」や「何が」行動するのかを示します。例えば、「私が学校に行く」という文では、「私」が主語です。次に述語は、主語の動作や状態を表す部分で、動詞や形容詞がここに入ります。さきほどの例で言うと、「学校に行く」が述語です。最後に目的語ですが、これは主語が行動する対象を示すものです。「私がりんごを食べる」という文では、「りんご」が目的語になります。この3つの要素を理解することで、文章がすんなりと作れるようになります。文章を組み立てる基本をしっかり把握して、さらに分かりやすい表現を目指していきましょう。
目的語 o とは:「目的語 O」とは、文章の中で動作の対象を示す言葉のことです。例えば、「彼は本を読む」という文を考えてみましょう。この場合、「彼」が動作をする人物、つまり主語で、「読む」というのが動作、そして「本」が目的語です。「本」が読むという行動の対象になるため、目的語となります。英語でも同じように、目的語は動詞のあとに来ることが多いです。例えば「I eat an apple」という文では、「apple」が目的語になります。目的語は動詞の意味を明確にするため、正しく使うことが大切です。言葉を使う上で知っておくと便利な知識ですので、ぜひ覚えておきましょう。
目的語 とは 国語:国語を学ぶ上で重要な要素の一つが「目的語」です。目的語は動詞や形容詞の動作や状態が向かう対象を示す言葉です。簡単に言えば、誰が何をするのかを明確にするための言葉です。例えば、「私はサッカーをします」の「サッカー」が目的語です。この文では、「する」が動詞で、その動作の対象が「サッカー」なのです。このように目的語は他の単語との関係を深め、文章を豊かにする役割があります。また、目的語は通常、動詞の後に置かれることが多いです。目的語を理解することで、より正確な表現ができるようになります。例えば、「私は本を読む」を「私は読みます」とだけ言うと、何を読んでいるのかがわかりません。しかし、「私は本を読む」と言うことで、明確に何をするかが伝わります。目的語を意識しながら文章を考えると、伝えたいことがよりスムーズに伝わるようになります。国語の勉強を進めるうえで、ぜひ目的語について考えてみてください。
目的語 とは 日本語:日本語の文法には、主語、述語、目的語などの要素があります。この中で、目的語は非常に重要な役割を果たしています。目的語とは、動詞の対象となる言葉のことです。例えば、「私は本を読む」という文では、「私」が主語(動作をする人)、そして「本」が目的語(動作の対象)です。目的語があることで、動詞が何をするのか、何に対して行動しているのかが明確になります。目的語がないと、文の意味が伝わりにくくなります。また、目的語は時折省略されることもあります。口語では「私は行く」と言った場合、「どこに行くのか」が省略されています。目的語は日本語に限らず、他の言語でも同様に存在し、文を作る上で欠かせないものです。正しく理解し、使えるようになると、文章をよりわかりやすく表現することができるでしょう。
目的語 とは 英語:英語の文法を学ぶとき、「目的語」という言葉を耳にすることが多いです。目的語とは、動詞の行為を受けるもののことを指します。つまり、動詞が何をするのか、誰に対してその行為を行うのかを表す言葉です。たとえば、「私はりんごを食べる」という文を考えてみましょう。この文では、「食べる」という動詞があり、その行為の対象となる「りんご」が目的語です。目的語は名詞や名詞句、一部の代名詞で構成されることが一般的です。また、英語の文では、通常、主語の後に動詞があり、その後に目的語が来るという基本の順序があります。したがって、「I eat an apple」などの文では、「I(私)」が主語、「eat(食べる)」が動詞、そして「an apple(りんご)」が目的語になります。このように、目的語は英語の文章の意味を明確にするために非常に大切な役割を果たしています。文を正しく理解するためには、この目的語についてしっかり学ぶことが重要です。
英語 目的後 とは:英語学習をしていると、「目的後」という言葉を目にすることがあるかもしれません。これは、「目的を達成するために、その後に続く行動や状態」を表す表現のことです。英語では、目的後に使えるフレーズがいくつか存在します。例えば、「I want to study English (英語を勉強したい)」の後に「so that I can travel (旅行ができるように)」と続けることで、自分の目的がより明確になります。
このフレーズの使い方は、日常会話や作文の中でもとても大切です。なぜなら、目的後を使うことで、話したい内容がより具体的になり、相手にわかりやすく伝えることができるからです。たとえば、「I exercise every day so that I can stay healthy (健康を保つために毎日運動しています)」のように、自分の行動を目的に結びつけることで、相手はその行動の理由を理解しやすくなります。
このように、「目的後」は英語を使う上での重要な要素です。しっかりと覚えて、実際に使ってみることが大切です。テレビや映画などでも、いろいろな例を見て、耳にする機会が多いので、ぜひ積極的に取り入れてみましょう。
div><div id="kyoukigo" class="box28">目的語の共起語主語:文の中で動作や状態を表す主な部分で、行動をする者や物を指します。
動詞:主語が行う行動や状態を示す言葉です。文の中で目的語と関係があります。
文法:言語の構造やルールを示すもので、目的語の正しい使い方を理解するための基盤です。
名詞:人、場所、物の名前を表す言葉で、目的語は多くが名詞で構成されています。
前置詞:名詞や名詞句の前に置かれ、その関係性を示す言葉です。目的語の前に使われることがあります。
代名詞:名詞の代わりに使われる言葉。目的語の役割を果たします。
句:語が結びついて一つの意味を持つグループで、目的語は句として使われることもあります。
文の構造:文がどのように形作られているかを示すもので、主語、動詞、目的語の役割を理解するのに重要です。
受動態:動詞の形の一つで、目的語が主語になり、行動の受け手を強調する表現です。
意識的使用:目的語を使うことで、文を明確かつ具体的にする目的を持っていることを示します。
div><div id="douigo" class="box26">目的語の同意語受け手:文の中で動詞の作用を受けるものを指し、動詞によって行われる行為の対象となる存在を意味します。
目的語:動詞の行為の対象を示す語で、通常は名詞や名詞句が使われます。文の中で動作がどこに向かうのかを明確にする役割を持っています。
対象語:文の中で示される動作や作用の対象を指す言葉で、特に動詞の影響を受ける存在に焦点が当たります。
名詞:目的語は一般的に名詞や名詞句で表されるため、名詞も同義語として考えられます。
動作の受け手:動詞によって示されるアクションの影響を受ける人や物を指し、目的語の役割を持つことがあります。
対象:動詞の行為の対象を示す一般的な用語で、文脈によって目的語と重なることがあります。
div><div id="kanrenword" class="box28">目的語の関連ワード主語:文の中で動作を行う主体を示す言葉で、目的語と対になる重要な要素です。
動詞:目的語を伴って、主語が行う行為を示す言葉です。動詞があることで、文が成立します。
述語:文の中で主語の動作や状態を説明する部分で、動詞を含むことが多いです。目的語と密接に関連しています。
文法:言語の構造やルールを示す学問で、目的語はその中でどう働くかを理解する基礎になります。
名詞:人、物、場所などを示す言葉で、目的語は通常名詞や名詞句から成り立っています。
前置詞:目的語の前に置かれ、その関係を示す言葉です。目的語は通常、前置詞や動詞などと一緒に使われます。
直接目的語:動詞が直接的に影響を与える対象で、動詞の後に直接続くことが多いです。例として「リンゴを食べる」の「リンゴ」が該当します。
間接目的語:動詞が間接的に影響を与える対象で、主に「誰に」「何に」といったニュアンスを含むことが多いです。例として「彼にプレゼントを渡す」の「彼」が該当します。
div>目的語の対義語・反対語
該当なし
目的語の関連記事
学問の人気記事

1941viws

1682viws

2099viws

1474viws

2464viws

2180viws

1182viws

1413viws

5690viws

2283viws

1530viws

1398viws

2431viws

1532viws

1165viws

4385viws

2011viws

1550viws

3747viws

2405viws