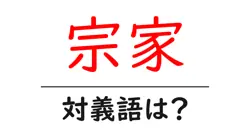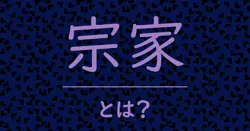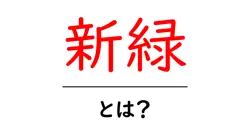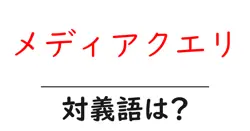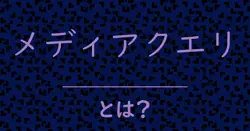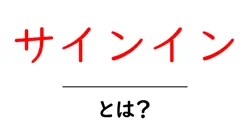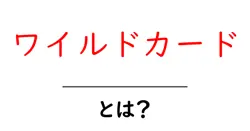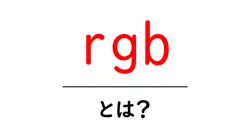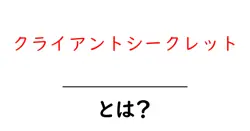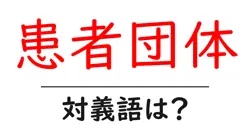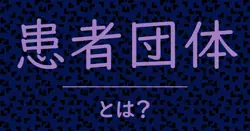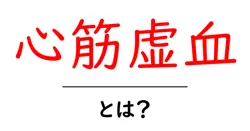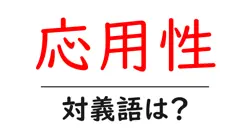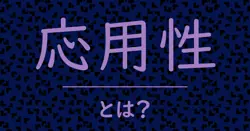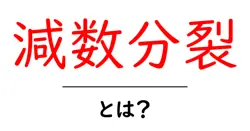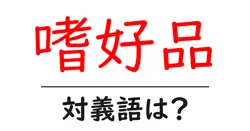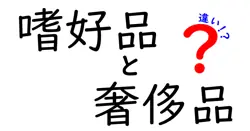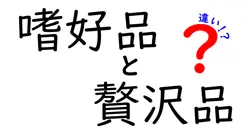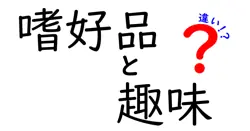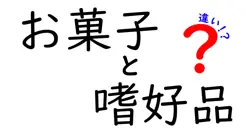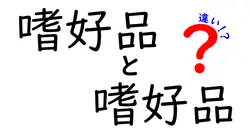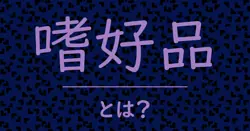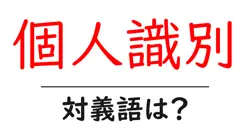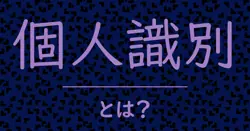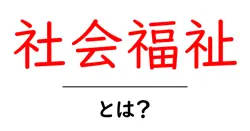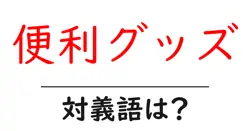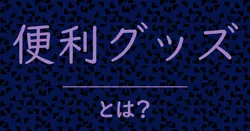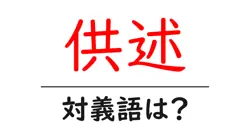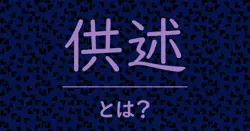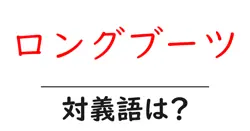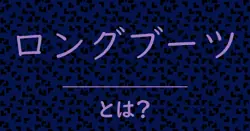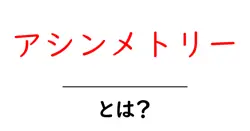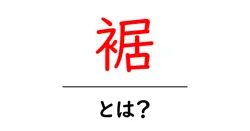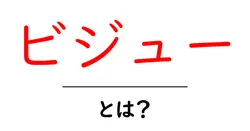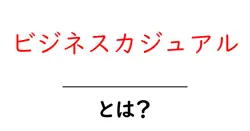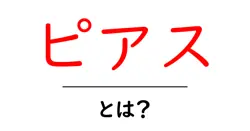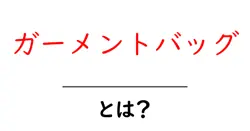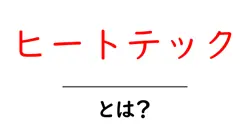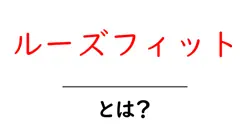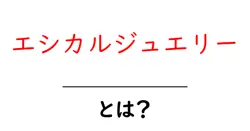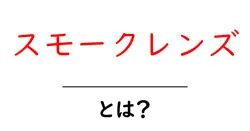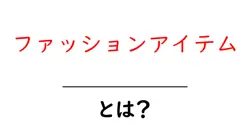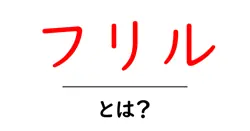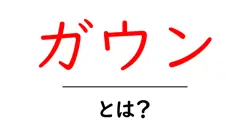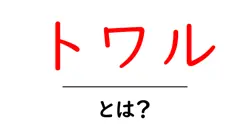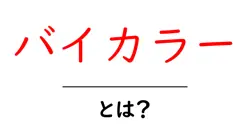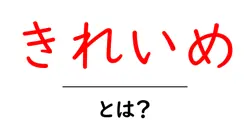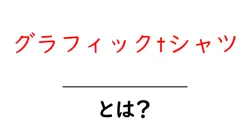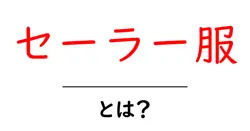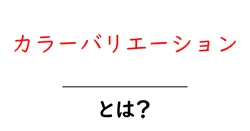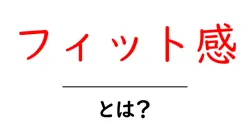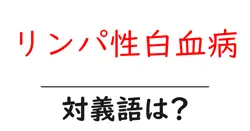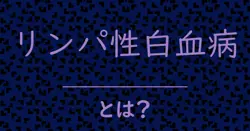宗家とは?その意味と日本の伝統文化における役割を解説!
「宗家(そうけ)」とは、日本の伝統文化の中で重要な役割を果たす言葉です。特に、武道や芸道、茶道、さらには伝統的な料理や芸能においても、宗家の存在はとても大切です。この言葉の意味や背景について、中学生でも理解しやすいように解説していきます。
宗家の基本的な意味
宗家とは、ある派閥や流派のトップや代表者を指します。特に、古くから伝わる技術や知識を継承している人のことを指すことが多いです。宗家はその流派の教えや技術を継承し、次の世代に伝える役割を担っています。また、宗家は単に技術だけでなく、流派の精神や理念も引き継いでいくことが重要です。
宗家の歴史と文化的背景
日本の歴史の中で、宗家という役割は非常に古くから存在しています。武士の時代や、江戸時代には、多くの流派が成立し、それぞれの宗家が登場しました。特に武道においては、その流派の代表者として、宗家が存在し、技術や理念を守り続けました。
例:武道における宗家
たとえば、剣道や空手などの武道では、宗家がその流派の技術や理念を引き継いでいます。宗家は、その流派の正式な認定を受けることが多く、流派の名称の由来ともなります。宗家が大会や競技で活躍することで、流派の名声も高まります。
宗家と弟子の関係
宗家にとって最も重要なのは、弟子たちを育てることです。弟子は宗家から教えを受け、その技術や理念を学びます。優れた弟子が育てば、宗家の名声も高まります。宗家は確かな技術を持つだけでなく、人間的な側面でも弟子を支える存在でなければなりません。
宗家と地域社会
宗家は流派の枠を超えて、地域社会にも影響を与えます。多くの宗家が地域に根ざした活動を行い、地域の文化やイベントに参加することで、伝統文化の普及に貢献しています。例えば、地域のお祭りやイベントでパフォーマンスを行うことがよくあります。
宗家の現代における役割
現代においても、宗家はその重要性を失っていません。むしろ、情報化社会の中で、宗家の役割はますます重要になっています。流派や伝統文化を守るために、積極的に活動し、若い世代にその魅力を伝えることが求められています。
まとめ
宗家は、日本の伝統文化において不可欠な存在です。技術や理念を継承し、弟子を育てることで、文化の未来に大きく貢献しています。私たちも宗家の存在を知ることで、もっと日本の伝統文化を理解し、応援していきましょう。
分家 宗家 とは:分家(ぶんけ)と宗家(そうけ)は、家族や親族の関係を表す言葉です。分家は、親の家から独立して新しい家を築くことを指します。例えば、兄弟がそれぞれ自分の家を持つことが分家です。一方、宗家は、その家の中心となる家、つまり先祖の家を指します。宗家は家族の代表として、伝統や文化を守る役割があります。たとえば、大きなお祭りや行事では宗家が重要な役割を果たすことがあります。分家は新しい生活を始めることで、家族のつながりを広げる役割を持ち、宗家はそのつながりを大切に保つ役割を果たしています。このように、分家と宗家は家族の築き方や伝統の維持において、それぞれ異なった大切な役割を持っているのです。家族の歴史を理解することで、自分のルーツを深く知ることができます。
宗家 とは 本家:「宗家」と「本家」という言葉は、日本の伝統文化において非常に重要です。まず、宗家(そうけ)とは、ある特定の家系や流派の中心的存在を指します。例えば、茶道や武道のような伝統的な技術や文化を家系で受け継ぐ場合、その流派の宗家が存在します。一方、本家(ほんけ)は、ある家系や家族の中で、特に重要な位置を占める家を意味します。本家は、親から受け継いだ土地や家を持っていることが多く、家族の中心としての役割を果たします。 宗家と本家は似たような意味を持っていますが、少し異なる役割があります。宗家は流派や技術の「リーダー」的な存在で、本家は家族の「中心」であると言えます。日本のさまざまな文化や伝統を理解するためには、こういった言葉や概念を知っておくことが大切です。特に、武道や茶道などの習い事をする際には、宗家や本家について学ぶことが、より深い理解につながります。
宗家 とは 韓国:韓国には「宗家(宗家)」という言葉があります。この言葉は、祖先が伝えた伝統の味や技を受け継ぐ家族や流派を指します。特に、食文化や工芸品の分野でよく使われます。たとえば、韓国の伝統料理であるキムチやビビンバを作る際、そのレシピや方法を代々受け継いでいる家族があります。こうした家族は、長い時間をかけて培った技術を大切にし、後世に伝える役割を担っています。宗家は単なる家族だけでなく、地域や文化を象徴する存在でもあります。たとえば、特定の地域で有名な料理の宗家は、その地域の伝統を語る大切な存在です。韓国では、宗家の考え方が非常に重視されており、料理を通じて文化が継承されていく様子が見られます。最近では、宗家の技術を学ぶために訪れる若者が増え、伝統を守りつつ新しい風を取り入れる動きも見られています。つまり、「宗家」とは、単に古いものを守るだけでなく、未来に向けて変化することも大事なのです。
歌舞伎 宗家 とは:歌舞伎の宗家とは、歌舞伎の世界で重要な役割を果たす家系や家のことを指します。歌舞伎は、日本の伝統的な演劇で、色鮮やかな衣装や独特な演技、豪華な舞台が特徴的です。その中でも宗家は、特定の演技スタイルや演目を守り継承する責任があります。具体的には、代表的な宗家の一つには「市川宗家」や「尾上宗家」があります。それぞれが伝統の中で独自のスタイルを持ちながら、歌舞伎を未来に伝えていく役目を担っています。演者たちは、宗家から技術や知恵を学び、その芸を受け継いで次の世代へと発展させていきます。また、歌舞伎の公演では宗家の名前を冠することで、その名家の技術と伝統が大切にされていることを示しています。このように、歌舞伎の宗家は、ただの家系ではなく、日本の文化を守り続ける大切な存在なのです。歌舞伎に興味がある方は、宗家が果たす役割を知ることで、さらに深くその魅力を感じられるでしょう。
家元:伝統芸能や武道などで、その技術や流派の代表者や指導者を指します。「宗家」と似た意味合いで使われることが多いです。
流派:特定の技術や芸術のスタイルを持つグループや学校のことを指します。「宗家」はその流派の頂点に立つ存在となることが一般的です。
伝統:古くから受け継がれてきた文化や技術のことを指し、宗家はこの伝統を守り、次世代に伝える役割があります。
弟子:宗家の元で学ぶ人や、その流派の技術を受け継ぐ者のことです。弟子は宗家から直接指導を受けることで、その技術を磨きます。
技術:特定の分野における専門的な知識や技能のこと。宗家はその技術を高め、保持する権威と責任を担っています。
系譜:ある伝統や流派における血統や師弟関係の歴史的な繋がりを示すもの。宗家はこの系譜の中心に位置する役割を持ちます。
儀式:特定の文化や宗教において、重要な出来事や節目を祝うために行われる形式的な行動。宗家が関与することが多いです。
継承:伝統や技術を次世代に受け継ぐことを指し、宗家はこの継承の中心的な役割を果たします。
技法:特定の技術や創作手法を指し、宗家はその技法の最高峰を示す存在となります。
教義:宗教や哲学などの基本的な信念や教えを指します。宗家の持つ教義は、その流派の根幹を成すものとなります。
家元:伝統的な技術や芸術の流派において、指導的な立場にある人。継承者であり、流派の代表者とも言える。
宗匠:特定の技芸や宗教の分野において、深い知識と技術を持ち、その分野の指導者として尊敬される人。
創始者:特定の流派や団体を創り上げた人。新しい考え方や技術を広める役割を担う。
流派の代表:特定の流派を代表し、その指導や運営を行う人。流派の顔とも言える存在。
指導者:教えたり指導したりする立場にある人。特定の技術や知識を生徒や弟子に伝える役目を持つ。
流派:特定の技術や思想を継承し、教えを広める集団やスタイルのこと。宗家はこの流派の中心的存在です。
師範:技術や知識を教える立場にある人。宗家の直弟子やその上の地位にある者が師範と呼ばれます。
継承:宗家が持つ技術や理念を次の世代に受け渡すこと。このプロセスは、流派の存続において非常に重要です。
伝統:時間を経て継承されてきた技術や文化。宗家はこの伝統を守りながら新しい発展を目指します。
道場:武道や芸術を学ぶ場所のこと。宗家が経営する道場で技術が学ばれます。
弟子:師匠から技術や知識を学ぶ人。宗家のもとで修行を積むことが多いです。
技術:特定の技能や知識のこと。宗家はその技術を体系化し、教える役割を果たします。
名跡:家系や流派の象徴となる称号や名前。宗家はしばしば伝統的な名跡を持っています。
教義:流派や宗家が持つ教えや信念のこと。宗家はその教義を守り、後継者に伝える役割を担います。
門弟:宗家に属する弟子たちのこと。彼らは宗家から直接指導を受け、成長することを目的としています。