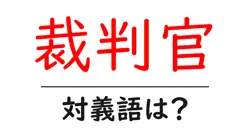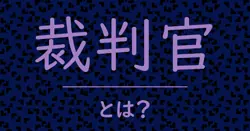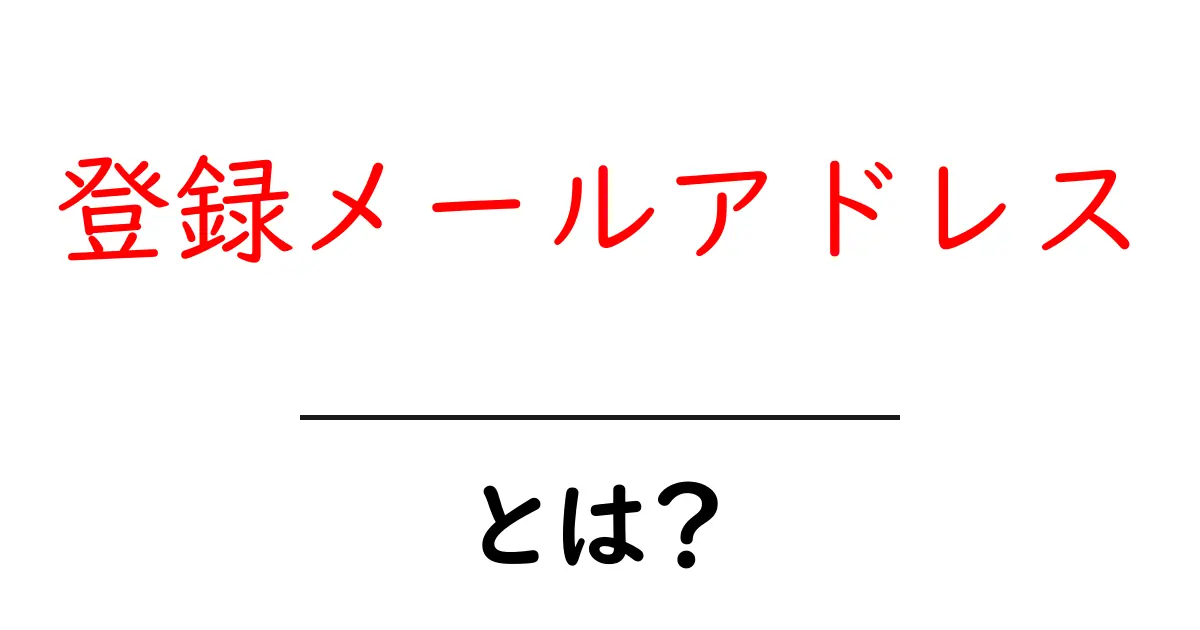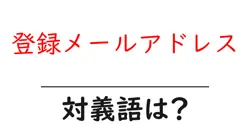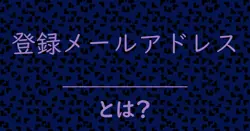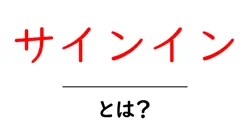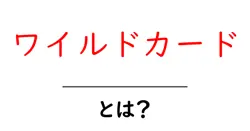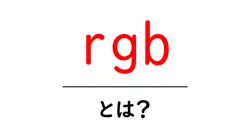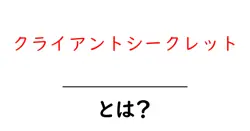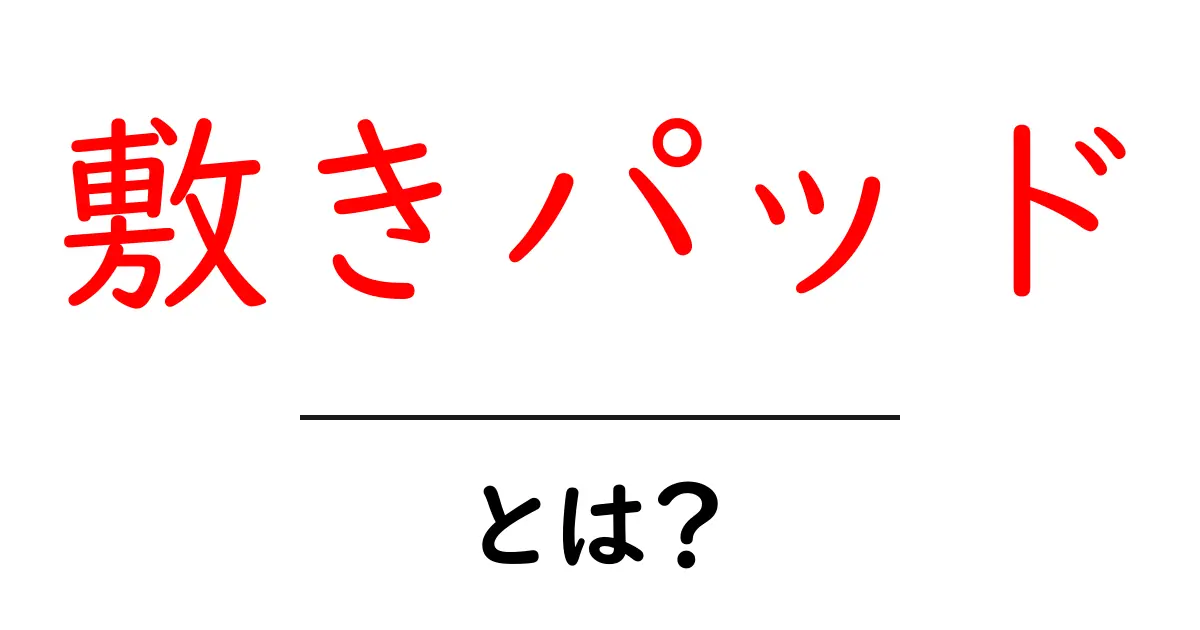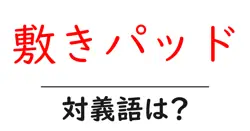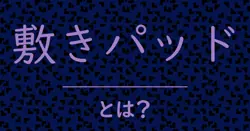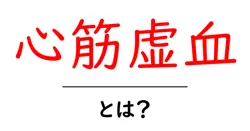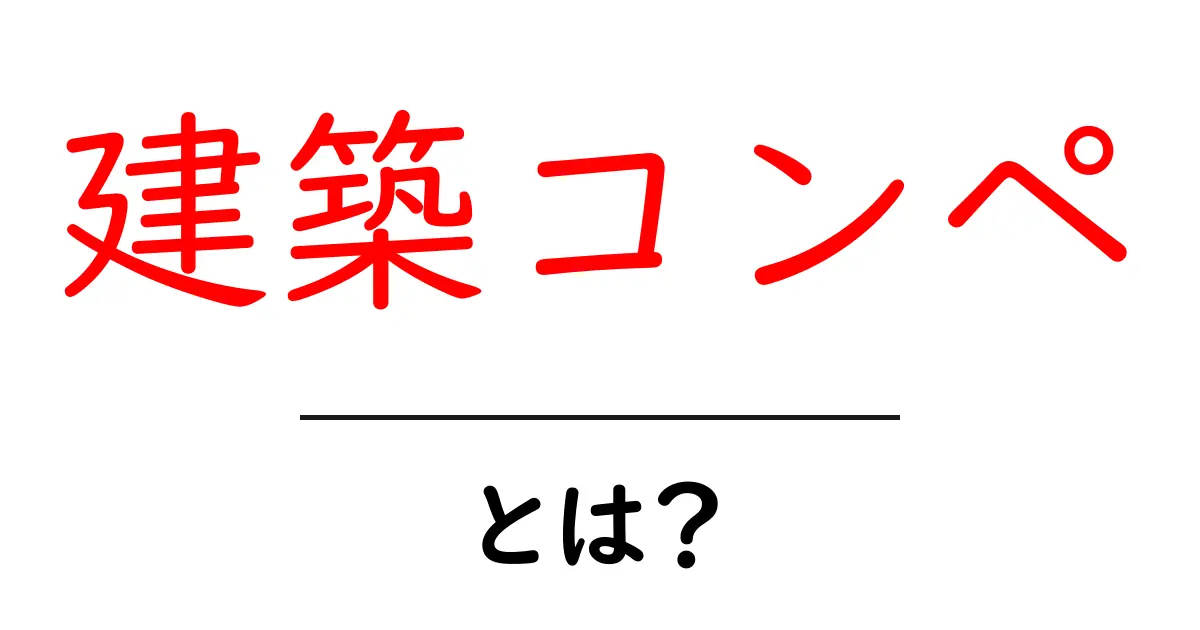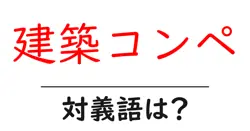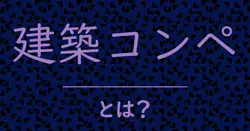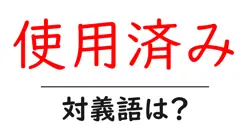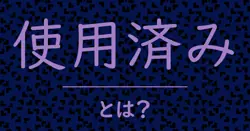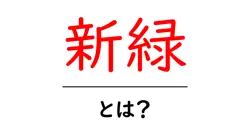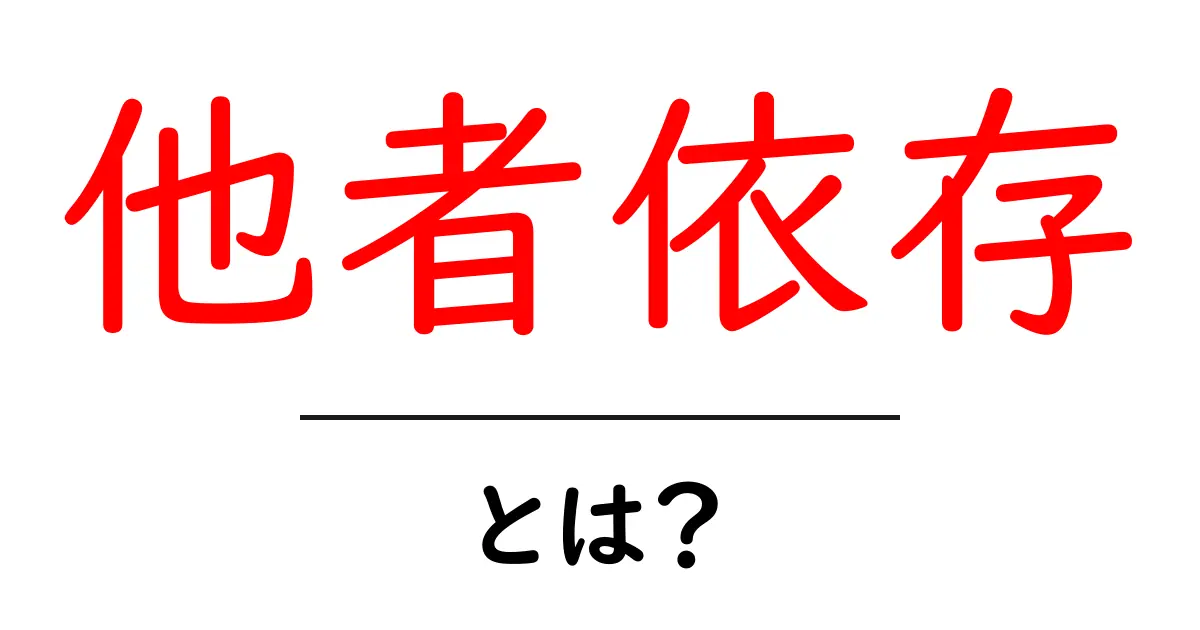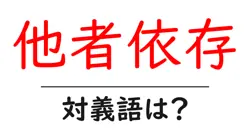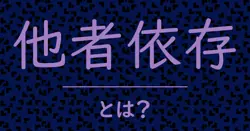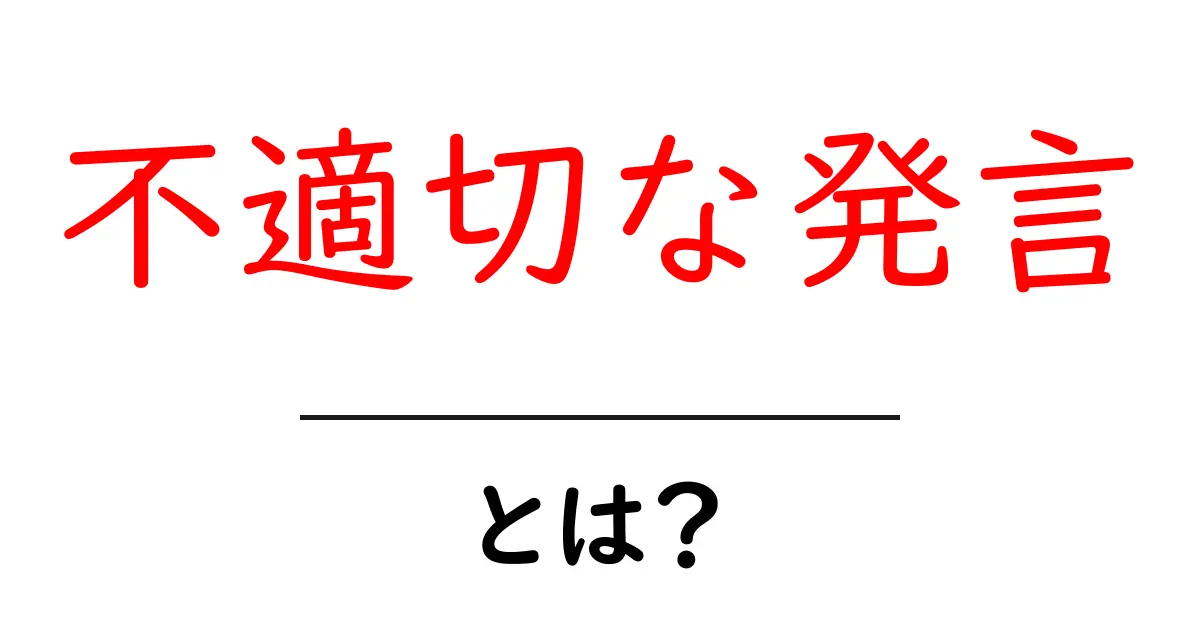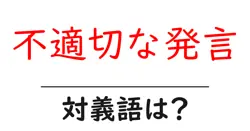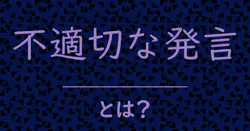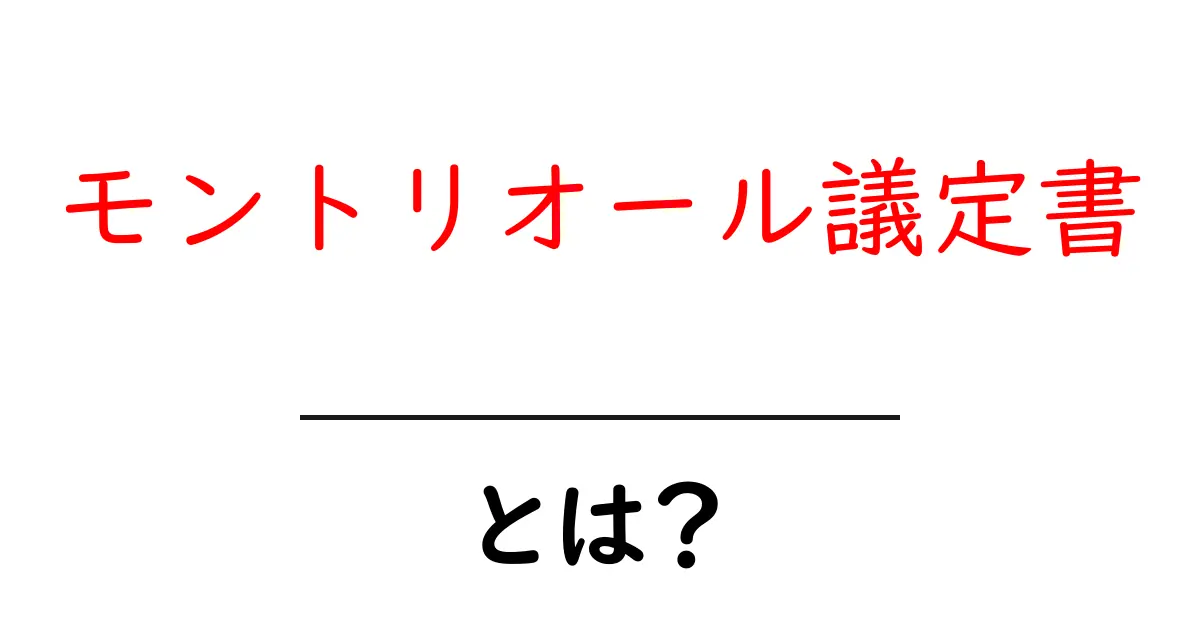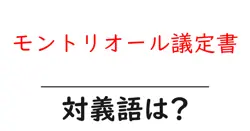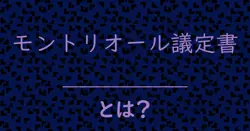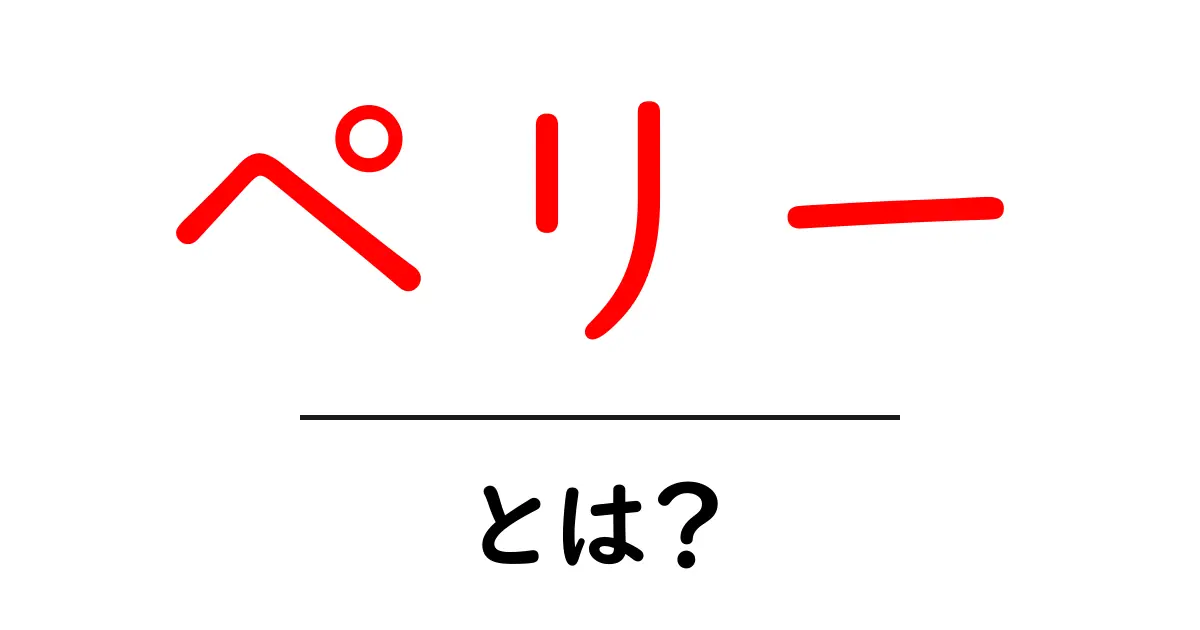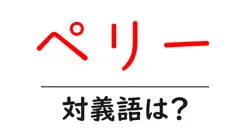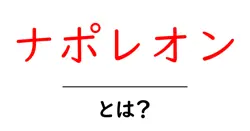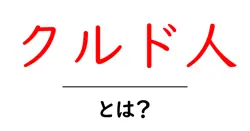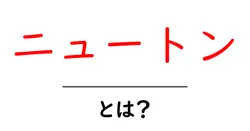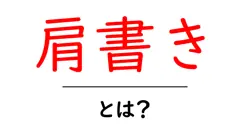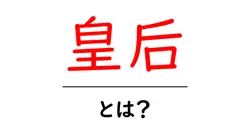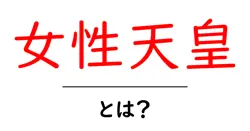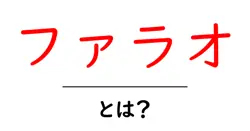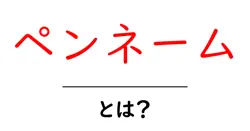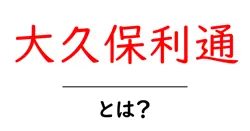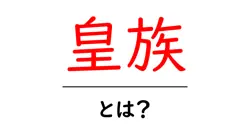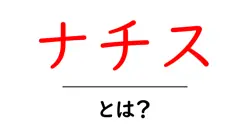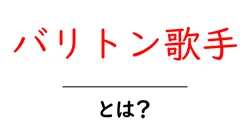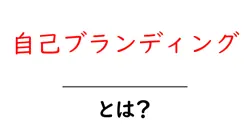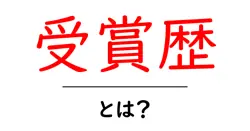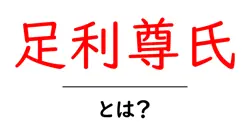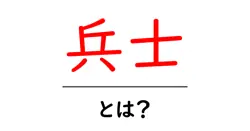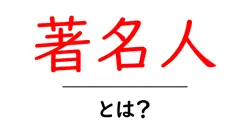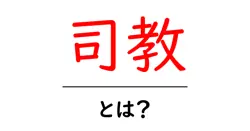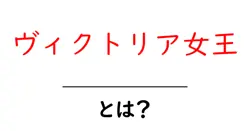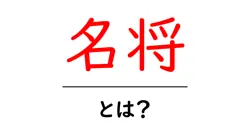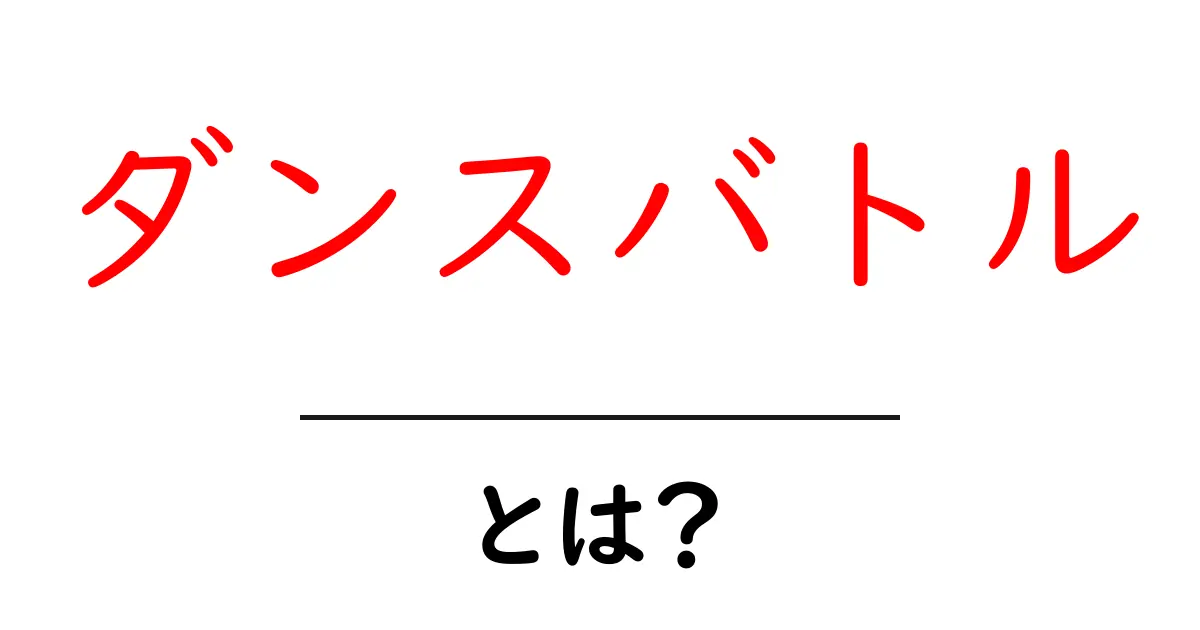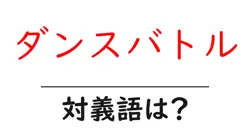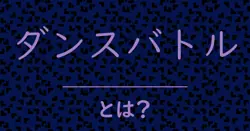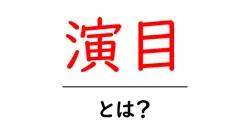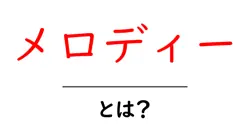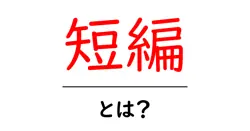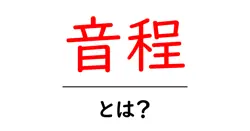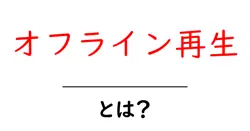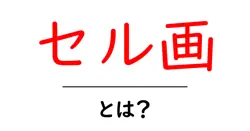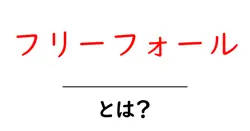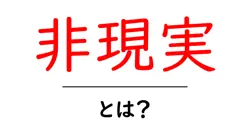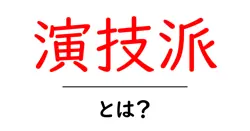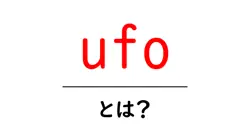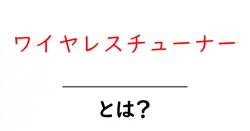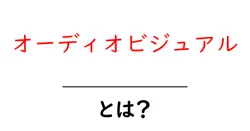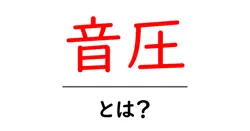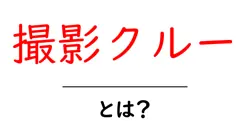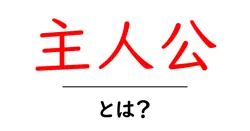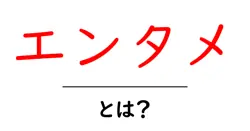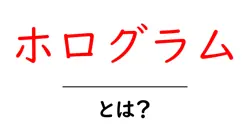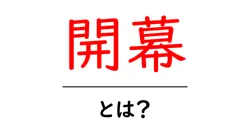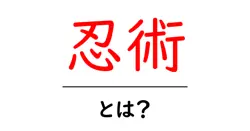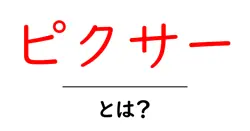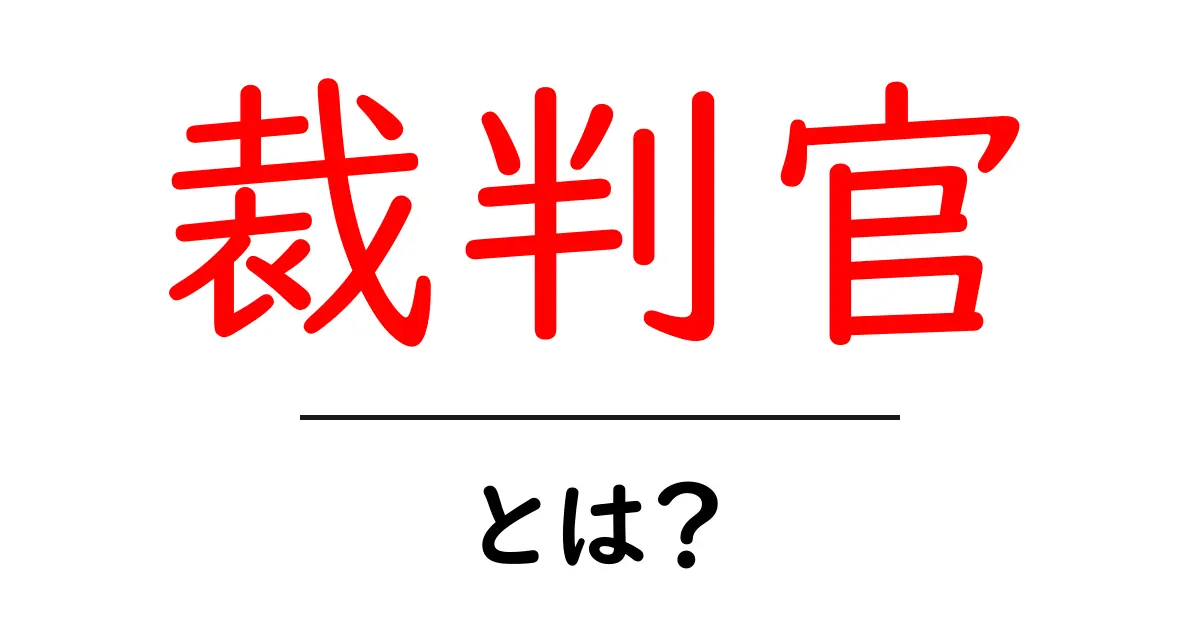
裁判官とは?
裁判官は、裁判所で法律に基づいて判断を下す者のことです。通常、裁判官は、刑事事件や民事事件、行政事件など、さまざまな種類の事件を扱います。この記事では、裁判官の役割、その仕事内容、そして裁判官になるための道について詳しく説明します。
裁判官の役割
裁判官の主な役割は、法律を踏まえた判断を行うことです。具体的には、次のような仕事をしています。
| 役割 | 説明 |
|---|---|
| 証拠の分析 | 事件に関する証拠や証言を確認し、どの情報が正しいかを判断します。 |
| 法律の解釈 | 法律の文言を参考にしながら、事件にどの法律が適用されるのかを考えます。 |
| 判決の作成 | 事件の結果に基づいて、どのような判決を出すかを決定し、その理由を明確に書きます。 |
裁判官になるための道
裁判官になるためには、次のステップがあります。
教育と資格
まず、法律を学びます。大学で法学を専攻し、法律についての知識を深めることが重要です。その後、司法試験を受けて合格しなければなりません。
司法修習
司法試験に合格した後は、司法修習と呼ばれる実務研修を受けます。ここで、実際の裁判や法律実務を学びます。
裁判官としての任命
修習を終えると、裁判官としての任命を受けることができます。その後は、各地の裁判所で勤務することになります。
裁判官の重要性
裁判官は、社会の公正や正義を守るために非常に重要な役割を担っています。彼らの判断は、個人や企業の権利に大きな影響を与えるため、しっかりとした知識と経験が求められています。
裁判官は、法律を守るためだけでなく、社会全体の信頼を高める役割も果たしています。そのため、彼らの仕事は非常に重要です。
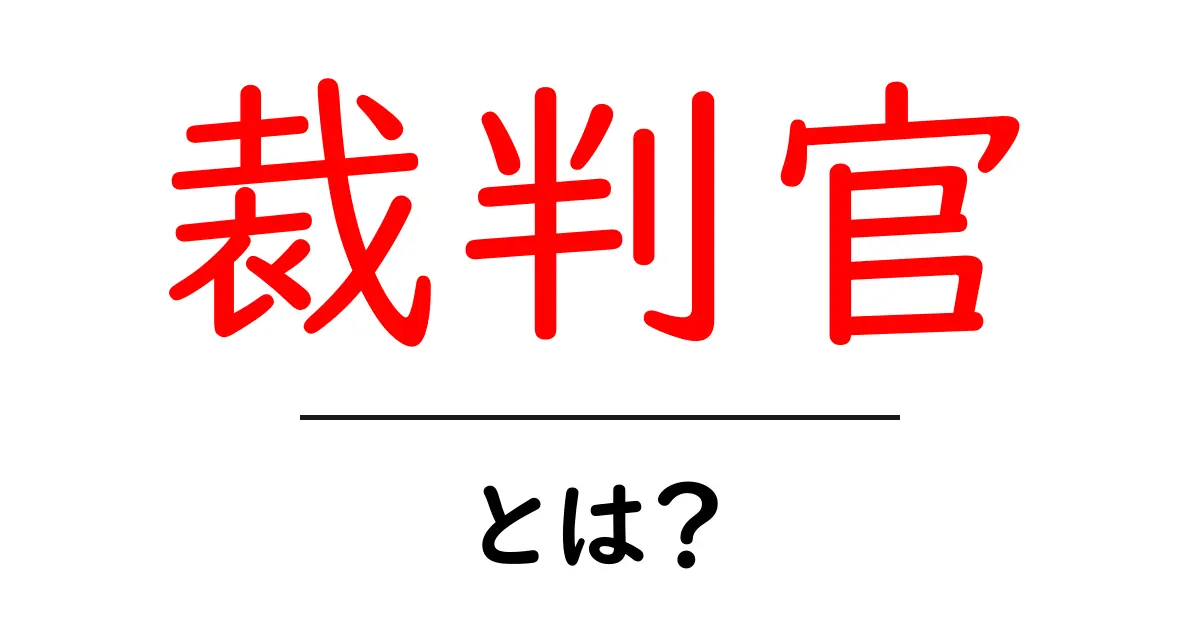
裁判官 とは 簡単に:裁判官とは、法律に基づいて法律を守るための判断を行う人のことです。特に、裁判所で事件を審理する役割を持っています。裁判官は訴えを聞き、証拠を見て、その上で誰が正しいかを決めます。日本では、裁判官になるためには多くの勉強が必要です。法律の専門知識だけでなく、公正さや判断力も求められます。裁判官の仕事はとても大切で、正義を守るためにシビアな判断を行います。裁判官は、刑事事件や民事事件などさまざまな事件を扱い、時には大きな社会問題に直面することもあります。例えば、犯罪者を裁く時には、被害者の気持ちや社会全体の安全を考慮しなければなりません。また、裁判官は法律に従って判決を下すため、個人的な感情に影響されないようにしなければなりません。このように、裁判官は法律に従いながら、公正で正しい判断を下す重要な役割を担っています。
裁判官 依願退官 とは:裁判官の依願退官とは、裁判官が自分の意思で職を辞めることを指します。通常、裁判官は定年まで職務を全うすることが求められますが、どうしても辞めたい理由がある場合に、依願退官を申し出ることができます。例えば、家庭の事情や健康問題、他のキャリアを追求したいなど、様々な理由があります。 依願退官の手続きは、まず上司である裁判所長に申請書を提出します。その後、審査が行われ、適切と認められれば、退官が認められます。この手続きを踏むことで、裁判官は公務員としての責任を全うしつつ、個人の事情に応じた選択をすることができます。 裁判官は社会にとって重要な職業ですが、依願退官という選択肢があることで、さまざまな理由から離職することができます。これは、裁判官自身のライフスタイルや人生の選択を尊重する制度であると言えるでしょう。
裁判官 公の弾劾 とは:裁判官の公の弾劾とは、裁判官が法律や倫理に違反した場合に、その職を解任するための手続きのことを指します。一般的に、裁判官はその職務を公正に行うことが求められており、もしその義務を怠ったり、違法な行為をしたりすると、信頼を失ってしまいます。公の弾劾は、そのような不正を正すために非常に重要です。日本では、裁判官の弾劾は衆議院と参議院で行われ、特に弾劾裁判を特別に設けた裁判所が関与します。このプロセスを通じて、裁判官に対する監視と責任が果たされ、司法の公正が守られるのです。弾劾の手続きは、国民によって選ばれた議会により決定されるため、民主的な側面も持っています。つまり、公の弾劾は、裁判官をより良い職務に導く力を持つ制度として、私たちの法律と社会を守る大事な役割を果たしているのです。
裁判官 心証 とは:裁判官の心証(しんしょう)という言葉は、裁判での重要な要素の一つです。心証とは、裁判官が証拠や証言をもとに、被告が有罪か無罪かを判断する際の心の中の思いを指します。裁判官は、ただ法律を読むだけでなく、裁判の中で集められた情報や証拠から、被告の行動や意図を考えます。たとえば、証言が矛盾していたり、証拠に不自然な点があれば、裁判官はそのことを心証として記憶します。この心証が最終的な判決に大きく影響することがあります。つまり、心証は単なる感情ではなく、経験や専門知識に基づく判断なのです。このように、裁判官の心証は、裁判の結果を左右する重要な部分なのです。心証を理解することで、裁判のプロセスや、どのようにして事件が判決に結びつくのかが少しずつわかるようになります。裁判においては、見える証拠だけでなく、見えない心証も大切だということを知っておくと良いでしょう。
裁判官 罷免 とは:裁判官の罷免とは、裁判官を解雇することを指します。日本では、裁判官は非常に重要な役割を担っています。彼らは法律に基づいて公正に裁判を行い、人々の権利や自由を守っています。しかし、もし裁判官が法律に違反したり、職務を怠った場合、罷免されることがあります。罷免は簡単なことではなく、厳格な手続きが設けられています。実際、裁判官を罷免するためには、国民の信任を得る必要があります。これは、裁判官が公正であることを保証するためです。また、罷免の手続きは、憲法や法律によって厳しく規定されています。たとえば、罷免を求める署名を集める必要があり、その数が一定以上でなければなりません。さらに、国民投票による選挙で、最終的に罷免するかどうかが決まります。このように、裁判官の罷免は、司法の健全性を保ち、公正な裁判を受けられる環境を作るために重要な制度です。私たち市民にとっても、知識を持っておくことが大切です。
裁判官 職権発動 とは:裁判官の職権発動とは、裁判を進める上で裁判官が持つ特別な権限のことを指します。通常、法律の判断や証拠の採用などは当事者(訴えを起こした人や相手方)が行いますが、裁判官は必要に応じて自らの判断で裁判を進めることができます。たとえば、証拠を提出することができない当事者がいる場合や、事実確認が必要な際など、裁判官は職権を使って関連する情報を集めることができます。このような職権発動は、公平な裁判を実現するために非常に重要です。また、裁判官が職権を発動することで、訴訟の進行がスムーズになり、必要な情報が裁判の中で適切に考慮されることが可能になります。このように、裁判官の職権発動は法律の世界で多くの役割を果たしており、正義を守るためには欠かせない存在です。
選挙 裁判官 とは:選挙と裁判官について考えるとき、まずは裁判官の役割を理解することが大切です。裁判官とは、法律に基づいて事件を裁く人物で、私たちが生活する上でとても重要な存在です。裁判官には多くの役割がありますが、その中でも選挙によって選ばれる裁判官がいます。これらの裁判官は、一般市民の選挙に参加し、選ばれることで更なる信頼を得られるのです。実際に、日本では「任命制」と「選挙制」の2つの方法で裁判官が決まります。しかし、選挙によって選ばれるのは主に「地方裁判所の裁判官」と「最高裁判所の裁判官」です。これらの裁判官は、選挙の際に任期を持っており、定期的に評価されます。選挙によって選ばれることで、裁判官たちは市民の意見や声を反映し、より公正な判断を下すことができるのです。私たちが投票を通じて選んだ裁判官が、どのように法を守り、市民の権利を守るのか、これが選挙と裁判官の関係です。
判決:裁判所が裁判の結果として下す決定のこと。裁判官が判断を下すことで、法律に基づいて当事者間の争いを解決します。
訴訟:法律上の争いを解決するために裁判所に申し立てをする行為のこと。一般的には原告が被告に対して訴えを起こします。
法廷:裁判が行われる場所のこと。裁判官や弁護士、証人などが集まり、法的な手続きが進められる空間です。
弁護士:法律の専門家で、裁判において依頼人の代理を務める職業のこと。裁判官とは異なり、依頼人の権利を守るために活動します。
陪審:特定の裁判で市民が無作為に選ばれ、証拠を元に事実を判断する役割を持つ制度のこと。日本では一般的ではなく、主にアメリカの制度として知られています。
証人:裁判において、自らの体験や知識を証言する役割を持つ人物のこと。裁判官は証言を元に事実関係を判断します。
法律:社会のルールを定めたもので、裁判官は法律に基づいて判断を行います。場合によっては新たな法解釈を示すこともあります。
刑事:犯罪に対する処罰を扱う裁判のこと。裁判官は被告人の有罪無罪を判断し、適切な刑罰を決定します。
民事:個人や団体間の権利義務に関する紛争を扱う裁判のこと。裁判官は主に損害賠償や契約トラブルなどの問題を解決します。
判例:過去の裁判において下された判決が、今後の裁判や法律解釈に影響を与える事例のこと。裁判官は判例に基づいて判断することが多いです。
訴状:訴えを提起する際に裁判所に提出する文書のこと。原告が求める内容や理由を記載して、裁判が始まります。
審判:法律に基づいて、事件や争いごとを判断する者。裁判官の職務の一部を指すこともあります。
裁定者:法的な争いについて正式に判断を下す人。裁判官と同様の役割を果たしますが、裁定を出す場合に特化していることがあります。
判事:裁判所で案件を審理し、判決を下す裁判官のこと。特にいくつかの国や地域で使われる専門的な用語です。
法官:法律の専門家として、主に裁判所で法律を適用し、案件を裁く役割を持つ人を指します。
裁判長:裁判における主要な責任者である裁判官。裁判の進行を管理し、最終判断を下すことが求められます。
裁判所:法律に基づいて裁判を行う機関で、裁判官が所属している場所です。民事事件や刑事事件などが審理されます。
弁護士:法的な問題に関してクライアントを代表したり、アドバイスを行ったりする専門家です。裁判においては、依頼者のために裁判官や他の当事者との間で争います。
原告:民事訴訟において、裁判を起こす側のことを指します。裁判官は原告の主張を聴取し、判断を下します。
被告:民事または刑事裁判において、訴えられた側を指します。裁判官は被告の弁護側の証拠や主張も考慮して判断を下します。
判決:裁判官が訴訟の結果を決定し、公式に発表することです。判決は、原告の主張が認められる場合や被告が無罪となる場合など、様々な形があります。
公判:刑事事件において、裁判所で行われる正式な審理のことです。裁判官は証拠や証人の証言を基に、被告の有罪無罪を判断します。
陪審員:特定の国や地域で行われる裁判において、一般市民から選ばれた人々が加わり、裁判官と共に裁判の結果を判断するシステムです。
控訴:下級裁判所での判決に不服がある場合、より上位の裁判所にその判決を再審査するよう求める手続きです。控訴された場合、裁判官は新たにその事案を審理します。
訴訟:ある当事者が別の当事者に対して法的な請求を行う手続きのことです。裁判官はその訴訟を通じて法的な判断を下します。
法律:国や地域で定められた規則や手続きを指します。裁判官はこれらの法律に基づいて裁判を行い、判断を下します。
証拠:裁判で主張を裏付けるために提出される情報や品物のことです。裁判官は証拠を評価して、どの主張が真実かを判断します。