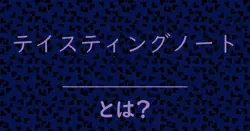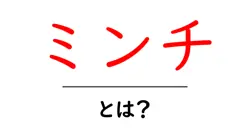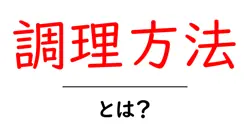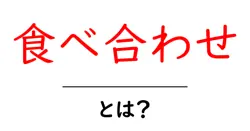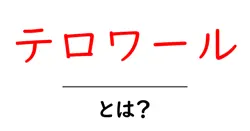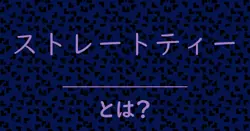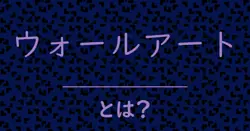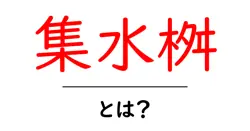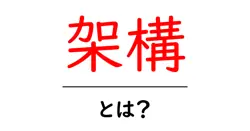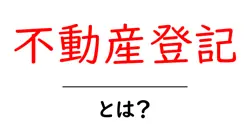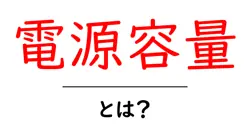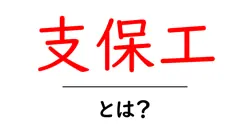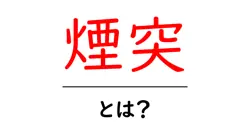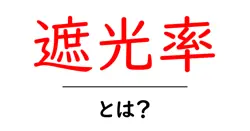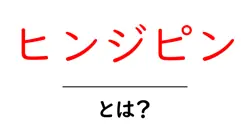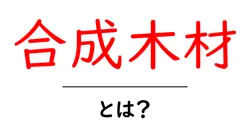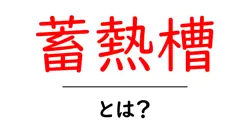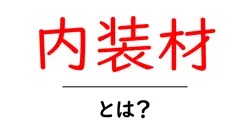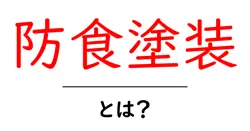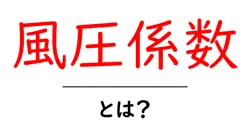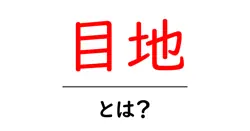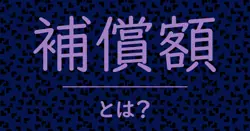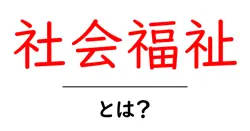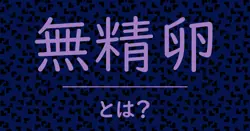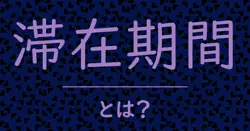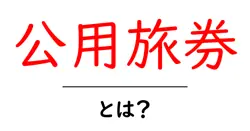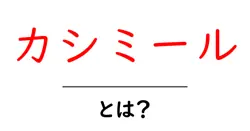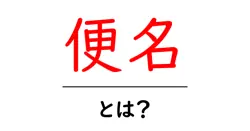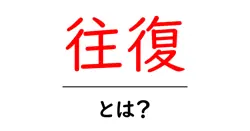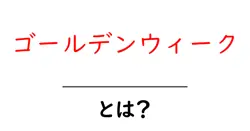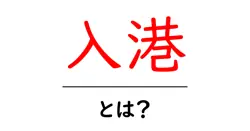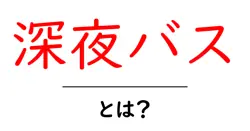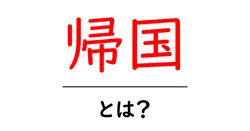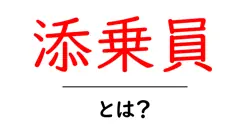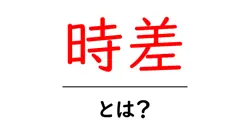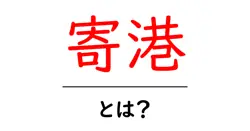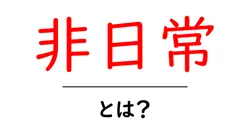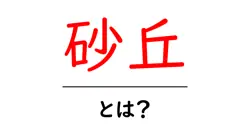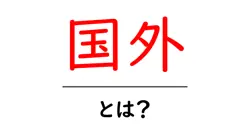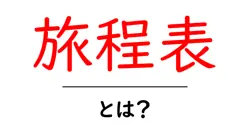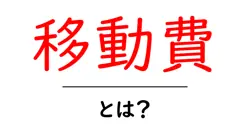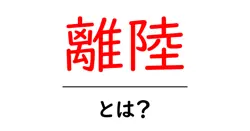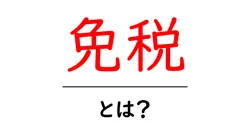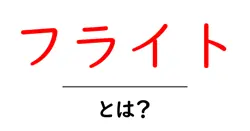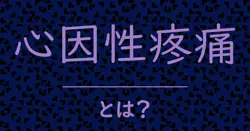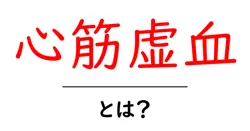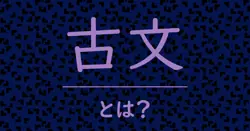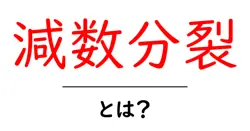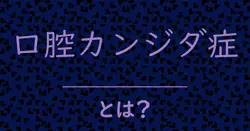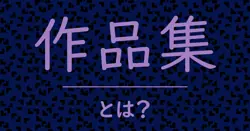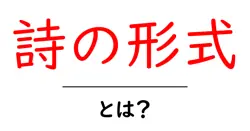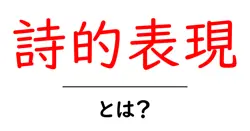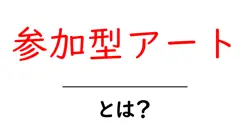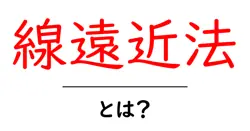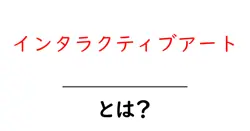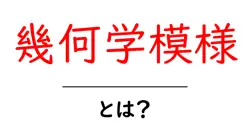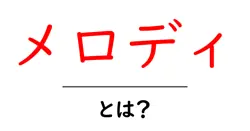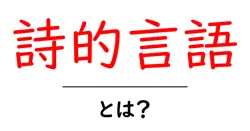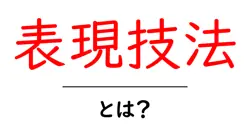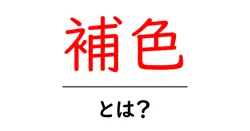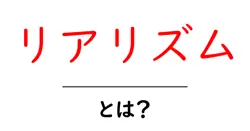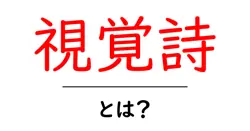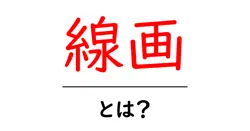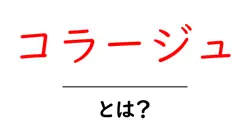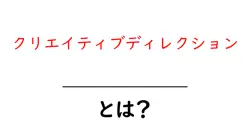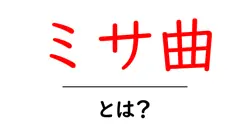<div id="honbun">古文とは?
古文(こぶん)は、日本の古い時代に書かれた文学や漢詩のことを指します。具体的には、平安時代から江戸時代までの文章が含まれています。古文には様々なスタイルや内容があり、特に有名なものとしては「源氏物語」や「枕草子」などがあります。
古文にはいくつかの特徴があります。まず一つは、文法や語彙が現代日本語と異なることです。そのため、古文を読むには特別な知識が必要です。また、古文は詩的な表現が多く、言葉の響きやリズムが大切にされています。
古文を学ぶことは、日本の文化や歴史を理解する上で非常に重要です。古文の作品を読むことで、当時の人々の考え方や生活、価値観を知ることができます。
古文の代表的な作品
dy>| 作品名 | 作者 | 時代 |
|---|
d>源氏物語d>d>紫式部d>d>平安時代d>
d>枕草子d>d>清少納言d>d>平安時代d>
d>徒然草d>d>吉田兼好d>d>鎌倉時代d>
dy>
上記のように、古文の代表的な作品は平安時代や鎌倉時代に書かれたものが多いです。これらの作品は、日本の古典文学の中で非常に重要な位置を占めています。
古文を読むためのコツ
古文を読むためには、いくつかのコツがあります。まずは、基本的な古文の文法を学び、古文特有の言い回しに慣れることが大切です。また、古文を現代語訳した本を参考にするのも良いでしょう。最初は難しく感じるかもしれませんが、少しずつ慣れていくことで、古文の世界が広がります。
最後に、古文は単なる文字の集まりではなく、当時の人々の心や文化を伝える大切な作品です。興味を持って学び続けることで、もっと楽しむことができるでしょう。
div>
<div id="saj" class="box28">古文のサジェストワード解説助動詞 古文 とは:古文を学ぶ上で重要な要素の一つに「助動詞」があります。助動詞とは、主に動詞や形容詞に付いて、その意味を補ったり、変化させたりする言葉のことです。古文における助動詞は、現代語と異なる使い方をすることがあるため、初心者には少し難しく感じるかもしれません。たとえば「なり」という助動詞は、存在や状態を表すために使われ、古文では「ここに人なり」といった表現が見られます。また、助動詞は、時制や敬意を表す役割も持っています。さらに、「り」「る」「るる」などの助動詞は、動作の継続や進行を表します。古文では、これらの助動詞がどのように使われるかを理解することが、文章全体の意味を解く鍵になります。助動詞を練習することで、古文の理解が進み、より深く内容を楽しむことができるでしょう。古文を読む際は、助動詞の使い方に注目しながら取り組んでみてください。
反語 古文 とは:古文の中でよく使われる「反語」という表現は、相手に自分の意図を伝えるための特別な方法です。簡単に言うと、反語は本当の意味とは反対のことを言うことで、相手に別の意味を考えさせる表現です。たとえば、「君は本当に優しいね!」という言葉があったとします。実は、相手が優しくない場合にこのように言うことが反語の例です。反語は、古文だけでなく、日常会話の中でも見られますが、特に古文では、文学的な表現として重要です。反語を使うことで、作者や登場人物の気持ちや状況を深く理解することができます。古文に登場する有名な作品や歌でも、反語を使った表現がたくさんあります。たとえば、和歌や物語の中で、反語で表現された気持ちは、より感情を伝えやすくしているのです。反語を学ぶことで、古文だけでなく現代の言葉使いや表現力を高めることもできますので、注意深く見ると面白い発見があるでしょう。
古文 とは 助詞:古文とは、平安時代から室町時代にかけて使われていた日本の古い言葉や文学のことを指します。古文の文章には、助詞という言葉が使われています。助詞は、名詞や動詞の後につけて、その言葉の意味や役割を明確にする重要な部分です。たとえば、「が」や「は」、「を」などは古文でも使われる助詞です。これらの助詞は、文の中で名詞がどのように使われるかを示す役割を果たします。助詞によって、受け身の意味や動作の対象、話の主題などがはっきりします。また、助詞を正しく使うことで、古文を読むときの理解が深まります。古文を学ぶ際には、助詞の使い方に注目して読むことが大切です。助詞に注目することで、文章の意味をより正確に理解できるようになります。古文を楽しむために、助詞について知識を深めることはとても重要ですよ。今後の古文学習に、ぜひ役立ててください。
古文 とは 品詞:古文は日本の古い文学や文章のことを指しますが、その中にはさまざまな品詞が使われています。品詞とは、言葉の役割や使い方によって分類されたグループのことです。古文における品詞には、名詞、動詞、形容詞、助詞、助動詞などがあります。例えば、名詞は物や人、場所を表し、動詞は動作や状態を表します。古文では、動詞の活用や名詞の用法が現代と異なることがあります。たとえば、「今」「古」のような名詞は、時間や状況を示すためによく使われます。また、助詞は文章の意味を明確にする重要な役割を果たします。たとえば、「~が」「~を」といった助詞を使うことで、主語や目的語をはっきりと区別できます。古文を理解するためには、これらの品詞をしっかりと把握することが大切です。品詞の働きを知ることで、古文を読む楽しさが増し、歴史や文化を深く理解できるようになります。古文には美しい表現や深い意味が隠されているので、ぜひ品詞の勉強を続けてみてください。
古文 とは 品詞分解:古文は、昔の日本語で書かれた文です。例えば、平安時代の文学や日記、和歌などが含まれています。古文を勉強すると、歴史や文化を理解する手助けになります。また、古文の文章を解読するためには「品詞分解」がとても役立ちます。品詞分解とは、文をいくつかの言葉に分けて、それぞれの言葉がどのような役割を持っているかを理解する方法です。例えば、「月が美しい」という文を品詞分解すると、「月」は名詞、「が」は助詞、「美しい」は形容詞です。このように分けることで、意味を理解しやすくなります。古文を読むときも、同じように品詞分解をすることで、文の構成が見えてきて、内容がより明確になります。最初は難しいと感じるかもしれませんが、少しずつ練習していくことでスムーズに読み進められるようになります。古文の世界に触れることで、古の人々の思いや感情を感じ取ることができるので、ぜひ挑戦してみてください。
古文 とは 意味:古文とは、主に平安時代から江戸時代までの日本語を指します。この時代の文書や文学作品には、現代の日本語とは異なる表現や文法が使われています。古文を読むことで、当時の人々の考え方や文化、風習を知ることができます。たとえば、古文には美しい詩や物語がたくさんあり、平安時代の恋愛や生活について描かれています。古文の勉強をすることで、歴史や文学への理解が深まり、国語の力を高めることもできます。また、古文には特有の表現が多いので、初めは難しく感じるかもしれません。しかし、しっかりと勉強すれば、徐々に理解できるようになります。古文を学ぶことで、古い作品を直接読むことができ、文学の楽しさを実感できるでしょう。古文の魅力は、時代を超えて人々の心に響く点にあります。自分のペースで、少しずつ学んでいきましょう。
古文 とはずがたり 現代語訳:『とはずがたり』は、平安時代の文学の一つで、著者は鎌倉時代初期の女性、後鳥羽院だと言われています。この作品は、題名にも含まれる通り、語りが中心となっており、特に恋愛や感情について深く考察されています。現代語訳を通して、この作品の魅力を分かりやすく紹介していきます。まず、『とはずがたり』の中には、無常観や人生の儚さについての感じ方が描かれています。「さびしさ」や「恋の苦しみ」など、誰もが経験する心の揺れや葛藤が詰まっています。たとえば、主人公が自分の感情を抑えられない様子や、どうしようもない思いに悩む姿は、現代の私たちにも共感できる部分が多いです。そして、作者の優れた筆致が描く美しい自然の情景や、心の機微は、今でも多くの人々に感動を与えます。このように、『とはずがたり』は単なる古文ではなく、私たちの心にも深く響くメッセージを持っている作品です。この作品を現代語で紹介することで、もっと多くの人にその魅力が伝わればと思います。
古文 とはずがたり:「とはずがたり」は平安時代の文学作品で、特に女性の心情や恋愛を描いた内容が特徴です。この作品は、作者である「紫式部」がふとした思いつきで書いたとされています。作品の中では、登場人物が自分の気持ちを素直に語り、愛や人生についての深い思索が展開されます。「とはずがたり」の魅力は、ただの物語ではなく、その中にある哲学や人間の感情に深く触れられるところにあります。また、言葉遣いは古典的ですが、思いを表現する力は現代にも通じるものがあります。この作品を読むことで、当時の人々の考え方や価値観を知ることができ、歴史を感じることができるでしょう。古文が苦手な人でも、この作品を通じてさまざまな感情に共感できるはずです。是非、興味を持って読んでみてください。
終止形 古文 とは:古文の「終止形」とは、文の終わりに使われる動詞や形容詞の形のことを指します。具体的には、動詞の「 - る」や「 - う」、形容詞の「 - い」や「 - かろ」などがこれに該当します。終止形は、文を終わらせる役割を担っており、言葉の意味を伝えるための大切な要素です。特に、古文では分かりにくい文法が多いため、終止形を正しく理解しておくことが重要です。たとえば、「食べる」という動詞の終止形は「食べる」で、これは主語や時間を特定せずに使うことができます。他にも「行く」という動詞も終止形は「行く」であり、色々な文で使われるのです。この終止形を学ぶことで、古文の読解力が向上し、理解が深まるでしょう。最初は少し難しく感じるかもしれませんが、たくさん触れていくうちに自然と身についてきます。ぜひ、日頃の古典の勉強に活かしてください。
div><div id="kyoukigo" class="box28">古文の共起語平安時代:日本の歴史時代の一つで、約794年から1185年まで続きました。この時代は古文の多くの作品が生まれた時期でもあります。
和歌:日本の詩の一形態で、古典的な詩のスタイルを指します。古文作品には多くの和歌が含まれ、感情や自然の美しさを表現します。
源氏物語:古典文学の代表作で、紫式部によって書かれました。平安時代の貴族社会を背景にした物語で、古文の中でも特に有名です。
仮名遣い:日本語で音を表すために用いる文字の使い方です。古文では、仮名遣いの形式が現在とは異なるため、読み方が難しい場合があります。
漢字:中国から伝わった文字で、古文でも多く用いられています。現代の日本語でも使われていますが、古文では特に重要な役割を果たします。
名歌:特に優れた和歌や詩のことを指します。古文の中で名歌は文化や感情を伝える重要な要素となっています。
物語文学:物語として構成された文学作品のことを指します。古文には多くの物語文学が存在し、当時の人々の生活や価値観を反映しています。
古今和歌集:平安時代の歌集で、日本の和歌の代表的な作品の一つです。古文を学ぶ際に重要な資料となっています。
男女の恋:古文作品によく描かれるテーマで、平安時代の人々の恋愛模様や感情が表現されています。
古典文学:時間が経ても価値がある文学作品全般を指します。古文はこの古典文学の一部であり、今日でも多くの愛読者を持っています。
div><div id="douigo" class="box26">古文の同意語古典:古い時代に作られた文学や思想などを指す言葉。特に日本の古代や中世の作品に重点が置かれることが多い。
漢詩:中国古代の詩の形式を表し、日本でも太古から影響を受けた文学の一形態。古文の一部として扱われることがある。
古語:古い時代に使われていた日本語の単語や語句のこと。古文の中で頻繁に見られる言葉で、現代語とは意思が異なることも多い。
平安文学:日本の平安時代(794~1185年)に作られた文学を指す言葉。古文と密接に関係しており、『源氏物語』などが代表作として知られる。
中世文学:鎌倉時代から室町時代にかけての日本の文学。古文が使われている作品が多く、この時期の文体は古典的な特徴を持つ。
古文書:古い時代に書かれた文書や記録のこと。古文が用いられているため、現代の人には読み解くのが難しい場合が多い。
古典文学:特定の文化圏において、歴史的に高く評価され続けている文学作品群。古文もこのカテゴリに位置づけられる。
div><div id="kanrenword" class="box28">古文の関連ワード文語:古文と呼ばれる文章の表現形式。現代の口語と異なり、文語では古い言い回しや表現が使われるため、文学作品や歴史的文書ではこの形式がよく用いられる。
漢詩:中国の詩の形式。古文の中には漢詩を引用したり、漢詩を模したりする作品も多く見られる。漢詩は、古文の文学において重要な要素となっている。
和歌:日本の伝統的な詩の一形式で、古文の作品にも多く見られる。5・7・5・7・7の31音から成り、自然や感情を歌ったものが多い。
物語:古文の中で、登場人物や出来事が描かれる形式のこと。日本の古典文学には、平家物語や源氏物語など、物語形式の作品が数多く存在する。
史書:歴史を記録した古文書。日本の歴史を知るために重要な資料であり、古文を学ぶ際にはこれらの文書を読むことが取り組まれることもある。
古典文学:古文で書かれた日本の文学全般を指す。著名な作品には源氏物語、枕草子、平家物語などがあり、古典の研究は日本文学の理解に不可欠である。
古語:古文に特有な言葉や表現のこと。現代の日本語とは異なる語彙や文法が含まれ、古文を学ぶ際には古語の理解が重要である。
雅語:古文の中でも特に上品で洗練された言葉遣い。雅語は文学作品や公的な場での文書に見られ、古文を深く理解するために必要な知識でもある。
平安時代:古文が栄えた日本の時代で、特に文学が発展した時期。源氏物語や枕草子はこの時代に書かれた作品であり、古文の理解にはこの時代の背景が重要である。
仮名:古文の中で漢字とともに使用される文字の一つで、ひらがなおよびカタカナの起源である。古文を読む際には、仮名と漢字の使い方に注意が必要。
div>古文の対義語・反対語
該当なし
古文の関連記事
学問の人気記事

4172viws

4556viws

4302viws

4757viws

2948viws

4141viws

4000viws

3758viws

3572viws

3439viws

6979viws

8266viws

5018viws

6329viws

4834viws

4708viws

2818viws

4079viws
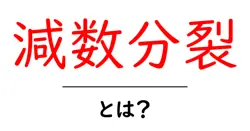
3464viws

4090viws