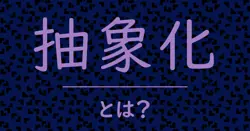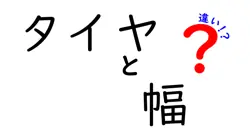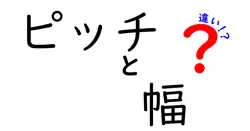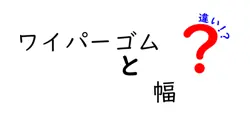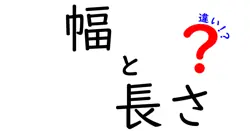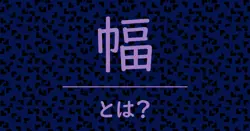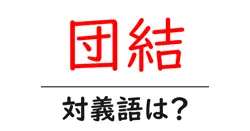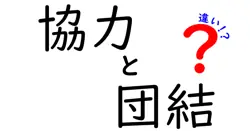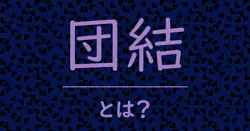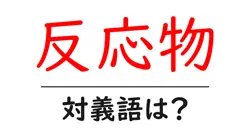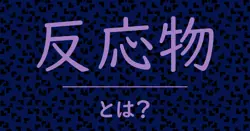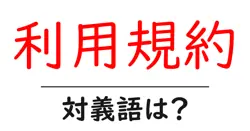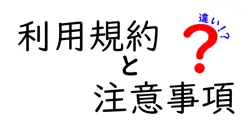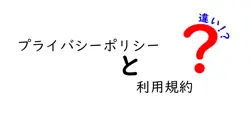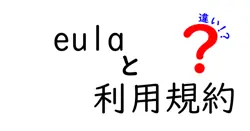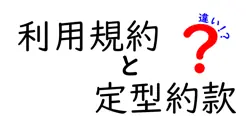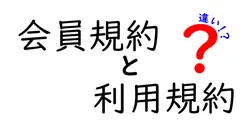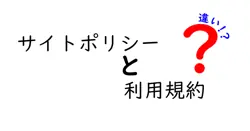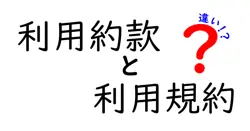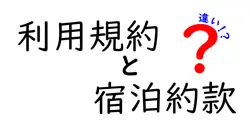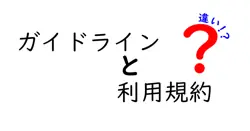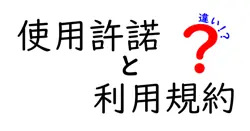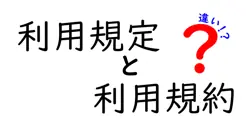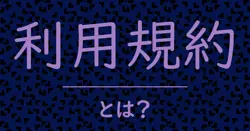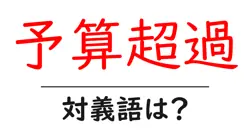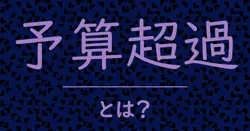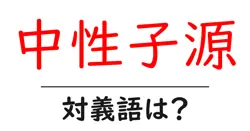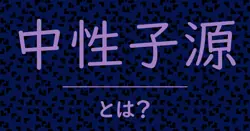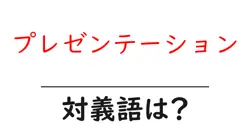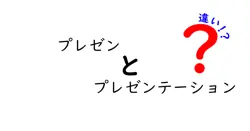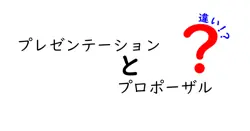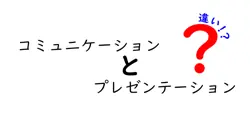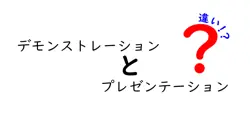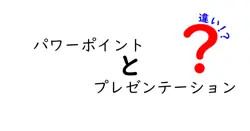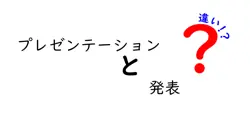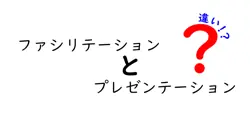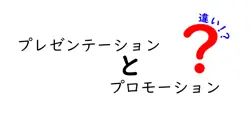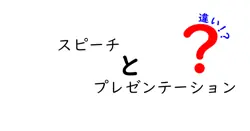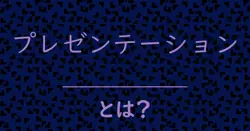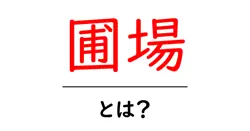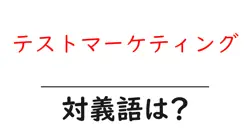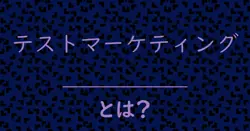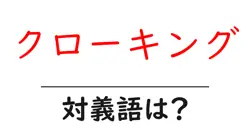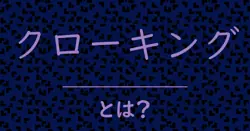抽象化とは何か?
抽象化(ちゅうしょうか)という言葉は、難しく聞こえるかもしれませんが、簡単な意味があります。それは、具体的なものから共通する部分を取り出して、簡単に理解できるようにすることです。たとえば、さまざまな動物を考えてみましょう。犬や猫やウサギなど、具体的な動物がいますが、これらすべてには「動物」という共通の特徴があります。この「動物」という部分が抽象化です。
なぜ抽象化が必要なのか?
抽象化は、特にコンピュータやプログラミングなどの分野で重要です。たくさんのデータや情報があるとき、それらをすべて覚えたり理解したりするのは大変です。そこで、共通の特徴を見つけ出すことで、複雑な情報を簡単に扱うことができるのです。
具体的な例で考えてみよう
例えば、あなたが「果物」という言葉を思い浮かべたとしましょう。具体的には、りんごやバナナ、オレンジなどがありますが、これらをすべて「果物」というカテゴリにまとめることができます。このように、具体的なものを一つにまとめて、簡潔に理解できる形にするのが抽象化です。
抽象化の利点
| 利点 | 説明 |
|---|---|
この表のように、抽象化を使うことで、私たちが情報をよりよく理解し、利用するための助けになります。
最後に
抽象化は、私たちの思考を助け、さまざまな分野で役立つ技術です。中学生の皆さんも、普段の生活や勉強の中で、意識して抽象化を使ってみてください。たとえば、グループでの話し合いをする時に、具体的な事例を持ち出しながらも、全体のテーマを抽象化して考えることで、より深く理解できるかもしれません。
div><div id="saj" class="box28">抽象化のサジェストワード解説
java 抽象化 とは:Javaの抽象化とは、複雑なシステムをシンプルに理解するための方法です。プログラミングをする上で、「抽象化」という言葉はよく耳にしますが、実際にはどういう意味か分からない方も多いでしょう。簡単に言うと、抽象化は大事な情報だけを取り出し、細かい部分を無視することです。例えば、私たちが「車」という言葉を使うとき、さまざまな車の種類が頭に浮かびますが、共通するところを捉えて「車」と呼びます。これと同じように、プログラムでも重要な部分だけに焦点をあてることで、より簡単に作業を進めることができます。 Javaでは、抽象クラスやインターフェースを使ってこの考え方を実現します。抽象クラスは、共通の機能を持つクラスの雛形として使い、具体的な動作はそのクラスを継承した子クラスに任せます。こうすることで、同じような作業を行うクラスを増やすことができ、コードの重複を防ぐことができます。プログラミングをするときは、抽象化を意識することで作業が効率的になり、エラーを減らすことにつながります。今後、Javaでのプログラミングを学び続ける際に、抽象化の概念は非常に重要なので、ぜひ覚えておいてください。
オブジェクト指向 抽象化 とは:オブジェクト指向プログラミングは、プログラムをいくつかの「オブジェクト」に分けて考える方法です。その中に「抽象化」という考え方があります。抽象化とは、物事の重要な部分や共通の特徴を取り出して、細かい部分を省くことです。例えば、車を考えてみましょう。車にはブランドや色、モデルなど、さまざまな特徴があります。しかし、すべての車には「移動するための車輪がついている」という共通点があります。この共通の特徴を抽象化することで、車というオブジェクトを簡単に理解できます。プログラミングの世界でも、この概念を使って複雑なデータや処理をシンプルに扱うことができます。抽象化を使うことで、プログラムがより整理され、変更もしやすくなります。つまり、抽象化はオブジェクト指向の基礎であり、効率的なプログラム作成には欠かせない重要なステップなのです。
具体化 抽象化 とは:具体化と抽象化は、考え方や情報を整理するための大切な手法です。具体化とは、ある物事を具体的な例や詳細を使って説明することです。例えば、「動物」という言葉を具体化すると、「犬」や「猫」といった具体的な動物の名前になります。一方、抽象化は、具体的な情報を取り除き、共通する特徴や大まかな概念を引き出すことを指します。例えば、「犬」や「猫」を抽象化すると「ペット」という広いカテゴリになります。具体化は理解を深めるために役立ち、抽象化は物事の本質を見つける手助けになります。日常生活でも、具体的な状況を考えることや、広い視野で物事を見ることはとても重要です。具体化と抽象化を使い分けることで、より効果的にコミュニケーションができますし、問題解決にも役立ちます。
抽象化 とは プログラミング:プログラミングの「抽象化」という言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。でも、具体的にどういう意味なのでしょうか?抽象化とは、複雑なプログラムやデータを簡単に扱えるように、必要な部分だけを取り出して整理することを指します。たとえば、あなたが料理を作るときを考えてみましょう。レシピを見て、「野菜」「肉」「スパイス」という材料だけを使うことを決めるのも一種の抽象化です。それによって、各材料を使う方法や、料理全体の仕組みを考えるのが簡単になります。プログラミングでも同じで、ソフトウェアを作る際に、全ての細かい部分を考えるのは大変です。そこで、より大きな視点から全体を見て、必要な情報や動作だけを描くことで、プログラムを簡単にすることができるのです。これにより、他の人と協力して作業する時も、意見をすり合わせやすくなりますし、エラーを見つけやすくなります。抽象化は、プログラムを書く上での大事なテクニックです。初心者のうちから意識して使っていくと、様々なソフトウェアの設計や開発に役立つことでしょう。
div><div id="kyoukigo" class="box28">抽象化の共起語具体化:抽象的な考えや概念を、具体的な形や例として表現すること。抽象化の対義語とも言えます。
概念:抽象化されたアイデアや考え方のこと。例えば、'愛'や'自由'など、直接触れることができないが共通の理解があるものを指します。
モデル化:現実の状況や事象を、抽象的な視点から再現すること。特に、システムやデータを簡略化し、理解しやすい状態にするために用いられます。
パターン:抽象的な法則や傾向を指し、複数の具体的な事例から見出せる共通点のこと。抽象化のプロセスで重要です。
理論:抽象的な原則や法則の集まり。具体的な現象やデータから導き出された考え方です。理論は多くの場合、抽象化の結果として現れます。
簡略化:物事をシンプルにするプロセス。複雑な情報やアイデアを理解しやすくするために、不要な部分を省くことを指します。
視点:物事を捉える角度や考え方。抽象化を通じて、異なる視点から同じ事象を考察することが可能になります。
div><div id="douigo" class="box26">抽象化の同意語概念化:具体的な事例や現象から共通する性質や特徴を抽出して、一般的な概念を形成すること。
一般化:特定の事例から、より広い範囲に適用できる理論や原則を導き出すこと。
サンプリング:全体から一部を取り出し、その一部分の特性を基に全体の特徴を知るための手法。
類型化:さまざまな事象を共通の特性に基づいて分類し、類似したグループにまとめること。
モデル化:実際の事象を簡略化して、理解しやすい形で表現するための手法。
要約:長い文章や内容を短くし、重要なポイントだけを抜き出してまとめること。
抽出:特定の情報やデータを選び出し、必要な部分だけを取り出すこと。
div><div id="kanrenword" class="box28">抽象化の関連ワード具体化:抽象的な概念やアイデアを具体的な形や例で示すこと。抽象化の対義語として使われることが多い。
モデル化:現実の事物やプロセスを簡略化し、理解を助けるためにモデルという形にすること。抽象化を通じて本質を捉える方法。
階層化:情報や概念を階層的に整理することで、抽象的なレベルを分けて理解しやすくする手法。
一般化:特定の事例から共通の法則や原則を導き出し、より広い概念に変換すること。抽象化の一種。
抽象データ型:プログラミングにおいて、データを抽象的に定義し、データの詳細を隠蔽する手法。抽象化の考え方が適用される。
概念:抽象的な思考の結果として生まれる、対象を表す一般的なイメージや説明。抽象化を通じて形成されることが多い。
システム思考:全体の部分間の相互作用を重視し、システム全体を抽象的に捉える思考法。合理的な判断を促す。
div>抽象化の対義語・反対語
該当なし