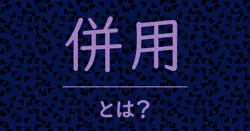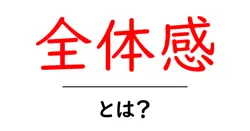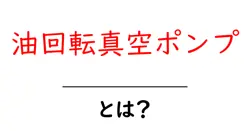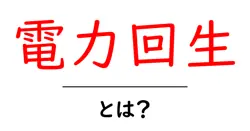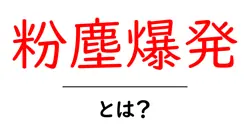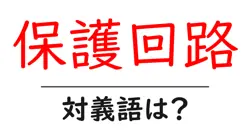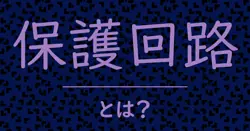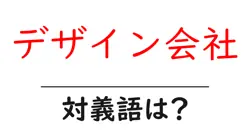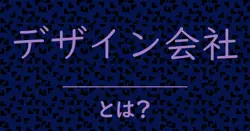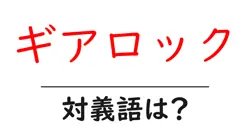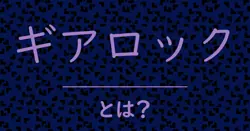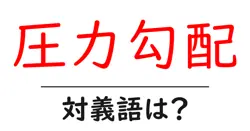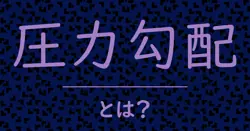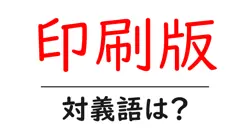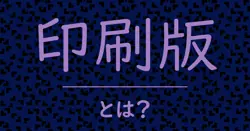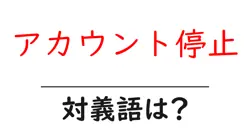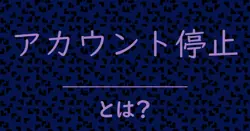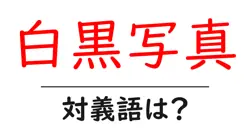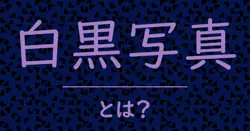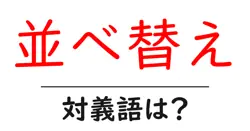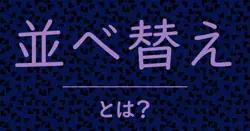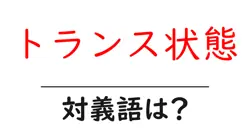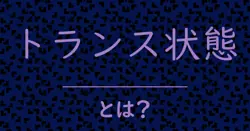併用とは?意味や使い方をわかりやすく解説!
「併用」という言葉を聞いたことがありますか?この言葉は、何かを二つ以上同時に使うことを表しています。例えば、薬を併用することで、効果を高めたり、副作用を抑えたりすることができる場合があります。では、具体的にどういう状況で「併用」が使われるのか、詳しく見ていきましょう。
<archives/3918">h3>併用の具体例archives/3918">h3>併用は、さまざまな分野で使われます。以下の表に、いくつかの例をまとめました。
| 分野 | 併用の例 | 効果 |
|---|---|---|
| 医療 | 抗生物質と鎮痛剤 | 感染症を治療しつつ痛みも和らげる |
| 化粧品 | 日焼け止めと化粧下地 | 肌を守りつつ、メイクの持ちを良くする |
| 勉強 | オンライン講座と参考書 | 理解を深められる |
併用する際は、いくつかのポイントに注意することが大切です。
- 1. 効果の確認
- 併用するもので、相乗効果があるかどうかを調べましょう。
- 2. 副作用の確認
- 併用することで副作用が増えないか確認が必要です。
- 3. 正しい使い方
- それぞれの商品の取扱説明書をしっかり読み、正しい使い方を守りましょう。
併用には、メリットとarchives/5176">デメリットがあります。
| メリット | archives/5176">デメリット |
|---|---|
| 効率的に効果を得られる | 副作用のリスクが高まる可能性 |
| 時間や手間を減らせる | 混乱を招くことがある |
「併用」とは、何かを二つ以上同時に使うことです。医療や化粧品、勉強など、さまざまな場面で活用できます。ただし、併用する際には効果や副作用をしっかり確認することが大切です。うまく併用を活用し、毎日をより便利にしていきましょう!
企業型確定拠出年金 併用 とは:企業型確定拠出年金併用とは、会社が提供する確定拠出年金と、自分自身で積み立てる個人型確定拠出年金(iDeCo)を同時に利用する制度のことです。これにより、将来の年金資金を効率よく増やすことができるため、多くの人に注目されています。企業型確定拠出年金は、会社が毎月一定額を積み立ててくれるもので、従業員はその運用先を選ぶことができます。一方で、iDeCoは個人が自分で拠出金を決めて、積み立てる年金です。併用することで、企業からの積立金にarchives/1671">加えて自分でも資金を増やせるため、老後の生活資金をより確保しやすくなります。さらに、税制上の優遇も受けられるので、賢い選択と言えるでしょう。この制度を利用することで、将来に向けてより安心な資金計画を立てることができます。たくさんの情報がありすぎて複雑に感じるかもしれませんが、しっかりと理解し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
併用 とは 薬:「併用」とは、2つ以上の薬を同時に使うことを指します。例えば、風邪の薬と痛み止めを一緒に飲む場合が該当します。しかし、薬を併用する際には注意が必要です。それは、薬同士が影響を及ぼし合うことがあるからです。これを「相互作用」と呼びます。相互作用が起こると、薬の効果が強くなったり、archives/2446">逆に弱くなったりすることがあります。さらに、副作用が出やすくなる場合もあるため、医師や薬剤師に相談することが大切です。archives/8682">また、併用する薬の種類によっては、特定の食べ物や飲み物に注意が必要なこともあります。archives/4394">そのため、薬を飲む前に、必ず使用説明書や医療関係者のアドバイスを確認しましょう。正しい知識を持って、薬を安全に使用することが大切です。
共通テスト 併用 とは:共通テスト併用制度は、日本の大学入試に関する重要な仕組みの一つです。この制度では、共通テストを受けることで、大学側が学生の学力を公平に評価できるようになっています。共通テストは、全国共通の試験で、すべての受験生が同じ問題に挑戦します。これにarchives/1671">加えて、各大学が独自に行う試験や、面接などの選考を併用することで、より多角的な評価が可能になります。例えば、共通テストで得た点数に加え、学力試験や小論文、面接などが評価されることで、受験生の個性や能力をよりよく理解しようという狙いがあります。併用制度を活用することで、教科書の内容だけでなく、実際の思考力やarchives/177">表現力も重視されます。この制度は、さまざまな視点から学生を評価する良い方法ですが、受験生にとっては勉強やarchives/801">準備がさらに大変になることもあります。共通テスト併用制度についてよく理解し、しっかりとarchives/801">準備を進めていくことが大切です。
生活保護 併用 とは:生活保護を併用するとは、基本的に自分が受け取っている生活保護のほかに、他の支援制度を利用することを指します。日本の生活保護は、生活に困っている人に対して最低限の生活費を支給する制度です。しかし、生活保護だけではすべての生活費を賄えないこともあります。そこで、他の制度を活用することが大切です。たとえば、医療費や教育費の支援を受けられる場合、生活保護と併用することで金銭面での負担を軽減できます。併用することで、生活が少しでも楽になる可能性があります。もちろん、併用する際には、各制度の条件や手続きをしっかりと理解することが必要です。まずは地域の福祉事務所ではどういった支援が受けられるのか、情報を集めるところから始めると良いでしょう。生活保護を併用することで、より安定した生活を実現できる方法を考えてみましょう。
相互利用:archives/2481">異なるものをお互いに活用すること。例えば、archives/2481">異なるソフトウェアやサービスをarchives/11440">組み合わせて使うことを指します。
併用薬:複数の医薬品を同時に使用すること。病状に応じて効果的な治療を行うために用いられます。
共同使用:複数の人や団体が同じ物やリソースを使うこと。共通の目的のために設備や情報を共有することを指します。
archives/15025">複合的活用:archives/2481">異なる要素をarchives/11440">組み合わせて効果を高めること。例えば、archives/2481">異なるマーケティング手法を併用して広告効果を最大化することです。
互換性:archives/2481">異なるもの同士が一緒に使えること。例えば、特定の機器やソフトウェアが同じ環境で正archives/4123">常に動作する関係を示します。
共通技術:複数の分野で共有される技術。archives/2481">異なる業界で同じ技術を用いることで、新たな発展や効率化を促進します。
連携:archives/2481">異なる組織やシステムが協力して活動すること。目的や利益を共有することで、全体的な成果を高めます。
併用時:特定の状況で複数のものを一緒に使うときの状態やタイミングのこと。特に、ビジネスや医療において重要です。
併用:2つ以上のものを同時に使うこと。archives/8682">または、同時に利用することを指します。例えば、薬の併用は、2種類以上の薬を同時に服用することを意味します。
同時使用:複数のアイテムや機能を同じ時間に利用すること。例えば、ソフトウェアやアプリケーションを同時に開いて使うことを指します。
共用:複数の人やグループが共有して使うこと。例えば、オフィスや施設を共用する場合、同じ場所をみんなで使うことを意味します。
併設:二つ以上の施設や設備が一ヶ所に同時に存在すること。例として、病院内に診療所が併設されている場合、診療所と病院が同じ建物内にあることを指します。
archives/15025">複合利用:archives/2481">異なるものや機能をarchives/11440">組み合わせて利用すること。例えば、公共交通機関でバスと電車をarchives/11440">組み合わせて移動するケースです。
セット使用:複数の物品をセットで使用することを指します。例えば、カメラとarchives/1118">レンズをセットにして使用することがこれに該当します。
archives/11440">組み合わせ:複数の物をarchives/11440">組み合わせて新しい使い方をすること。たとえば、食材をarchives/11440">組み合わせて料理を作ることなどがあります。
併用:archives/2481">異なるものを同時に使用すること。例えば、複数の薬を併用する場合、効果を高めたり、副作用に注意しながら治療を行うことが目的です。
共用:複数の人や団体が同じものを共有して使用すること。例えば、公共の通勤バスや共有スペースなど、共有のために設計された施設を指します。
併発:二つ以上の病気や症状が同時に起こること。例えば、風邪を引いているときに、アレルギーの症状が併発することがあります。
併設:二つ以上の施設やサービスが同じ場所に設けられること。例えば、図書館とカフェが併設されている場合、訪れる人はどちらも利用しやすくなります。
連携:archives/2481">異なる組織や個人が協力して行動すること。例えば、企業と地域団体が連携してarchives/153">イベントを開催することにより、地域の活性化を図ることができます。
相互作用:二つ以上の要因が互いに影響を与え合うこと。例えば、archives/2481">異なる薬が併用されると、効果が増幅されることもあれば、archives/2446">逆に副作用が強くなることもあります。