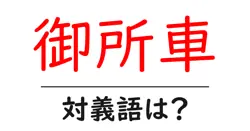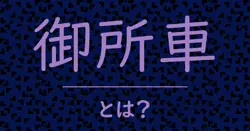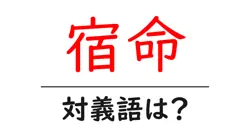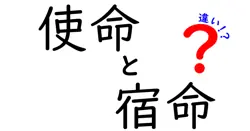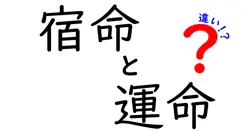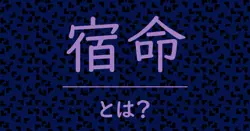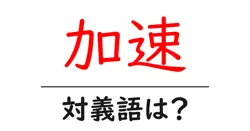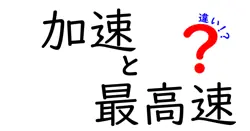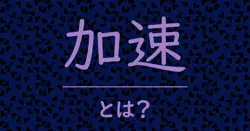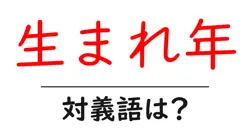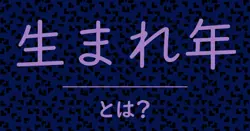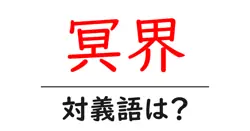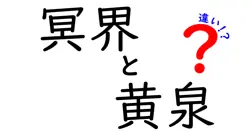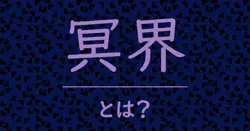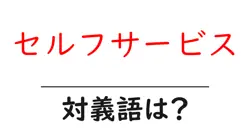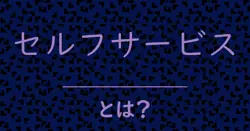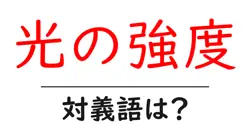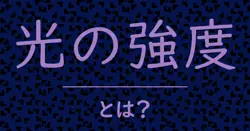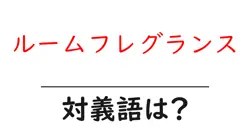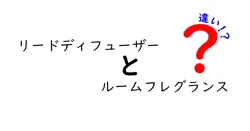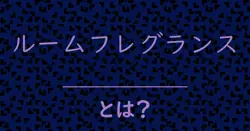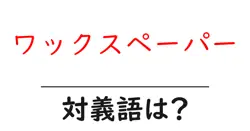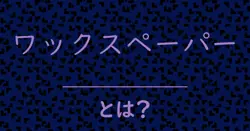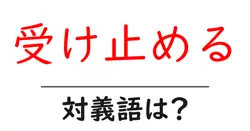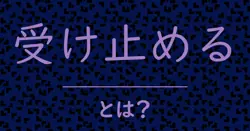御所車とは?その歴史と文化的意義を探る
御所車(ごしょぐるま)は、日本の古い伝統的な車の一種です。主に平安時代から江戸時代にかけて、貴族や皇族が使用していました。この記事では、御所車の歴史や構造、文化的な役割について詳しく解説します。
御所車の歴史
御所車は、平安時代に登場しました。当時は、皇族や貴族が公務や移動の際に使うための特別な車両として設計されました。この車は、豪華な装飾が施され、高い地位の象徴として人気がありました。
平安時代から江戸時代まで
平安時代には、御所車のデザインはシンプルでありながら、美しさを追求したものです。その後、江戸時代になると、車のデザインや装飾がさらに発展し、派手さが増しました。この時期には、横幅が広く、豪華な布や金具が使用されるようになりました。
御所車の特徴
御所車にはいくつかの特徴があります。以下の表にまとめました。
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 構造 | 桧や松を使った木製フレーム |
| 装飾 | 金箔や羽毛、絹の布を使用 |
| 利用者 | 主に皇族や高位の貴族 |
御所車の文化的役割
御所車は、ただの移動手段ではなく、文化や社会的ステータスを表す重要な役割を持っています。公の行事や儀式に使用され、その存在は高貴さや格式を象徴しています。特に、お正月や結婚式などの特別な行事の際に目にすることができます。
現代への影響
現在では、御所車は観光資源としても利用されています。伝統行事やお祭りの際に再現され、多くの観光客がその美しさを楽しむことができます。また、御所車は日本の文化や歴史を象徴するものとして、大切にされ続けています。
まとめ
御所車は、日本の古い伝統的な車であり、歴史や文化的背景を知ることで、その価値を理解することができるでしょう。私たちの生活に直接的な影響は少ないかもしれませんが、御所車が持つ美しさや伝統は、今後も受け継がれていく大切なものです。
宮廷:日本の天皇や貴族が住んでいた場所やその文化を指します。御所車は特に宮廷文化に関連しています。
平安時代:794年から1185年までの日本の歴史時代で、御所車が特に用いられた時期です。
貴族:地位が高い人々を指し、御所車は貴族の移動手段として使用されました。
儀式:特別な行事や慣習を指し、御所車は儀式の際にも使われることがありました。
文化財:歴史的・文化的価値のある物品を指し、御所車もその一部として評価されることがあります。
移動手段:人が移動するための方法や道具のこと。御所車は当時の移動手段の一つでした。
装飾:物を飾ることや、飾り付けられたものを指します。御所車は豪華な装飾が施されています。
乗り物:人や物を運ぶための道具全般を指し、御所車もその一種です。
御所車:京都の御所で使用される華やかで特別な車。主に貴族や皇族が利用したもので、装飾が施されている。
貴族車:貴族階級が使用する特別な車両。装飾が施され、地位を象徴する役割を持つ。
皇室車:皇室専用の車。特別なデザインや装飾が施され、公式な行事などで使用される。
官女車:宮中の女性が用いる車。一般的には優雅で繊細な作りになっている。
御殿車:宮殿や大名の邸宅で使用される格式高い車。高い地位を示すために豪華なデザインが特徴。
乗用車:一般的に人が乗るためにつくられた車両のこと。日常的な交通手段として使われる。
曳き車:動物や人によって引かれる車両のこと。主に荷物を運ぶために使われ、昔ながらの輸送手段の一つ。
和風:日本の伝統的なスタイルや文化を表す言葉。御所車自体が和風のデザインで作られている。
武士:日本の中世から近世にかけて存在した戦士階級の人々。御所車は彼らに関連する文化や歴史の中で使われた。
宮廷:皇族や貴族が住む場所やその周辺。御所車は宮廷文化において重要な役割を果たした。
伝統工芸:地域特有の技術や技法に基づいて作られる工芸品。御所車もその美しさや技巧から伝統工芸の一部とされる。
儀式:特定の目的のために行われる正式な行動。また、御所車は様々な儀式や重要な場面で使われることがある。
衣装:特定の目的や場面に適した服装のこと。御所車を運ぶ際には、特別な衣装を着ることが一般的。
日本の文化:伝統や習慣、芸術など、日本特有の文化全般を指す。御所車は日本の文化を象徴する一つの例である。