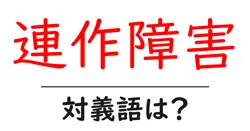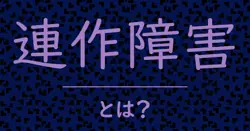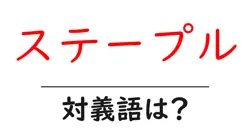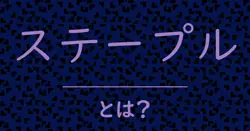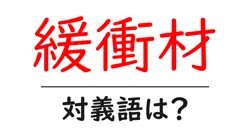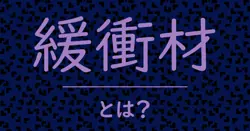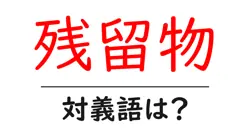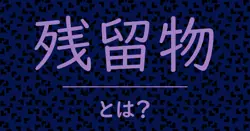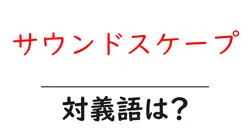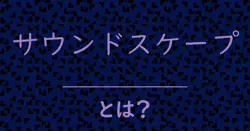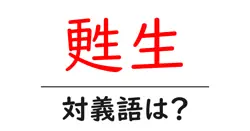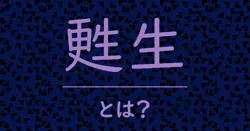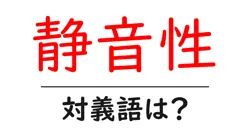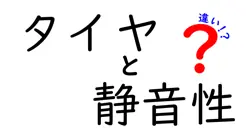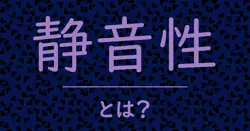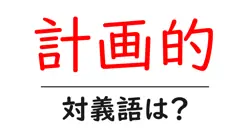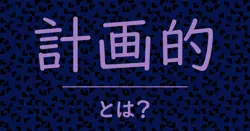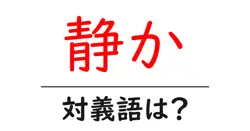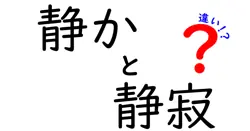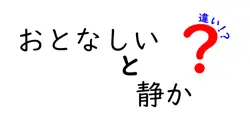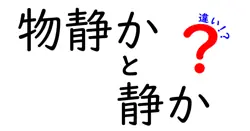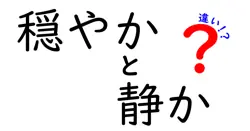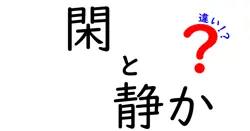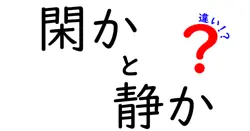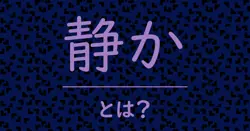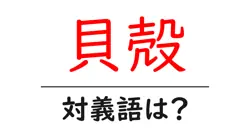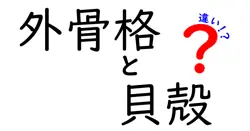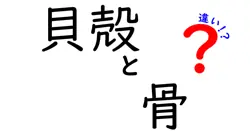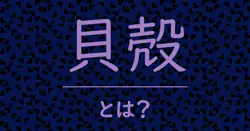連作障害とは?
連作障害(れんさくしょうがい)とは、同じ場所で同じ作物を繰り返し栽培することで起こる問題のことを指します。農業では、同じ作物を何年も連続して栽培すると、土壌の栄養が偏ったり、病気や害虫が増えたりすることがあります。これが連作障害です。
連作障害が起こる原因
連作障害が何故起こるのか、主な原因を紹介します。
| 原因 | 説明 |
|---|---|
| 土壌の栄養素不足 | 同じ作物を栽培することで特定の栄養素が消費され、他の作物には必要な栄養素が不足します。 |
| 病害虫の繁殖 | 同じ作物を栽培することで、その作物特有の病害虫が繁殖しやすくなります。 |
| 土壌構造の劣化 | 繰り返し同じ作物を栽培することで、土壌の物理的な特性が変わり、根が育ちにくくなります。 |
連作障害の対策方法
連作障害を避けるための効果的な対策があります。以下にいくつかの方法を紹介します。
- crop rotation(輪作):異なる作物を順番に栽培することで、土壌の栄養を均等に保つことができます。
- soil amendment(土壌改良):堆肥や化学肥料を使い、土壌の栄養を補充しましょう。
- pest management(害虫管理):天敵を利用したり、有機的な防除を取り入れたりすることで、害虫の被害を軽減します。
おわりに
連作障害は、農業を行う上で避けて通れない問題ですが、適切な知識と対策を知っておくことで、被害を最小限に抑えることができます。初心者の方でも、この知識を活かして、安全で豊かな農業を目指しましょう。
さつまいも 連作障害 とは:さつまいもを育てるとき、同じ場所で何年も連続して栽培することがありますが、それが「連作障害」を引き起こす原因になることがあります。連作障害は、同じ作物を繰り返し育てることで土壌が疲れてしまい、作物がうまく育たなくなる現象です。さつまいもは特に連作に弱い作物の一つで、土の中にある病原菌や害虫が増えてしまうことが問題です。これらの病害虫はさつまいもの成長を妨げ、結果的に収穫が減ってしまいます。連作を避けるためには、さつまいもを育てる場所を定期的に換えたり、他の作物を栽培して土壌を休ませることが大切です。また、適切な肥料を使って土の栄養を保つことも効果的です。連作障害を理解して、さつまいもを健康に育てる方法を学ぶことが重要です。これからさつまいもを育てたいと思っている方は、連作障害を意識してみてください。きっと美味しいさつまいもが収穫できるでしょう!
じゃがいも 連作障害 とは:じゃがいもを育てるときには、連作障害に注意する必要があります。連作障害とは、同じ場所で同じ作物を何度も育てることで、土壌の養分が減少したり、有害な病原菌が増えたりして、作物がうまく育たなくなる現象のことです。じゃがいもは特にこの影響を受けやすく、連続して同じ場所で育てると、根腐れや葉枯れなどの病気にかかるリスクが高まります。 連作障害を防ぐためには、じゃがいもを育てた後は、別の場所で他の作物を植えるローテーション方式を採用することが重要です。例えば、1年目にじゃがいもを育てたら、2年目にはトマトやきゅうりなど、まったく異なる作物を育てると良いです。このようにすることで、土壌の栄養バランスが整い、健康な作物を育てやすくなります。もし連作障害を防げたら、もっと美味しいじゃがいもを収穫できるかもしれません。どんな作物でも、大切に育てるためには、土壌と作物の関係を理解することが大切です。みなさんも、自分の畑や庭で試してみてください。
植物:地面に根を下ろして成長する生物で、連作障害の影響を受けるため、作物の育成に重要です。
土壌:植物が育つための基盤であり、連作障害は土壌中の養分や微生物のバランスに関連しています。
耐性:特定の植物が連作障害に対して持つ能力。耐性のある作物を選ぶことが対策の一つです。
作物:農業で育てられる植物のこと。連作障害は特定の作物の連続栽培によって引き起こされます。
養分:植物が成長するために必要な栄養素。連作障害が発生すると、養分の depletion(枯渇)が問題となります。
根:植物の下部にある部分で、養分や水分を吸収します。連作障害は根の発育にも影響を及ぼします。
農薬:害虫や病気から作物を守るために使われる化学物質。連作障害により病害が増えると、農薬の使用が増えます。
輪作:異なる作物を順番に栽培する方法。連作障害を防ぐために重要な対策として推奨されています。
微生物:土壌中に存在する小さな生物で、植物の成長を助ける役割を持つ。連作障害は微生物のバランスにも影響を与えます。
病害:植物の健康を脅かす病気。連作障害があると、特定の病気が発生しやすくなります。
連作障害(れんさくしょうがい):同じ作物を同じ場所で繰り返し栽培することで発生する様々な障害。作物の成長や収量が低下する原因となります。
土壌疲弊(どじょうひへい):特定の作物ばかりを栽培することによって、土壌が栄養を失い、植物がうまく育たなくなる状態。
病害虫の蓄積(びょうがいちゅうのちくせき):同じ作物が何度も栽培されることで、その作物特有の病気や害虫が増加し、影響を及ぼすこと。
土壌劣化(どじょうれっか):作物の栽培に伴い、土壌の物理的、化学的、または生物的な性質が悪化すること。
作物の健康不良(さくもつのけんこうふりょう):連作によるストレスや病害虫の影響で、作物が健康に育たない状態。
栄養失調(えいようしっちょう):土壌中の栄養素が消耗され、作物に必要な栄養を供給できなくなること。
土壌:植物が育つための栄養分や水分を含んだ地面のこと。連作障害はこの土壌に関係している。
養分:植物が成長するために必要な栄養素のこと。連作障害は土壌の養分が失われることから起こる。
病害虫:植物に害を与える病気や虫のこと。連作障害は特定の病害虫が増えやすい環境を作ることがある。
輪作:異なる作物を順番に栽培する方法で、連作障害を防ぐのに役立つ。
短所:連作を続けることで発生する問題やネガティブな結果のこと。これには土壌の質の低下が含まれる。
長所:輪作のような方法で連作障害を回避することで得られるメリットのこと。土壌の健康を保つことができる。
微生物:土壌中に生息する小さな生物のこと。連作障害の影響で微生物のバランスが崩れることがある。
施肥:土壌に肥料を与えること。連作の場合、特に注意して施肥を行うことが重要となる。
作物:農業で育てられる植物のこと。連作障害は同じ作物を続けて栽培した場合に起こりやすい。
土壌改良:土壌の質を改善するための方法で、連作障害の対策の一環として行われる。