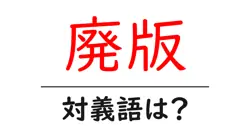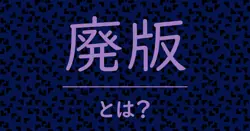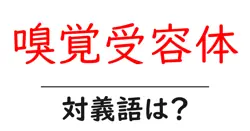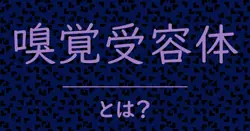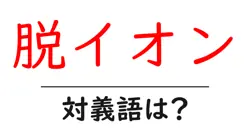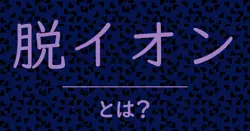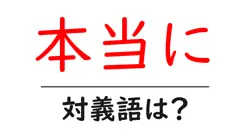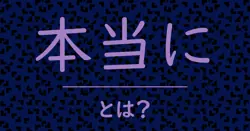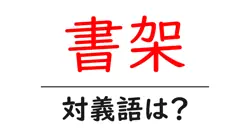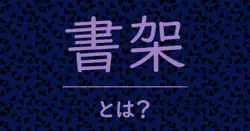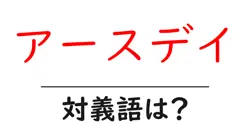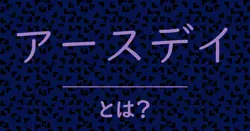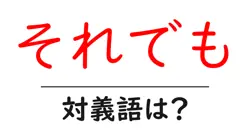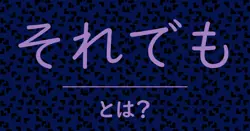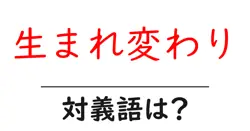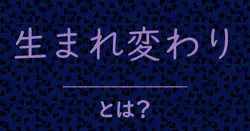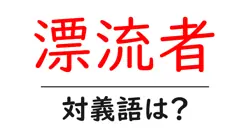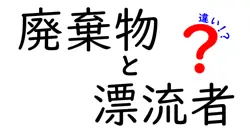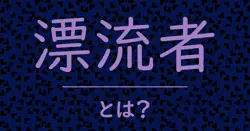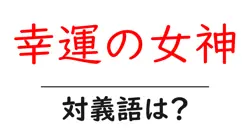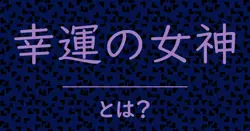廃版とは?
「廃版」という言葉は、一般的に書籍や商品などが市場に出回らなくなったこと、つまり、その商品や書籍が製造されなくなった状態を指します。例えば、本屋さんで見かけた好きな本がいつの間にか手に入らなくなってしまった、ということがありますよね。それが「廃版」という状態です。
廃版になる理由
廃版はさまざまな理由で起こりますが、主なものを以下にまとめました。
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| 需要の低下 | 消費者の興味が薄れ、売れなくなった場合。 |
| 新しいモデルの登場 | 新たな商品や版がリリースされ、旧版が不要になること。 |
| 製造コストの上昇 | 製造が収益的に不利になり、生産をやめること。 |
廃版の影響
廃版になると、消費者や読者にとってはアクセスできない状態になるため、人気商品や名著が手に入らないことがあります。特に漫画やゲームなど、人気が一時的に高まったものが廃番になると、ファンからの悲鳴が聞こえてくることもあります。また、コレクターにとってはその商品が希少価値を持つことになり、逆に高く取引されることもあります。
どうすれば廃版に備えられるのか
廃版のリスクを理解し、好きな商品や書籍が廃版になる前に慎重に購入することが大切です。そのための方法としては:
まとめ
「廃版」という言葉は、私たちの身近なところで起こる現象です。お気に入りの本や商品が手に入らなくなる前に、しっかりと情報をチェックし、計画的に購入しておくことが重要だということを覚えておきましょう。
製品:廃版に関連する商品やアイテムのことを指します。廃止された製品は市場に存在しないため、新しいものと区別されることがあります。
在庫:廃版になると、その製品の在庫も少なくなります。流通在庫が残っている場合、消費者はその製品を購入できることもあります。
需要:廃版となる製品に対する需要は、時に高まります。特に、コレクターズアイテムや特定のファン層がある場合、需要が残ることがあります。
買い替え:廃版となった製品に代わる新しい製品を購入することを指します。これにより、企業は最新のモデルを提供し続けることができます。
サポート:廃版になると、その製品に対するサポートが終了することが多いです。修理や部品供給ができなくなることがあります。
リニューアル:廃版から新しい製品が登場する際に、その製品の機能やデザインを刷新することを指します。
エンドオブライフ:製品の販売終了やサポート停止を指す言葉で、廃版のプロセスを示す専門的な用語です。
代替品:廃版となった製品の代わりに使える類似の製品を指します。消費者は廃版製品の代替品を探すことが一般的です。
ライセンス:ある製品が廃版になると、その製品に関連するライセンスも終了する場合があります。これにより、新たな製品の開発が制約されることがあります。
マーケット:廃版品が出ると、そのマーケットでの競争や流通に影響を与えることがあります。市場の供給と需要が変動するためです。
終了:製品やサービスの提供が終わり、もはや利用できない状態を指します。
販売終了:特定の商品がもはや市場に出ておらず、売られていない状態です。
絶版:書籍や雑誌などが再販されないため、流通が終わった状態を示します。
取り扱い停止:メーカーや販売店がその商品を扱わなくなったことを指します。
排版:生産が終了し、商品が市場に出回らなくなることを表現しています。
廃止:特定の法令や制度、サービスが無効になり、存在しなくなることを指します。
廃業:事業を終了し、企業が活動を行わなくなること。商品やサービスの提供を停止します。
在庫処分:販売が終了した商品や古くなった在庫を処分すること。廃版になった商品も含まれ、処分セールなどで安価で販売されることがあります。
エンドオブライフ:製品やサービスが生産・販売を終了すること。これにより、サポートも終了する場合が多いです。
リファービッシュ:廃版・旧モデルの製品を再生・修理して販売すること。新しいモデルの普及に伴い、これら旧製品が廃版になることがあります。
需要の減少:消費者のニーズが減少し、商品やサービスの販売が落ち込むこと。これが原因で商品が廃版になることがあります。
製品ライフサイクル:製品が市場に投入されてから廃版になるまでの過程。導入期、成長期、成熟期、衰退期を経て廃版になります。
代替品:廃版になった商品に代わって新しく登場した商品。消費者は新モデルや競合品に移行することが多いです。
マーケティング戦略:販売している商品が廃版になる過程での市場動向に応じて企業がとる方針。需要を見極め、計画的に廃版を行います。
製品のリニューアル:廃版になった商品の機能やデザインを改良し、新たに製品を投入すること。廃版を受け、新たな需要に応える期待があります。