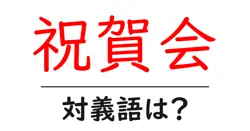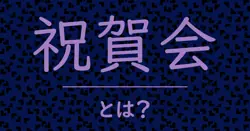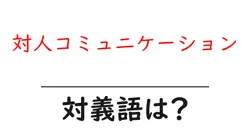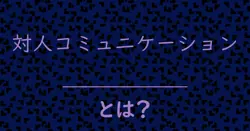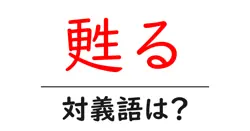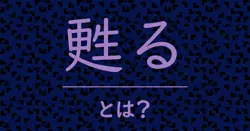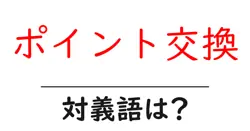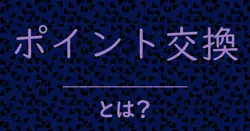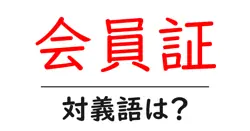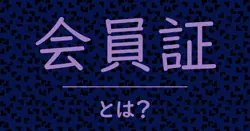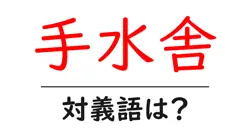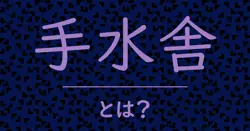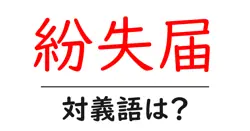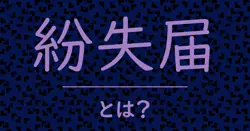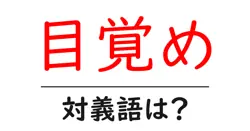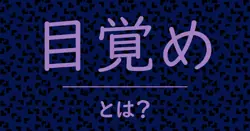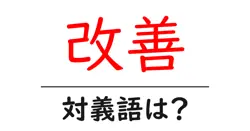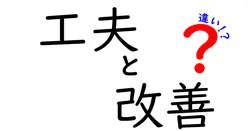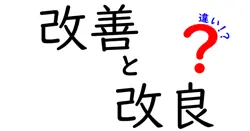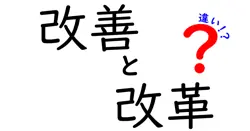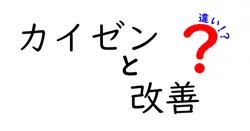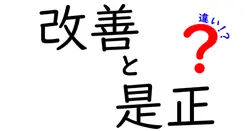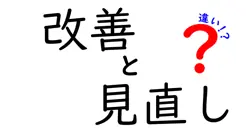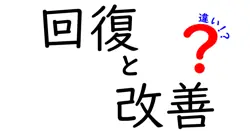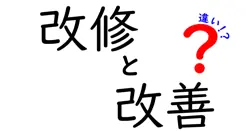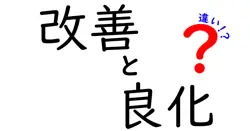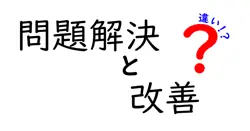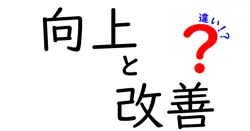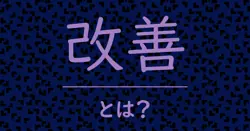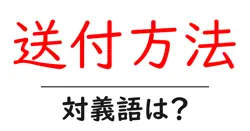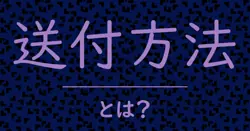「改善」とは?
「改善」という言葉は、物事をより良くすることを意味します。何か問題や課題があった場合、それを見つけて、より良い状態にするための行動をとることが「改善」です。例えば、学校の勉強がうまくいっていないと感じるとき、どうすれば成績を上げられるか考えて、そのために勉強法を変えることが「改善」に当たります。
「改善」の具体例
この「改善」という言葉は、さまざまな場面で使われます。以下にいくつかの具体例を挙げてみましょう。
| 場面 | 具体例 |
|---|
| 学校 | 勉強方法の見直し |
| 仕事 | 業務効率の向上 |
| 家庭 | 家事の分担を見直す |
| 健康 | 食生活の改善 |
改善のステップ
改善には、いくつかのステップがあります。まず、現状を把握し、次に問題点を特定、そして改善案を考え、最後に実行し、結果を確認するという流れです。このプロセスを繰り返すことで、常により良い状態を目指すことができます。
なぜ改善が重要なのか?
改善は、ただ単に自分や周りを良くするだけでなく、チームや組織全体のパフォーマンスを向上させるためにも重要です。また、改善を意識することで自己成長にもつながります。例えば、スポーツや勉強、人間関係など、どんな分野でも改善を繰り返すことで、自分のスキルや知識が向上します。
「改善」という考え方は、個人の生活だけでなく、社会全体にも影響を与えます。企業が製品を改善し続けることで、消費者にとってより良いサービスや商品が提供され、経済全体が発展するのです。そのため、「改善」は私たちが日々の生活に取り入れ、実践していくべき大切な概念といえるでしょう。
改善のサジェストワード解説cip とは 改善:CIPという言葉は、「継続的改善プロセス」を意味しています。この考え方は、組織や事業の効率を常に向上させるために用いられます。CIPは、一度きりの改善ではなく、継続的に少しずつ改善していくことが大切です。たとえば、学校の授業を考えてみましょう。先生が生徒の意見を聞いて、授業の内容や進め方を少しずつ変えていくようなものです。このような段階的なアプローチにより、学びやすい環境が整えられ、生徒たちの成績向上にもつながります。CIPは、製造業やサービス業など、さまざまな分野で活用されています。また、従業員が自分たちの業務を見直し、改善のアイデアを出し合うことで、組織の一体感も生まれます。このように、CIPは単なる効率化だけでなく、みんなの意識を高めるための手法でもあります。業務やプロジェクトの成果を続けて向上させたい場合には、CIPの考え方を取り入れてみると良いでしょう。
kaizen institute とは:Kaizen Institute(カイゼン・インスティテュート)は、企業や組織が持続的に改善を果たせるようサポートする専門機関です。「カイゼン」とは日本語で「改善」を意味し、特に製造業やサービス業での効率的な働き方を追求した手法として広まっています。カイゼン・インスティテュートは世界中にオフィスを持ち、企業に対してトレーニングやコンサルティングサービスを提供しています。彼らが教えるのは、小さな変化を積み重ねることで大きな成果を上げる考え方です。例えば、工場の作業を少しだけ改善することで、時間やコストを大幅に削減できることがあります。カイゼンの理念は、社員全員が参加して提案をすることにあります。これにより、現場のアイデアを活かした改善が実現します。成果が出ると、社員のモチベーションも上がり、より良い職場環境を作ることにもつながります。まとめると、Kaizen Instituteは組織が効率を上げるための知識や手法を提供する、改善の専門機関です。
kaizen platform とは:Kaizen Platform(カイゼン プラットフォーム)とは、企業が業務改善を行うためのオンラインツールです。特に、大きな変化を求めるのではなく、少しずつの改善を積み重ねることを目指しています。この考え方は、「カイゼン」と呼ばれ、もともとは日本の製造業から発展しました。カイゼンプラットフォームでは、社員が自身の業務を見直し、改善案を提案することができます。例えば、製品の制作過程やサービスの提供方法など、あらゆる面で改善を目指すことが可能です。提案が出されると、それを企業が受け入れて実行することによって、業務が効率化され、コスト削減にもつながるのです。このプラットフォームの最大の利点は、社内のアイデアを集めやすくし、全員でより良い環境を作ろうとする姿勢を促すところにあります。結果として、社員のモチベーションも向上し、企業としての競争力も増すことが期待できます。
kaizen とは:Kaizen(カイゼン)とは、日本語で「改善」を意味します。特にビジネスの世界でよく使われる言葉で、品質や効率を向上させるための方法論として広まりました。カイゼンは、少しずつ改善していくことを重視し、小さな変更でも積み重ねていくことで大きな成果を生み出すという考え方です。たとえば、工場での作業手順を見直して、無駄な時間を減らすことで生産性を高めることがカイゼンの一例です。また、カイゼンは全社員が参加することが大切です。各人がアイデアを出し合い、改善アクションを提案することで、全体の業務が良くなっていきます。このように、カイゼンは単なる手法だけでなく、企業文化として定着しているのです。日本だけでなく、アメリカやヨーロッパなどでも広く採用され、競争力を高めるための重要な戦略となっています。カイゼンを実践することで、企業は効率的に成長し、持続可能な発展を目指すことができるのです。
インスリン抵抗性 改善 とは:インスリン抵抗性とは、インスリンというホルモンが体の細胞にうまく働かない状態を指します。これが起こると、血糖値が上がりやすくなり、糖尿病や心臓病のリスクが高まります。しかし、良いニュースがあります!インスリン抵抗性は改善できるのです。まず、食事から見直しましょう。野菜や果物、全粒穀物を多く食べ、加工食品や砂糖の摂取を控えることが大切です。そして、定期的に運動をすることも重要です。有酸素運動や筋トレを行うと、体がインスリンをうまく使えるようになります。さらに、ストレス管理や十分な睡眠も大事です。体が健康になれば、インスリン抵抗性も改善しやすくなります。これらを実践することで、より健康的な生活が送れるようになります。少しずつ挑戦して、毎日を楽しく過ごしましょう!
カイゼン とは:カイゼンとは、日本語で「改善」を意味します。この言葉は主にビジネスの現場で使われていて、仕事のやり方や製品の品質を少しずつ良くしていくことを指します。例えば、ある会社が製品の不良を減らすために作業の手順を見直したり、従業員が提案したアイデアを取り入れることもカイゼンの一環です。カイゼンは大きな変化を狙うのではなく、日々の小さな改善を積み重ねることが重要です。この方法はチーム全員が参加できるもので、みんなの意見を聞くことでより良い結果を得ることができます。カイゼンを実践することで、仕事の効率も上がり、製品やサービスの質も向上します。私たちの生活の中でも、カイゼンを意識することで、勉強の方法を見直したり、生活習慣を改善することができます。つまり、カイゼンはビジネスだけでなく、私たちの日常生活にも役立つ考え方なのです。
改善 5原則 とは:改善 5原則とは、業務やプロセスをより良くするために覚えておくべき5つの基本的な考え方のことです。この5原則は、企業や団体が品質向上や効率化、顧客満足度向上を目指すときに役立ちます。具体的には、まず1つ目は「顧客の視点」です。改善の目的は顧客を喜ばせることで、顧客のニーズを理解することが大切です。2つ目は「データの重要性」。データをもとに状況を把握し、何が問題かを明確にすることが改善の第一歩です。3つ目は「チームでの協力」。一人でできることには限界があるため、みんなでアイデアを出し合い、協力して改善します。4つ目の原則は「持続的な改善」です。改善は一度で終わるものではなく、常に見直しと更新が必要です。最後に5つ目は「プラン・ドゥ・チェック・アクト(PDCAサイクル)」。改善を計画(プラン)し、実行(ドゥ)したら、その結果を確認(チェック)し、さらに改善策を考え(アクト)ることが重要です。このような原則を実践することで、より良い結果を生むことができるのです。
改善 とは トヨタ:「改善」とは、物事をより良くするために行う工夫や努力のことを指します。特にトヨタ自動車で使われている「カイゼン」という考え方は、少しずつでも改善を積み重ねることで、全体の効率や品質を向上させることを目指しています。トヨタでは、全社員がカイゼンに取り組むことを推奨しており、自分の仕事に対して常に改善点を探し、実行することが求められます。たとえば、ある作業を行う中で、もっと早くできる方法や無駄を減らせる方法を見つけたら、そのアイデアを提案します。その結果、作業がスムーズになり、時間やコストが節約できることがあるのです。カイゼンは、身の回りの小さなことから始められるため、特別なスキルがなくても誰でも実践可能です。そして、この考え方は、仕事だけでなく、家庭や学校生活にも取り入れられます。たとえば、勉強方法を見直したり、家事の手順を工夫したりすることもカイゼンの一部と言えます。改善によって、一人ひとりの成長へとつながるので、この考え方をぜひ取り入れてみてください。
改善の共起語向上:物事のレベルや質をよりよくすること。改善と密接に関連しており、成果や効果を高めることを指します。
効率:作業やプロセスがどれだけ効果的に行われるかということ。改善は効率を高める手段の一つです。
分析:データや情報を詳しく調べ、問題点や改善点を見つけ出す行為。改善には、まず正確な分析が必要です。
戦略:目標を達成するための計画や方針を指します。改善には、しっかりとした戦略が求められます。
フィードバック:行動や成果についての反応や意見を指します。この情報を基に、改善を図ることが重要です。
成果:取組の結果として得られるもの。改善を行うことで成果が向上することが期待されます。
活動:改善のために実施する具体的な行動。なにかを改善するためには活動が欠かせません。
目標:達成したい具体的な状態や結果を指します。改善はこの目標に向かって進むプロセスの一部です。
課題:解決すべき問題や不足している部分を指します。改善には、これらの課題を特定し、克服することが必要です。
実行:計画や戦略を具体的に行動に移すこと。改善のためには、単に考えるだけでなく、実行が不可欠です。
改善の同意語向上:物事をより良い状態にすること。特に、技術や成績などを高めることを指します。
改良:既存のものをより良くするために手を加えること。製品やシステムの効率や機能を向上させる作業です。
改善策:現在の問題や欠点を解決するための具体的な方法やプランを意味します。
修正:誤りや不備を取り除き、より正確で適切な状態にすることです。文書やデータに対して行われることが多いです。
調整:何かが最適な状態になるように微調整を行うこと。特に設定や計画のバランスを取る作業に使われます。
改善活動:問題を特定し、解決策を実行するための一連の行動を指します。特に企業やチームでの取り組みに多く見られます。
改善の関連ワード最適化:特定の目標に対して、最も効果的な手段を見つけること。例えば、ウェブサイトの表示速度やSEOの向上を目指す場合に行われます。
フィードバック:実施した行動やプロセスに対する反応や評価のこと。改善に活かすための情報源として重要です。
評価指標:特定の目的に対する進捗や成果を測定するための基準。例えば、アクセス数やコンバージョン率などが含まれます。
プロセス:特定の目標を達成するための一連の手順や方法。改善活動では、このプロセスを見直すことで効果を上げます。
データ分析:収集したデータを整理し、そこから意味を見出すこと。改善のために必要な情報や問題点を特定するのに役立ちます。
ベンチマーキング:他の競合や業界ベストプラクティスと自社のパフォーマンスを比較し、改善点を見つける手法。
継続的改善:少しずつでも常に改善を行い続けること。これは、長期にわたって競争力を維持するために重要です。
アクションプラン:具体的な改善策や対応方法をまとめた計画。実施するべき行動を明確にすることで、効率的な改善を実現します。
問題特定:改善すべき問題や課題を見つけ出すプロセス。これがなければ、実際に何を改善するかを理解することは難しいです。
目標設定:改善を行う際に、達成したい具体的な成果を決めること。明確な目標があれば、それに向けた行動がしやすくなります。
改善の対義語・反対語
改善の関連記事
生活・文化の人気記事

2777viws

2435viws

1762viws

2289viws

1633viws

2313viws

1923viws

1608viws

1768viws

2935viws

2794viws

6195viws

2573viws

2972viws

2087viws

4444viws

2933viws

4328viws

2380viws

2297viws