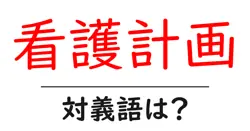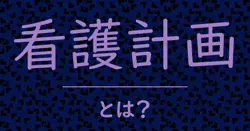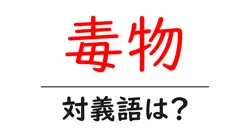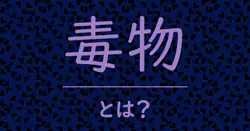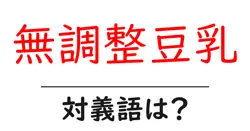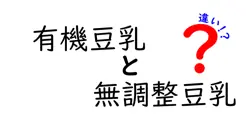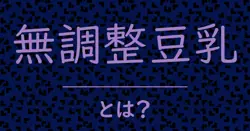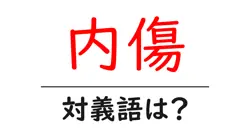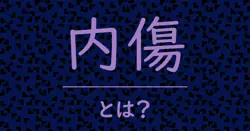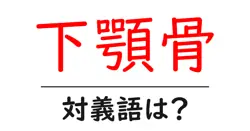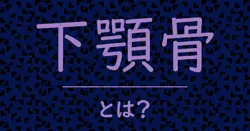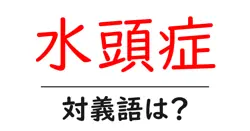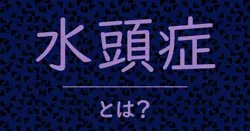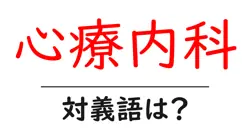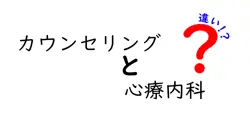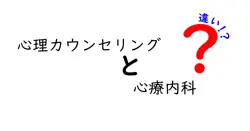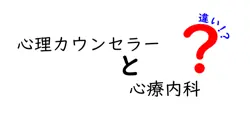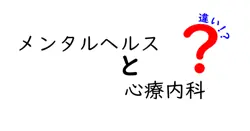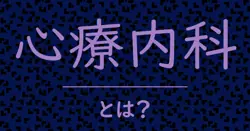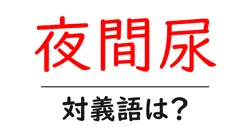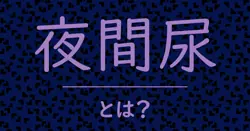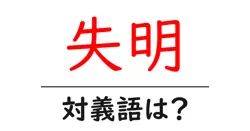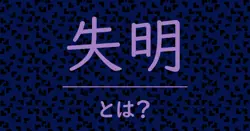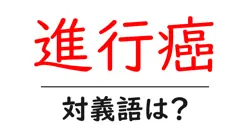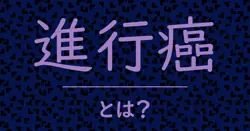看護計画とは?
看護計画とは、患者さんの健康状態を把握し、最適な看護を提供するための計画のことです。これにより、看護師は患者さん一人ひとりにあったケアを行うことができます。
看護計画の目的
看護計画の目的は、以下の点にあります。
| 目的 | 説明 |
|---|---|
| 患者の状態の把握 | 患者さんの病状や生活状況を理解すること。 |
| 必要な看護の提供 | 患者さんに必要な看護やケアを計画し実施すること。 |
| 効果的なコミュニケーション | 看護師同士や他の医療スタッフとの情報共有を円滑にすること。 |
看護計画の作成手順
看護計画は以下のステップで作成されます。
1. 評価
まず、患者さんの状態を評価します。これには、体温や血圧、患者さんの話などが含まれます。
2. 問題点の特定
評価の結果から、患者さんの問題点を見つけます。
3. 目標設定
患者さんのための目標を設定します。たとえば、「痛みを軽減する」「歩行能力を改善する」などです。
4. 看護介入の計画
目標を達成するために、具体的な看護介入を計画します。
5. 結果の評価
計画を実施した後、結果を評価し、必要に応じて計画を修正します。
看護計画の重要性
看護計画はただの書類ではありません。患者さんの健康や生活に大きな影響を与えます。これにより、患者さんに安全で質の高い看護を提供することができるのです。
まとめ
看護計画は、患者さん一人ひとりに合った看護を提供するための重要なツールです。計画の作成には時間と労力が必要ですが、その結果、患者さんがより良い状態になる手助けをすることができます。
看護師 看護計画 とは:看護計画とは、患者さんに対する看護の方法や方針を具体的にまとめたものです。看護師は、患者さんの状態を把握し、必要なケアを考えるために、この計画を作成します。看護計画を作る際には、まず患者さんの健康状態を評価し、その情報を基に目標を設定します。その後、どのような看護を提供するか、具体的な介入内容を決めます。例えば、薬の投与、食事の管理、リハビリテーションなどが含まれます。看護計画は、患者さんがより良い健康を得られるようにするための大事な手段です。また、看護計画は定期的に見直されます。患者さんの状態が変わったり、目標が達成された場合には、計画を更新する必要があります。このように、看護計画は、患者さん一人ひとりに合った最適な看護を提供するために欠かせないものです。看護師はこの計画を通じて、患者さんとのコミュニケーションを大切にし、信頼関係を築いていきます。
看護計画 tp とは:看護計画tpとは、看護の現場で使われる「看護計画」と呼ばれるものをコンパクトにまとめたものです。看護計画は、患者さんの健康状態を把握し、適切な看護を提供するために必要な情報を整理する手助けをします。tpというのは、‘treatment protocol’の略で、治療の手順や流れを示すものです。看護計画tpを使うことで、看護師は患者さん一人ひとりに対してどのような治療やケアを行うべきかを明確にすることができます。これにより、患者さんのニーズに合った適切な看護ができるようになります。初心者でも、看護計画tpを理解することで、実際の看護現場でどのようにケアを行うかを学ぶことができ、スムーズな業務の進行が期待できるのです。これらの情報は、看護師や医療関係者だけでなく、患者さんやその家族にとっても重要な知識となります。
看護診断:患者の健康状態や問題点を特定するための評価プロセス。
介入:看護計画に基づいて行う具体的な行動や施策のこと。
評価:看護介入の効果を確認し、必要に応じて計画を見直すプロセス。
患者教育:患者に対して健康管理や病気に関する知識を提供すること。
目標設定:看護計画の中で、患者の状態を改善するために達成すべき具体的な目標を定めること。
関連要因:看護診断の根本原因や影響を与える要素のこと。
看護過程:看護計画を立てるための一連のステップ(評価、診断、計画、介入、評価)を指す。
アセスメント:患者の状態を詳しく評価し、情報を収集するプロセス。
チームアプローチ:複数の医療従事者が連携して患者に最適なケアを提供する方法。
看護計画書:看護を行う際に患者の状態や必要なケアを具体的に示した文書です。
クリティカルパス:患者の治療やケアの流れを一連の手順として整理したもので、看護計画の一環として用いられることがあります。
看護プロセス:看護計画を作成するためのステップや過程のことを指し、アセスメント、診断、計画、実施、評価の各段階から成り立っています。
ケアプラン:患者の問題に基づいて立てられた具体的な看護の方針や手順です。看護計画とほぼ同義ですが、より広い意味合いを持つ場合もあります。
看護実践ガイド:看護師が実際の看護を行う際の指針を示した文書で、特定の患者に対してどのような看護を提供すべきかの参考になります。
看護診断:患者の健康状態やニーズを評価し、看護に必要な問題を特定すること。看護計画の基盤となります。
看護目標:患者に対して設定された具体的な成果や改善の目標。看護計画内での達成を目指します。
看護介入:看護計画に基づいて行う具体的なアクションや施策。患者の健康を支えるために行う手段です。
評価:看護介入の効果を確認し、目標が達成されたかどうかを判断するプロセス。看護計画が有効であるかの見直しにもつながります。
個別性:看護計画は患者一人ひとりの状況に応じて、個別に構成されるべきであるという考え方。すべての患者に対してユニークなアプローチを必要とします。
多職種連携:看護師以外の医療従事者(医師、理学療法士など)が協力して患者の看護計画を策定・実施すること。チームワークが重要です。
優先順位:複数の看護診断や目標がある場合、どれを優先的に解決するべきかを決定すること。限られたリソースを効果的に使います。
持続可能性:看護計画が時間をかけても実施可能であり、患者の生活に長期的に寄与することを指します。短期の効果ではなく、持続的な改善を目指します。