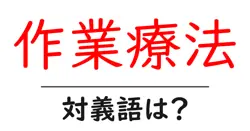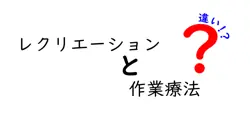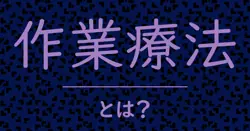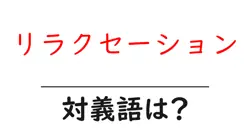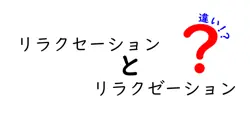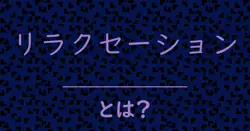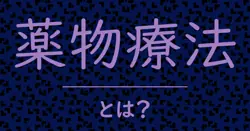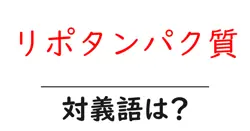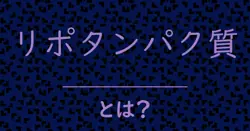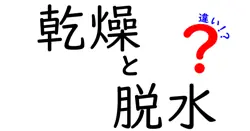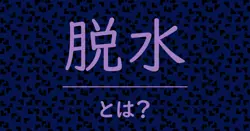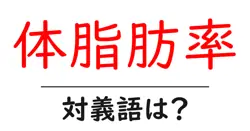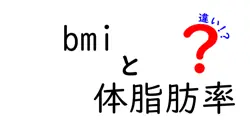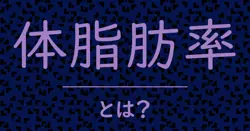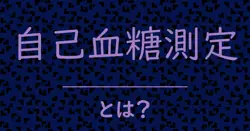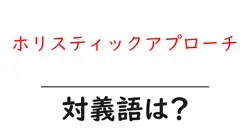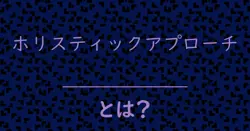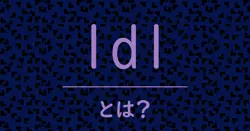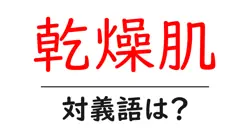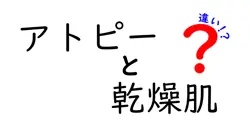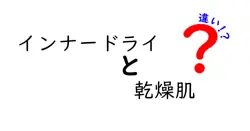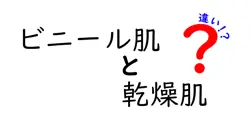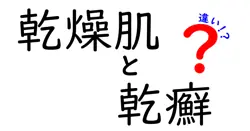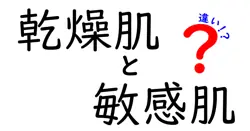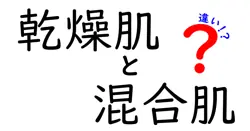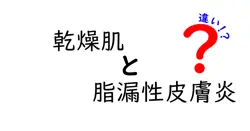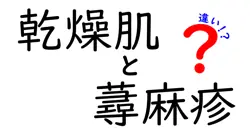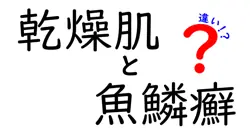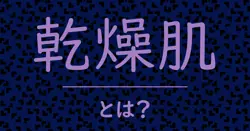作業療法とは?
作業療法(さぎょうりょうほう)は、病気やけが、または障害がある人が、自立した生活を送るために行う治療法です。この療法では、日常生活に必要な動作や活動を通じて、体と心の機能を改善していきます。
作業療法の目的
作業療法の主な目的は、自分でできることを増やし、より良い生活を送ることです。たとえば、けがをした後に元のように歩けるようにするためのリハビリテーションや、認知症の家族のサポートなども含まれます。
作業療法の進め方
作業療法は、以下のような手順で進められます:
- 評価: 患者さんの状態を詳しく調べます。
- 目標設定: 患者さんと一緒に、どのような生活を送りたいかを決めます。
- プランニング: 目標を達成するための具体的な方法を考えます。
- 実施: 患者さんに合わせた活動を行います。
- 評価と調整: 結果を見ながら、計画を見直します。
どんな活動があるの?
作業療法では、様々な活動が行われます。以下はその一例です:
| 活動 | 目的 |
|---|---|
| 料理 | 日常生活の自立を促進する |
| 手芸 | 集中力や指先の運動機能を向上させる |
| スポーツ | 体力の向上と社会性を身につける |
作業療法のメリット
作業療法の大きなメリットは、自分の好きなことを通じてリハビリテーションを行えるため、患者さんが楽しく感じられることです。また、社会参加を促進し、コミュニケーション能力を高める機会にもなります。
まとめ
作業療法は、患者さんがより良い生活を送るために欠かせない治療法です。自立を促すための活動を通じて、心と体の健康を支援します。リハビリが必要な時には、ぜひ作業療法を考えてみてください。
obp とは 作業療法:作業療法におけるOBP(アウトカムベースのプラクティス)とは、患者さんの治療やリハビリの効果をしっかりと測るための考え方です。これにより、どんな治療が実際に役立っているのか、どんな効果が出ているのかを具体的に知ることができます。OBPは、治療を受けている人の視点を大切にし、患者さん自身の目標や生活の質を基にして、治療の方向性を決めます。例えば、ただ単に身体の動かし方を教えるだけでなく、「この動きができるようになったら、日常生活がもっと楽になる」といった具体的な目的を持つことが重要です。これにより、治療がより効果的になり、患者さんの満足度も上がります。作業療法士はOBPを通じて、患者さんとコミュニケーションを取りながら、一緒に目標を設定し、進捗を確認しています。結果的に、OBPはより個別化された治療を実現し、患者さんの回復をサポートする強力なツールと言えます。
作業分析 とは 作業療法:作業分析とは、特定の作業やアクティビティを細かく分解して、その内容や必要なスキルを理解するプロセスのことです。これは特に作業療法の分野で重要で、患者が実生活で必要な動作を行えるようにサポートするために行われます。例えば、病気やけがで手が不自由になった人が、自分で衣服を着ることができるようになるためには、どのような動作が必要かを分析します。作業分析によって、達成可能な目標を設定したり、必要なサポートや道具を導入することができます。これにより、患者が自立した生活を送れるように手助けすることが目的です。作業療法士は、患者の個々の状況や目標に応じて、作業分析を行い、最適なアプローチを考えます。このように、作業分析は、患者が生活の質を向上させるための第一歩となるのです。
作業療法 ot とは:作業療法(OT)は、心や体に障害がある人がより良い生活を送るために行うリハビリテーションの一つです。OTは、単に身体的なリハビリだけでなく、日常生活に必要な「作業」ができるように支援することを目的としています。ここで言う「作業」とは、食事や着替え、趣味活動など、生活の中で楽しんだり役立ったりすることを指します。OTの専門家である作業療法士は、個々の状況に応じて、必要なスキルや作業を身につけられるように指導します。たとえば、事故や病気で手を使うことが難しくなった人には、特別な道具を使う練習をしたり、動かしやすくするための運動を提案したりします。こうしたサポートを受けることで、患者さんは自分自身の力で生活を楽しむことができるようになります。作業療法は、リハビリテーションの中でもとても重要な役割を果たしており、多くの人々の生活を支えています。
作業療法 とは 精神科:作業療法(さぎょうりょうほう)とは、患者さんが日常生活をより良く送るために行われる治療方法の一つです。特に精神科では、心の病気を持つ方に対して、作業療法がとても大切です。この治療は、患者さんが自分でできる作業や活動を通じて、より良い生活を目指すことを目的としています。 具体的には、作業療法士(さぎょうりょうほうし)が患者さんと一緒にいろいろな活動をします。絵を描いたり、手芸をしたり、日常生活に必要なスキルを磨くための練習をしたりします。これらの活動は、楽しみながら心を落ち着ける助けにもなります。 また、作業療法は、患者さんが達成感を感じたり、自信をつけたりするのに役立ちます。新しいことに挑戦することで、少しずつ自分の力を感じることができ、生活の質を向上させることができます。精神科での作業療法は、心の病気と戦うための大きな力になります。このように、作業療法は患者さんにとって、日常生活を取り戻すためのサポートをする重要な役割を果たしています。
理学療法 作業療法 とは:理学療法(りがくりょうほう)と作業療法(さぎょうりょうほう)は、リハビリテーションにおいてとても重要な役割を果たします。理学療法は、体の運動機能を改善するための治療です。例えば、けがをした後に体を動かすためのトレーニングや、強い痛みを和らげるための治療を行います。一方、作業療法は、日常生活で必要な動作や作業を通じて、心と体をリハビリする方法です。これには、食事をする、着替えをする、学校や仕事に復帰するための練習などがあります。理学療法は体に焦点を当てていますが、作業療法は生活全体、特に心理面や社会生活に重点を置いています。この二つの療法を組み合わせることで、利用者がより早く社会復帰できるようサポートしていくのです。リハビリの際には、専門のスタッフがそれぞれの療法を適切に組み合わせてくれるので、安心して取り組むことができます。
リハビリテーション:作業療法が対象とする、体や心の機能を回復するための治療や支援全般を指します。
自立支援:患者が日常生活を自分で行えるようにすることを目指す取り組みで、作業療法の重要な目的の一つです。
職業訓練:作業療法の一環として、患者が仕事を再開できるように必要なスキルを身につけるための訓練を指します。
評価:患者の機能や能力を測定し、作業療法の進行状況を確認するためのプロセスです。
介護:高齢者や障害者を対象に行われるサポートを指し、作業療法とも密接に関連しています。
機能訓練:特定の動作や技能を向上させるための訓練を指し、作業療法の主要な内容となります。
心のケア:身体的なリハビリだけでなく、心理的なサポートや治療を含む、作業療法の側面を指します。
生活動作:日常生活に必要な基本的な動作(食事、入浴、着替えなど)に焦点をあて、作業療法で訓練される内容です。
リハビリテーション:身体機能や日常生活の再獲得を目的とした支援や治療のこと。作業療法はその一環として行われる。
作業技術療法:作業を通じて患者の機能回復を図る療法。特に職業に関連した技能の向上を目的とすることが多い。
機能回復訓練:身体の治癒や機能を回復するための訓練。作業療法はこの訓練を通じて行われることもある。
生活支援:日常生活をスムーズに送るための支援。作業療法は、クライアントがより良い生活を送れるよう助けることを目指す。
作業支援:作業を行う上で必要な支援を行うこと。作業療法では、患者が作業を通じて社会参加できるようサポートする。
身体作業療法:身体の機能改善を目的とした作業療法の一種で、特に身体の動かし方や使用方法に焦点を当てる。
生活の質の向上:患者の生活の質を向上させることを目的とした療法。作業療法はこの質の向上を重視して取り組まれる。
リハビリテーション:身体的または精神的な疾患や障害を持つ人々が、可能な限り自立した生活を送り、社会に参加できるようにするための支援・治療方法です。
作業:作業療法においては、日常生活や職業、趣味、社交の場での活動を指し、参加や意味を持った行動を通じて人間らしさを取り戻すことを目指します。
クライエント中心アプローチ:作業療法では、クライエントのニーズや価値観に基づき、個別の支援計画を作成する方法論です。
運動療法:身体機能の改善を図るために行う運動です。作業療法の一環として、体力や機能を高めるために使われます。
心理社会的アプローチ:心の健康や社会的な関係性を重視し、クライエントの心理的支援や社会参加を促す手法です。
評価:クライエントの状態やニーズを把握するために行う観察やテストのこと。適切な介入を計画するために必要です。
介入:評価に基づいて、実際に行う支援や治療のこと。目的を達成するために色々な手段や方法が用いられます。
ADL(Activities of Daily Living):日常生活動作の略で、食事、入浴、着替えなど、日常生活を送るために必要な基本的な行動を指します。
家庭訪問:作業療法士がクライエントの自宅を訪れ、生活環境を評価し、必要な支援を提供することです。
サポートグループ:同じような問題を抱える人々が集まり、お互いにサポートし合うためのグループです。クライエントの社会的支援として有効です。