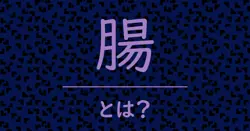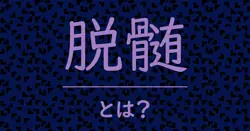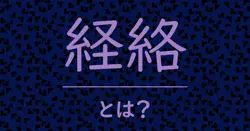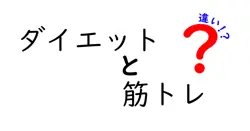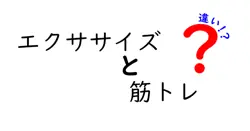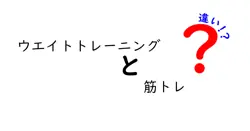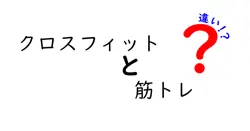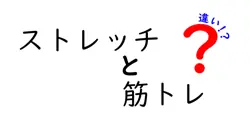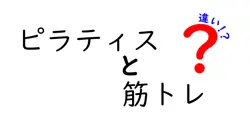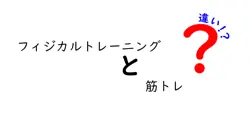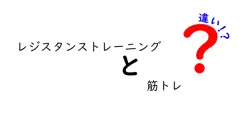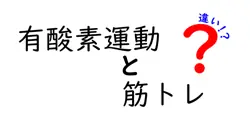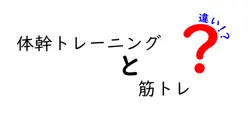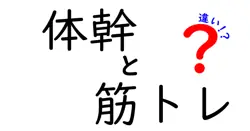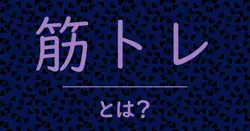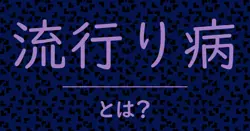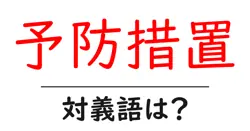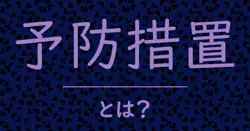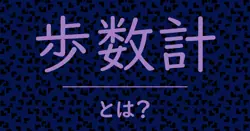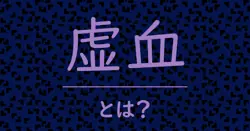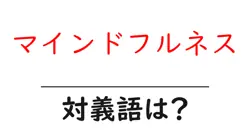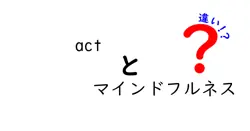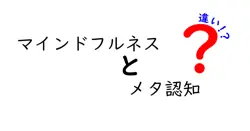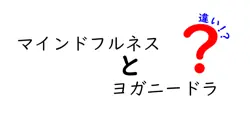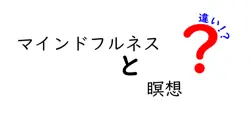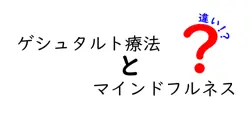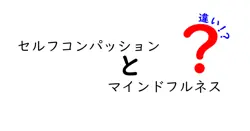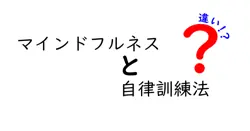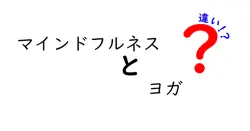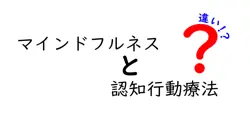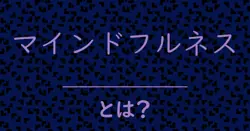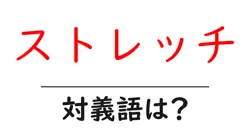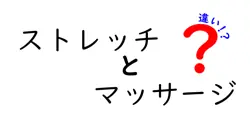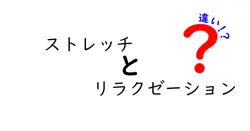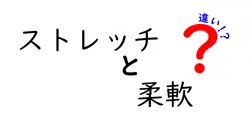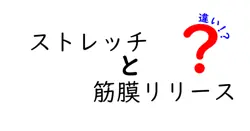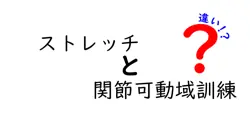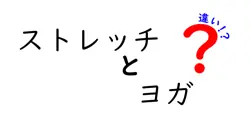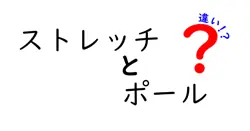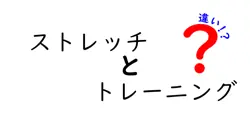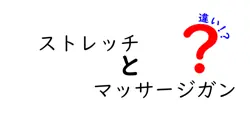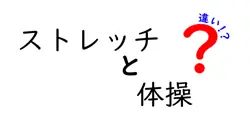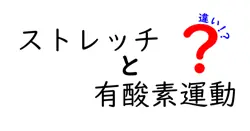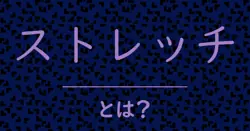筋トレとは?中学生にもできる筋力トレーニングの魅力と基本
筋トレ、つまり筋力トレーニングは、筋肉を強くしたり、健康を保つために行う運動のことです。特に成長期の中学生にとって、筋トレは体を作る大切な活動となります。今回は筋トレの基本やその効果について解説していきます。
筋トレの基本とは?
筋トレにはさまざまな方法がありますが、基本的なトレーニングには以下のようなものがあります。
| 種目 | 内容 | 効果 |
|---|
| 腕立て伏せ | 両手を地面に置いて体を上下させる | 胸の筋肉を鍛える |
| スクワット | 足を肩幅に開いてお尻を下げる | 太ももとお尻の筋肉を鍛える |
| 腹筋 | 仰向けになり、上半身を起こす | 腹筋を鍛える |
筋トレのメリット
筋トレをすることで、次のようなメリットがあります。
- 体力向上:筋肉が強くなることで、日常生活での活動が楽になります。
- 健康維持:筋力が増すことで新陳代謝が上がり、太りにくい体になることができます。
- 精神的効果:筋トレを続けることで、自己肯定感が高まり、ストレス解消にもつながります。
筋トレの注意点
筋トレは良いことばかりではありません。以下の点に注意しましょう。
- 無理をしないこと:体に負担をかけすぎないよう、自分のペースで行いましょう。
- 正しいフォーム:間違ったフォームで行うと怪我をする原因になります。鏡で自分の姿を確認することが大切です。
- 休息を取ること:筋トレをした後は筋肉が疲れていますので、しっかり休むことが重要です。
まとめ
筋トレは中学生でも始めやすく、健康や体力向上にとても効果的な運動です。自分の体を大切にしながら、無理のない範囲で続けていきましょう。
筋トレのサジェストワード解説big3 筋トレ とは:筋トレを始めたばかりの人にとって、「Big3」という言葉は耳にしたことがあるかもしれません。Big3とは、スクワット、ベンチプレス、デッドリフトの3つの基本的なエクササイズのことを指します。これらは、全身の主要な筋肉群を同時に鍛えることができるため、非常に効率的です。
まず、スクワットは脚やお尻の筋肉を鍛える運動で、体の中心を支える力を強くします。次に、ベンチプレスは胸や腕の筋肉を強化し、厚い胸板を作るのに役立ちます。そしてデッドリフトは、背中や脚の筋肉を使って持ち上げる運動で、全身の筋力をバランスよく鍛えます。
この3つの運動をすることで、体全体をしっかりと鍛えることができ、筋力を効率的に増やすことができます。特に、筋トレ初心者にはこのBig3を取り入れることで、体の使い方や基本的なフォームを学ぶ良い機会にもなります。最初は軽い重量から始め、自分のペースで徐々に負荷を増やしていくのがポイントです。さあ、あなたもBig3にチャレンジして、筋トレライフを楽しみましょう!
rm 筋トレ とは:RM筋トレ(レペティションマキシマム筋トレ)とは、最大で持ち上げられる重量を基にしたトレーニング方法です。簡単に言うと、あなたが一度だけ持ち上げられる重さを使って、その筋肉を鍛えるというやり方です。この方法は主に筋肉を大きくするために使われることが多いですが、正しい方法で行うことがとても大事です。
例えば、重量を選ぶことが最初のステップです。自分が持ち上げられる重さを知るためには、まず軽い重量から始めて、徐々に重くしていくのがいいでしょう。目安として、自分の最大の重さの70~80%くらいを使って10回前後が目標です。そして、しっかりしたフォームを保ちながら、筋肉に負荷をかけていきます。
また、RM筋トレをする際には、充分な休憩も重要です。筋肉を休ませることで、さらに強くなっていくためです。中学生でも簡単にできるこのトレーニング方法は、友達と一緒にやるとモチベーションも上がりますよ。健康的でかっこいい体を目指して、RM筋トレを楽しんでみてください!
ネガティブ 筋トレ とは:ネガティブ筋トレという言葉を聞いたことがありますか?これは、筋肉を鍛える一つの方法で、特に筋肉の力を使ってゆっくり動かすトレーニングを指します。通常、筋トレでは重りを持ち上げることが多いですが、ネガティブ筋トレでは、重りを下ろすことに焦点を当てます。例えば、バーベルを持ち上げた後、やさしく下に降ろすときに筋肉が非常に強く働きます。この方法の良いところは、筋肉に大きな負荷をかけることができ、筋力アップに効果的です。特に筋肉が疲れているときでも、重りを持つことによる怪我のリスクが減ります。初心者でも取り組みやすいので、是非チャレンジしてみてください。ただし、正しいやり方やフォームを守ることが重要です!
ハムケツ 筋トレ とは:ハムケツ筋トレとは、主にハムストリングスと大臀筋を鍛えるトレーニングのことです。これらの筋肉を鍛えることで、ヒップラインが美しくなり、さらにスポーツのパフォーマンス向上にもつながります。特にハムストリングスは、太ももの裏にある筋肉で、走ったり跳んだりする際に重要です。筋トレ初心者でもできるエクササイズには、スクワットやヒップリフトがあります。スクワットは、足を肩幅に開いて腰を下げる動きで、トレーニングを行う時は背筋を伸ばし、膝がつま先を越えないように注意しましょう。ヒップリフトは、仰向けに寝て膝を曲げ、足を床につけた状態で、腰を持ち上げる運動です。この時、お尻をキュッと締めるイメージで行うと効果的です。ハムケツ筋トレは、週に2~3回行うことで、徐々に筋肉がつきます。美尻を手に入れたい人は、ぜひチャレンジしてみてください。
バルク 筋トレ とは:バルク筋トレとは、筋肉を大きくするためのトレーニングのことです。バルクとは、「大きくする」という意味があり、特に筋肉量を増やしたいと考えている人にとって大切な方法です。バルク筋トレは、重いウェイトを使って強度の高いトレーニングを行います。このトレーニングは、効果的に筋肉を発達させ、見た目を良くするだけでなく、基礎代謝を上げて脂肪を燃焼しやすくする効果もあります。 具体的には、ベンチプレスやスクワット、デッドリフトなど、全身の主要な筋肉を使うエクササイズが一般的です。 また、筋トレだけでなく、食事も非常に重要です。たんぱく質を多く含む食品をしっかり食べることで、筋肉の成長を助けます。例えば、鶏肉、魚、豆腐などが良いでしょう。さらに、十分な睡眠を取ることも、筋肉の回復と成長には欠かせません。 つまり、バルク筋トレは、正しいトレーニング、食事、休養の三つが揃って初めて効果を発揮するのです。初心者の方も自分のペースで少しずつ行ってみてください!
ビックスリー 筋トレ とは:ビックスリー筋トレという言葉を聞いたことがありますか?ビックスリーとは、筋力トレーニングの基本となる3つのエクササイズのことを指しています。この3つのトレーニングは、ベンチプレス、スクワット、デッドリフトです。これらは、全身の筋肉をバランスよく鍛えることができるため、非常に効果的です。まず、ベンチプレスは胸と腕の筋肉を強化します。これからの季節、筋肉を大きくしたいと思っている人には特におすすめです。次にスクワットですが、これは下半身の筋肉を中心に鍛えます。お尻や太ももを鍛えることができ、体全体のバランスを良くします。最後のデッドリフトは、背中や脚の筋肉を強化するエクササイズです。姿勢を良くするのにも役立ちます。ビックスリーを続けることで、筋肉量が増えて基礎代謝も上がり、ダイエットにも効果的です。もし筋トレを始めたいけれど、何から始めたらいいのかわからない人は、ビックスリーを取り入れてみると良いでしょう!
レップ とは 筋トレ:筋トレを始めたばかりの人にとって、「レップ」という言葉はよく耳にするかもしれません。では、この「レップ」とは一体何なのでしょうか?レップは、「rep」とも書かれ、トレーニングの中での「繰り返し」を意味します。具体的には、例えば腕立て伏せを1回行うことを1レップと呼びます。どんな筋トレでも、このレップ数を設定することで、どれだけの回数トレーニングをするかが決まります。テストステロンや成長ホルモンの分泌を促すためにも、適切なレップ数を守ることが重要です。さらに、初心者の場合は、負荷をかけすぎないように注意が必要です。まずは自分の体に合ったレップ数を見つけて、無理なく続けることが筋トレの秘訣です。筋肉を大きくしたり、体を引き締めたりするためには、様々なレップ数でのメニューを組み合わせることもおすすめです。ルーチンを作ることで、結果が出るのを楽しみにしながらトレーニングを続けられるでしょう。
筋トレ とは 略:筋トレとは「筋力トレーニング」の略で、筋肉を強くするための運動を指します。特に、重い負荷をかけることで筋肉が成長する仕組みがあります。筋トレの目的は、体を引き締めたい、スポーツの成績を上げたい、健康を維持したいなど様々です。最近は、社会人や学生も筋トレをする人が増えてきており、特にジムに通うケースが多いです。筋トレには主に自重トレーニングとウエイトトレーニングの2種類があります。自重トレーニングは、自分の体の重さを使って行う運動で、腕立て伏せや腹筋などがこれにあたります。一方、ウエイトトレーニングは、ダンベルやバーベルを使い、より負荷をかけてトレーニングを行います。初めて筋トレをする方は、無理をせず自分に合った方法で少しずつ取り入れることが大切です。正しいフォームで行うことでケガのリスクを下げ、効果的な筋トレが実現できます。筋トレを続けることで、見た目が良くなるだけでなく、心身の健康にも良い影響を与えますよ。
自重 筋トレ とは:自重筋トレは、自分の体重を使って行うトレーニングのことを指します。たとえば、腕立て伏せや腹筋、スクワットなどがその代表です。これらの運動は、特別な器具がなくてもできるため、家の中や公園など、どこでも気軽に行えます。自重筋トレの魅力は、特に初心者にとって始めやすく、道具を持っていない人も参加できる点にあります。また、体の意識や筋力バランスを整えることができるため、自己の持つ全身の力を効率的に鍛えることができます。さらに、自重筋トレは体脂肪を燃焼させたり、持久力を向上させたりする効果もあります。運動不足を解消したり、ダイエットを考えている人にもオススメの方法です。運動の基本ともいえる自重筋トレを活用して、健康的な体を手に入れてみましょう!
筋トレの共起語フィットネス:健康や体力を維持・向上させるための運動全般を指します。筋トレもフィットネスの一環であり、多くの人が取り入れています。
ダイエット:体重を減らすことを目的とした食事制限や運動のことです。筋トレは基礎代謝を上げるため、ダイエットにも効果的です。
プロテイン:筋肉を作るための栄養素であるたんぱく質を補給するための食品やサプリメントのことです。筋トレの後に摂ることが推奨されています。
筋肉:体を動かすための組織であり、筋トレによって強化される部分です。筋肉量が増えると、基礎代謝が向上します。
レップ:「反復」を意味し、1回の運動を何回繰り返すかを示します。筋トレでは通常、何レップ行うかが設定されます。
セット:筋トレにおいて、一定回数のレップを繰り返す単位のことです。例えば、10レップを1セットとし、3セット行うといった形式です。
サプリメント:食事から十分に摂取できない栄養素を補うための補助食品です。筋トレを行う人たちには、プロテインやBCAAなどが人気です。
マシン:筋トレを行うための器具や設備のことです。トレーニングマシンを使うことで、特定の筋肉を効果的に鍛えることができます。
ハードウエイト:重い負荷をかけることで筋肉に強い刺激を与えるトレーニングのスタイルです。筋トレの中で特に筋肉を増強するのに効果的です。
柔軟:筋肉や関節を柔らかくするためのストレッチや運動を指します。筋トレの前後に行うことで、怪我を防ぐために重要です。
筋トレの同意語ウェイトトレーニング:バーベルやダンベルなどの重りを使ったトレーニングのこと。筋肉を効果的に増強するための方法として広く用いられています。
筋力トレーニング:筋肉の力を高めるためのトレーニング全般を指します。筋肉を鍛えることで体力向上や怪我防止につながります。
フィジカルトレーニング:体力や運動能力の向上を目指すトレーニング全般を指します。筋肉だけでなく、スタミナや柔軟性も向上させることが目的です。
ボディビルディング:筋肉を大きく見せるために特化したトレーニングと食事管理のこと。筋肉のバランスや形に重点を置きます。
トレーニング:体を鍛えるための運動全般を指します。筋トレもその一部であり、心肺機能や柔軟性の向上も含まれます。
ストレングストレーニング:筋肉の強さを向上させるトレーニングを意味し、主に抵抗をかけることで行われます。ウェイトトレーニングや自重トレーニングが含まれます。
パワートレーニング:瞬発力や筋力を高めるためのトレーニングで、特にスポーツ選手に多く取り入れられています。
筋トレの関連ワードウェイトトレーニング:筋肉を強化するために、ダンベルやバーベルなどの重りを使って運動することです。
筋肥大:筋肉のサイズが大きくなることを指します。筋トレを行うことで、筋肉の繊維が肥大化します。
筋力:筋肉が持つ力や能力のことです。筋力トレーニングを通じて、筋肉の力を向上させることができます。
レップ:同じ動作を繰り返す回数のことです。例えば、10回の腕立て伏せを行うと、10レップと呼びます。
セット:一定のレップ数を1回行った後の休憩を含むグループです。例えば、10レップを1回行った後の休憩を1セットと呼びます。
オーバーロード:筋肉に対して通常以上の負荷をかけるトレーニング方法です。これにより筋肉は成長しやすくなります。
コンパウンドエクササイズ:複数の筋肉群を同時に使うトレーニング運動のことです。例えば、スクワットやベンチプレスが挙げられます。
アイソレーションエクササイズ:特定の筋肉群に焦点を当てたトレーニング運動です。例えば、二頭筋のカールなどが該当します。
プロテイン:筋肉の修復や成長に必要な栄養素で、肉や魚、大豆製品などから摂取できます。
栄養補助食品:不足しがちな栄養素を補うためのサプリメントです。筋トレを行う人にはプロテインが人気です。
リカバリー:筋トレ後の筋肉の回復を指します。十分な休息と栄養摂取が重要です。
フォーム:トレーニングを行う際の体の動かし方や姿勢のことを指します。正しいフォームが怪我を防ぐために重要です。
ウォームアップ:筋トレを始める前に行う準備運動で、体を温め、筋肉や関節をほぐすために行います。
クールダウン:筋トレ後のストレッチや軽い運動で、体をリラックスさせるための活動です。
筋トレの対義語・反対語
該当なし
筋トレの関連記事
健康と医療の人気記事

2254viws

1885viws

2235viws

1587viws

1701viws

1229viws

1470viws

1422viws

997viws

2118viws

2179viws

2103viws

3579viws

1454viws

2023viws

1669viws

2248viws

1956viws

2076viws

2102viws