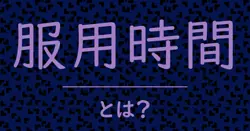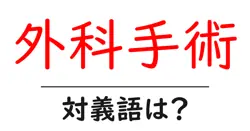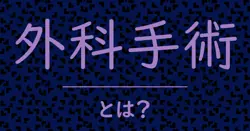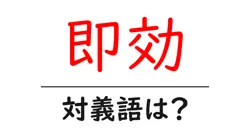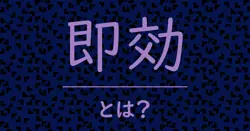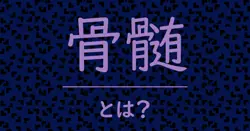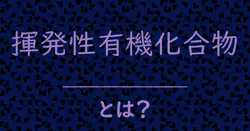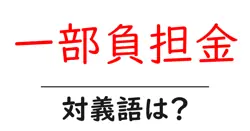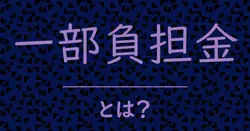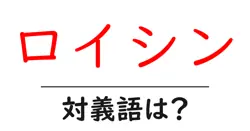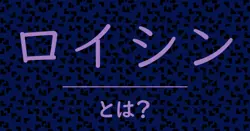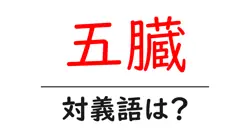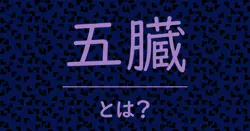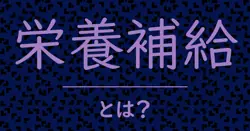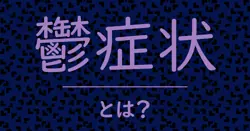服用時間とは?
服用時間とは、薬を飲む時間のことを指します。薬の効果を十分に発揮させるためには、適切なタイミングで服用することが重要です。例えば、朝食後に飲む薬や、就寝前に飲む薬などがあります。また、食事の有無によっても服用の効果が変わる場合があるため、注意が必要です。
服用時間の重要性
薬を服用する時間によって、体内での吸収速度や効果が変わることがあるため、服用時間は非常に重要です。薬のパッケージや医師の説明に沿って、正確に服用しましょう。
服用時間を守るメリット
- 効果的な治療:正しい服用時間を守ることで、薬の効果が最大限に引き出されます。
- 副作用の軽減:服用時間を守ることで、体への負担を減らし、副作用のリスクを下げることができます。
- 服用の習慣化:同じ時間に服用することで、薬を飲むことが習慣になりやすくなります。
服用時間の種類
服用時間にはいくつかの種類があります。以下は代表的な服用時間です。
| 服用時間 | 具体例 | 食事の影響 |
|---|---|---|
| 朝食前 | 空腹時に飲む薬 | 食事の影響を受けにくい |
| 朝食後 | 食後に飲む薬 | 食事が吸収を助ける |
| 就寝前 | 寝る前に飲む薬 | 睡眠の品質を向上させる |
薬の飲み方の注意点
以下の点にも注意が必要です。
服用:薬やサプリメントなどを飲むこと。健康管理や病気の治療のために必要な行為。
時間:ある行動を行うために必要な持続の長さ。服用する際の具体的な時間帯や期間を指す。
間隔:服用時間の間に設けられる時間のこと。例えば、食後何時間後に服用するかを示す。
服薬指導:薬剤師が患者に対して、正しい服用方法や服用時間について詳しく説明すること。
副作用:薬を服用した際に起こる、期待されない不快な症状のこと。服用時間によって影響が出る場合もある。
タイミング:服用する最適な時期やタイミングを指すこと。食事前や後など、効果を最大限にするための要素。
遵守:医師や薬剤師の指示した服用時間を守ること。遵守することで、治療効果が高まる。
効能:薬やサプリメントが持つ効果のこと。服用時間を守ることで最適な効能を得られる。
服用時刻:薬を飲むべき具体的な時間を指します。
投与時間:薬を患者に投与する際の時間を意味します。
服薬タイミング:薬を飲むべきタイミングや時期を指し、食前や食後などの条件を含むことがあります。
摂取時間:栄養素や薬を体に取り入れる時間を表します。
投薬時期:治療において薬を投与する特定の期間や時期を指します。
服用スケジュール:薬を服用する際の計画や時間の表を意味します。
薬の服用時間:特定の薬剤を飲むために設定された具体的な時間を指しています。
服用:薬を飲んだり、飲み込んだりする行為。処方された薬を決められた対象者が使用することで、その効果を得ることを目的としています。
服用時間:薬を服用する際の時間。一般的には1日何回、どのタイミングで服用するかを指します。服用時間を守ることで、薬の効果を最大限に引き出すことができます。
服用間隔:次の服用までの時間のこと。例えば、8時間ごとに服用する場合は、最初の服用から8時間後に次の服用を行うことを意味します。
服用方法:薬を使用する際の具体的な手順や方式。例えば、錠剤を水で飲み込む、散剤を食べ物に混ぜるなど、薬の形状や特性に応じて異なります。
副作用:薬を服用した際に現れる予期しない不利益な反応。副作用は望ましくない結果をもたらすことがあるため、服用時間や方法に注意が必要です。
薬の種類:医療目的によって分類された薬の異なるタイプ。痛み止め、抗生物質、睡眠薬など、症状や目的に応じた多くの薬があります。
服用指示:医師や薬剤師が薬の服用に関して指示する内容。服用する時間、回数、方法を含むことが多く、患者はこれに従うことが重要です。
飲み合わせ:異なる薬を同時に服用する際の相互作用のこと。一部の薬は一緒に飲むと効果が減少したり、副作用が増加したりすることがあります。
服用記録:薬の服用履歴を記録すること。服用時間や量を記入し、医師や薬剤師と相談する際に役立ちます。
保管方法:薬を正しく保存するための条件。温度、湿度、光などに配慮し、効果を保持するための適切な場所に保管します。
服用時間の対義語・反対語
該当なし