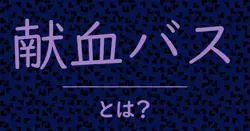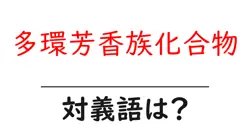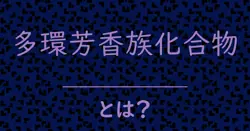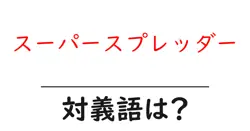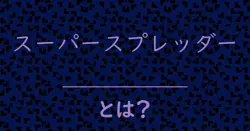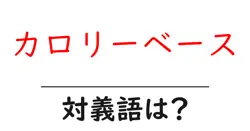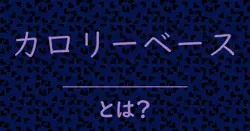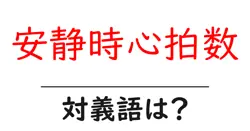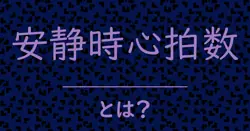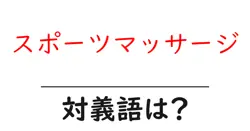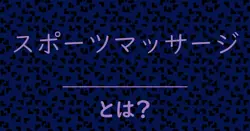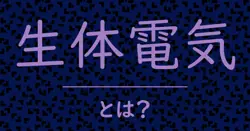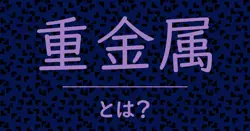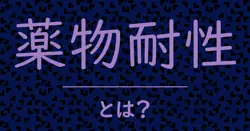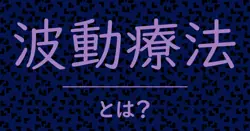献血バスとは?その役割と利用方法をわかりやすく解説!
こんにちは!今日のテーマは「献血バス」です。皆さんは献血バスを見たことがありますか?街中で見ることが多いので、きっと見かけたことがあると思います。でも、献血バスが何なのか、どうして大切なのか、そしてどのように利用するのかは、知らない人も多いかもしれません。ここでは、献血バスについて詳しく説明していきます。
献血バスの基本情報
献血バスとは、文字通り献血を行うための専用の車両です。病院や献血ルームへ行かなくても、街中で手軽に献血ができる場所として利用されています。献血バスには、医療スタッフが常駐しており、献血に必要な設備が整っています。
献血バスの主な役割
献血バスの主な役割は、血液を集めることです。血液は様々な病気の治療に使われています。特に、大きな手術や事故による怪我、癌や血液の病気の患者さんにとって、必要不可欠なものです。献血バスがあることで、より多くの人が手軽に献血に参加できるようになります。
献血バスを利用するメリット
献血バスを利用するメリットはたくさんあります。以下の表にまとめてみました。
| メリット | 説明 |
|---|---|
| 手軽さ | 身近な場所で献血ができるため、気軽に参加しやすい。 |
| 時間の節約 | 病院に行く必要がないため、時間を無駄にせずに済む。 |
| 地域貢献 | 地域で献血を行うことで、地元の医療に貢献できる。 |
献血バスの利用方法
献血バスを利用するには、以下のような流れになります。
献血バスは、常に人を集める必要があります。協力してくれる人が多ければ多いほど、多くの命を救うことができるのです。ぜひ、近くに献血バスが来たら、参加してみてください。
まとめ
献血バスは、病気の治療に欠かせない血液を集めるための大切な存在です。手軽に参加できるため、地域の皆さんが協力しやすい環境を作っています。献血を通じて、命を救うお手伝いをしましょう!
血液:人間の体内を流れる液体で、酸素や栄養を運ぶ重要な役割を持っています。献血バスではこの血液を集めるために、ボランティアから血液を提供してもらいます。
ボランティア:無償で自らの時間や労力を提供する人々のことです。献血バスで血を提供する人も、ボランティアとしての活動の一環と考えられます。
臓器:体内の特定の機能を持つ器官のことで、血液は臓器への栄養や酸素を届ける役割があります。献血された血液は、手術や病気の治療のために臓器に供給されます。
健康診断:自分の健康状態を測るためのチェックです。献血の際には、簡単な健康診断を行い、献血ができるかどうかを確認します。
待機時間:献血を行うための順番を待っている時間のことです。献血バス内は、この待機時間を過ごすための環境が整っています。
献血者:献血を行う人のことを指します。献血バスでは多くの献血者が集まり、自分の血を提供します。
血漿:血液の液体成分で、栄養素やホルモンを運ぶ役割を果たします。献血では血漿も重要な成分として収集されることがあります。
無償:対価を求めずに行うことを意味します。献血は無償で行われ、多くの人の命を救う大切な活動です。
献血車:血液を集めるために特別に改造された車両で、定期的に地域を訪れて献血を呼びかけます。
献血スポット:献血が行われる特定の場所やイベント会場のことを指し、ここでも献血バスが配置されることがあります。
移動献血所:固定の献血ルームではなく、移動可能な車両として場所を変えながら献血を受け付けるところ。
献血:自分の血液を無償で提供し、血液製剤として必要としている人々に役立てる活動。
献血ルーム:献血を行うために設けられた専用の施設。こちらでも献血ができるが、バスと違い常設されている場所が多い。
血液型:人間の血液はA型、B型、AB型、O型の4つに分類され、献血の際には自身の血液型を知っておくことが重要。
血液製剤:献血された血液から作られる医療用の商品で、輸血や治療に利用される。
輸血:病気や事故などで失った血液を補うために、他人から提供された血液を体内に注入する行為。
健康診断:献血を行う際には、事前に健康状態の確認が行われる。これにより、献血者が健康であることが確認される。
予約:献血バスや献血ルームでの献血に関して、事前に日時を確定するための行為。
輸血用血液:病院での治療に用いることを目的とした血液のこと。献血によって集まった血液がこのカテゴリーに入る。
ドナー:献血を行う人のことを指し、他者のために自己の血液を提供する重要な役割を担っている。
啓発活動:献血の重要性や意義を広めるためのキャンペーンやイベントなどの活動。
献血バスの対義語・反対語
該当なし