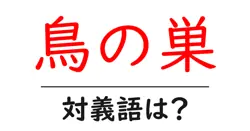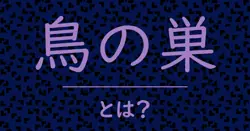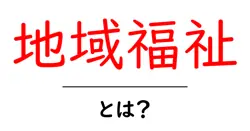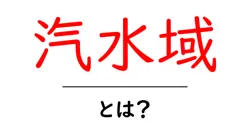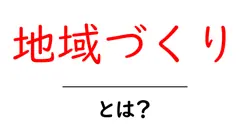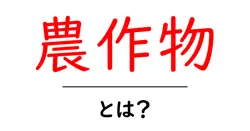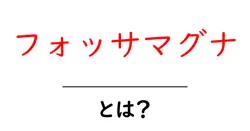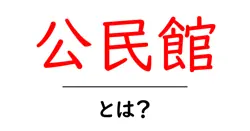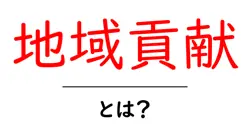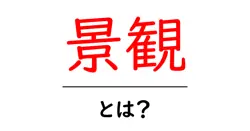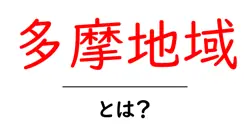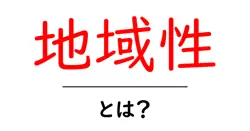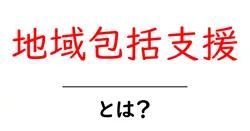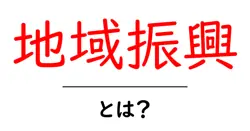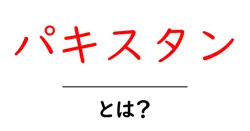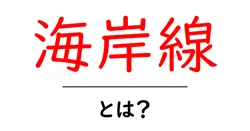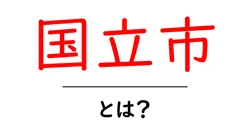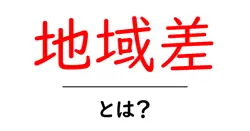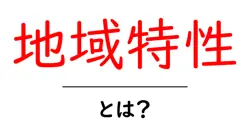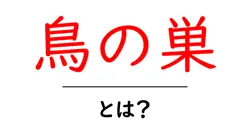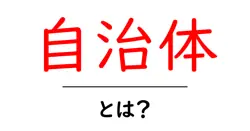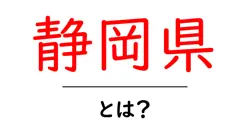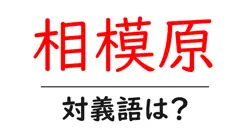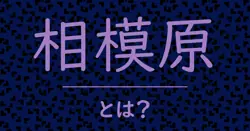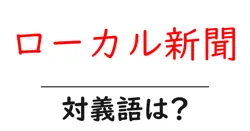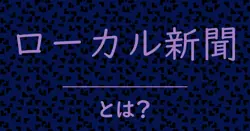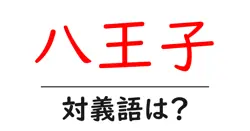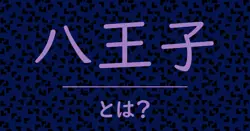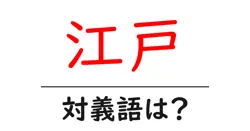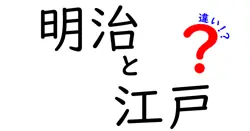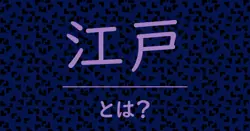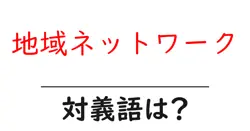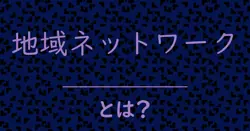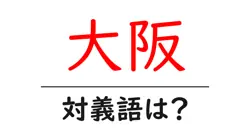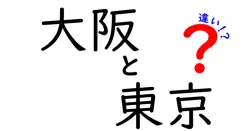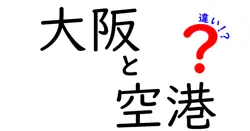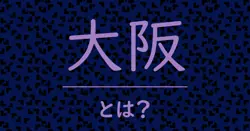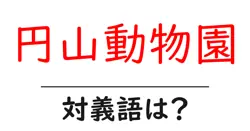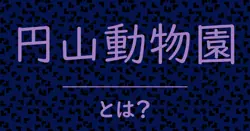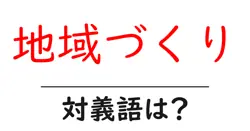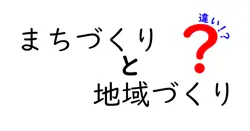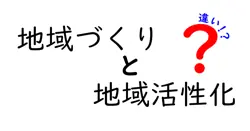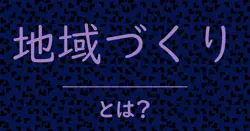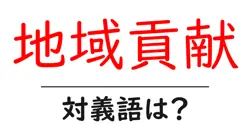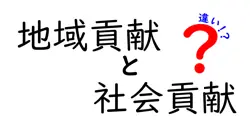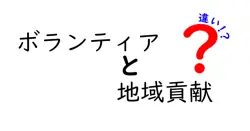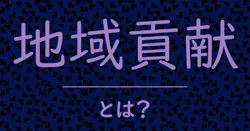江戸とは?江戸時代の文化や歴史を知ろう
江戸という言葉を聞いたことがある人は多いでしょうが、実際に江戸がどのような場所だったのかを知らない方もいるのではないでしょうか。江戸は、現在の東京が位置する地域を指しており、特に江戸時代(1603年から1868年まで)には日本の政治、文化、経済の中心地でした。
江戸時代の始まり
江戸時代は、徳川家康が天下を統一し、江戸を政権の中心にしたことから始まりました。家康は、1639年に日本を鎖国し、外国との貿易を制限しました。これにより、内需が発展し、日本国内での文化が大いに栄えました。
江戸の街の特徴
江戸は、当時の日本の人口の約3分の1が住んでいた超大都市でした。商人や町人が集まり、さまざまな文化が混じり合っていました。江戸の街は、武士の住む「城下町」でありながら、商人や職人たちが活発に暮らす町でもありました。江戸の町の一部は、今でも残っており、浅草や神楽坂などがその代表的な地区です。
江戸の文化
江戸時代には、浮世絵や歌舞伎、茶道、花道など、日本の伝統文化が盛んに発展しました。また、教育にも力を入れられ、寺子屋などの教育機関が増加しました。これにより、江戸は文化的にも豊かな時代を迎えることができたのです。
江戸時代の終わり
江戸時代は、明治維新(1868年)によって終わりを迎えました。この時期、多くの改革が行われ、日本は近代国家へと変貌していきました。江戸はその後、東京と呼ばれるようになり、今では日本の首都となっています。
江戸の資料
| 年 | 出来事 |
|---|
| 1603年 | 徳川家康が江戸幕府を開く |
| 1639年 | 日本が鎖国する |
| 1868年 | 明治維新により江戸幕府が崩壊 |
江戸という場所がどのような役割を果たしていたのか、歴史を遡ることで理解できましたね。現在の東京に多くの文化的な影響を与えたこの時代を知ることで、私たちの生活にもつながりがあることが感じられるでしょう。江戸は日本の歴史に欠かせない存在なのです。
江戸のサジェストワード解説さんば とは 江戸:「さんば」という言葉は、江戸時代の特定の料理や風習を指します。この言葉は特に江戸の町で人気があり、多くの人々が楽しんでいました。江戸時代は今から約400年前、まだ情報があまりなかった時代です。その中で「さんば」は、主に魚を使った料理で、さまざまな調理法がありました。
さんばは、もともと魚を干したり、塩漬けにしたりして保存するための料理です。そのため、ご飯にとても合うのです。江戸の町では、商人や庶民がこの料理を楽しむ姿がよく見られました。特に、江戸っ子たちは魚を使った料理を好み、さんばと一緒に食べることが多かったと言われています。
当時、屋台や食堂で気軽に楽しめる料理として親しまれていました。食材の新鮮さも大切にされており、市場で新鮮な魚を選ぶことが、料理の味を大きく左右したのです。江戸の人々は、さんばを囲んで楽しい会話を交わし、食事の時間を心から楽しんでいました。
このように、さんばはただの料理ではなく、江戸時代の人々の日常生活や文化を象徴するものでもあるのです。今ではなかなか目にする機会が少なくなりましたが、江戸の歴史を感じる一品として、ぜひ知っておきたいものです。
地本問屋 江戸 とは:「地本問屋 江戸」とは、江戸時代において特に重要な商業機関の一つを指します。地本問屋は、地方から江戸に送られてくる商品の卸売を行う業者であり、江戸の人々にとって欠かせない存在でした。例えば、農産物や生地、日用品などが地本問屋を通じて江戸の町に届けられました。これにより、江戸の住民たちは多様な商品を手に入れることができ、生活が豊かになりました。地本問屋は、地元の農家や職人から商品を仕入れ、それを江戸の商人や消費者に販売する役割を果たしました。また、江戸の経済が成長する中で、多くの地本問屋が設立され、競争が激化しました。その結果、商品価格が適正化され、より多くの人々が商品を手に入れることができるようになったのです。地本問屋は単なる商業活動だけでなく、地方と江戸を結ぶ重要な役割を果たし、地域経済を支える存在でもありました。江戸時代の商業の歴史において、地本問屋の存在は欠かせないものであったと言えるでしょう。
大名 とは 江戸:江戸時代、大名とは大きな土地を持ち、幕府に仕える武士のことを指します。大名は、領地を治めるために城を持ち、領民を守ったり、税を集めたりしていました。江戸時代は約260年間続いた時代で、戦が少なく、平和な時代でした。これによって大名は、領地の発展を考え、農業や商業を奨励しました。
大名は、江戸城に住む幕府の将軍に仕え、定期的に江戸に行く「参勤交代」を行っていました。これにより、大名は自分の土地から一定の時間、江戸に滞在しなければならず、わずかに大名の権力を抑える役割も果たしていました。江戸では、華やかな生活を送り、大名たちは文化や芸術の patron(パトロン)としても知られています。
また、江戸時代には多くの大名が存在し、それぞれ異なる文化や特色を持つことから、日本各地の文化の多様性も生まれました。大名の影響を受けた食文化や衣服、祭りなどは、今でも日本の文化として受け継がれています。大名は、単に土地を支配する存在ではなく、日本の歴史や文化を形成する重要な役割を持った存在なのです。
江戸 とは コピペ:江戸(えど)とは、日本の歴史において非常に重要な時代である江戸時代に関わる場所や時期を指します。江戸時代は、1603年から1868年までの約260年間のことを言います。この時代、徳川家康が江戸(現在の東京)に幕府を開きました。江戸時代は平和な時代で、多くの人々が商業や文化を発展させました。例えば、浮世絵や歌舞伎など、今でも親しまれている日本の伝統文化がこの時期に生まれました。また、江戸時代には厳しい身分制度があり、武士、農民、商人など、それぞれの役割が明確に分かれていました。とはいえ、人々はこの時代にかけがえのない日常を築き、庶民文化も栄えました。江戸には多くの人が集まり、賑やかな市場や大名の住むお城などがありました。江戸とは、ただの地名ではなく、日本の歴史や文化に深く関わった特別な場所であると言えるでしょう。江戸を理解することは、日本の豊かな文化を知るための第一歩です。
江戸 上方 とは:「江戸」と「上方」は、歴史や文化において重要な二つの地域を指します。江戸は現在の東京付近を指し、幕末まで日本の政治の中心地でした。江戸時代には多くの人々が集まり、商業が発展したことから、文化や芸術も栄えました。一方、上方は主に京都・大阪地域のことを指し、こちらも日本文化の中心として、特に茶道や華道などの和の文化が育まれました。この二つの地域は、時代によって異なる特色を持ちながら認識されています。江戸では町人文化が発展し、浮世絵や歌舞伎が人気を博しました。一方、上方では文楽や落語など、特に言葉を大切にした芸術が成長しました。江戸と上方は相互に影響を与え合い、多様な文化が生まれる基盤となったのです。これらの地域の違いを知ることで、日本の歴史や文化をより深く理解することができます。
江戸 八百八町 とは:江戸八百八町は、江戸時代の東京、つまり江戸に存在していた町のことを指します。江戸は、日本の政治の中心であり、多くの人々が集まる場所でした。八百八町という名前は、実際にはきちんとした数ではなく、たくさんの町があったことを示すための表現です。江戸時代の町は、職人や商人が住む町、武士の家が並ぶ町、さまざまな人々が暮らしていました。町ごとに雰囲気や特色がありました。例えば、中心の町の一つである浅草では、多くの人々が集まり、活気にあふれていました。いっぽう、山の手と呼ばれる地域には、武士が住んでいたため、落ち着いた雰囲気がありました。八百八町の中には、その時代を象徴するような美しい景色や人々の生活があり、さまざまな風情が楽しめました。江戸八百八町は、当時の日本の文化や社会を知るための大切な情報源です。
江戸 切り そば とは:江戸切りそばは、日本の伝統的なそば料理の一つです。このそばは、特に江戸時代に発展しました。そばが細くて長く切られているのが特徴で、他の地域のそばとは一味違います。江戸切りそばは、乾燥させたそばの実を使い、手作りで作られることが多いです。そのため、そばの香りや風味が豊かで、とても美味しいと評判です。江戸切りそばは、つけ汁につけて食べるのが一般的で、このつけ汁には、出汁を使ったものや、醤油ベースのものがあります。また、薬味としてわさびやネギを添えることが多いです。歴史的には、江戸時代の商人たちが忙しい合間にさっと食べられる食事として人気を博しました。現在でも、多くの人々に愛されており、居酒屋やそば屋で楽しむことができます。江戸切りそばを食べると、昔の日本の雰囲気を感じることができるので、とても魅力的なお料理です。
江戸 切子 とは:江戸切子(えどきりこ)とは、日本の伝統的なガラス工芸品の一つで、東京都を中心に作られています。この技法は、江戸時代に始まり、今日まで受け継がれています。江戸切子の特徴は、その美しい模様や色合いです。透明なガラスにカットが施され、光が当たるとキラキラと輝きます。また、江戸切子は手作りであり、職人の技術がとても大切です。職人はガラスを高温で溶かし、成形してから細かいカットを施します。これにより、複雑な模様や美しい形が生まれるのです。江戸切子は、おしゃれな食器やインテリアとして人気があり、贈り物にも最適です。特に、お酒を注ぐグラスは、飲み物の色や味を引き立てるため、多くの人に愛されています。江戸切子の魅力を知ることで、あなたもこの素晴らしい日本の伝統工芸に興味を持つことができるでしょう。
飛脚 とは 江戸:江戸時代、日本の交通手段は現在とは大きく異なりました。その時代、人々の大切な荷物や手紙を運ぶ役割を担っていたのが「飛脚」と呼ばれる運び屋たちです。飛脚は、速さと正確さが求められる仕事で、江戸の町では非常に重要な存在でした。彼らは特別に訓練を受け、一定のルートを持って、荷物を運ぶために走り続けました。
飛脚の役割は、ただ荷物を運ぶだけでなく、商人や武士の間での信頼を築くことにもありました。彼らの仕事があったおかげで、江戸時代の人々は遠くの友人や親戚と連絡を取りやすくなったのです。また、飛脚は荷物を届ける時間が決まっていて、きちんと時間通りに到着することで、人々の信頼を得ていました。
飛脚は、時には嵐や悪天候を乗り越えてでも、荷物を届けるために最大限努力しました。彼らの存在は、江戸時代の人々にとってあたりまえで、街の重要なコミュニティの一部を形成していたのです。飛脚を通じて、江戸の人々の生活は豊かさを増し、広がりを持ち続けていました。今でもその精神や仕事へのこだわりは、多くの人に語り継がれています。
江戸の共起語江戸時代:日本の歴史において、1603年から1868年までの約260年間を指します。この時代は、平和で経済が発展し、文化や芸術が栄えました。
幕府:江戸時代の政治体制を指し、将軍が政権を握っていました。特に徳川幕府が有名です。
浮世絵:江戸時代に発展した日本の版画術の一つで、日常の風景や人物、風俗などを描いた作品が特徴です。
歌舞伎:江戸時代に発展した日本の伝統的な演劇で、豪華な衣装や派手な演技が特徴です。
町人:江戸時代における商人や職人を指し、町を形成した重要な社会層です。
商業:江戸時代は商業が発展し、商人たちが経済の中心的な役割を果たした時期です。
武士:江戸時代の支配階級で、武士は土地を持って軍事や政治に関与していました。
江戸城:江戸時代の幕府が置かれた城で、現在の東京に位置しています。
遊郭:江戸時代の日本における風俗街で、娯楽や遊びの中心地として知られていました。
江戸しぐさ:江戸時代の人々が持っていた生活の知恵や作法を指し、現代においても参考にされることがあります。
江戸の同意語東京:江戸は、1868年の明治維新まで東京の名前として知られていました。江戸時代の文化や政治の中心地でもあり、その後近代化を遂げた都市です。
江戸時代:江戸という言葉は、主に1603年から1868年までの期間を指し、この時代の日本の歴史を特徴づける特定の時代を表しています。
江戸文化:江戸時代に特有の文化や芸術を指し、歌舞伎や浮世絵、町人文化が栄えた時代を表しています。江戸時代の価値観や生活様式を理解するための重要な概念です。
江戸っ子:江戸に住む人々、または江戸の風習を受け継ぐ人々を指します。江戸っ子には特有の性格や文化があります。
武家:江戸は武士階級が政治的権力を握っていた時代でもあったため、江戸時代の武士や武家を指すこともあります。
江戸城:江戸時代の中心的な政治の舞台で、幕府の重要な拠点として知られていました。今の東京の皇居の基礎となっています。
江戸の関連ワード江戸時代:江戸時代は、1603年から1868年までの約260年間を指し、徳川家康が幕府を開いた時期です。この時代は平和で商業が発展し、文化や芸術も栄えました。
江戸城:江戸城は、江戸時代に徳川幕府の中心として機能した城で、現在の東京都千代田区に位置しています。幕府の首都であり、重要な政治の拠点でした。
浮世絵:浮世絵は、江戸時代に人気を博した版画のスタイルで、風景や人物、歌舞伎の役者を描いた作品が多く見られます。日本の文化を代表するアート形式の一つです。
町人:町人は、江戸時代の都市に住む商人や職人を指します。彼らは経済を支え、文化の発展にも大きな役割を果たしました。
武士:武士は江戸時代の日本における戦士階級で、主に大名に仕官し、政治や軍事に携わりました。武士としての誇りや倫理が重視され、独自の文化が育まれました。
参勤交代:参勤交代は、江戸時代の大名が定期的に江戸と自領を往復する制度で、幕府の統治を強化するための政策でした。大名にとっては経済的負担が大きく、人質として家族を江戸に置くことも義務付けられました。
蕎麦:蕎麦は、江戸時代に庶民に親しまれた食べ物で、日本の伝統的な麺料理の一つです。江戸の名物として、特に江戸蕎麦が有名で、さまざまなスタイルで楽しめます。
江戸文化:江戸文化は、江戸時代に栄えた独自の文化で、歌舞伎や浄瑠璃、文学、絵画など多彩な芸術が発展しました。庶民の生活や価値観を反映した文化が特徴です。
商業:江戸時代には商業が著しく発展し、江戸は商人の集まる中心地となりました。市場は活況を呈し、多様な商品が取引されました。
神社・寺院:江戸には多くの神社や寺院が存在し、宗教的な活動や地域コミュニティの中心となっていました。信仰の場としてだけでなく、文化イベントや祭りの場としても重要でした。
江戸の対義語・反対語
江戸の関連記事
地域の人気記事
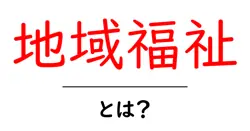
1976viws
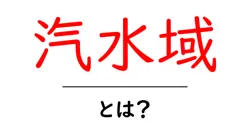
1345viws
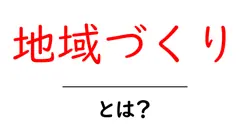
1797viws
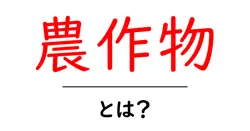
1952viws
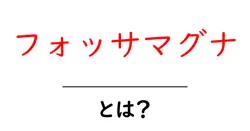
3910viws
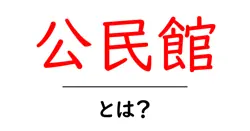
1301viws
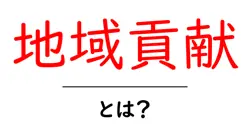
1789viws
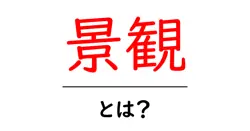
534viws
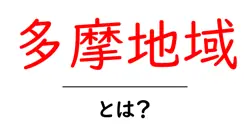
1345viws
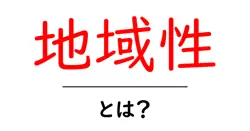
3934viws
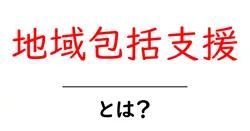
3311viws
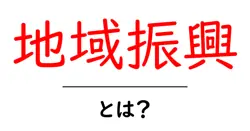
5159viws
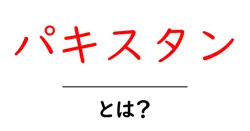
1352viws
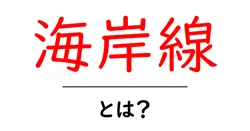
1800viws
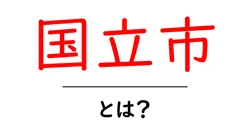
822viws
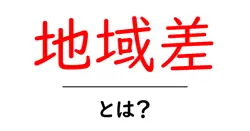
3528viws
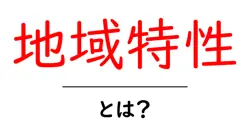
3424viws
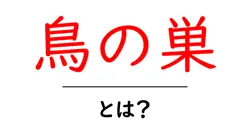
1383viws
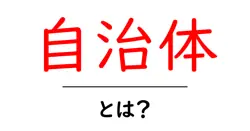
3502viws
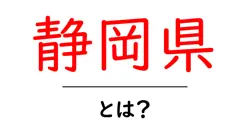
3777viws