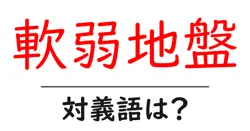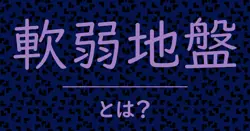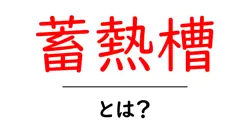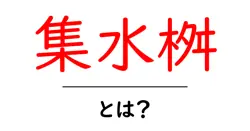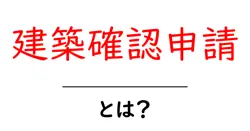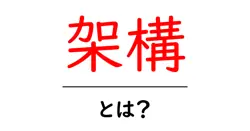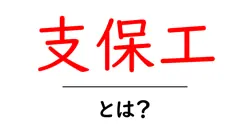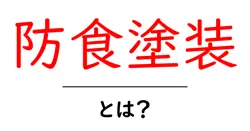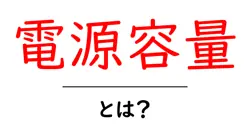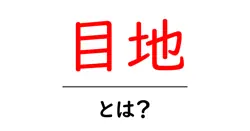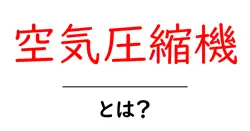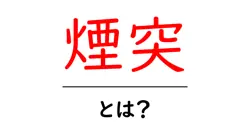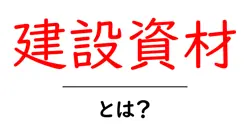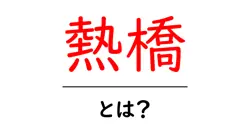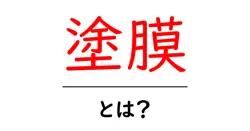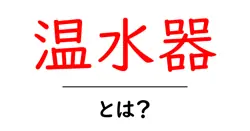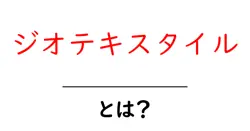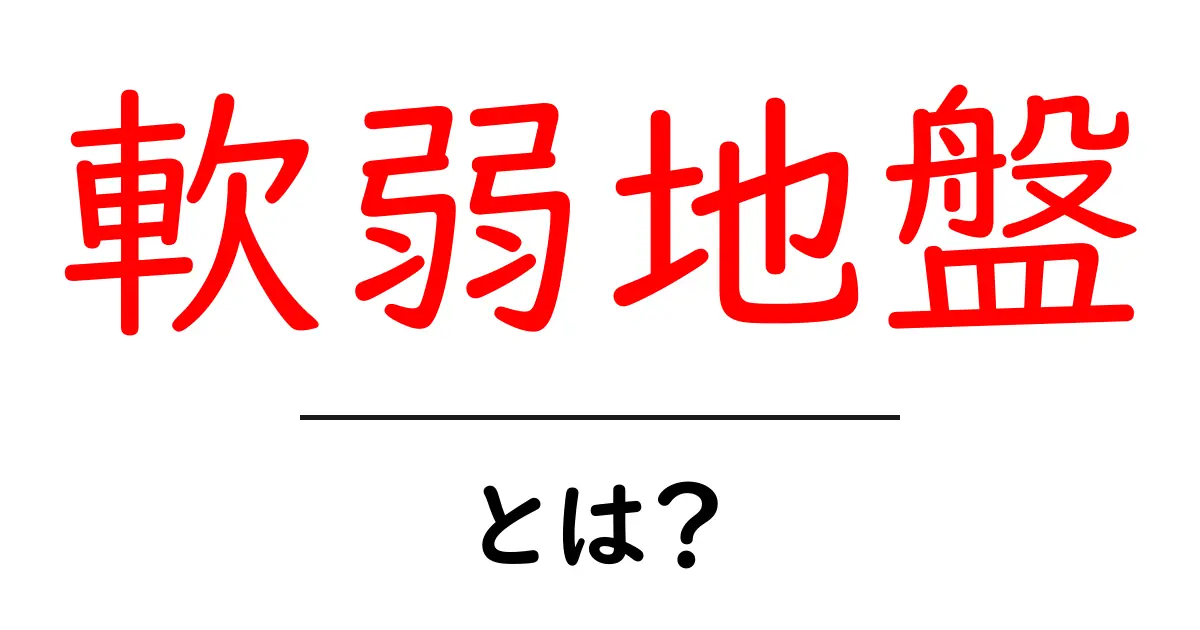
軟弱地盤とは?
軟弱地盤(なんじゃくちばん)とは、土の性質が柔らかく、重い建物や構造物を支える力が弱い地盤のことを指します。特に、砂や粘土が多く含まれている地盤は、地震や大雨の影響を受けやすく、沈下やひび割れを起こすリスクがあります。
軟弱地盤の特徴
軟弱地盤の特徴には、以下のようなものがあります。
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 柔らかい土質 | 土が柔らかいと、構造物の重さをしっかり受け止められません。 |
| 水を含みやすい | 普通の土よりも水を吸収しやすく、湿った状態になるとさらに弱くなります。 |
| 地震や雨の影響を受けやすい | 大雨や地震時に、土が流されるリスクが高いです。 |
軟弱地盤の影響
このような軟弱地盤の上に建てられた建物は、沈下や倒壊の危険性が増します。日本は地震が多い国なので、特に注意が必要です。家を建てる場合は、地盤調査を行い、軟弱地盤かどうかを確認することが大切です。
軟弱地盤への対策
軟弱地盤には、以下のような対策があります。
まとめ
軟弱地盤は、特に日本のような地震の多い地域では注意が必要な存在です。家を建てる際には、事前に地盤の状態を調査し、必要に応じて適切な対策を講じることが重要です。
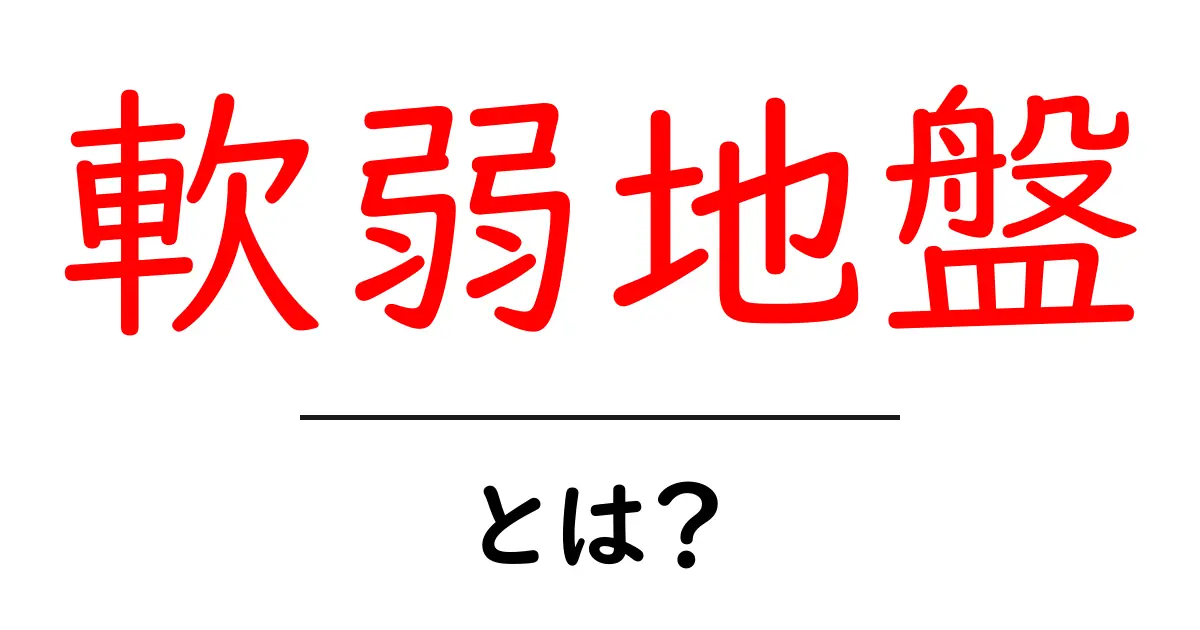
地盤:地面の構造や性質を示す用語で、建物や構造物が立っている基盤を指します。
耐震性:地震に対する建物や構造物の強さや抵抗能力のことです。軟弱地盤は耐震性に影響を与える可能性があります。
土質調査:地盤の構成や性質を調べるための調査で、建物の設計や施工の前に行われます。
支持力:地盤が構造物の重みを支える力のことで、軟弱地盤では支持力が低くなることがあります。
沈下:建物や構造物が地盤により沈むことを指し、軟弱地盤ではこの現象が起こりやすいです。
排水:水を地面から排出する作業や機能のこと。軟弱地盤では水分が多く、適切な排水が求められます。
基礎工事:建物の土台を作る工事で、軟弱地盤では特に強化が必要です。
地盤改良:軟弱地盤を強化するための工事や技術のこと。これにより、建物の支持力を向上させます。
揺れ:地震などの振動により引き起こされる動きで、軟弱地盤は揺れやすくなります。
地盤の安定性:地面がどれだけ安定しているかの指標で、軟弱地盤の場合、安定性が低くなることがあります。
不良地盤:建物や構造物を支える力が弱く、安定しない地面のことを指します。
軟弱地層:十分な支持力を持たず、沈下や変形を引き起こす可能性のある土層のことです。
軟土:土の一種で、粘土やシルト(微細土)が多く含まれており、圧縮されやすい性質を持っています。
低支持力土:支持力が低く、建物や構造物を安全に支えることが難しい土壌を指します。
沼地:水分が多く、地盤が軟らかくなっている状態の土地で、特に基礎工事において問題となることがあります。
地盤:建物や構造物を支える土や岩の層のことです。地盤がしっかりしていると、建物が安定して立つことができます。
地質:地球の表面や内部を構成する材料や構造のことを指します。地質の種類によって地盤の性質が変わります。
土壌:地面に存在する有機物や鉱物から成る物質のことです。土壌は植物の根を支え、栄養を供給します。
沈下:建物や構造物が地盤によって押し下げられて、地面の高さが低くなる現象のことです。軟弱地盤では沈下のリスクが高まります。
支持力:地盤が建物や構造物を支えるための能力のことです。支持力が弱いと、建物が不安定になる原因となります。
液状化:地震などの振動によって、土が水分を含んでいる状態で流動化してしまう現象です。軟弱地盤では液状化が起こりやすく、危険です。
改良工法:軟弱地盤を強化するために行う工事のことです。地盤改良によって支持力を高め、沈下や液状化を防ぐことができます。
透水性:土や岩が水を通しやすい性質のことです。軟弱地盤では透水性が高いと水が溜まりやすく、地盤が弱くなる原因になります。
密度:土の粒子が詰まった状態のことを指します。密度が低いと、地盤が軟弱とされることが多いです。
硬化剤:土壌を固化するための材料のことです。軟弱地盤を強化したい場合に使用されることがあります。
軟弱地盤の対義語・反対語
硬質地盤と軟弱地盤。その違いとは? | 住まいの安心研究所 - JHS
硬質地盤と軟弱地盤。その違いとは? | 住まいの安心研究所 - JHS