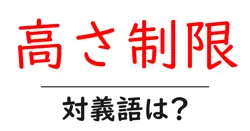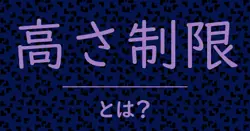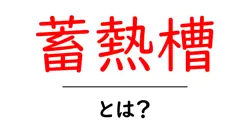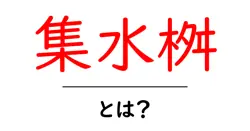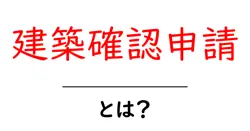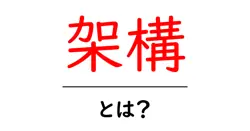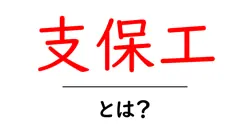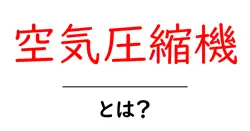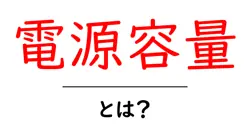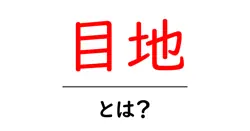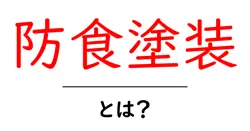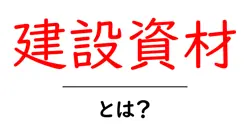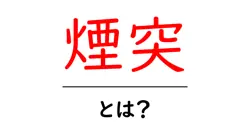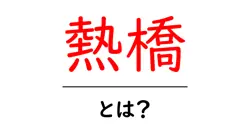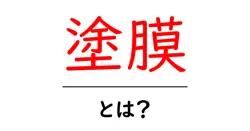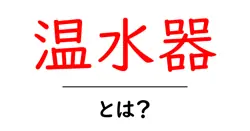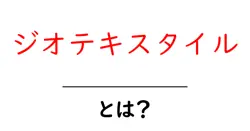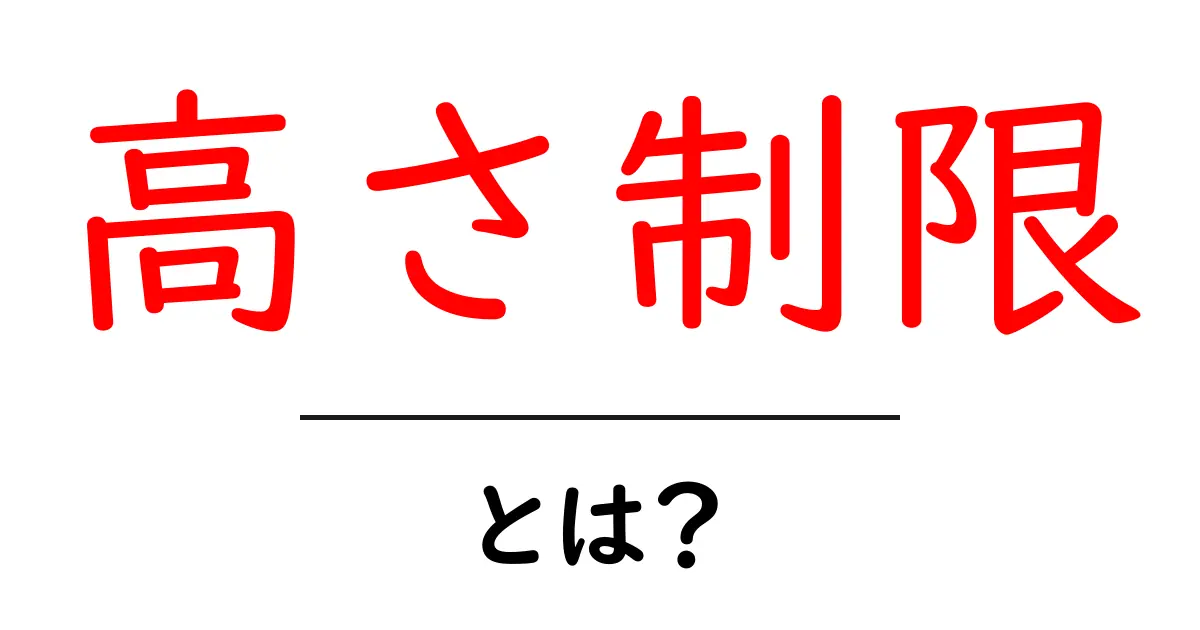
高さ制限とは?
「高さ制限」というのは、建物や構造物の高さを制限するルールや規制のことを指します。この規制は、様々な理由から設定されています。例えば、安全性や周囲の環境との調和、景観の保護などが主な理由です。
高さ制限が必要な理由
高さ制限にはいくつかの重要な理由があります。その一部を以下に紹介します。
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| 安全性 | 高い建物が風に対して不安定になることもあるため、市民の安全を保つために必要です。 |
| 景観の保護 | 高すぎる建物があると、周囲の風景が損なわれることがあるため、景観を守るために制限があります。 |
| 周囲との調和 | 地域の特性にあった建物が求められるため、周囲の建物とのバランスを考慮することが大切です。 |
高さ制限の具体例
高さ制限の具体例として、都市計画が挙げられます。例えば、都市部の一部地域では、建物の高さが10階建てまでと決められていることがあります。これは、周囲の環境や交通に与える影響を考慮した結果です。
また、自然公園などの地域では、高さ制限が厳しく設定されており、環境保護が考慮されます。こうした制限があることで、景観が美しく保たれ、自然が大切にされるのです。
高さ制限を守ることの重要性
高さ制限を守ることは、私たちの生活環境をより良くするために非常に重要です。これにより、安全で快適な生活を送ることができるとともに、地域社会や環境を保護することができます。
以上が「高さ制限」についての基本的な情報です。このような規制は、私たちが住む街や地域をより良くするために必要不可欠なものだと言えるでしょう。
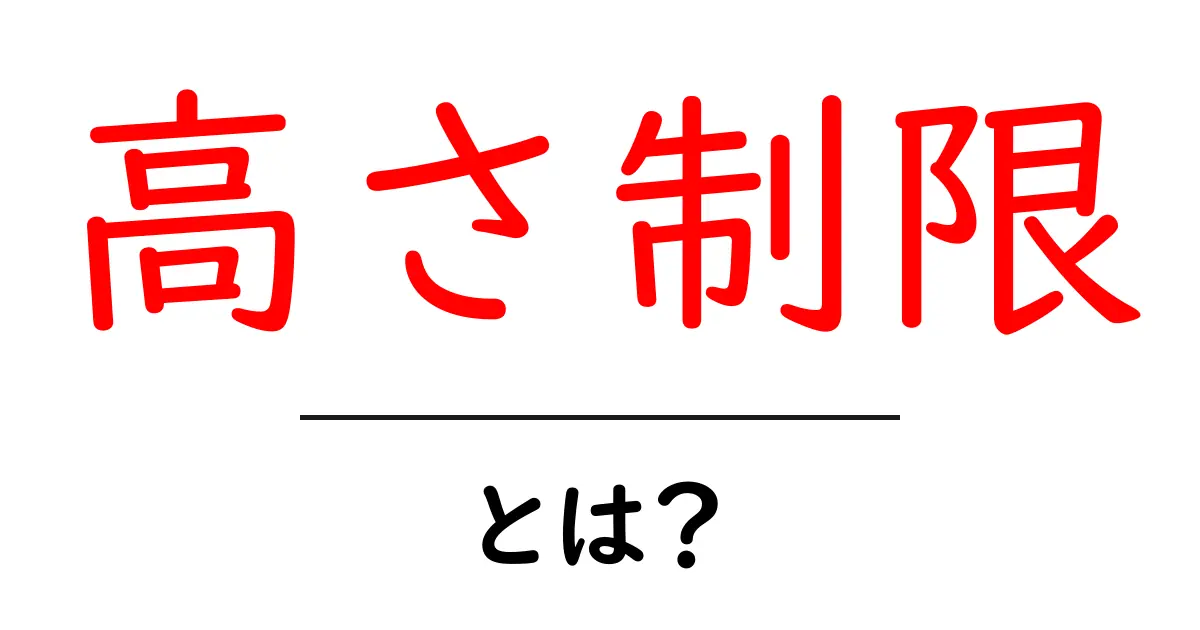
制限:ある範囲や条件を超えないようにすること。高さ制限では建物や構造物の高さを制約することを指します。
建築基準法:日本での建物の設計や施工に関する法律。高さ制限はこの法律に基づいて決められることが多いです。
用途地域:都市計画によって区分けされた地域で、特定の用途(住宅、商業、工業など)によってルールが異なること。用途地域によって高さ制限が異なる場合があります。
土地利用:土地の使用目的や方法を指します。高さ制限は土地利用の計画に密接に関連しています。
景観:地域の見た目や雰囲気を形成する要素。高さ制限は良好な景観を保つために重要です。
隣地影響:隣接する土地に対する影響や影のことです。高さ制限は隣地への影響を考慮して設けられます。
環境保護:自然環境や生態系を守るための取り組み。高さ制限は環境への影響を考慮する一環です。
日照権:隣接する土地の住居の光を受ける権利。高さ制限は日照権を守るために設けられることがあります。
風通し:風が通ること。高さ制限が適用されることで、地域の風通しが良くなることがあります。
都市計画:将来の都市の発展や土地利用を計画すること。高さ制限は都市計画の一部として重要な役割を果たします.
高さ制約:物の高さに関する制限や決まりのこと。特に建物や構築物の高さが法律や規則によって定められている場合によく使われる表現です。
高さの上限:ある物体や構造物が持つことができる最大の高さ。これも建築や土木の分野でよく使用されます。
最高高さ:その物体や構造物で許可されている最も高い位置を指します。主に建物などの構造物に関連して使われます。
高さ制限値:建物や構造物が持つことのできる最大の高さを数値として示したもの。行政の条例や規制に基づいて設定されます。
制限高さ:特定の場所や地域において、建物の高さに対する規制を指す言葉。これは通常、景観や安全性を考慮したものです。
高さ制限:建物や構造物の高さを規制する法律や条例のこと。周辺環境や景観、日照権などを守るために設けられています。
建築基準法:日本における建築物の設計や施工に関する基準を定めた法律。高さ制限もこの法律に基づいて定められることがあります。
用途地域:都市計画において、地域ごとに建物の用途や高さについての制限を設けるための区域。商業地域、住居地域などがあります。
日照権:建物の高さや配置が周囲の建物に影響を与えないようにするための権利。これを考慮することで、高さ制限が定められることがあります。
景観条例:地域の自然環境や文化的な景観を守るために定められる法律や規則。高さ制限もこれに影響されることがあります。
土地利用計画:地域の土地をどのように利用するかを計画するもので、高さ制限を含む建物の規制を設ける要素となります。
容積率:土地の面積に対する建物の延べ床面積の比率。高さ制限と密接に関連しており、より高い建物を建設する場合には、この制限も考慮する必要があります。
建ぺい率:土地の面積に対して建物が占める面積の割合。この比率も高さ制限と関係しており、特に都市部では重要な規制となります。