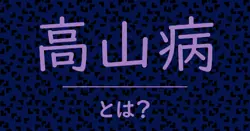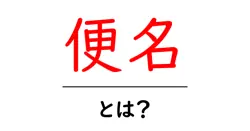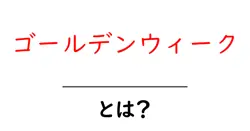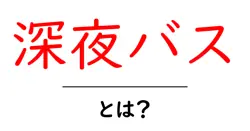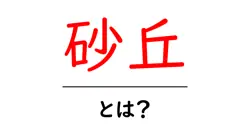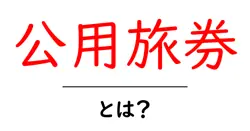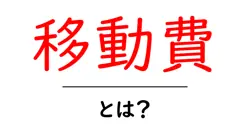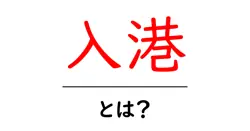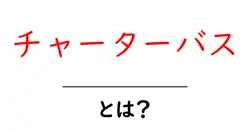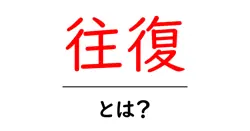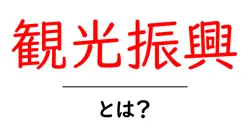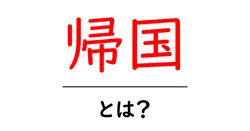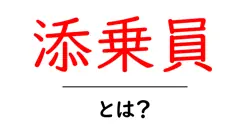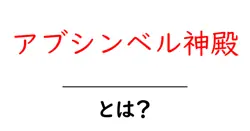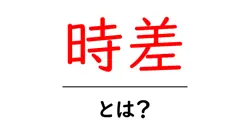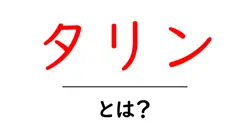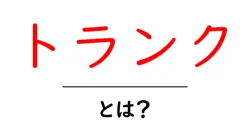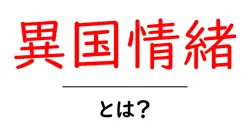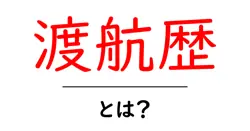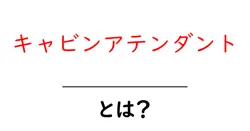高山病とは?症状や予防法を詳しく解説
高山病は、高い山に登ったときに起こる体の不調のことです。特に、標高が2500メートル以上の場所で感じることが多いです。この病気は、空気中の酸素が薄くなるため、体がその環境に適応できなくなってしまうことから起こります。
高山病の症状
高山病の主な症状には、次のようなものがあります:
| 症状 | 説明 |
|---|---|
| 頭痛 | 特に高い場所での酸素不足が原因です。 |
| めまい | 脳が酸素不足になり、ふらふらすることがあります。 |
| 吐き気 | 消化器官も影響を受けるため、気持ち悪くなることがあります。 |
| 倦怠感 | 体がだるく感じ、普段通りの活動が難しくなります。 |
| 息切れ | 運動したときに特に感じやすいです。 |
高山病の原因
高山病は、基本的に低酸素状態が原因です。高所では酸素の濃度が低くなるため、体が酸素を取り込むのが難しくなります。特に急に高い場所に行くと、体が慣れる前に症状が出ることがあります。
高山病の予防法
高山病を予防するためには、いくつかの方法があります:
- 徐々に高度を上げる - 急に高い場所に行かず、少しずつ高度を上げて体を慣らします。
- 十分な水分補給 - 水をたくさん飲んで、体を hydrated に保ちましょう。
- 軽い食事を心掛ける - 重い食事は避け、消化に良い食べ物を選びましょう。
- 休息をとる - 高い場所では無理をせず、しっかり休むことが大切です。
最後に
高山病は多くの人に影響を与える可能性がありますが、正しい知識と対策を取ることで、十分に予防することができます。高山に行く際は、この記事を参考にして楽しい登山を楽しんでください。
高山病 初期症状 とは:高山病って聞いたことありますか?これは、山の高いところに行ったときに起こる病気です。特に、標高が3000メートル以上になると、高山病になるリスクが高まります。初期症状としては、頭痛、めまい、吐き気、食欲不振、そして疲れやすさがあります。これらの症状は、高山に登り始めた直後から現れることが多いです。高山に登ったときは、普段と違う環境に体が順応しなければなりません。しかし、無理をせずに休んだり、水分をしっかり取ることが大切です。もし症状が治まらず、悪化するようであれば、早めに下山することを考えましょう。高山病は軽度のものから重度までさまざまですが、最初の症状に気づいて適切に対処することが大切です。登山を楽しむためにも、高山病の初期症状を理解しておきましょう。
高山病 肺水腫 とは:高山病と肺水腫は、山岳地域でよく見られる体調不良ですが、異なる状態です。高山病は、酸素が薄い高い場所に長時間いることで起こります。特に、標高が2500メートル以上になると、頭痛、めまい、息切れなどの症状が出ることがあります。これに対して、肺水腫は高山病の一種で、特に重症化した場合に見られる状態です。肺水腫になると、肺に液体がたまり、呼吸が苦しくなります。高山病の予防には、ゆっくりと標高を上げることや十分な水分を摂ることが大切です。もし症状が強く出た場合は、高い場所から下りたり、医師の診察を受けることが必要です。知らないままでは危険なこともあるので、しっかりと知識を持って、高山を楽しみましょう!
酸素:高山病は、高地において酸素が薄くなることによって引き起こされる症状です。特に標高が高い場所では、酸素の濃度が低下し、体が酸素不足に陥ります。
症状:高山病のさまざまな症状には、頭痛、吐き気、疲労感、めまいなどがあります。これらの症状は、体が高地に適応しようとする過程で現れます。
高地:高山病は高地にいるときに発症するため、標高が2500メートル以上の場所で特にリスクが高まります。
適応:体は高地に適応するために時間が必要です。緩やかに標高を上げていくことが、高山病の予防につながります。
予防:高山病を予防するためには、十分な水分補給や急激な標高上昇を避けることが重要です。また、必要に応じて高山病の治療薬を使うことも考慮されます。
標高:標高は地面からの高さを示し、高山病の発症リスクは標高が上がることに比例します。標高が高くなるほど、酸素が薄くなります。
降下:高山病の症状がひどくなる場合は、すぐに標高を下げることが最も効果的な対処法です。再び低地に降りることで、症状が緩和されます。
水分補給:高山病を予防するためには、水分補給が特に重要です。高地では脱水症状が起こりやすいため、意識して水を飲むことが大切です。
急性高山病:高地に急に行くことで体が順応できずに起こる症状の一つで、頭痛や吐き気を伴うことがあります。
高地病:高所に移動することで生じる体の不調を指します。高山病とほぼ同義ですが、より広い範囲を指すことが多いです。
高山障害:高地に適応できずに生じる健康問題を指します。症状は急性高山病と共通しています。
二酸化炭素蓄積症候群:高地で酸素が不足することによって体が酸欠状態になり、二酸化炭素が体に蓄積することで起こる症状のことです。
高山酸素不足症:高地では酸素の濃度が低くなるため、酸素不足によって引き起こされる体調不良を指します。
標高:気象条件や環境が変化する理由となる地表からの地面の高さ。高山病は一般的に標高が2,500メートル以上になるとリスクが増加する。
酸素不足:高い標高では空気中の酸素分圧が低くなり、体に必要な酸素が不足しやすくなる状態。これが高山病の主な原因。
急性高山病:高い山に急に登った際に引き起こされる、一時的な症状。頭痛、吐き気、めまいなどが含まれる。
慢性高山病:長期間高地にいる場合に見られる、高山病の持続的な症状。体が高地に適応できない場合に発生する。
適応:高高度に体が慣れていく過程。体は気圧や酸素濃度が低い環境に適応するために、様々な生理的変化を行う。
高山症:高山病の別名で、急性高山病や慢性高山病を含む広い意味で使われることがある。
標高病:高山病の一種で、高い場所に急に行くことで生じる身体的症状を指す。
運動機能:高地での運動能力が低下することが多く、特に息切れや疲労感が影響を受ける。
降下:高山病の症状が悪化した場合、標高を下げることで症状が軽減することが多い。この行動を降下と呼ぶ。
予防策:高山病を防ぐための方法で、ゆっくりと段階的に高度を上げたり、水分補給を怠らないことなどが含まれる。
高山病の対義語・反対語
該当なし