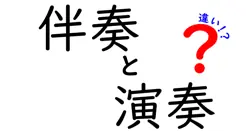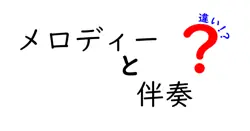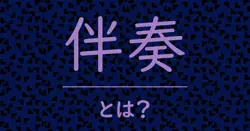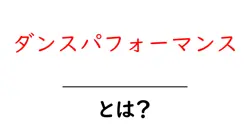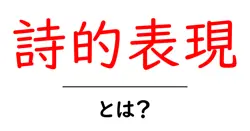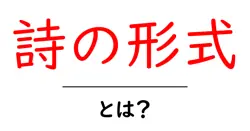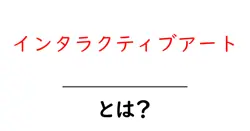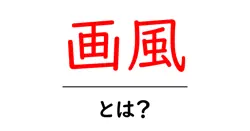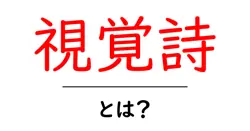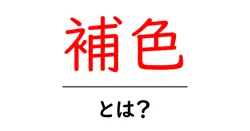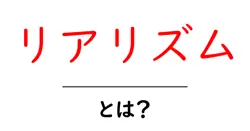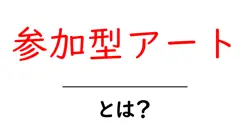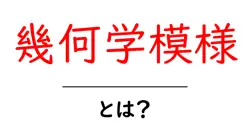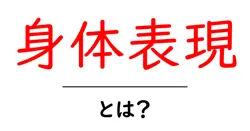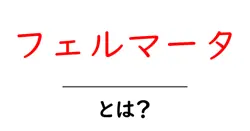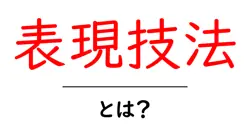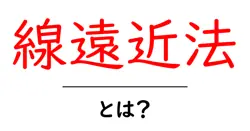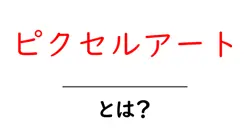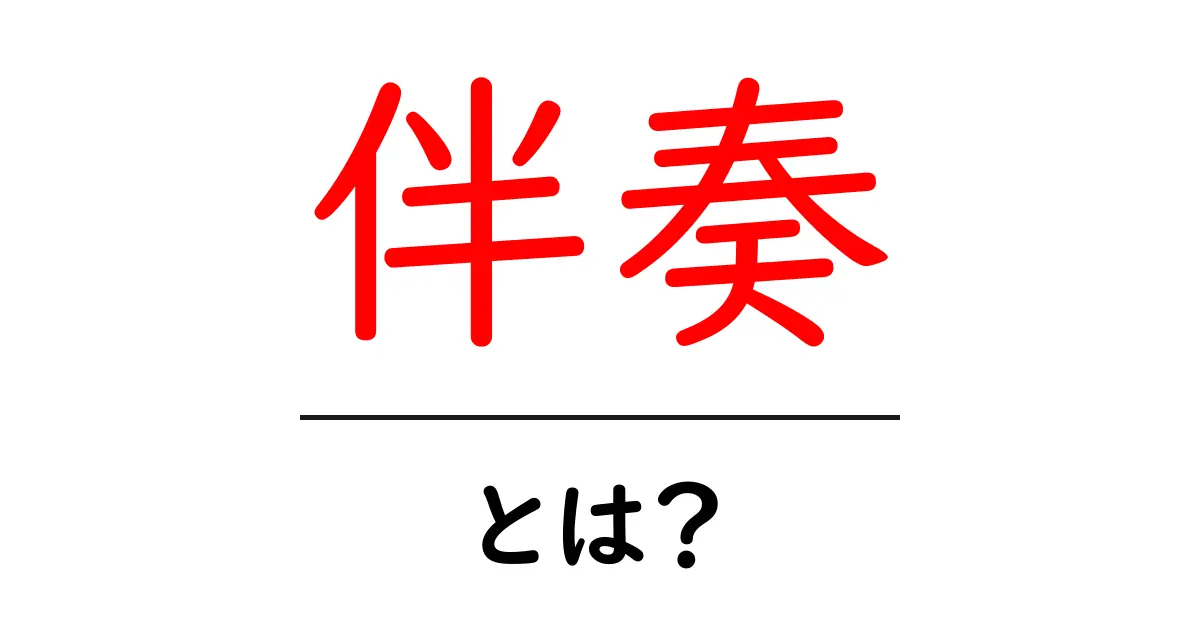
「伴奏」とは? 音楽の世界での役割をわかりやすく解説
音楽において、「伴奏」という言葉はとても重要です。伴奏は、主に歌や楽器の演奏を支える役割を果たします。例えば、歌手が歌うとき、後ろでギターやピアノが演奏されていることがありますよね。このように、伴奏は主旋律を引き立て、音楽全体に深みを与える役割を担っています。
伴奏の種類
伴奏にはいくつかの種類がありますが、ここでは主なものを紹介しましょう。
| 伴奏の種類 | 説明 |
|---|---|
| 和声伴奏 | 和音を使ってメロディを支える形式。ピアノやギターが多く用いられます。 |
| リズム伴奏 | リズムを提供してメロディを引き立てる形式。ドラムなどが代表的です。 |
| 旋律伴奏 | メロディを一部サポートする形式。一部の楽器が同じ旋律を奏でたり、オフビートで和音を入れたりします。 |
伴奏の重要性
伴奏は音楽の雰囲気を決定づける重要な要素です。主旋律が一人で歌っていても、伴奏によってその歌がどのように聞こえるかが大きく変わります。例えば、静かなバラードと、元気なポップソングでは、伴奏のスタイルが全く異なるはずです。この変化によってリスナーの感じ方も変わってきます。
例としての有名な伴奏
著名な作曲家の楽曲を考えてみましょう。有名なピアニストが伴奏を務めることがあり、それによって歌手が持つメロディの美しさを際立たせるのです。さらに、オーケストラでは、さまざまな楽器が一緒に演奏し、伴奏がより豊かになります。
まとめ
「伴奏」という言葉は、音楽の中で非常に重要な役割を持っています。伴奏があることで、メロディが引き立ち、全体としてより美しい音楽が生まれるのです。音楽を聴くときには、ぜひ伴奏にも注目してみてください。
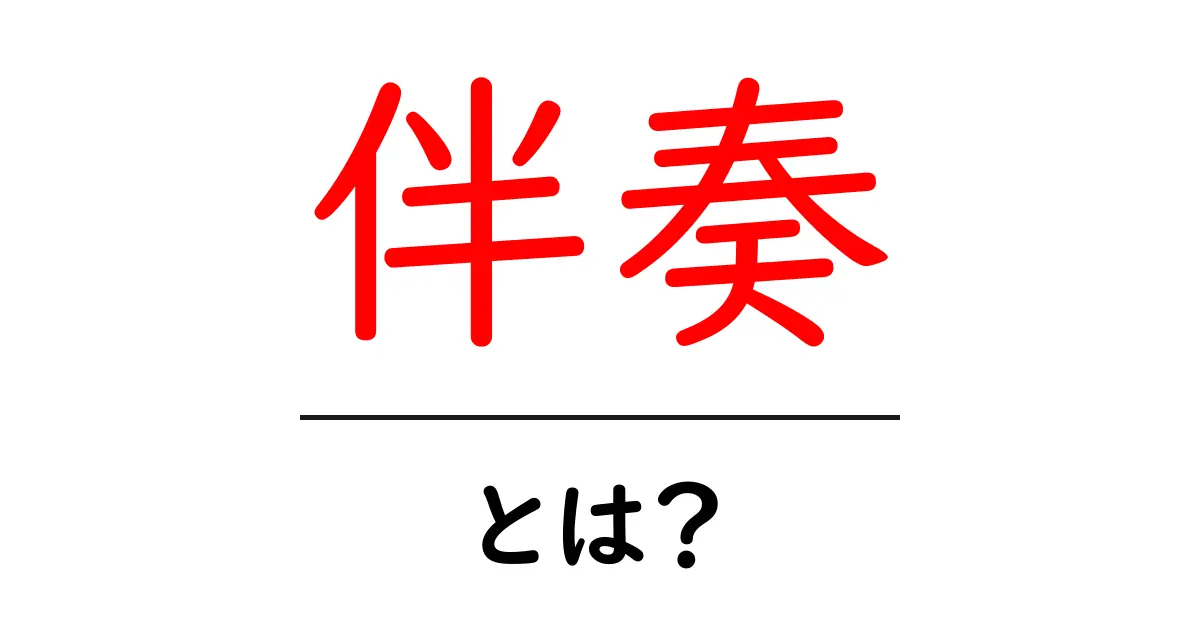
コード 伴奏 とは:音楽を楽しむうえで「コード伴奏」という言葉をよく耳にしますが、具体的には何なのでしょうか?まず、コードとは音楽の和音を指します。つまり、複数の音を同時に奏でることで、メロディを支える役割を果たします。伴奏というのは、そのメロディに寄り添い、支える部分のことです。例えば、ピアノで曲を演奏するとき、右手でメロディを弾きながら、左手でコードを弾いて支えることが一般的です。これがコード伴奏です。中でも、ギターなどの弦楽器では、コード伴奏を使ってシンプルに曲を演奏することが多いです。コード伴奏を覚えることによって、もっと自由に曲作りや即興演奏ができるようになります。また、友達と一緒に演奏する時などにも、コード伴奏を使うとみんなで楽しく音楽を楽しむことができます。最初は難しいと感じることもありますが、少しずつ練習していけば、必ずできるようになります。
伴奏 とは ピアノ:ピアノの伴奏とは、歌や他の楽器の演奏を支える役割を持つピアノの演奏スタイルです。伴奏は、メロディー(主旋律)を際立たせるために必要で、曲にリズムやハーモニーを加えることができます。初心者でも簡単にできる伴奏スタイルとしては、コードストロークやアルペジオという方法があります。 コードストロークは、和音を一度に押さえてポンと弾くスタイルです。これにより、リズムがしっかりと保たれ、楽曲に厚みを加えることができます。一方、アルペジオは、和音の音を一つずつ順番に弾くスタイルで、流れるような印象を与えられます。 また、伴奏をするときは、歌う人と息を合わせることも大切です。曲のテンポや雰囲気を感じ取りながら、ピアノの演奏をすることがポイントです。ピアノの伴奏を楽しみながら練習して、少しずつ自信をつけていきましょう!
音楽:伴奏は通常、メロディを支えるための音楽的なパートを指します。主に楽器で演奏されます。
メロディ:伴奏は、主にメロディを強調する役割を果たします。メロディは曲の中心となる旋律です。
ハーモニー:伴奏にはハーモニーが含まれ、メロディを美しく響かせるための和音や進行が使われます。
リズム:伴奏はリズムを提供し、曲のテンポを維持するための重要な要素です。
楽器:伴奏にはピアノ、ギター、ドラムなどの楽器が使われ、様々なスタイルで演奏されることが多いです。
歌:伴奏は歌と一緒に使用されることが多く、歌の表現を豊かにする役割を果たします。
伴奏者:伴奏を担当する人を伴奏者と呼び、演奏者がメロディを歌ったり演奏したりするためにサポートします。
音楽理論:伴奏を理解するためには音楽理論が役立ちます。和音や音程についての知識があります。
即興:伴奏は即興で作成されることもあり、演奏者の創造性が発揮されます。
アコーディオン:音楽において、メロディを奏でる楽器の一種で、伴奏を提供することが多い。
バックグランド:主に音楽やパフォーマンスにおいて、主要な要素を引き立てるための背景的存在。
伴奏楽器:メロディの横に演奏され、全体を支える役割を果たす楽器のこと。ピアノやギター、弦楽器などが含まれる。
サポート:メロディの演奏を助ける役割。音楽以外でも、誰かを支えることを示す言葉として使用される。
ハーモニー:複数の音が同時に鳴り響くことで生じる音の調和。伴奏の重要な要素でもある。
演奏:楽器や声を使って音楽を表現する行為。伴奏は演奏の一部として行われる。
音楽:伴奏は通常、楽器や声で演奏される音楽の一部です。メロディを支えたり、リズムを提供したりします。
メロディ:伴奏はメロディ(主旋律)を引き立てる役割があります。メロディは曲の主な部分で、伴奏はその周囲を飾ります。
ハーモニー:伴奏はハーモニーを作り出すことが多いです。ハーモニーは複数の音が同時に響くことで生まれる、心地よい音の重なりを指します。
リズム:伴奏ではリズムも非常に重要です。リズムは音楽の時間的な流れを作り、曲の雰囲気を左右します。
和声:和声は音楽における伴奏で使われる技術で、和音を用いてメロディを補完します。より深みのあるサウンドを生み出します。
楽器:伴奏を行う楽器にはピアノ、ギター、弦楽器、打楽器などがあり、それぞれの特徴により異なる音色を生み出します。
アンサンブル:アンサンブルは複数の楽器や声が一緒に演奏するスタイルを指します。伴奏はアンサンブルで非常に重要な役割を果たします。
ソロ:ソロは一人で演奏するスタイルです。伴奏がない場合、ソロ演奏は主にメロディが際立つ形になります。
演奏:伴奏は音楽の演奏における構成要素の一つであり、曲の全体を形成します。演奏者は伴奏を通じて表現を豊かにします。
合唱:合唱は多人数で歌うスタイルです。伴奏は合唱の音域をサポートし、全体の音楽的なバランスを取ります。