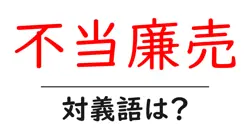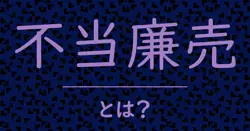不当廉売とは?その説明と影響を解説
不当廉売(ふとうれんばい)とは、製品やサービスを本来の価格よりも極端に安く販売することを指します。これは市場の正当な競争を妨げる可能性があり、安全性や質を脅かすことにもなります。
不当廉売の目的
多くの場合、企業が不当廉売を行うのは、競合他社を排除するためや、市場シェアを獲得するためです。安売りをすることで、消費者を引き寄せ、より多くの利益を得ようとします。
一般的な例
例えば、ある企業が新製品を通常よりも50%も安く販売することがあります。この場合、他の企業はその価格に合わせるか、商品を売れなくなってしまう可能性があります。
不当廉売が引き起こす問題
不当廉売は短期的には消費者にとって魅力的な選択ですが、長期的には市場全体に悪影響を及ぼすことが多いです。以下にその影響を表で示します。
| 影響 | 説明 |
|---|---|
| 競争の減少 | 大手企業が安売りをすると、小規模な企業が市場から退出しやすくなる。 |
| 品質の低下 | 安売りをする企業はコストを削減するために製品の品質を犠牲にすることがある。 |
| 市場の不安定化 | 一時的な安売りが市場を不安定にし、価格の過剰競争を引き起こすことがある。 |
不当廉売に対する対策
不当廉売を防ぐためには、法律や規制が重要です。政府は不当廉売を禁止する法律を整備したり、監視機関を設けたりしている場合があります。
また、企業自身も倫理的なビジネス慣行を守ることが重要です。「安売りではなく、付加価値を提供する」という考え方が求められます。
まとめ
不当廉売は短期的には消費者に利益を与えることが多いですが、長期的には市場全体に悪影響を与える可能性があります。健全な市場競争のためには、法律や企業の倫理が重要です。
価格:商品やサービスの一般的な」(販売」または『提供のために設定される金額のこと。
競争:市場における複数の企業やサービスが売上を増やすために、互いに努力すること。
市場:商品やサービスが売買される場所や、その活動が行われる環境のこと。
規制:国や地方自治体が法律やルールとして、特定の行動や活動を制限したり、管理したりすること。
利益:企業が商売を通じて得る収入から、コストを差し引いた後に残る金額のこと。
掠奪的価格:一時的に非常に低い価格を設定して競合他社を市場から排除するための戦略のこと。
公正取引:市場での取引が公平に行われることを目指す原則や法律のこと。
取引:商品やサービスを売買する行為やその条件のこと。
ダンピング:商品やサービスの価格を市場価格よりも著しく低く設定すること。特に、競合他社を排除する目的で行われる。
過剰競争:市場に過剰な競争が存在し、価格が不当なまでに引き下げられる状態。
不正価格設定:市場や法律に反して、不当に安い価格で商品を販売すること。
価格破壊:極端に低い価格で商品を提供し、他の競合他社を圧倒すること。
不当廉売:市場価格よりも著しく低い価格で商品の販売を行い、他の競争業者を排除する行為を指します。これは不正な競争にあたるため、法律で規制されています。
競争法:企業の競争行為を監視し、公正な競争を促進するための法律です。国や地域によって異なりますが、不当廉売のような行為を規制する目的があります。
市場占有率:特定の市場において、ある企業が占める販売量や売上高の割合を示す指標です。不当廉売によって競合他社を排除することは、市場占有率を不正に高める行為となります。
価格カルテル:複数の企業が互いに合意して価格を設定する行為を指します。これは一般的に不当急激な価格変更と見なされることが多く、法律に抵触します。不当廉売とは異なりますが、競争を妨げる点で関連があります。
独占禁止法:市場における独占や不当な競争を防ぐための法律です。日本では「独占禁止法」に基づき、企業の不当な競争行為を取り締まるための規定があります。不当廉売もこの法律の下で問題視されることがあります。
損害賠償:不当廉売などによって他の企業が損失を被った場合、その補償を求めることができます。企業は、不当廉売を行った場合に他の競合から訴えられるリスクがあります。
競争の促進:市場における競争を活性化させることを指します。公正な価格設定と競争環境を維持することが、消費者にとっての利益となります。不当廉売はこの競争環境を脅かす行為です。
粗利益:企業が商品を販売することで得る利益のうち、コストを引いた後の利益を指します。不当廉売を行うことで本来得られる粗利益が減少します。