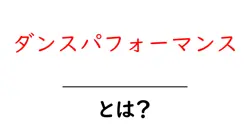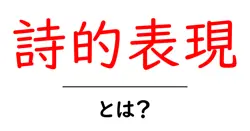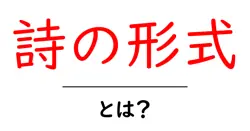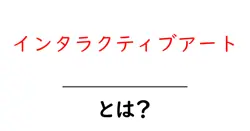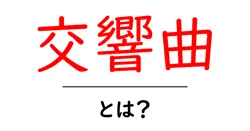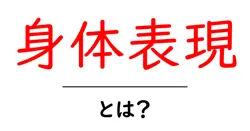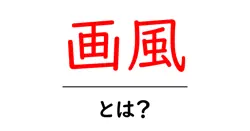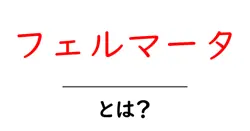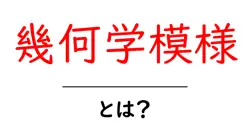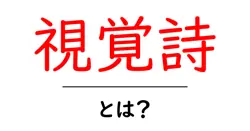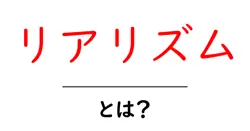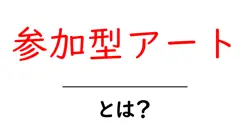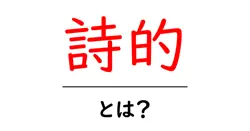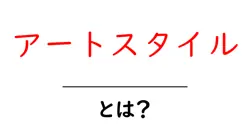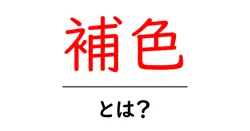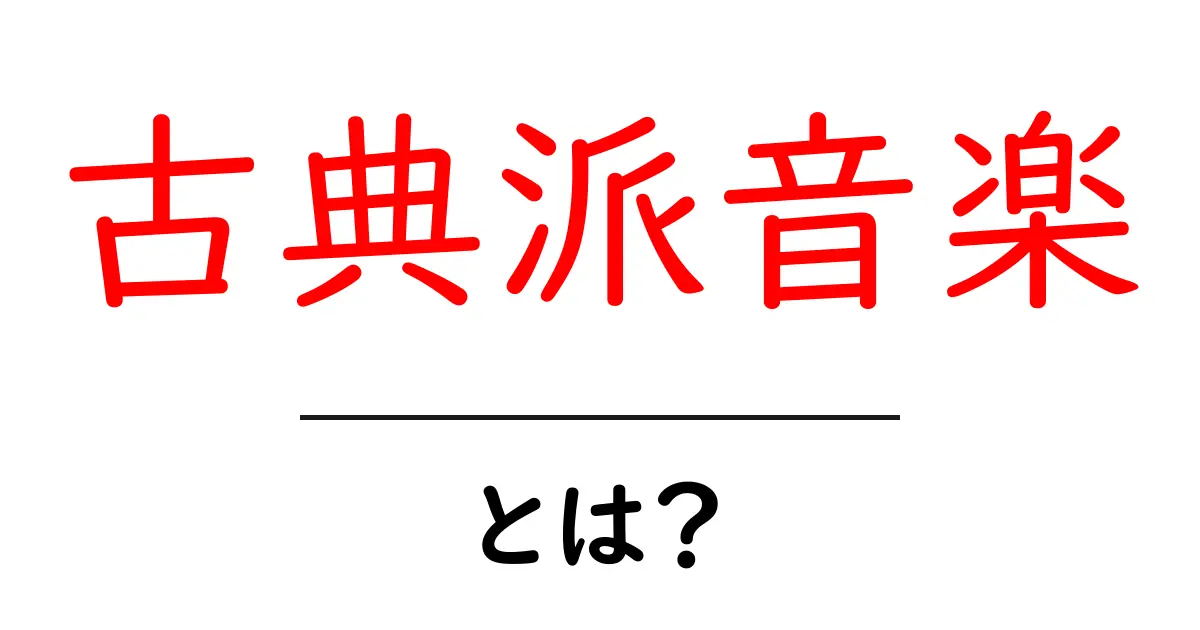
古典派音楽とは?その魅力と特徴を知ろう!
古典派音楽(こてんはおんがく)は、18世紀後半から19世紀初頭にかけて発展した西洋の音楽スタイルの一つです。この時代は、音楽がよりシンプルで構造的な形式を重視するようになりました。ここでは、古典派音楽の特徴や代表的な作曲家について学んでいきましょう。
古典派音楽の特徴
古典派音楽にはいくつかの大きな特徴があります。
- 均整の取れた構造:古典派音楽では、曲が4つの部分から構成されることが多いです。この形式は「ソナタ形式」と呼ばれ、主題が提示され、展開され、再度主題が戻ってくるという流れがあります。
- メロディの明確さ:耳に残るメロディが主役で、シンプルで美しい旋律が特徴です。
- 感情表現の発展:古典派音楽では、感情を表現する手法が多様化しました。感情のコントラストやダイナミクスの変化が重要です。
代表的な作曲家
古典派音楽には多くの偉大な作曲家がいます。以下にその一部を紹介します。
| 作曲家名 | 代表作 |
|---|---|
| ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト | 「フィガロの結婚」、「レクイエム」 |
| ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン | 「交響曲第5番」、弦楽四重奏曲など |
| ヨーゼフ・ハイドン | 「弦楽四重奏曲」、「ロンドン交響曲」 |
古典派音楽の影響
古典派音楽は、その後のロマン派音楽にも大きな影響を与えました。また、現在のポピュラー音楽にもそのエッセンスは受け継がれています。特に、メロディの美しさや、感情表現の技法は多くのアーティストによって引き継がれています。
まとめ
古典派音楽は、ある時代の特定のスタイルを持った音楽ですが、その魅力は今も色あせることなく、多くの人に愛されています。モーツァルトやベートーヴェンなどの偉大な作曲家たちによる作品を聴くことで、その美しさを心から感じることができるでしょう。ぜひ、古典派音楽に触れてみてください。
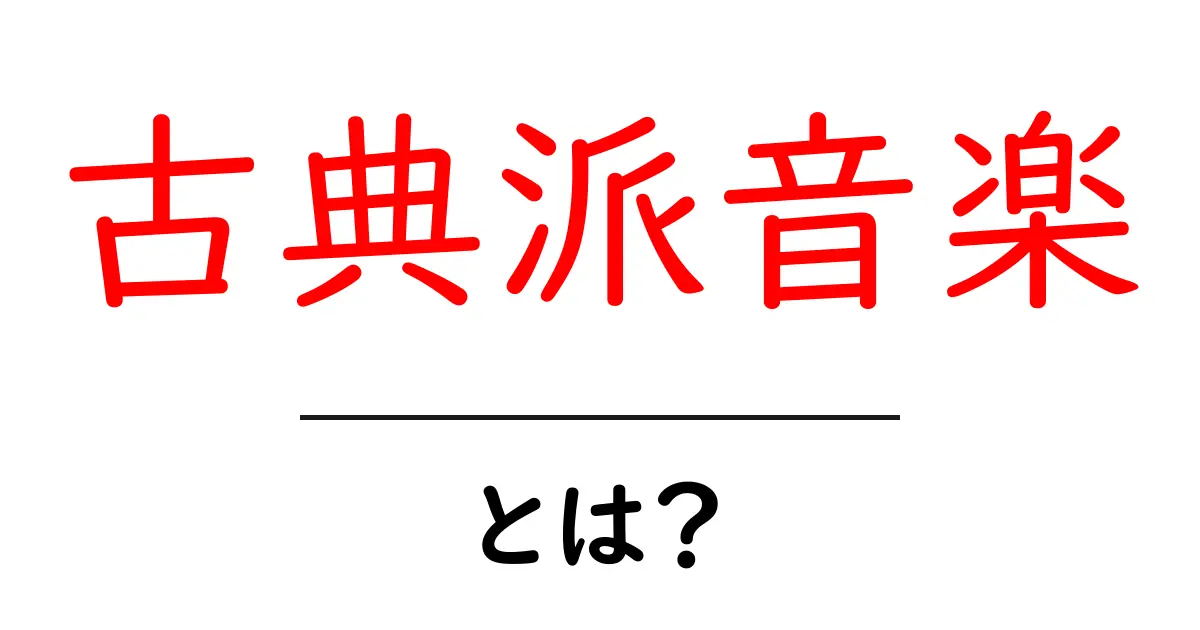
クラシック:古典派音楽はクラシック音楽の一部であり、特に18世紀から19世紀初頭にかけて発展した音楽スタイルです。
楽器:古典派音楽では、弦楽器や管楽器、ピアノなどが主に使用され、それぞれの楽器の特性を生かした演奏が特徴です。
オーケストラ:古典派音楽の多くはオーケストラ演奏用に作曲されており、交響曲や協奏曲などの形が一般的です。
作曲家:モーツァルトやハイドン、ベートーヴェンなどが古典派音楽の代表的な作曲家であり、彼らの作品が中心となります。
旋律:古典派音楽では、旋律が非常に重要で、聴きやすく、記憶に残る美しいメロディが多く含まれています。
形式:ソナタ形式や変奏曲など、古典派音楽には特定の音楽形式があり、これらの構造に基づいて作曲されています。
和声:和声の使い方も古典派音楽の特徴で、和音の重なりや対位法が巧みに用いられています。
フーガ:古典派の後期に影響を受けたフーガは、特にバッハの作品から派生し、対位法的な要素を強調します。
音楽理論:古典派音楽の作曲には、音楽理論が重要で、和声や対位法、形式を理解することが求められます。
クラシック音楽:18世紀から19世紀初頭にかけて発展した、特にオーケストラによる演奏や室内楽が特徴の音楽ジャンル。精緻な構成と調和を重視します。
古典音楽:主に18世紀から19世紀ににかけて作曲された音楽を指し、古典派時代の作品が含まれる。特にハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンの作品が有名です。
ロマン派音楽:古典派音楽の後に続く音楽のスタイルで、感情表現や個人的な経験を重視する特徴があります。ベートーヴェン以降の音楽がこれに該当しますが、約束事に捉われない自由な表現が特徴です。
西洋音楽:主にヨーロッパで発展した音楽全般を指し、古典派だけでなく、各時代の音楽も含まれます。多様なスタイルがあり、今日の音楽に大きな影響を与えています。
オーケストラ音楽:オーケストラによって演奏される音楽のこと。古典派音楽はこのスタイルで数多くの作品が作られ、特に交響曲や協奏曲が有名です。
室内楽:少人数の演奏者による音楽で、古典派の時代にも多くの作品が作られました。弦楽四重奏やピアノ五重奏など、親密な音楽体験が特徴です。
バロック音楽:古典派音楽の前の時代の音楽であり、約1600年から1750年まで広がりました。重厚な和声が特徴で、作曲家にはバッハやヘンデルがいます。
ロマン派音楽:古典派音楽の後に続く音楽スタイルで、約19世紀初頭から20世紀初頭まで発展しました。感情や個人の表現を重視し、作曲家にはショパンやワーグナーが含まれます。
モーツァルト:古典派音楽の重要な作曲家の一人で、1756年から1791年まで生きました。オペラ、交響曲、室内楽など、多くのジャンルで作品を残し、旋律の美しさが特に評価されています。
ハイドン:古典派音楽の基礎を築いた作曲家で、1732年から1809年まで活躍しました。交響曲や弦楽四重奏において革新的な形式を導入し、多くの「父」と称されています。
形式:古典派音楽においては、ソナタ形式やロンド形式など、特定の構造がよく用いられます。これらの形式は音楽の展開や対比を明確にするための手法です。
交響曲:オーケストラのために書かれた大規模な楽曲形式で、通常4つの楽章で構成されます。古典派音楽の主なジャンルの一つであり、特にモーツァルトやハイドンの作品が有名です。
室内楽:少人数の演奏者によって演奏される音楽の形式で、弦楽四重奏やピアノ三重奏などが含まれます。古典派音楽では、この形式においても多くの名作が創出されました。
音楽理論:古典派音楽の楽曲を理解し、分析するためのルールや規則を学ぶ学問です。和声やメロディーの構造を理解するために役立ちます。
演奏スタイル:古典派音楽を演奏する際の技術や表現方法を指します。当時の楽器の特性や演奏者の解釈によって異なります。特にアーティキュレーションやダイナミクスに注意が払われます。
古典派音楽の対義語・反対語
該当なし