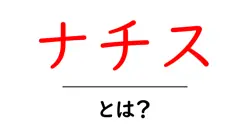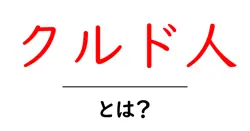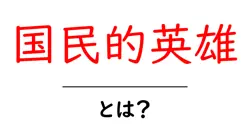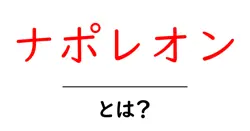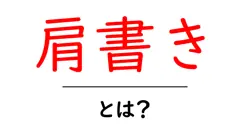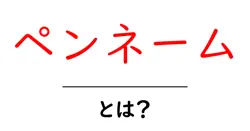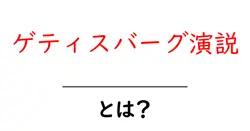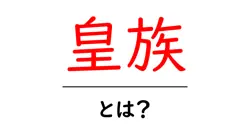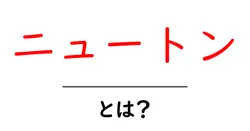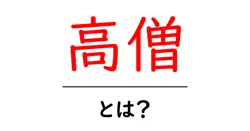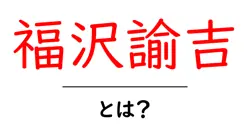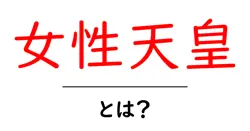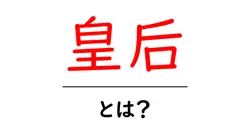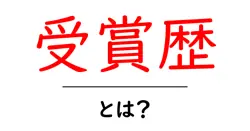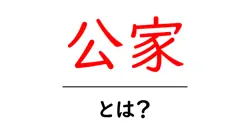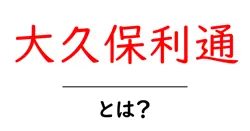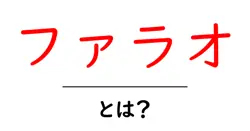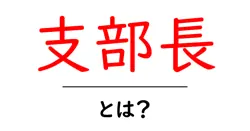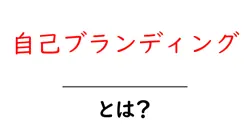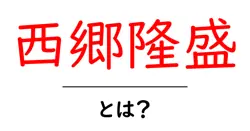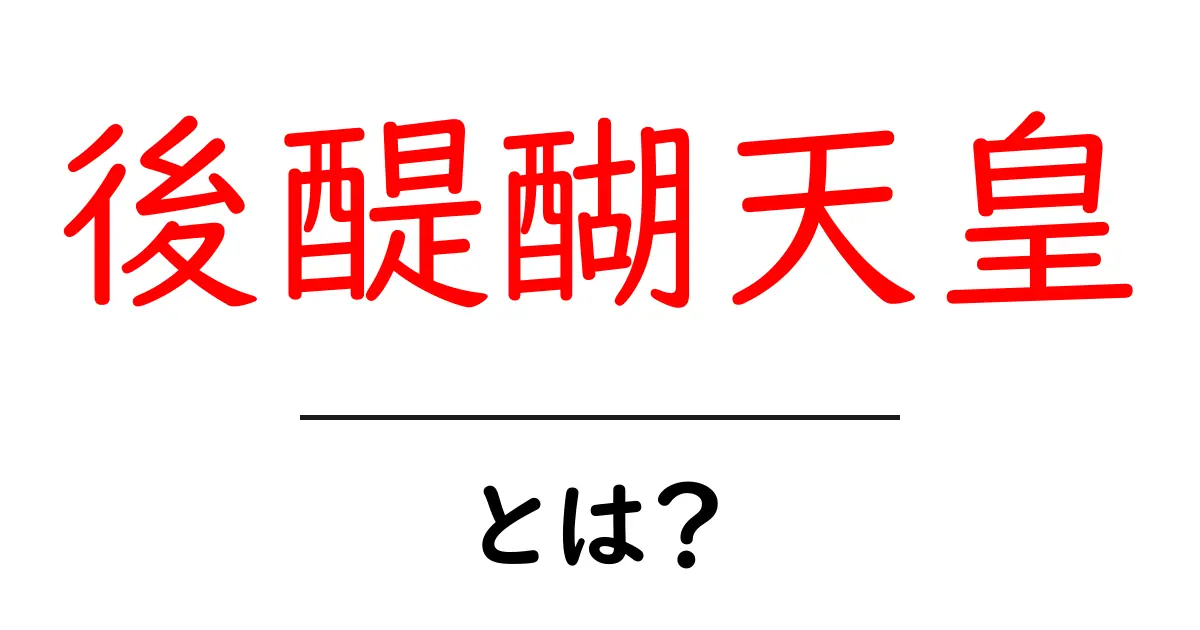
後醍醐天皇とは?その基本情報
後醍醐天皇(ごだいごてんのう)は、日本の歴史において非常に重要な人物の一人です。彼は、鎌倉時代の末期から南北朝時代にかけての天皇であり、在位期間は1318年から1339年まででした。後醍醐天皇は、幕府に対抗し、天皇の力を取り戻そうとする運動を行いました。これが「建武の新政」と呼ばれるものです。
後醍醐天皇の生涯
生い立ちと即位
後醍醐天皇は、1288年に生まれました。彼は比較的若い頃から天皇としての役割を期待されていました。1318年、46歳のときに天皇に即位しました。ただし、彼が天皇になる前、日本は鎌倉幕府の支配下にありました。
建武の新政
後醍醐天皇は、若い頃から幕府の力を弱め、天皇の権威を復活させることを考えていました。1333年、彼は武士である新田義貞や足利尊氏と共に、鎌倉幕府を滅ぼすための戦いを開始しました。
ついに、彼の軍は勝利を収め、鎌倉幕府は崩壊しました。これを機に後醍醐天皇は「建武の新政」を行い、天皇の力を強化しようとしました。しかし、この新政は多くの分裂を生むことになりました。
南北朝時代と後の人生
後醍醐天皇の新政は成功しなかったため、支持を失い、1336年には足利尊氏に敗れ、吉野に逃れます。そこから彼は、南朝を設立し続け戦い続けました。南北朝の時代は、天皇の権威をめぐる激しい戦いが続く時期となりました。
彼は、1348年に亡くなるまで南朝を支持し続けました。
後醍醐天皇の影響
後醍醐天皇は、当時の日本の政治に多くの影響を与えた人物です。彼の行った「建武の新政」は、後の時代においても重要な教訓となります。天皇の力を取り戻そうとした彼の試みは、政治的な改革や武士の役割の変化をもたらしました。
後醍醐天皇の評価
後醍醐天皇は日本の歴史で評価が分かれています。一部の人々にとっては、彼の試みは失敗と見なされることがありますが、他の人々は彼を自由を求めた勇気ある人物として評価しています。
まとめ
後醍醐天皇は、日本の歴史の中で非常に重要な役割を果たした天皇です。彼の生涯を通じての行動は、現在でも多くの人々に影響を与えています。
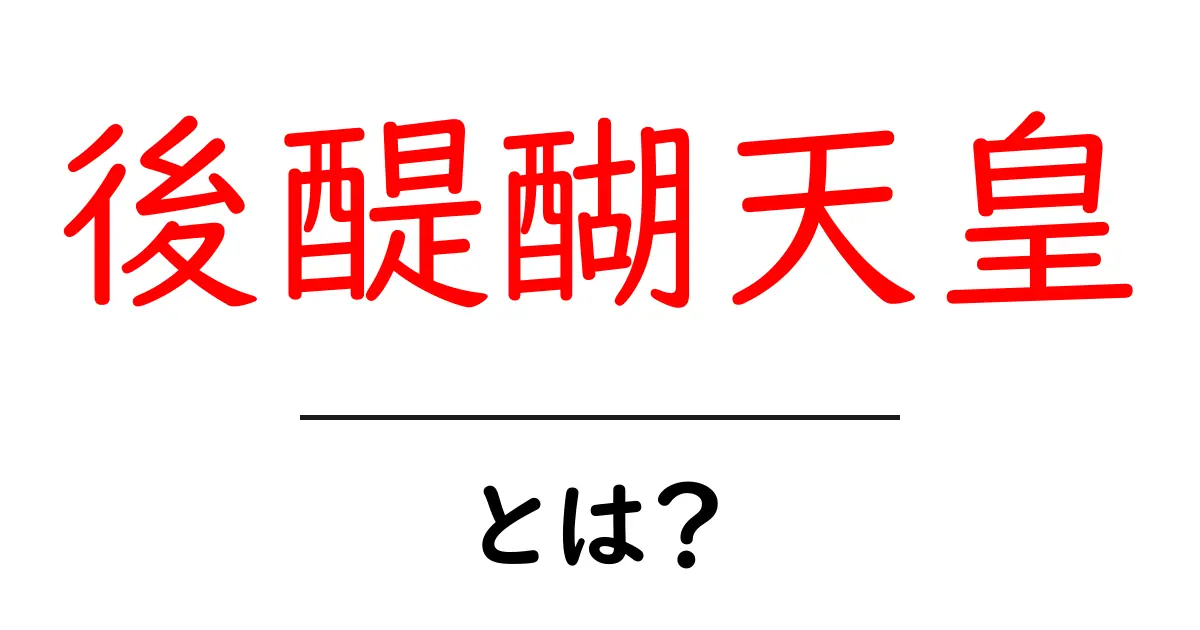
後醍醐天皇 とは 簡単に:後醍醐天皇は、日本の鎌倉時代の末期から南北朝時代にかけて生きた天皇です。彼は1288年に生まれ、1333年に鎌倉幕府を倒し、新しい時代を開くために立ち上がりました。この出来事は「建武の新政」と呼ばれています。後醍醐天皇は、天皇の権威を取り戻そうとし、政治改革を進めました。しかし、彼の政権は長続きせず、1336年には敵に敗れて逃げることになりました。後に日本は南北朝に分かれてしまいます。後醍醐天皇は、再び天皇としての地位を確立しようとしましたが、結局は南朝としての地位に留まりました。彼の生涯は日本の歴史において非常に重要で、後醍醐天皇の名前は今でも多くの人々に知られています。彼の努力は、後の歴史に大きな影響を与えました。彼の物語を知ることで、当時の人々の思いや、政治の変遷について考えることができるでしょう。
南朝:後醍醐天皇が設立した南朝(なんちょう)は、日本の歴史における天皇系の一派で、正統な天皇としての地位を主張していました。
建武の新政:後醍醐天皇が行った政治改革で、1380年代に日本の政治を中央集権的な体制に戻そうとした試みを指します。
鎌倉幕府:後醍醐天皇が生きていた時代に存在した日本の武士政権であり、後の南北朝時代の背景となる重要な存在です。
北朝:後醍醐天皇の対立相手として輩出された天皇系の一派で、南朝と対をなす存在です。特に、北朝の天皇たちが正当な支配者として認識されることが多かった。
後醍醐:後醍醐天皇(ごだいごてんのう)は、1333年に鎌倉幕府を倒し、自らの王朝を立ち上げた日本の天皇です。
武士:後醍醐天皇の時代に重要な役割を果たした軍事的な支配者たちで、天皇に仕える存在として政治や戦争に関与していました。
南北朝時代:後醍醐天皇の死後、南朝と北朝が対立した時代を指し、日本の歴史における重要な転換期となりました。
天皇:日本の君主の称号であり、後醍醐天皇はその一人として日本の歴史に名を刻んでいます。
天皇:日本の皇室の最高位にある君主の称号。特に後醍醐天皇は鎌倉時代から南北朝時代にかけての天皇で、反抗的な姿勢で有名。
南朝:南北朝時代に設立された朝廷の一つで、後醍醐天皇が設立した。北朝と対立する形で存在していた。
皇帝:天皇と同様に国家の最高君主を指す言葉。特に西洋や他の文化圏における君主制とは異なるが、後醍醐天皇もその地位にあった。
公家:平安時代から江戸時代にかけての日本の貴族階級。後醍醐天皇はこの公家出身であり、彼らとの関係が重要であった。
政治家:国家や地域の統治に関わる人。後醍醐天皇は天皇としてだけでなく、政治的なリーダーシップを発揮していた。
武士:戦国時代や鎌倉時代の日本での戦士階級。後醍醐天皇は武士と連携し、朝廷の権威を回復しようとした。
反乱者:権力者に対抗して派閥を形成する者。後醍醐天皇は、権力を持つ北朝に対抗して反乱を企てた代表的な存在。
南朝:後醍醐天皇が建てた政権が南朝です。北朝と対立し、南北朝時代を形成しました。
北朝:後醍醐天皇に対抗して成立した政権で、南朝と対立しました。南北朝時代のもう一方の政権です。
建武の新政:後醍醐天皇が1242年に実施した政治改革で、封建制度の改革を目指しました。この政策は短命に終わりましたが、重要な意味を持ちます。
瑞宝院:後醍醐天皇が建立した寺院で、彼の宗教的な側面を示す場所でもあります。
白河天皇:後醍醐天皇の祖先であり、平安時代の天皇の一人です。彼の治世は日本の古代史において非常に重要です。
倒幕運動:後醍醐天皇が主導した、鎌倉幕府を倒そうとする運動のことです。彼の信念がこの運動に大きな影響を与えました。
文武両道:後醍醐天皇の治世において強調された、学問と武道の両方を重んじる考え方です。
天皇:日本の皇室の最高位にある人物で、後醍醐天皇はその一人として特に歴史的な重要性を持っています。
後醍醐天皇の対義語・反対語
該当なし