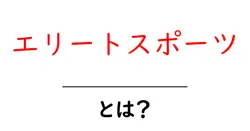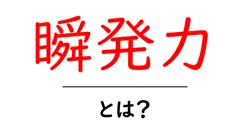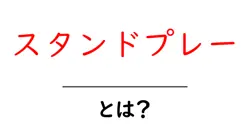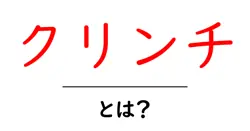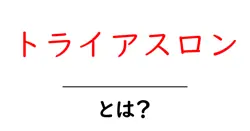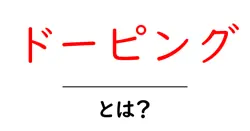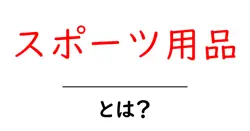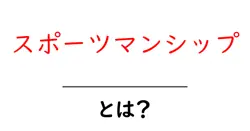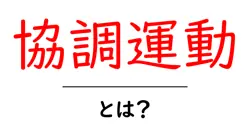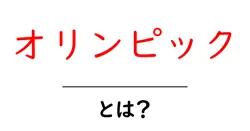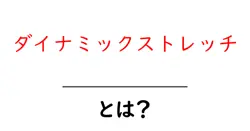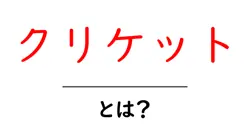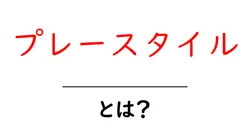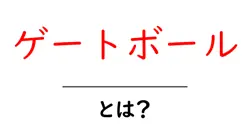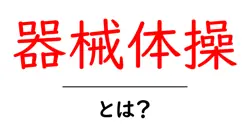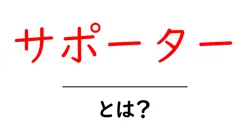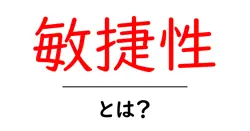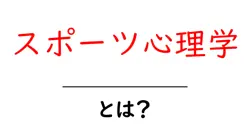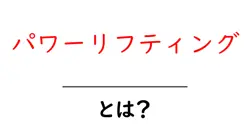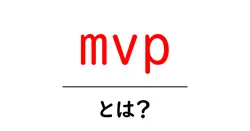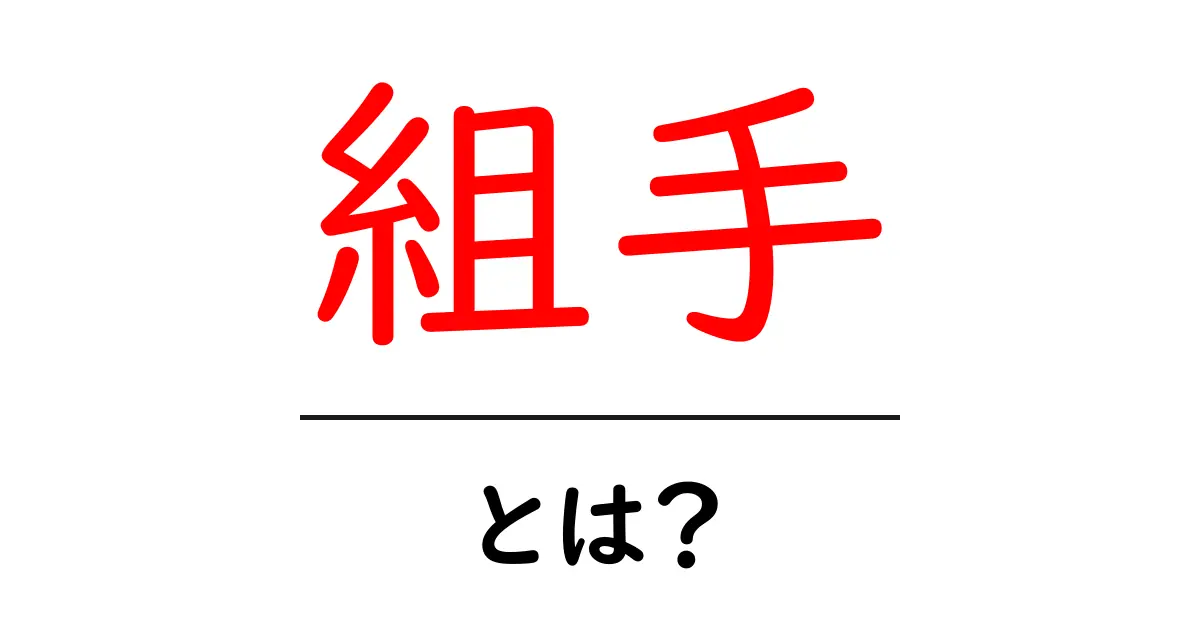
組手とは何か?
組手(くみて)は、主に武道や格闘技において相手と対峙し、技をかけたり、防御したりする実技のことを指します。日本の武道、特に空手や柔道、剣道などでよく見られます。
組手の歴史
組手の起源は、古代の戦闘技術に由来しています。戦士たちは相手との間合いや攻撃、受け流しの技術を磨くため、練習として組手を行っていました。特に日本の武道では、組手が重要な位置を占めています。
組手の種類
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 自由組手 | 実際の試合に近い形で行われる組手。 |
| 型組手 | 決まった動作に基づいて行う、演技的な側面が強い。 |
| 練習組手 | 技術向上のために行う、安全を重視した形式。 |
組手のメリット
組手を行うことにはいくつかの利点があります。まず、実践的な技術を身につけることができる点です。また、相手との相互作用を学ぶことで、戦略や判断力を向上させることができます。そして、体力や敏捷性も鍛えられます。
練習方法
初心者が組手を学ぶためには、まず基本的な動作を練習することが大切です。以下のような方法で練習を進めてみましょう。
- ストレッチやウォームアップで体をほぐす。
- 基本技の習得から始める。
- 仲間とペアを組んで、軽い組手を行う。
まとめ
組手は、武道を行う上で非常に重要な技術です。安全に配慮しながら楽しく練習を重ねることで、技術向上だけでなく、仲間との絆も深まります。興味がある方はぜひ、組手を学んでみてください。
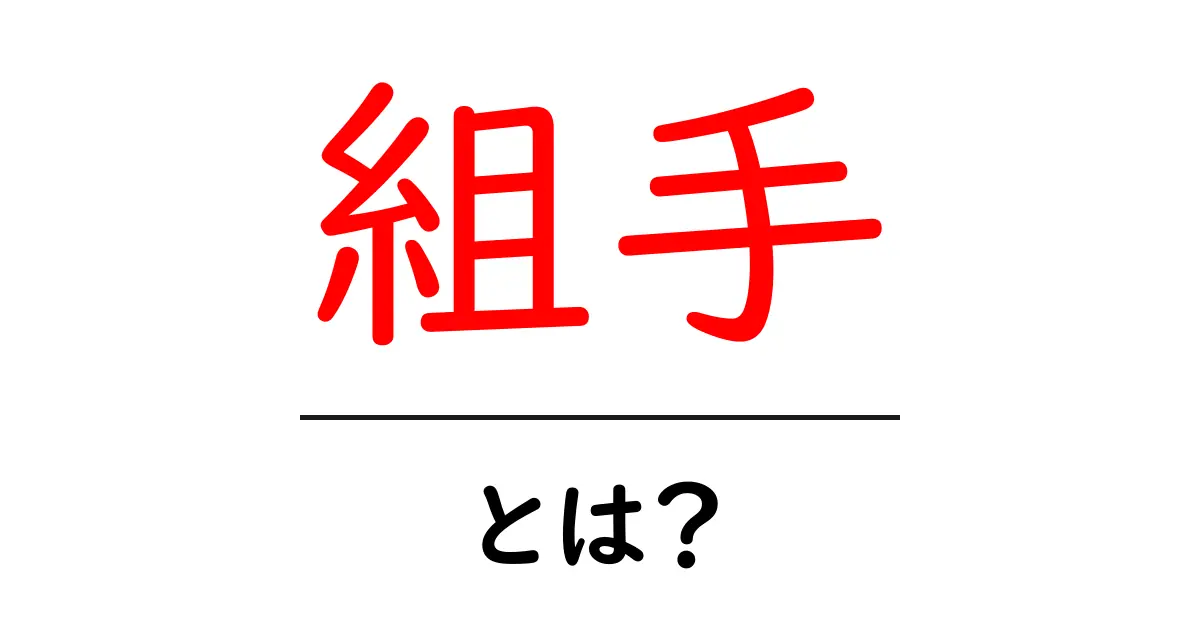
柔道 組み手 とは:柔道の組み手とは、相手と接触する際の体の持ち方や技を使うための最初のポジションのことを指します。柔道では、組み手が非常に重要です。なぜなら、良い組み手ができれば、相手を投げたり、抑え込みなどの技に繋げることができるからです。組み手には、いくつかの基本的なスタイルがあります。例えば、片襟を持つ「片襟組み」、両襟を持つ「両襟組み」、そして一方の襟と相手の腕を持つ「袖組み」などです。これらの組み手は、技をかけるための準備でもあり、相手の動きを制御するための重要なテクニックでもあります。練習して自分なりの組み手を身につけることで、試合で勝ちやすくなります。組み手のコツとしては、常に相手との距離感を見て、自分のバランスを崩さないようにすることが大切です。また、組み手のバリエーションを増やして、状況に応じた技を使えるようになりましょう。これを積み重ねていくことで、自然と柔道の実力が上がっていくのです。これから柔道に挑戦する皆さん、まずは組み手をしっかりと学んでみてください。
空手 組み手 とは:空手の組み手(くみて)は、空手の型(かた)や基本(きほん)を練習することに加えて、実際に相手と対戦(たいせん)することを指します。空手の組み手では、相手と直接手を使った攻撃(こうげき)や防御(ぼうぎょ)を行いますが、ルールが存在(そんざい)します。 通常、組み手は「自由組み手(じゆうくみて)」と「型組み手(かたくみて)」に分かれます。自由組み手では、自分の判断で技を使ってまともに戦いますが、型組み手では事前に決まった型を使って相手と戦います。 組み手の練習は、体力や反射神経(はんしゃしんけい)を向上(こうじょう)させるためにも非常に重要です。また、相手との距離感や動き方を理解(りかい)することも学べます。試合を通じて、仲間とのコミュニケーションや礼儀(れいぎ)も学ぶことができるため、心も育てる場でもあります。 初心者でも安心して始められるように、空手道場では経験豊富な指導者がしっかりと指導してくれますので、空手の技を楽しみながら磨いていけます。さあ、あなたも空手の組み手に挑戦(ちょうせん)してみませんか?
空手 組手 とは:空手の組手(くみて)とは、対戦相手と実際に技を使って戦う練習や試合のことを指します。空手は単なる体を動かすスポーツではなく、心を鍛え、技術を高める武道でもあります。組手の目的は、相手との距離感や攻防のタイミングを学ぶこと、そして自分の技を実践し、心の強さを育てることです。学ぶべき基本のルールとしては、相手に直接的な攻撃を加えない「ポイント制」があります。これは、安全第一で、選手が怪我をしないようにするためです。組手では、技を決めてポイントを獲得していくため、スピードと正確さが求められます。さらに、組手はただ勝つための試合ではなく、友情や礼儀を重んじる場でもあります。仲間と切磋琢磨(せっさたくま)しながら、楽しく練習することが大切です。空手の組手を通じて、自信を持ち、相手へのリスペクトを養う貴重な経験が得られるでしょう。
組み手 とは:「組み手」という言葉は、主に武道や格闘技で使われる用語です。組み手は、相手と直接接触する技術や動きのことを指します。例えば、空手や柔道では、組み手の練習が大切です。この練習を通じて、相手とどのように接触するかや、どうやって自分の技を出すかを学んでいきます。組み手の技術は、単に力を使うだけではなく、相手の動きを読み、上手に対応することが求められます。これにより、自分だけでなく相手の安全も守ることができます。また、組み手を行うことで、身体能力の向上や反射神経を鍛えることができ、自分の技術を試す貴重な場となります。このように、武道や格闘技において組み手は非常に重要な要素で、技術を磨くための基本的な練習方法の一つです。これから武道を始めたい人にとって、組み手はまだ見ぬ自分の力を発見するための第一歩とも言えるでしょう。
空手:日本の武道の一つで、拳や足などを使った打撃技が特徴です。
道場:武道や武術を学ぶ場所のこと。練習や試合が行われる。
対戦:二人以上の選手が技を競い合うこと。特に試合形式で行われる。
打撃:技や攻撃として、相手を打つことを指します。組手においては技の一部。
防御:相手の攻撃を避けたり、ブロックしたりする技術。
ポイント制度:試合において、技の成功や相手に与えたダメージに応じて得られる点数。
ルール:試合や組手を行う際の規則や指針。
競技:特定のルールに基づいて行われるスポーツのこと。組手もその一部。
トレーニング:技術や体力を向上させるための練習やフィジカルトレーニング。
試合:選手同士が実力を競い合う公式な対戦。
選手:組手や他の武道で競技に参加する人のこと。
技術:特定の戦闘や運動におけるスキルや動作のこと。
リアルタイム:試合の進行中に選手が相手の動きを瞬時に判断し対応すること。
ストラテジー:対戦時の戦略や戦術のこと。どのように戦うかを考えること。
心構え:試合や組手に臨む際のメンタル態勢や意識のこと。
格闘:身体を使って対戦相手と戦うこと。
戦闘:敵と直接戦う行為。
組み合い:相手と体の接触を持ち、絡み合うこと。
対戦:二者が互いに対抗し合うこと。
試合:競技や戦闘を行うイベントのこと。
バトル:相手と遂行する競り合いや戦い。
マッチ:競技者同士の対決や試合。
戦い:敵や対戦相手に対して行う行動全般。
組手:主に武道や格闘技において、相手と実際に対戦することを指します。練習や試合の一環として行われ、技術や反応を鍛えるための重要な要素です。
型:武道や格闘技において、特定の技や動きを決まった形で繰り返し練習することを意味します。組手とは異なり、実戦的な対戦ではなく、基本技術を体得するための方法です。
対戦:二人以上の選手が技術を競うことを指します。組手は対戦の一形態であり、ルールに基づいて行われるため、結果に応じて勝敗が決まります。
反応:相手の動きに対して、素早く対応する能力を指します。組手では相手の技や攻撃に即座に反応することが求められ、これを鍛えることで実戦力が向上します。
スパーリング:実戦に近い状況で、相手と組手を行う練習形態です。目的は技術の向上や戦略の確認であり、一般的には安全に配慮した範囲で行われます。
練習:技術や体力を向上させるために行う行為全般を指します。組手の練習は、実戦に役立てるために行う重要なトレーニングです。
ルール:組手や対戦における戦い方のガイドラインを示します。ルールは安全を確保し、公平な競技を行うために設定されており、各武道や格闘技ごとに異なる場合があります。
試合:選手同士がルールに則って争う競技イベントを指します。組手は試合の中で行われ、選手が技術や体力を競い合うことが目的です。
技術:武道や格闘技における特定の動きや技を指します。組手ではこれらの技術を駆使して相手と戦うことが求められます。
体力:組手において求められる身体的な能力を指します。高い体力は持久力や反応速度を向上させ、実戦でのパフォーマンスを向上させます。
組手の対義語・反対語
該当なし