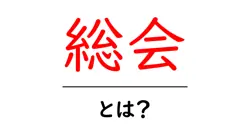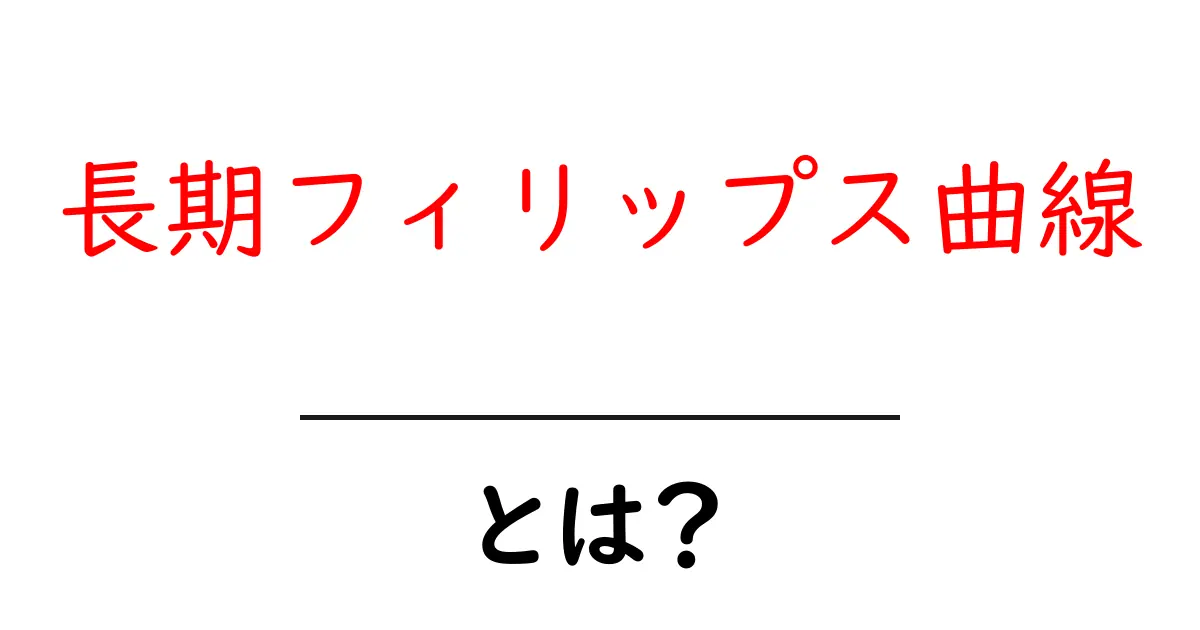
長期フィリップス曲線とは?
長期フィリップス曲線は、経済学における重要な概念のひとつです。簡単に言うと、国のインフレ率と失業率の関係を示すグラフのことです。これを理解することで、経済がどのように動いているのかを知る手助けになります。
フィリップス曲線の基本
フィリップス曲線自体は、1958年にニュージーランドの経済学者ア.W.フィリップスによって提唱されました。彼は、失業率が低いとインフレ率が高くなるという関係に注目しました。つまり、雇用が増えると物価が上昇しやすいということです。
短期と長期の違い
フィリップス曲線には短期と長期がありますが、ここで焦点を当てるのは「長期フィリップス曲線」です。短期的には、企業は需要が増えると生産を増やし、雇用を増やすことで失業率が下がりますが、長期的にはこの関係が変わります。
長期フィリップス曲線の特性
長期的には、経済は自然失業率という一定のレベルに戻るとされています。この自然失業率とは、経済が健全に機能しているときの失業率のことです。したがって、長期フィリップス曲線は、インフレ率が高まっても失業率は変わらないと考えられています。以下の表は、短期と長期のフィリップス曲線の違いを示しています。
| 要素 | 短期フィリップス曲線 | 長期フィリップス曲線 |
|---|---|---|
| インフレ率 | 失業率が低いほど高くなる | 一定 |
| 失業率 | インフレ率が高いほど下がる | 自然失業率に戻る |
実際の経済への影響
長期フィリップス曲線が示す考え方は、政策決定者にとって重要です。たとえば、景気を刺激するために中央銀行が金利を下げると、一時的には失業率が低下するかもしれません。しかし、長期的には物価が上昇し、失業率は自然失業率に戻るという事実を理解することが必要です。
まとめ
長期フィリップス曲線は、経済の安定性を考える上で重要なツールです。短期的な政策がもたらす影響を理解しつつ、長期的な視点を持つことが、経済の健全な成長につながります。
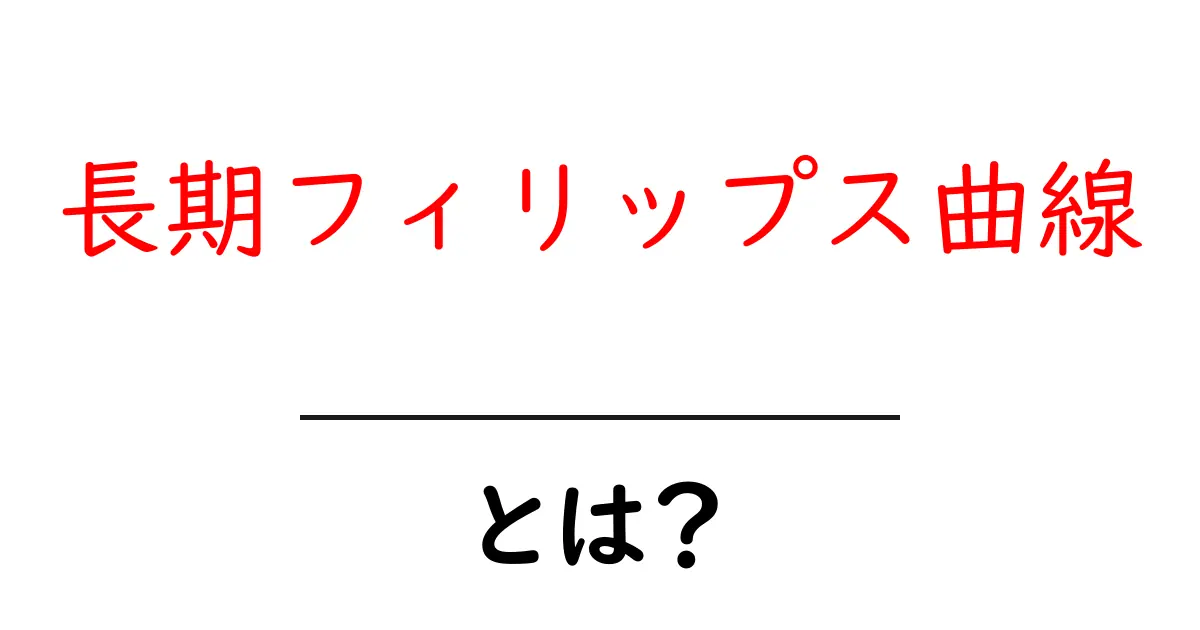 フィリップス曲線とは?経済の未来を考える基礎知識共起語・同意語も併せて解説!">
フィリップス曲線とは?経済の未来を考える基礎知識共起語・同意語も併せて解説!">インフレーション:物の値段が全体的に上昇すること。通貨の価値が下がることを意味し、長期フィリップス曲線ではインフレーション率との関係が注目されます。
失業率:働きたいが仕事がない人の割合を示します。長期フィリップス曲線では、失業率とインフレーション率の関係を考察します。
経済政策:政府や中央銀行が経済の安定や成長を促すために行うさまざまな施策のこと。長期フィリップス曲線の理解は、経済政策の適用に重要です。
デフレーション:物の価格が全般的に下降する現象で、長期フィリップス曲線ではインフレーションと対照的な概念とされます。
供給側の要因:生産や供給に関連する要素。長期フィリップス曲線では、供給側の変化がどのようにインフレーションや失業に影響を与えるかも考慮されます。
需要側の要因:消費者の需要や経済活動に関連する要素。需要側の変化により、長期フィリップス曲線におけるインフレーションや失業に影響を及ぼすことがあります。
自然失業率:経済が完全雇用に達したときの失業率。長期フィリップス曲線では、この自然失業率がインフレーションとどのように関連するかが重要です。
フィリップス曲線:インフレーション率と失業率の逆相関関係を示すグラフ。長期フィリップス曲線は、この関係が長期的には成立しないことを示します。
経済成長:国内総生産(GDP)が時間とともに増加すること。長期フィリップス曲線では、経済成長が失業やインフレーションにどのように影響を与えるかが考慮されます。
フィリップス曲線:インフレーション率と失業率の関係を示す経済学のモデル。短期と長期の2種類があり、長期フィリップス曲線ではインフレと失業に関するトレードオフが存在しないとされる。
短期フィリップス曲線:短期的な経済状況におけるインフレーションと失業の関係を表した曲線。こちらでは、インフレ率が高いと失業率が低くなる傾向があるとされます。
NAIRU(ノンアクセプタブル・インフレ率・ユニット):非加速的インフレ率を指し、インフレが持続的に上昇しないような失業率の水準を示します。長期フィリップス曲線に関連付けられることが多いです。
インフレーション経済学:インフレーションに関する理論やモデルを分析する経済学の一分野。長期フィリップス曲線はこの経済学の重要な要素です。
経済循環モデル:経済が成長し、変動する様子をモデル化したもの。長期フィリップス曲線は経済循環における失業とインフレの関係を理解する手助けをします。
フィリップス曲線:フィリップス曲線とは、失業率とインフレーション率(物価上昇率)との関係を示す経済学のモデルです。通常、失業率が低いとインフレーションが高くなるという逆相関の関係が見られます。
短期フィリップス曲線:短期フィリップス曲線は、短期的な経済状況における失業率とインフレーション率との関係を示しています。物価の変動や景気の影響を受けやすく、失業率が低いとインフレーションが上がる傾向があります。
長期経済成長:長期経済成長とは、時間をかけて経済が成長し続けるプロセスのことです。短期的な景気の波を超えて、持続的な成長を達成するためには、技術革新や資本の蓄積が重要です。
自然失業率:自然失業率とは、経済が完全雇用の状態にあるときに存在する失業率のことです。これには、季節的な変動や摩擦的失業が含まれており、景気の影響を受けにくいとされています。
金融政策:金融政策は、中央銀行が行う経済を安定させるための政策のことです。金利や通貨供給量を調整することで、インフレーションや失業率をコントロールしようとします。
財政政策:財政政策とは、政府が行う経済を調整するための政策で、税金や公共支出を通じて経済活動を促進したり抑制したりします。これにより、景気を安定させることが狙いです。
インフレーションターゲット:インフレーションターゲットとは、中央銀行が設定するインフレーション率の目標です。これにより、物価の安定を目指し、経済政策を調整する基準となります。
経済循環:経済循環は、生産・消費・貯蓄の循環過程を指します。企業が商品を生産し、消費者がそれを購入することで、経済が回る仕組みを説明する概念です。
長期フィリップス曲線の対義語・反対語
該当なし