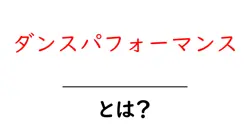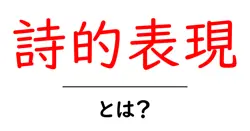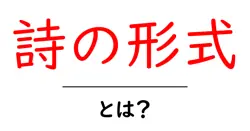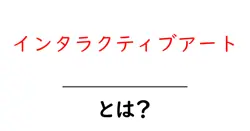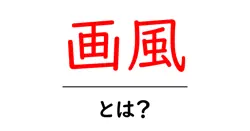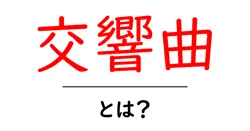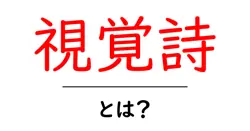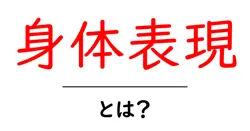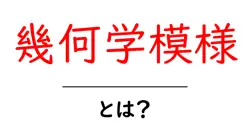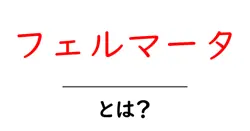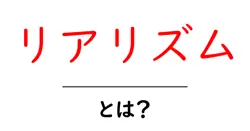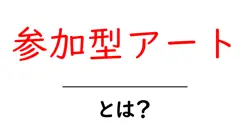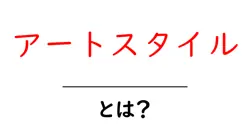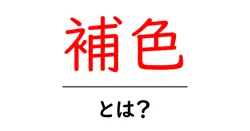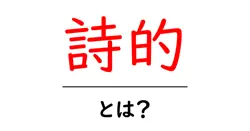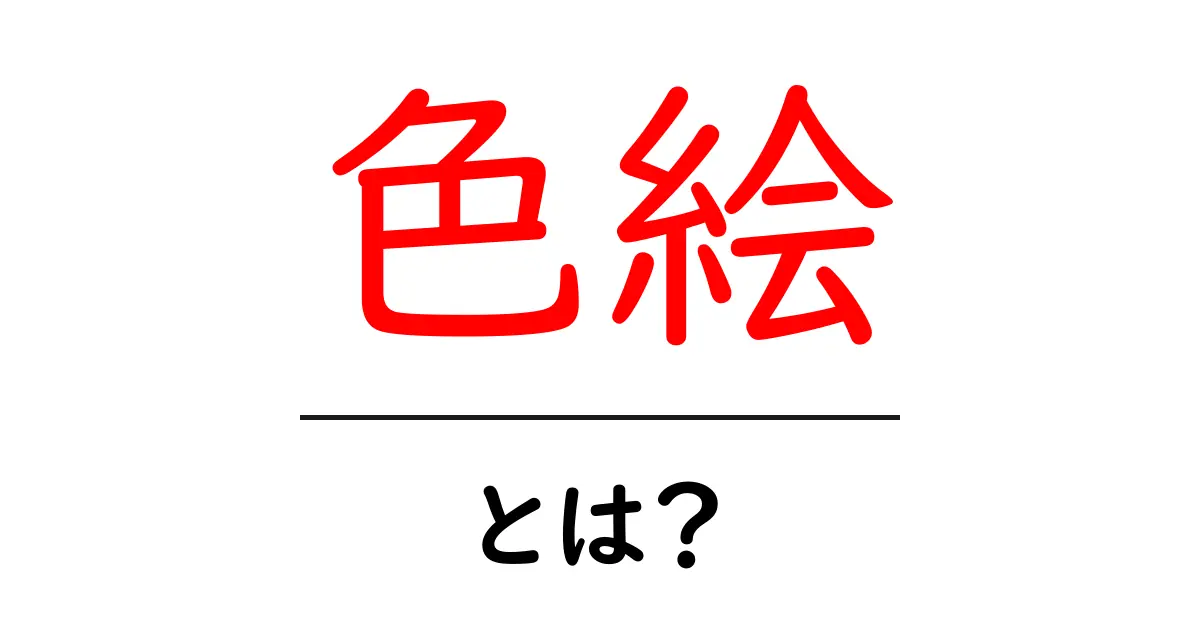
色絵とは?
色絵(いろえ)は、絵付けの技法の一つで、陶器や磁器の器を彩るために使われる技術です。特に、日本の有名な陶器である「有田焼」や「九谷焼」などで、この技術が多く取り入れられています。色絵は、様々な色や模様で器を美しく彩ることができるため、多くの人々に愛されています。
色絵の歴史
色絵の起源は、古くは中国にまで遡りますが、日本で色絵が本格的に盛んになったのは、江戸時代のことです。この時代には、絵師たちが色絵の技術を極め、独自のスタイルを持つ器を生み出しました。例えば、華やかな花模様や、面白い動物の絵が描かれた器が多く作られました。
色絵の技術
色絵の技術には、主に以下のような工程があります:
| 工程 | 説明 |
|---|---|
| 素焼き | 器を一度焼いて、土の状態を固めます。 |
| 絵付け | 素焼きした器に、色のついた絵の具で模様を描きます。 |
| 本焼き | 絵付けした器を再度焼き、色を定着させます。 |
色妍の種類
色絵には、様々な種類がありますが、代表的なものを以下に示します:
- 有田焼:華やかな色使いと繊細な模様が特徴です。
- 九谷焼:五色(青、赤、黄、紫、緑)を使った独特のスタイルです。
- 信楽焼: rusticな雰囲気を持ち、手作り感が魅力です。
色絵の魅力
色絵の魅力は、その美しさだけでなく、職人たちの技術の結晶でもあります。一つ一つの器は、手作りであり、世界に一つだけの存在です。また、色絵の器は、日常使いでも特別な日に使っても、どちらでも楽しむことができます。
色絵の世界は非常に奥が深く、見る人を惹きつける魅力があります。器をひとつ持つことで、日常生活がより豊かになるんです。ぜひ、色絵の器を手に取って、その美しさを楽しんでみてください。
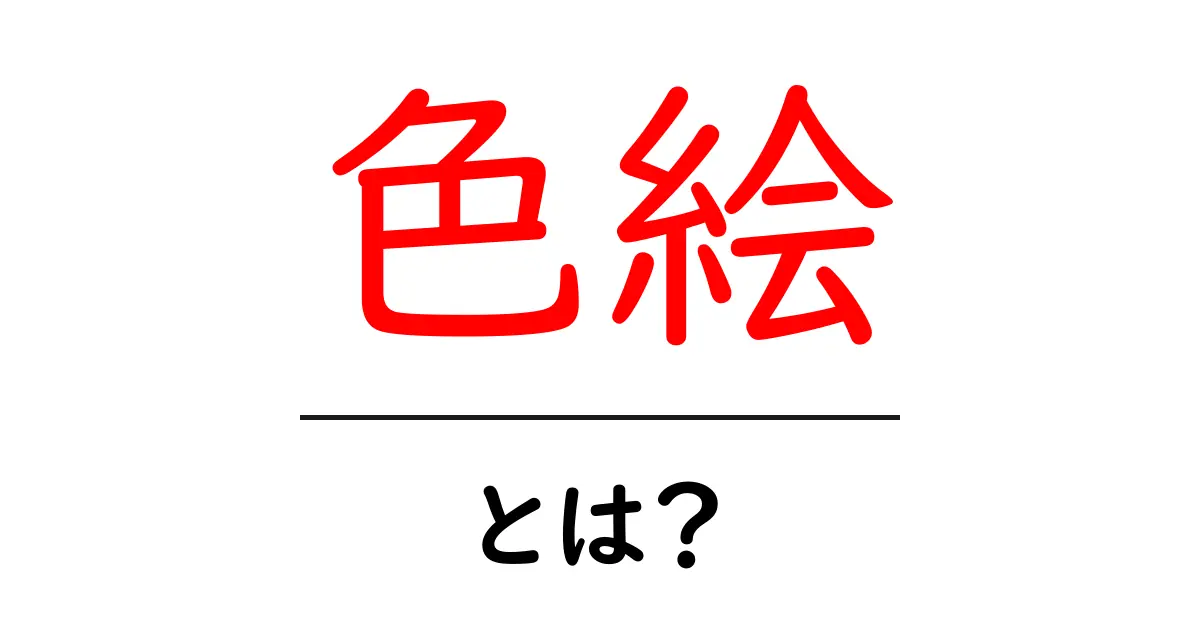
陶器:焼き物の一種で、粘土を焼き固めて作られる器や装飾品を指します。色絵は陶器の表面に施される色の絵柄を指すことが多いです。
磁器:硬く、透明感があり、主に高温で焼かれる陶器の一種です。色絵は磁器の表面にも描かれることがあります。
絵付け:器や陶器の表面に絵や模様を描くことを指します。色絵はこの絵付け技術の一つで、色彩豊かな絵柄が特徴的です。
彩色:色をつけることや、色を施すことを意味します。色絵は彩色を施した作品であり、多彩な色が楽しめます。
装飾:物体を美しくするための飾りを指します。色絵は陶器や磁器の装飾手法の一つです。
伝統工芸:地域や国に特有の技術や美術を使った工芸品を作ることです。色絵は日本の伝統工芸の一環でもあります。
手描き:機械ではなく、手で直接描くことを指します。色絵の多くは手描きで行われます。
焼成:陶器や磁器を焼くことを意味し、材料を高温で焼き固め、色絵を施すための下地を作ります。
アート:芸術作品や技術のことを指します。色絵は陶器や磁器のアートとしても評価されています。
彩色:異なる色を用いて絵を描くこと。色鮮やかに仕上げる技法を指す場合も多い。
色彩画:色を使って描かれた絵画の総称。色の美しさや表現力が重視される。
カラードローイング:カラーを使った絵やデッサンのこと。色鉛筆やマーカーなどで描かれることが一般的。
ポリクローム:多様な色を用いた装飾や絵画。特に中世の美術に見られるスタイル。
カラーイラスト:色を使ったイラストレーションのこと。広告や書籍、ゲームなど多岐にわたって使用される。
色絵:色絵は、陶器や磁器の表面に色を付けて装飾する技法のことです。日本や中国の伝統的な工芸品によく見られます。
陶器:陶器は、粘土を焼き固めて作られる器のことで、一般的には色絵を施して decorative な表現がされることが多いです。
磁器:磁器は、高温で焼かれる陶器の一種で、しばしば美しい色絵が施されています。磁器は、通常、強度があり、光沢があります。
絵付け:絵付けとは、陶器や磁器の表面に絵や模様を描く技法で、色絵もその一部です。焼成前や後に行うことができます。
絵具:絵具は、色絵に使用される色を付けるための材料で、焼き付けられることで定着します。陶器専用のものや食品安全性に配慮されたものがあります。
釉薬:釉薬は、焼成された陶器や磁器の表面を覆うガラス質の層で、色絵を保護し、光沢を与えます。
焼成:焼成は、陶器や磁器を高温で焼いて形成する過程を指します。色絵は、焼成によって定着し、その美しい色合いが引き立ちます。
伝統工芸:伝統工芸は、その地域や文化に根ざした手工芸のことで、色絵の技法は日本や中国の伝統工芸の一つとされています。
デザイン:デザインは、色絵の模様や形を考えるプロセスで、独自のスタイルやテーマを表現する重要な要素です。
色絵の対義語・反対語
該当なし