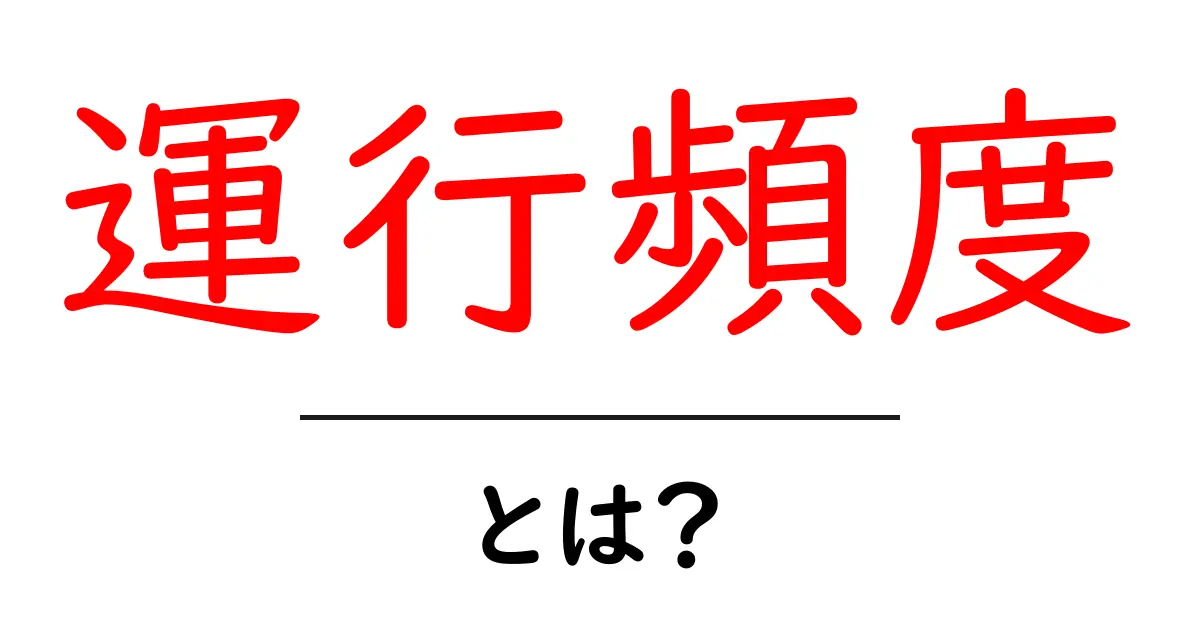
運行頻度とは?
運行頻度(うんこうひんど)とは、公共交通機関や他のサービスが、特定の時間にどれくらいの頻度で運行されるかを示す言葉です。例えば、電車やバスが何分ごとに到着するのかを示す指標となります。運行頻度が高いほど、利用者にとって便利で、移動しやすいと言えるでしょう。
運行頻度が重要な理由
運行頻度は、交通手段を選ぶ際に非常に重要です。例えば、あるバスが30分おきに来るのと、10分おきに来るのでは、利用者の選択が大きく変わります。運行頻度が高いと、待ち時間が短くなるため、移動がスムーズに行えます。
運行頻度の計算方法
運行頻度は、運行される本数を基に計算されます。例えば、1時間に6本のバスが走っている場合、そのバスの運行頻度は10分ごとになります。利用者は、目的地や時間帯に応じて、運行頻度が高いルートを選ぶことが多いです。
運行頻度の例
| 交通機関 | 時間帯 | 運行頻度 |
|---|---|---|
| 電車 | 平日昼間 | 5分ごと |
| バス | 朝ラッシュ | 10分ごと |
| 地下鉄 | 夕方ラッシュ | 3分ごと |
運行頻度に基づく計画
運行頻度を理解することで、計画を立てやすくなります。例えば、友人と会う約束をする際、どの時間帯に出発するかを決めるのに運行頻度が役立ちます。運行頻度の高い時間帯を選ぶことで、より快適に移動ができます。
運行頻度改善の取り組み
交通機関の運行頻度を向上させることは、公共交通機関の重要な課題です。政府や運営会社は、利用者の利便性を高めるために、運行する本数を増やす努力をしています。
まとめ
運行頻度は、公共交通を利用する上で非常に重要な要素です。高い運行頻度は、待ち時間を短縮し、移動をスムーズにします。次回交通機関を利用する際には、運行頻度をチェックして、より快適な移動を実現しましょう。
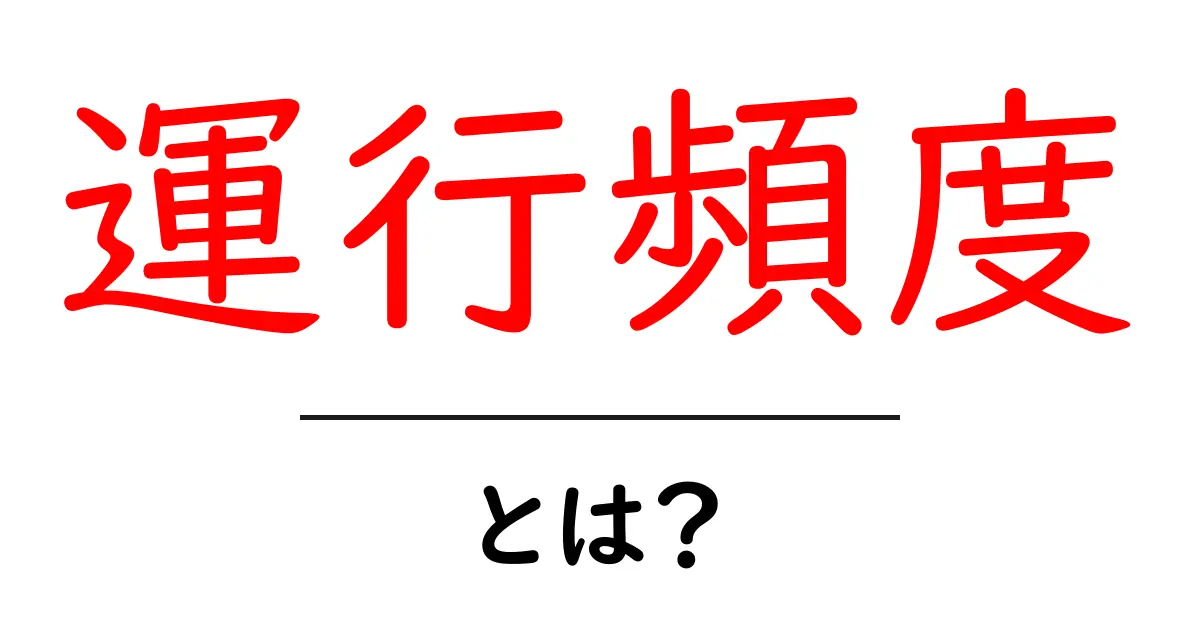 交通機関の運行を知るための基本知識共起語・同意語も併せて解説!">
交通機関の運行を知るための基本知識共起語・同意語も併せて解説!">ダイヤ:ダイヤとは、交通機関が運行する際の時刻表のことを指します。運行頻度を考える上で、ダイヤの整備は非常に重要です。
運行時間:運行時間は、交通機関が運行を開始する時間や終了する時間を指します。運行頻度を分析する際に、どの時間帯に多く運行されているかがわかります。
乗客数:乗客数は、ある交通機関を利用する人の数を示します。運行頻度が高いと、乗客数も増える傾向があります。
路線:路線とは、交通機関が運行する具体的なコースや経路を指します。運行頻度は、特定の路線ごとにも大きな違いがあります。
運行間隔:運行間隔は、次の運行がどれくらいの間隔で行われるかを示します。例えば、10分ごとに運行される場合、運行頻度が高いと言えます。
週末:週末は、金曜日から日曜日までの期間を指し、多くの交通機関では運行頻度が変わることがあります。特に観光地へのアクセスが増えるため、運行頻度を考慮する重要な要素です。
需要:需要は、乗客が交通機関を利用したいという欲求を指します。運行頻度は需要に基づいて調整されることが多く、需要が高い時間帯や路線では頻繁に運行される傾向があります。
運行会社:運行会社は、交通機関を運営・管理する企業や団体のことを指します。各運行会社によって運行頻度やサービスが異なるため、どの会社の運行が良いかを比較することが重要です。
運行間隔:運行のあいだにどれくらいの時間があるかを示す言葉です。例えば、バスや電車が何分ごとに来るのかを表します。
運行スケジュール:運行の予定を示すもので、何時にどの車両が出発するかなどの情報が含まれています。
運行予定:物の運行を計画する際の予定を指し、どれくらいの頻度で運行が行われるかを示します。
運行頻度:特定の時間内に運行される回数を示す言葉で、乗り物やサービスがどれくらいの頻度で利用できるかを知るために重要です。
発車間隔:特定の地点から出発する際の時間的な間隔、つまり乗り物がどのくらいのタイミングで出発するかを表します。
サービス頻度:特定のサービスがどれだけの回数提供されるかを示し、例えば観光地のシャトルバスの運行頻度などを指します。
運行:特定のルートやスケジュールに従って交通機関が移動すること。例えば、バスや電車が決まった時間に運行されることを指します。
頻度:ある事象が発生する回数や度合い。運行頻度の場合、どのくらいの間隔で運行が行われるかを示します。
スケジュール:運行の時間や順序を定めた計画。交通機関では、発車時刻や到着時刻が含まれます。
路線:運行される交通機関の特定の道筋。バスや電車は、それぞれの路線に沿って運行されます。
ダイヤ:運行スケジュールのこと。電車やバスの運行時刻を示した表として掲載されます。
交通機関:人や物を目的地まで運ぶための手段。バス、電車、飛行機などが含まれます。
定時運行:運行が予告通りの時刻に行われること。利用者にとって信頼性の高い運行形態です。
遅延:運行の時間が予定よりも遅れること。天候や交通渋滞などが原因となることが多いです。
利用者:交通機関を実際に利用する人々のこと。運行頻度は利用者の利便性に大きく影響します。
需要:交通機関を利用する人々がどの程度多いかということ。運行頻度はこの需要に基づいて決定されることがあります。
運行頻度の対義語・反対語
該当なし





















