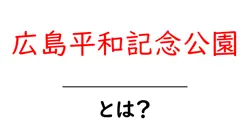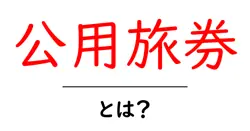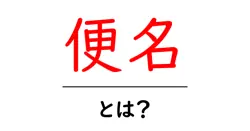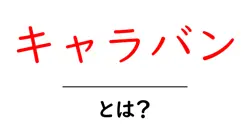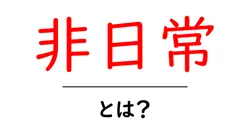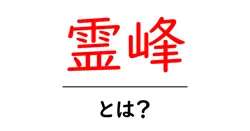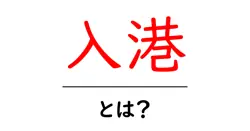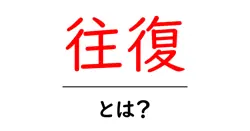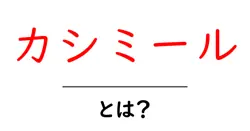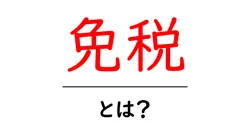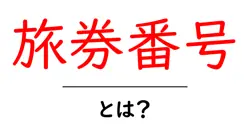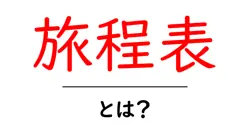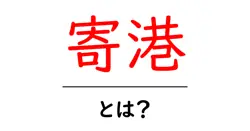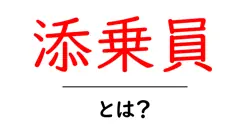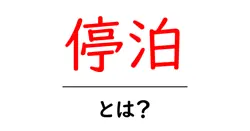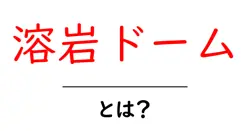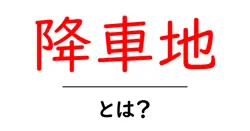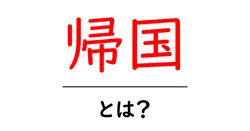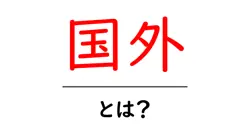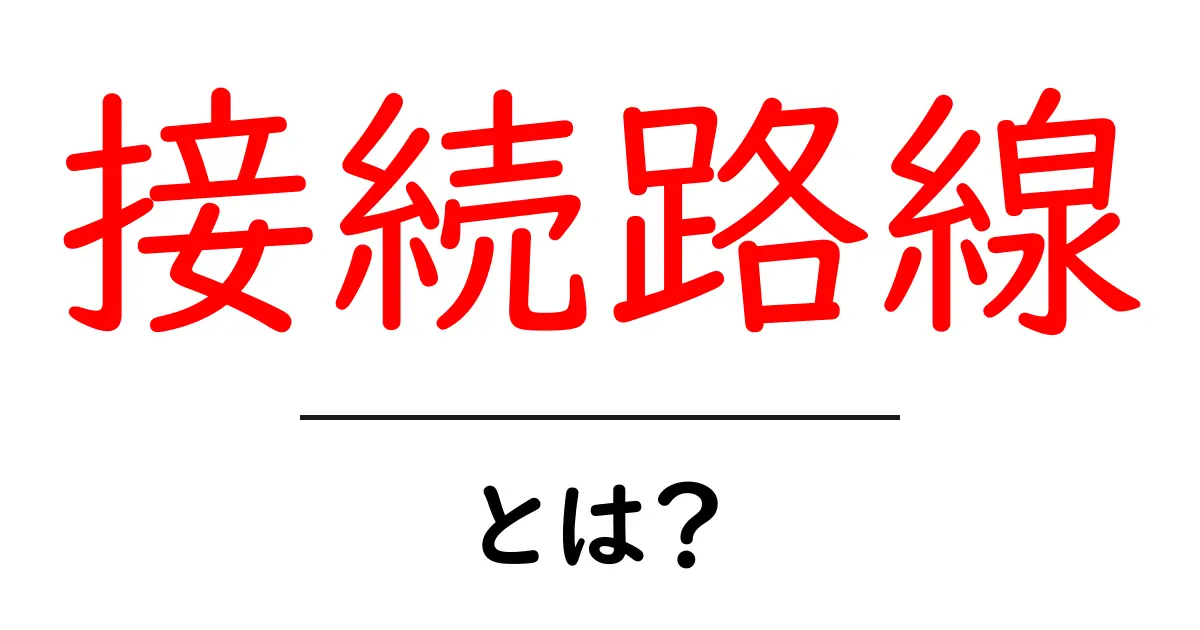
接続路線とは?
「接続路線」とは、主に交通機関において使用される言葉で、異なる路線が交わる場所や、乗り換えができる路線のことを指します。たとえば、鉄道やバスの路線が別々の場所から出発して、ある駅やバス停で合流し、一緒に利用できるようになる場合がこれに当たります。
接続路線の重要性
接続路線は、私たちの移動をスムーズにしてくれる大切な役割を果たしています。例えば、ある駅で特急列車から各駅停車に乗り換えることで、目的地に早く着くことが可能になります。また、接続路線が充実している地域では、多くの場所に簡単にアクセスできるため、住みやすい環境となります。
接続路線の例
| 路線名 | 接続地点 | 目的地 |
|---|---|---|
| 山手線 | 新宿駅 | 渋谷 |
| 東京メトロ丸ノ内線 | 新宿三丁目駅 | 池袋 |
| 東急田園都市線 | 渋谷駅 | 中目黒 |
接続路線を使うメリット
接続路線を利用することで、以下のようなメリットがあります:
- 移動時間の短縮
- 対面する駅での乗り換えにより、余分な移動時間を削減できます。
- 旅行の柔軟性
- 異なる路線を組み合わせることで、多様な旅行ルートを選ぶことができます。
- コストパフォーマンスの向上
- 早く目的地に着くことで、時間を無駄にせず、旅費の効果的な使い方が可能です。
このように「接続路線」は、私たちの移動を助け、便利な生活を実現するための重要な要素です。駅やバス停での接続を意識して、効率よく移動していきましょう!
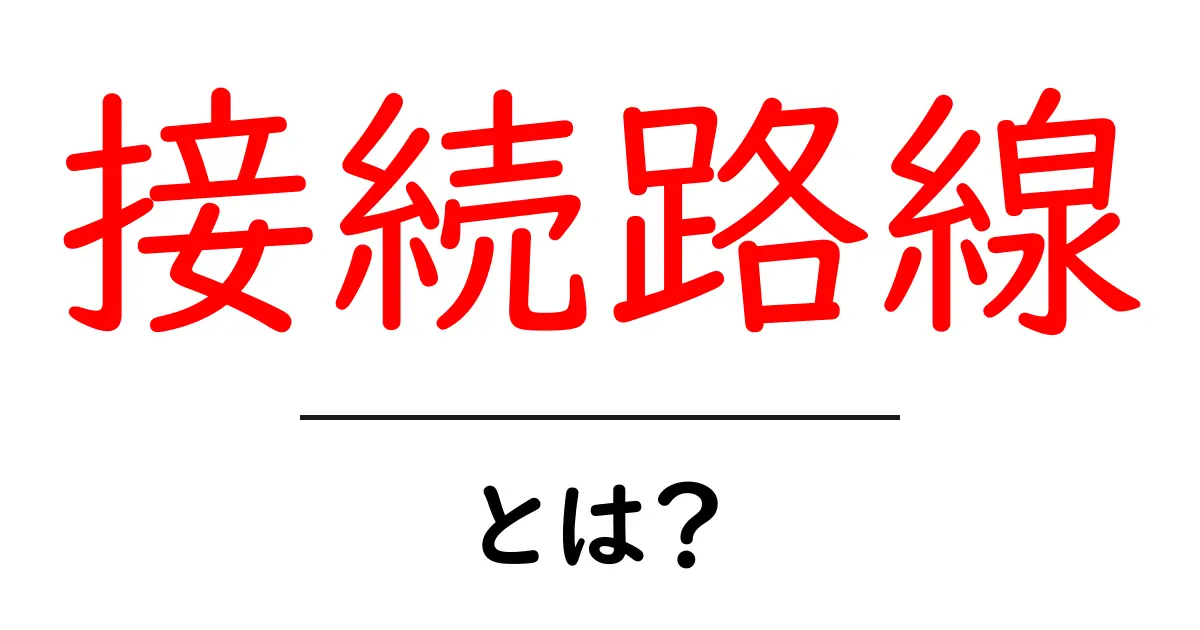
鉄道路線:鉄道が通る道のこと。接続路線は他の路線と結びつくことが多い。
乗換駅:異なる路線へ乗り換えることができる駅のこと。接続路線が交わる地点。
交通網:複数の交通手段や路線が連携している全体のシステムのこと。接続路線は交通の利便性を向上させる。
通勤:仕事や学校に行くための移動のこと。接続路線があれば通勤がスムーズになる。
アクセス:ある場所に到達するための道筋や手段のこと。接続路線は目的地へのアクセスを改善する。
公共交通機関:バスや電車など、多くの人が利用できる交通手段のこと。接続路線が公共交通の利便性を高める。
終点:路線の最後の駅やバス停のこと。接続路線は他の路線の終点と関連する場合がある。
運行ダイヤ:運行する時間やスケジュールのこと。接続路線のダイヤが調整されることで便利に移動できる。
トランジット:乗り換えや経由のこと。接続路線を使う際の重要な要素。
ダイヤ改正:運行スケジュールの変更のこと。接続路線に影響を及ぼすことがある。
接続線:異なる路線をつなぐ線路のこと。接続路線とも同様の意味で使われ、特に鉄道などで利用される。
連絡路線:異なる交通機関や路線を結ぶための路線。旅行者がスムーズに移動できるように設計されている。
交差路線:二つ以上の路線が交差する地点での接続を指す。乗り換えが必要な場所でよく使われる。
連結路線:異なる路線どうしを連結している区間。旅客や貨物の輸送において、スムーズな移動を可能にする。
接続交通:一つの交通機関から別の交通機関への移動をサポートするシステム全般を指す。接続路線が重要な役割を果たす。
接続路線:異なる鉄道路線や交通機関が接続し、乗り継ぎできる場所や区間のこと。例えば、ある駅でJRと私鉄が接続している場合、乗客はそれらの線を利用して目的地に向かうことができる。
乗り換え:1つの交通手段から別の交通手段に乗り換えること。接続路線を利用することで、乗客は目的地までの最適なルートを見つけやすくなる。
路線図:鉄道やバスなどの交通機関の運行路線を示した地図のこと。接続路線を視覚的に把握するのに役立つ。
ダイヤ:交通機関の運行時刻表。各接続路線の運行間隔や接続時刻などが記載されており、乗客が効率よく移動するために必要な情報となる。
ハブ:交通の要所を指し、複数の接続路線が集まり、乗り換えが便利な場所を示す。大都市の主要駅などがその代表例。
アクセス:ある地点への到達手段や経路を意味し、接続路線が良好であれば、目的地へのアクセスが便利だと言える。
直通運転:異なる路線間で、途中駅を経由せずに直通で運行される列車のこと。接続路線を使わずに目的地まで行けるため、移動時間が短縮される。
トランジット:交通機関での乗り換えや、異なる交通手段を介して移動することを指す。接続路線が整備されていると、トランジットがスムーズになる。
接続路線の対義語・反対語
該当なし