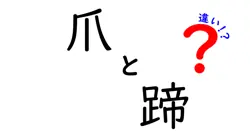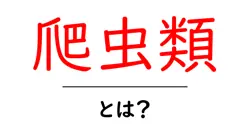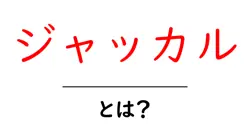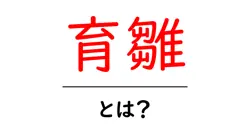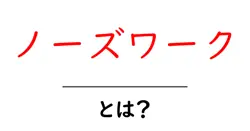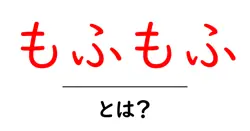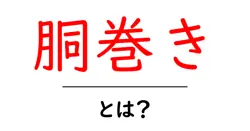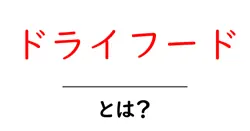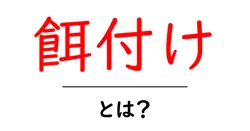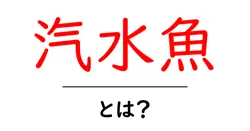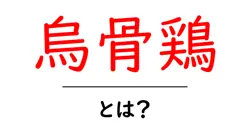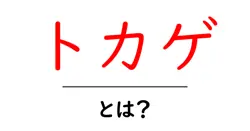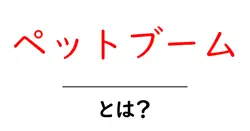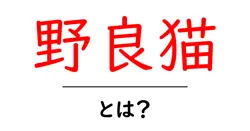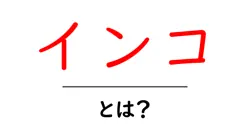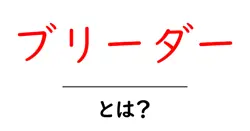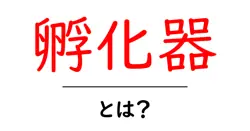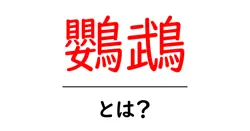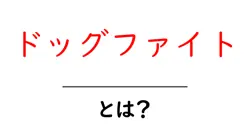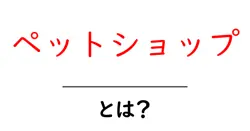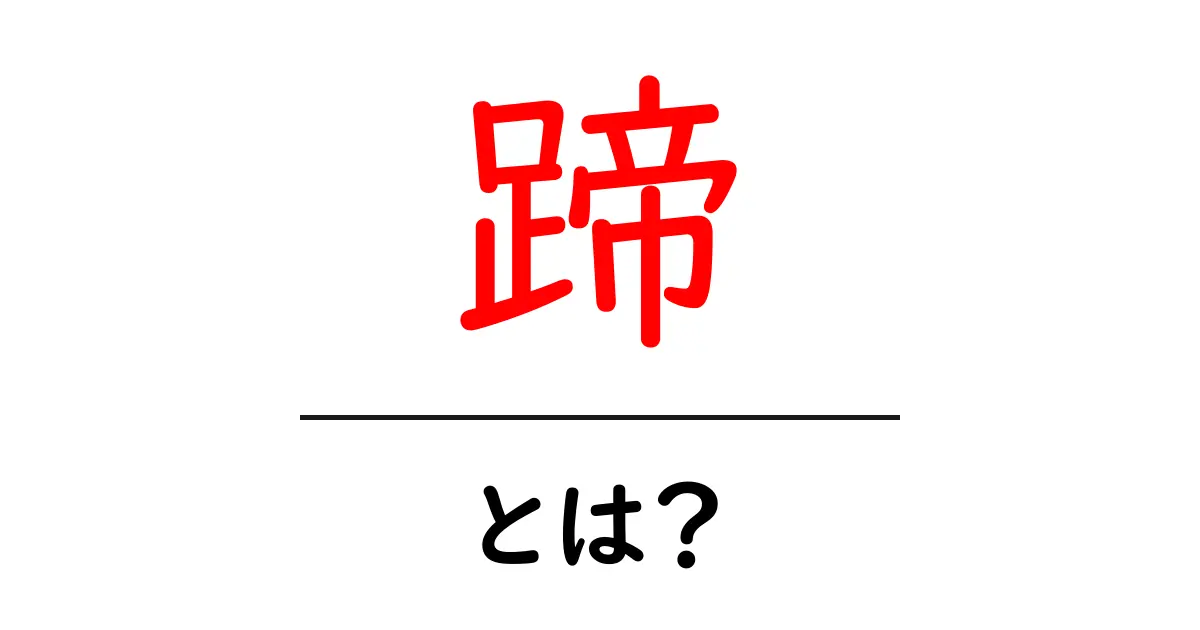
蹄とは?
蹄(ひづめ)は、主に馬や牛、羊などの動物の足の先にある硬い部分です。この部分は、動物が歩いたり走ったりする際に非常に重要な役割を果たします。蹄は、皮膚や骨、角質によって構成されており、動物によって形や大きさが異なります。
蹄の構造
蹄は、数つの部分に分かれています。
| 部分名 | 説明 |
|---|---|
| 蹄冠(ひづめかん) | 蹄の上部で、蹄の成長を支える部分です。 |
| 蹄壁(ひづべかべ) | 蹄の外側を覆う硬い部分で、石や地面から足を保護します。 |
| 蹄底(ひづめぞこ) | 地面に接する部分で、クッションの役割を持っています。 |
蹄の役割
蹄は動物が地面をしっかりと捉えるために必要です。地面からの衝撃を吸収し、体重を支えることで、動物が安定した状態で移動できるようにします。また、蹄の健康は動物の元気さや運動能力にも影響を与えます。蹄が傷んだり、感染症にかかったりすると、動物は歩くのが大変になってしまいます。
蹄のお手入れ
特に家畜の動物にとって、蹄のお手入れはとても大切です。飼い主や獣医師によって定期的にケアをすることで、蹄の健康を保つことができます。これには、蹄を切ったり、磨いたりする作業が含まれます。
正しいお手入れをすることで、動物が元気に走り回ることができ、生活の質も向上します。ここで特に重要なのは、日常的に観察し、何か異常があれば早めに対処することです。
まとめ
蹄は動物にとって非常に重要な部分であり、適切なお手入れによってその健康を保つことができます。動物たちが元気に暮らせるためにも、蹄についての理解を深めることが大切です。
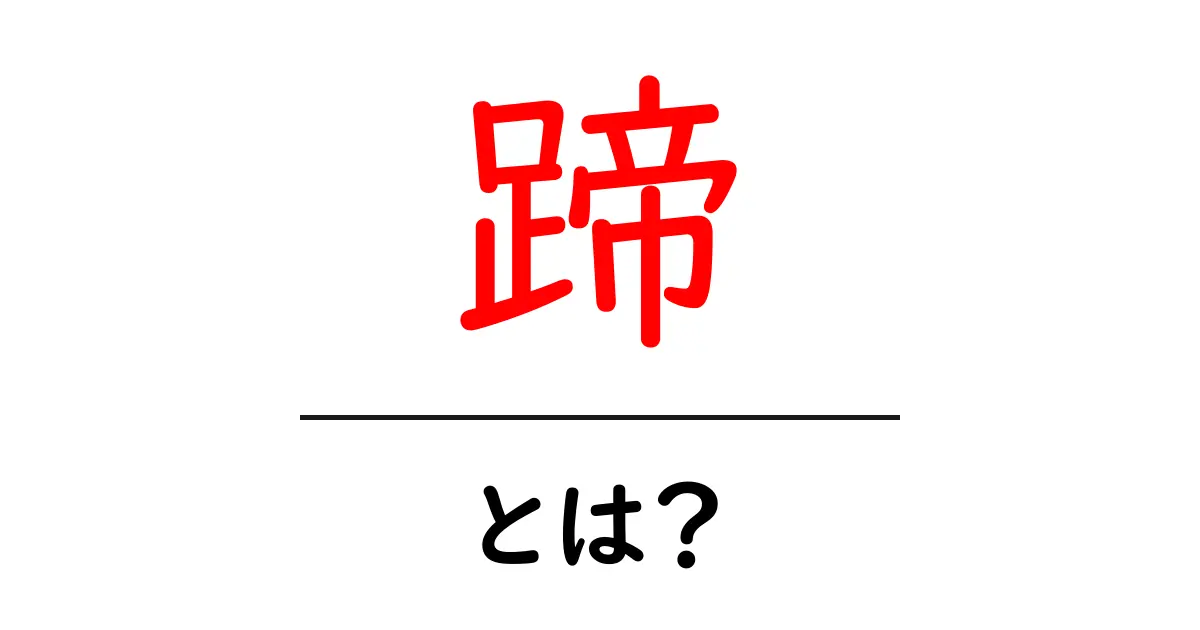
ひづめ とは:「ひづめ」とは、主に馬や牛といった動物の足の先端にある硬い部分のことを指します。ひづめは、動物が歩いたり走ったりするために非常に重要な役割を果たしています。特に、大きな体を支えるために、頑丈でしっかりとした作りになっています。ひづめは、動物が地面をしっかりと踏みしめることを助け、滑りにくく、また疲れにくい構造になっています。ひづめの内部には、血管や神経も通っていて、これらの部分が健康を保つために必要です。まさに動物の「足元の宝」と言えるでしょう。ひづめの健康を保つためには、適切な手入れが必要です。たとえば、ひづめが割れたり、病気になったりしないように、定期的なチェックや清掃が欠かせません。また、栄養バランスの良い食事もひづめの健康に影響を与えます。ひづめについて知ることで、動物のケアに対する理解が深まるかもしれません。
ヒヅメ とは:「ヒヅメ」とは、主にウマやシカなどの動物の足の先にある硬い部分のことを指します。この部分は、動物が歩いたり走ったりするためにとても重要です。ヒヅメは、一般的にケラチンというたんぱく質からできていて、爪や髪の毛と同じ成分です。ヒヅメがしっかりしていると、地面にしっかりと接地して安定感を保ちながら、様々な地形をやすやすと移動することができます。また、ヒヅメは動物にとって「バランスを取る器具」としての役割も果たしています。例えば、山を登ったり、泥の中を歩いたりする際も、ヒヅメがしっかりとした構造を持っていると、滑りにくくなります。特に厳しい環境に生息する動物にとっては、このヒヅメが生存に大きな影響を及ぼすのです。扱いやすさや地面との摩擦を考えたヒヅメの進化は、動物たちがより多くの環境に適応するための重要な要素であると言えます。
樋爪 とは:樋爪(ひづめ)とは、主に建物の雨水を受けるために設置される屋根の部分や、水道などの配管に関する用語です。樋は雨水を集めて地面に流す役割があり、爪はその固定部分を指します。樋爪は屋根の端に取り付けられ、雨水が屋根から直接流れ出ないようにするための大切なパーツです。これがないと、雨水が壁や基礎に直接当たってしまい、建物が傷む原因になります。さらに、樋爪は屋根の形やデザインに合わせて作られ、見た目にも大きな影響を与えることがあります。最近では、樋爪を取り入れたもっとおしゃれなデザインのものも登場しています。水や雨に対する注意は大切で、樋爪を適切に設置することことで、長持ちする建物を実現できるのです。これから家を建てる人や、リフォームを考えている人には、樋爪の重要性を理解してもらいたいですね。
樋詰 とは:樋詰(ひづまり)は、雨水を流すための樋が詰まってしまうことを指します。特に、大雨の時期になると、樋に落ち葉やゴミがたまりやすくなります。この状態が続くと、雨水がうまく流れず、家の屋根や外壁に水が溜まってしまうことがあります。これが原因で、雨漏りやカビの発生、さらには建物の劣化を引き起こすこともあるため、非常に危険です。樋詰を防ぐためには、定期的に樋を掃除し、詰まりがないか確認することが大切です。また、適切な樋の設置も重要なので、メンテナンスを怠らないようにしましょう。樋詰を防ぐことで、家を長持ちさせることができるのです。特に日本では梅雨の時期に雨が多くなるため、樋詰に注意して、快適な生活を維持するよう心がけましょう。
馬 ひづめ とは:馬のひづめ(蹄)は、馬の足にある特別な部分です。ひづめは、馬が地面をしっかりとつかむために大切な役割を果たしています。ひづめは硬い角質でできていて、馬の歩き方や走り方にも深く関わっています。ひづめがないと、馬は簡単に怪我をしたり、病気になったりしてしまうことがあります。そのため、飼い主はひづめの手入れを定期的に行うことが重要です。また、ひづめの健康状態によっては、馬の運動能力や元気にも影響が出ることがあります。ひづめが健康な状態を保つことで、馬が長く元気に走り回ることができるのです。馬のひづめには、さまざまな種類や形があり、それぞれの馬に合った手入れ方が必要です。馬を飼う上で、「ひづめ」を理解することはとても大切なことなのです。
動物:蹄を持つ動物は一般的に四足歩行のもので、馬や牛、羊などがこのカテゴリーに含まれます。
蹄鉄:蹄を保護するために装着される金属製の靴のことです。特に馬に施されることが多いです。
草食性:蹄を持つ動物の多くは草食性で、主に草や葉を食べて生活します。
サフォーク:イギリス原産の羊の一種で、特徴的な大きな蹄を持っています。
角:角を持つ動物(例えば牛など)は、しばしば蹄と共に紹介されることがあります。
爪:蹄は爪と同様に、動物の足部の一部であり、他のいくつかの動物と比較されることがあります。
やぎ:やぎも蹄を持つ動物で、特に厳しい環境で生き抜くための優れた脚力を持っています。
トゲ:一部の動物は自衛のためにトゲを持っていますが、蹄とは異なりますが、しばしば比較的に考慮されます。
獣医:蹄の健康を守るために獣医さんが定期的にチェックを行うことが一般的です。
農業:蹄を持つ動物は農業において重要な役割を果たし、農作業や乳製品の生産に利用されます。
足:動物の足部全体を指し、特に走ったり歩いたりするための構造を含みますが、蹄は特定の動物に特有の、硬い外側の部分を指します。
爪:爪は一般的に動物の指先の硬化した部分で、蹄もその一種と考えられます。蹄は特に馬や牛などの大型動物の爪のような構造です。
蹄鉄:蹄の保護や機能を向上させるために取り付ける金属製の器具です。特に馬に使用されます。
蹄底:蹄の底部を指し、地面と接する部分です。蹄底は動物の歩行や走行の安定性に重要な役割を果たします。
肉球:犬や猫のような肉食動物の足の底の柔らかい部分を指します。蹄とは異なりますが、動物の足に関連しています。
蹄鉄:蹄鉄(ていせつ)は、馬やその他の動物の蹄を保護するために装着される金属製の器具です。地面との摩擦を減らしたり、怪我を防いだりする役割があります。
蹄音:蹄音(ていおん)は、馬やウシなどの動物が歩いたり走ったりする際に、蹄が地面に当たることで発生する音のことです。これにより、動物の健康状態や行動を判断したり、周囲の環境音を把握する手助けとなります。
蹄叶:蹄叶(ていよう)は、蹄の一部の構造を指します。特に馬の蹄では、蹄葉が外的な衝撃を吸収し、地面からの力を均等に分散させる重要な役割を果たします。
蹄の手入れ:蹄の手入れは、馬や家畜の健康を保つために行う作業で、蹄の洗浄や削り、蹄鉄の装着などが含まれます。適切な手入れが行われることで、動物の移動能力や健康が向上します。
蹄病:蹄病(ていびょう)は、動物の蹄に発生する様々な病気や障害を指します。感染症や炎症、外傷などが含まれ、放置すると動物の歩行に支障をきたすことがあります。
蹄の構造:蹄の構造は、ケラチンというタンパク質から成る外層、内部の軟部組織、神経や血管を含む中心部分から構成されています。この構造は、動物の歩行や負荷に対する耐性を高めるために非常に重要です。
蹄の成長:蹄は固定的な部分ではなく、時間とともに成長し続けます。動物の健康状態や飼育環境によって成長速度が異なるため、定期的な手入れが必要です。
蹄の種類:蹄には代表的な種類があり、馬のような単蹄(たんてい)やウシのような偶蹄(ぐうてい)などがあります。それぞれ異なる生態や環境に適応した形を持っており、動物の行動や生活様式に影響を与えています。
蹄の対義語・反対語
該当なし