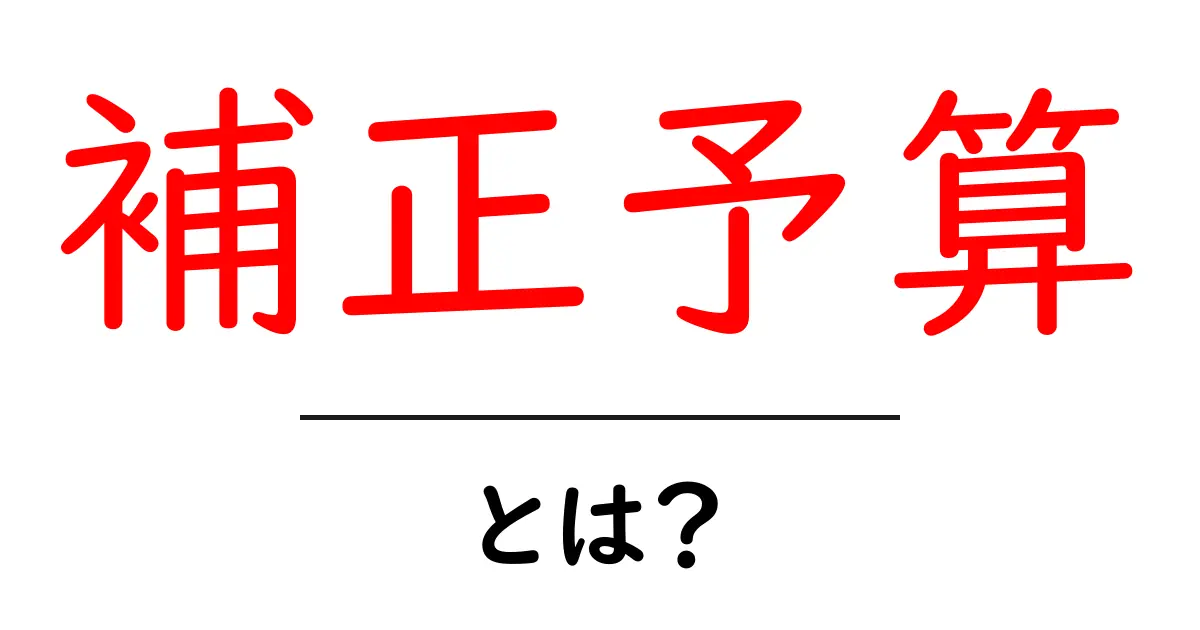
補正予算とは何か?
補正予算(ほせいよさん)とは、国や地方公共団体が、その年度の予算を変更するための予算のことを言います。通常、予算は年度の初めに作成されますが、様々な事情でその予算を見直さなければならない場合があります。そんなときに補正予算が必要になります。
なぜ補正予算が必要になるのか?
補正予算が必要になる理由はいくつかあります。例えば、天災や事故、経済の変動などがある場合、その影響を受けて予算を見直す必要があります。また、新たに必要な事業が発生したり、予想以上の税収があった場合にも、補正予算が活用されます。
補正予算の種類
補正予算には、大きく分けて2つの種類があります。一つは「第一次補正予算」で、年度の途中で一度目の見直しを行うものです。そしてもう一つが「第二次補正予算」で、さらに二度目の見直しを行うものです。これにより、より適切な使い道にお金を振り分けることができます。
補正予算の具体例
具体的な補正予算の例として、2011年の東日本大震災の際には、復興のために大規模な補正予算が組まれました。このように、非常時に迅速に対応するために補正予算は非常に重要です。
補正予算の流れ
補正予算がどのように決まるかを見てみましょう。まず、必要性が認識されると、行政機関が予算案を作成します。この案は、議会に提出され、議会での審議を経て、最終的に承認される必要があります。ここでの議論は、とても重要です。
補正予算の影響
補正予算が通ると、どのように国民生活に影響があるのか、疑問に思う人も多いでしょう。例えば、災害復興に必要な道路や学校の建設にお金が使われることになります。このように、補正予算によって、私たちの生活に直接影響を与えることが多いです。
まとめ
補正予算は、国や自治体が予想外の事態に柔軟に対応するために必要不可欠なものです。国民の生活を守るためにも、しっかりとした審議と透明性のある予算運営が求められます。
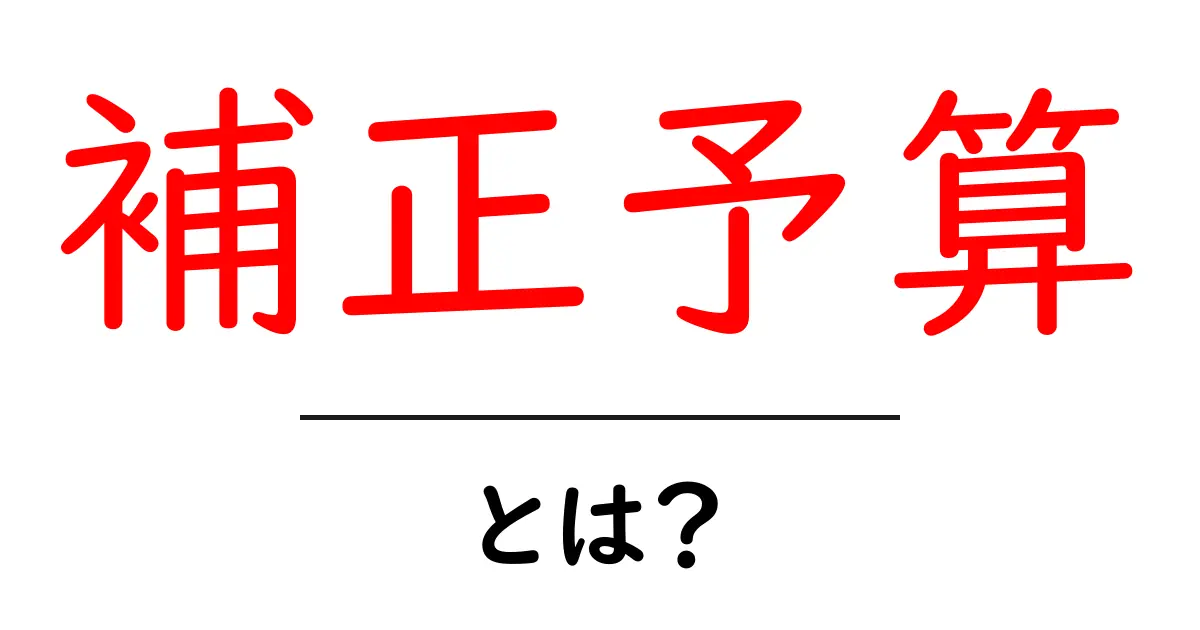
一般会計 補正予算 とは:一般会計補正予算とは、国や地方自治体が年度の途中で収入や支出の見込みを見直し、必要な変更を行うための予算のことです。通常、予算は年度の初めに決められますが、予想外の出来事や変化があった場合に、そのままでは希望通りのサービスを提供できなくなることがあります。たとえば、自然災害や経済の変動があったときに、新しいお金が必要になることがあります。こうした時に補正予算が役立ちます。補正予算では、追加の支出や収入の増加を反映させ、必要な資金を振り分け直すことで、公共サービスの維持や社会の安定を図ります。これにより、国や自治体は、より良いサービスを住民に提供することができるようになります。理解を深めるためには、過去の具体的な事例や、どのようなチューニングが行われるのかに注目することも重要です。
国 補正予算 とは:国の補正予算とは、年度の途中で新たに必要だと判断された経費を追加で計上する予算のことです。通常、政府は毎年4月に予算を立てますが、予想外の事態が起きたときには補正予算が必要になります。例えば、大きな自然災害があったり、経済が急に悪化したりすると、追加の資金が必要になることがあるんです。このような場合、政府は補正予算を作成し、国会に提出します。この予算が承認されると、必要な費用が確保され、様々な対策が実施されるのです。補正予算は、国民の生活や経済を守るために重要な役割を果たしています。特に、経済が不安定なときには、迅速に対応するためにも欠かせない制度です。補正予算があることで、国は臨機応変に対応し、必要な支援を行うことができます。こうした国の取り組みが、私たちの生活や地域の発展にどれだけ影響を及ぼしているのかを理解することが大切です。
補正予算 とは わかりやすい:補正予算とは、国や地方公共団体が予算を追加したり修正したりすることを指します。普段は新年度の予算を立てますが、予期しない支出や収入の変化によって、当初の予算だけでは足りなくなることがあります。たとえば、自然災害が発生した場合、救助活動や復旧作業に必要な費用を追加するために補正予算が必要になることがあります。 また、経済が悪化したときには、景気を刺激するための支出を増やす目的でも補正予算が使われます。補正予算は、政府や自治体が柔軟に対応できるようにするための重要な仕組みなのです。これによって、急に必要とされる支出を確保することができ、市民生活や経済活動に影響を与えないように努めているのです。 補正予算は通常、議会で承認される必要があります。ですから、衆議院や地方議会で話し合われてから決まります。議論の過程で、さまざまな意見が出てきて、最終的にどういう用途にお金を使うかが決まります。これは、透明性を持たせるために大切なステップです。
補正予算 とは 企業:補正予算とは、既に決定された予算を見直し、変更するための予算のことを指します。企業が補正予算を組む理由はさまざまですが、主に予想外の出費や収入の変動に対応するためです。たとえば、売上が急に増えた場合、そのお金をどのように使うかを再考する必要がでてきます。また、想定以上に経費がかかったり、プロジェクトが遅れたりした場合にも補正予算が必要です。この修正を行うことで、企業は資源を有効に活用し、健全な経営を維持することができます。企業が補正予算を行うと、経営陣はより柔軟に対応できるようになり、計画の見直しをすることで新たなチャンスを作り出すことができるのです。このように、補正予算は企業の経営戦略において非常に重要な役割を果たしています。
予算:特定の期間や事業に対して、どれだけの金額を使うかを計画したもの。
財源:予算を実施するための資金の出所や方法のこと。
政府:国家の政治を行う組織。補正予算は政府が必要に応じて編成することが多い。
支出:予算に基づいて、実際にお金を使うこと。
歳入:政府や団体が得る収入、特に税金などの収入を指す。
経済対策:経済を活性化させるために行う施策。補正予算は経済対策の一環として用いられることが多い。
予算案:今後の計画的な支出を示す文書。補正予算はその予算案の見直し版といえる。
議会:法律や予算を審議し、決定するための組織。補正予算の承認は議会の役割。
施策:国や自治体が実施する具体的な政策や計画のこと。補正予算が施策を支える重要な要素となる。
景気:国や地域の経済の状態。景気を反映して補正予算が編成されることがある。
追加予算:既存の予算に対して、追加で計上される予算のこと。予想外の支出や新たな事業のために用いられます。
補充予算:必要に応じて、新たに予算を補填することを指します。特定のプロジェクトや施策が当初の予算では賄えない場合に用います。
再配分予算:すでに割り当てられた予算を見直し、必要な分を別の項目に再配分する際の予算を指します。
臨時予算:急な需要や状況変化に応じて一時的に設ける予算のこと。通常の予算とは別に、特別な事情に基づいて設計されます。
修正予算:既存の予算を見直して変更することを意味します。予算計画の実績に基づいて調整されることが多いです。
当初予算:ある年度の始めに政府や企業が計画する予算のこと。補正予算はこの当初予算に追加や変更を加えるものです。
財政出動:政府が公共投資や補助金支出を通じて経済を活性化させるために行動すること。補正予算はこのような財政出動を促す役割を持つことがあります。
景気対策:経済の悪化を防ぐために政府が行う施策のこと。補正予算は、特定の景気対策を実施するための資金を確保するために編成されることがあります。
赤字国債:政府の歳入が歳出を下回る場合に、その不足分を補うために発行される国債。補正予算によって赤字国債の発行が決まることもあります。
歳入:政府や企業が得る収入のこと。補正予算では歳入の見積もりが見直されることがあります。
歳出:政府や企業の支出のこと。補正予算では特定の事業や施策の歳出が増減することが反映されます。
執行:予算で決定された支出を実行すること。補正予算が承認された後、その執行が行われます。
審議:予算案についての詳細を議論し、判断を下す過程。補正予算も国会などで審議を経て承認される必要があります。
予算編成:来年度の予算を立てるプロセス。補正予算は、通常の予算編成とは別に行われますが、その影響を受けることがあります。
補正予算の対義語・反対語
該当なし





















