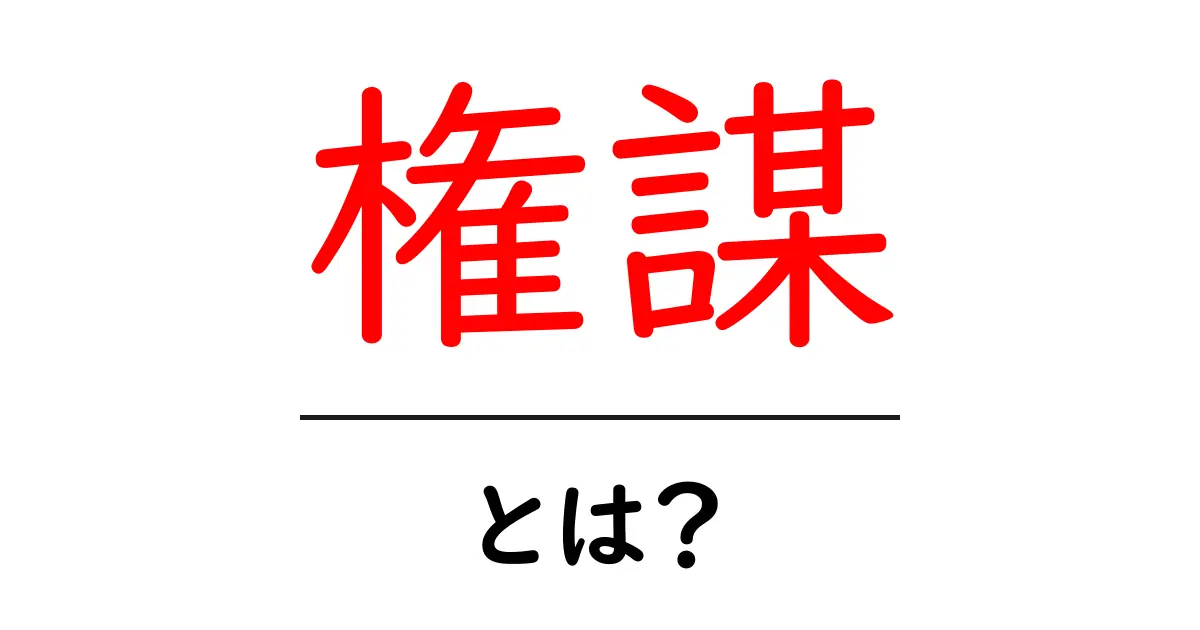
権謀とは?その意味と歴史をわかりやすく解説
権謀(けんぼう)という言葉は、特に歴史や文学の中でよく使われる言葉です。権謀とは、「権力や利益を得るための計略や策謀」を指します。つまり、ある目的のために使われる策略や計画のことです。
権謀の由来と歴史
この言葉の起源は古い中国の思想にまで遡ります。特に、戦国時代の政治や戦争において、このような計略が数多く用いられました。権謀術数と言われるように、相手を出し抜くための巧妙な策略が多く存在しました。日本の歴史においても、織田信長や豊臣秀吉など多くの武将がこの権謀を使って成功を収めました。
権謀と現代
現代でも、ビジネスや人間関係において権謀が重要な役割を果たすことがあります。特に競争が激しいビジネスの世界では、自社の利益を最大化するために戦略的に行動する必要があります。この点では、権謀が特に重要になります。
権謀の例
| 状況 | 権謀の内容 |
|---|---|
| ビジネスの競争 | 新商品を他社より早く発売することで市場シェアを奪う |
| 友達関係 | 友達を怒らせた相手に優しくすることで自分への信用を高める |
もちろん、権謀は時には悪用されることもあります。利益や権力を追い求めるあまり、他人を騙したり、信頼関係を壊したりしてしまうことがあります。したがって、権謀を使う際には、倫理や道徳を考慮することが重要です。
まとめ
権謀という言葉は、目的を達成するための策略を意味します。この考え方は古代から現代にかけて、さまざまな場面で使われてきました。正しい使い方を心がけ、他人を尊重しながら自分の目標を追求することが大切です。
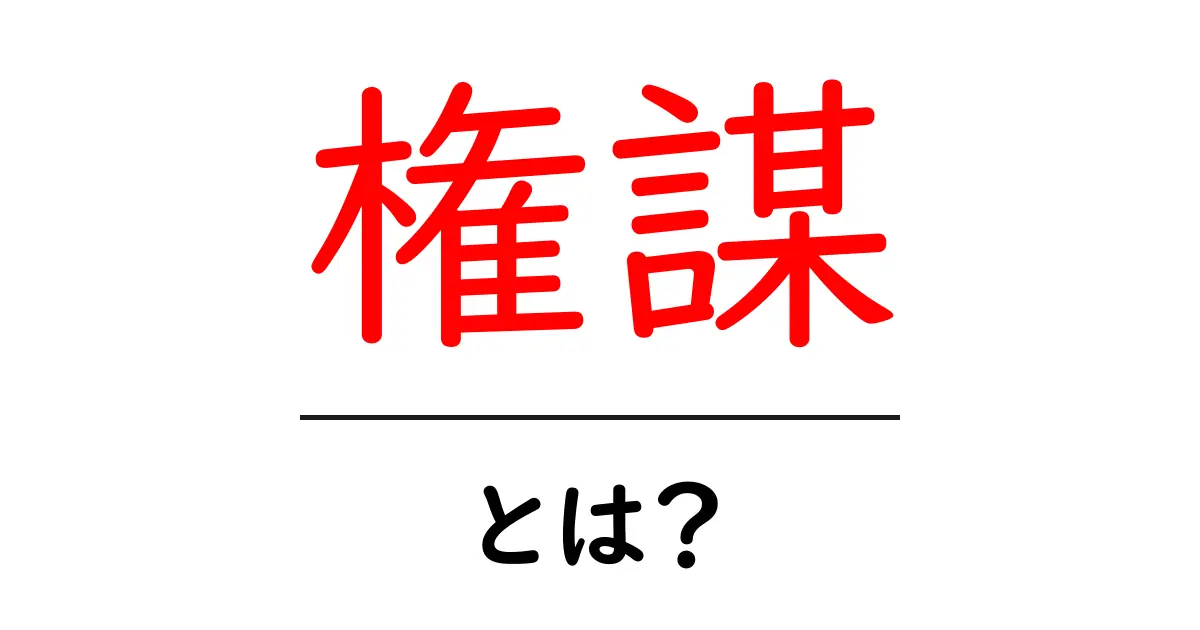
策略:目的を達成するための計画や行動のこと。権謀はしばしば策略を伴って行われます。
陰謀:秘密裡に進められる計画や行動で、しばしば権力を手に入れるために他者を欺くことを含みます。
権力:他者を支配または影響を与える能力のこと。権謀は権力を得るための手段として利用されることが多いです。
駆け引き:相手との関係や状況に応じて有利に進めるために使う巧妙なやり取り。権謀の一部として重要です。
巧妙:技術が優れていることや、狡猾であること。権謀には巧妙な戦略が求められます。
策略家:計画や策略を用いて行動する人。権謀に関与する人はしばしば策略家と見なされます。
裏切り:信じていた相手に対して裏切る行為。権謀では、裏切りが成功と失敗を分けることがあります。
策略:特定の目的を達成するために用いる計画や手段。
陰謀:表向きには明らかでない計画や企み、特に他者を陥れたりするためのもの。
巧妙な手段:非常に賢く考えられた方法や技術。
計略:特定の目的を遂げるために用いる計画や戦略、主に軍事やビジネスにおいて使われることが多い。
陰策:影で行われる策略や計画、特に他人を操るためにこっそりと仕掛けられること。
智謀:知恵や機知を用いた計略や策略、特に困難な状況を乗り越えるための知的な工夫。
狡猾さ:非常に賢く、時には不正直な方法を使って目的を達成しようとすること。
策略:ある目的を達成するために考え出した計画や手段。特に状況に応じて柔軟に変更されるものを指す。
陰謀:表立っては分からないように進められる秘密の計画や行動。通常は不正な目的が含まれることが多い。
権力:他者に対して影響を与えたり、支配したりする能力や地位。権謀はしばしば権力の獲得や維持に関連する。
政治:社会の中で権力を持つ者と持たざる者の関係をマネジメントする行動や思想。権謀は政治において特に重要な要素となる。
操り:他人を思い通りに動かしたり、コントロールしたりすること。権謀家はしばしば他人を操る技術に長けている。
駆け引き:相手の出方を見ながら、自分の利得を最大化するために行う戦略的なやり取り。これも権謀の一環である。
欺瞞:人を騙すための嘘や偽りの行動。権謀の一部には、相手を欺くことも含まれる。
駆動:権謀や策略によって、特定の行動や決定を引き起こすこと。これが権力の維持に貢献する。
結束:目的を達成するために、同じ立場の者が集まって協力すること。権謀では、こういった結束が重要な要素になる。
権謀の対義語・反対語
該当なし





















