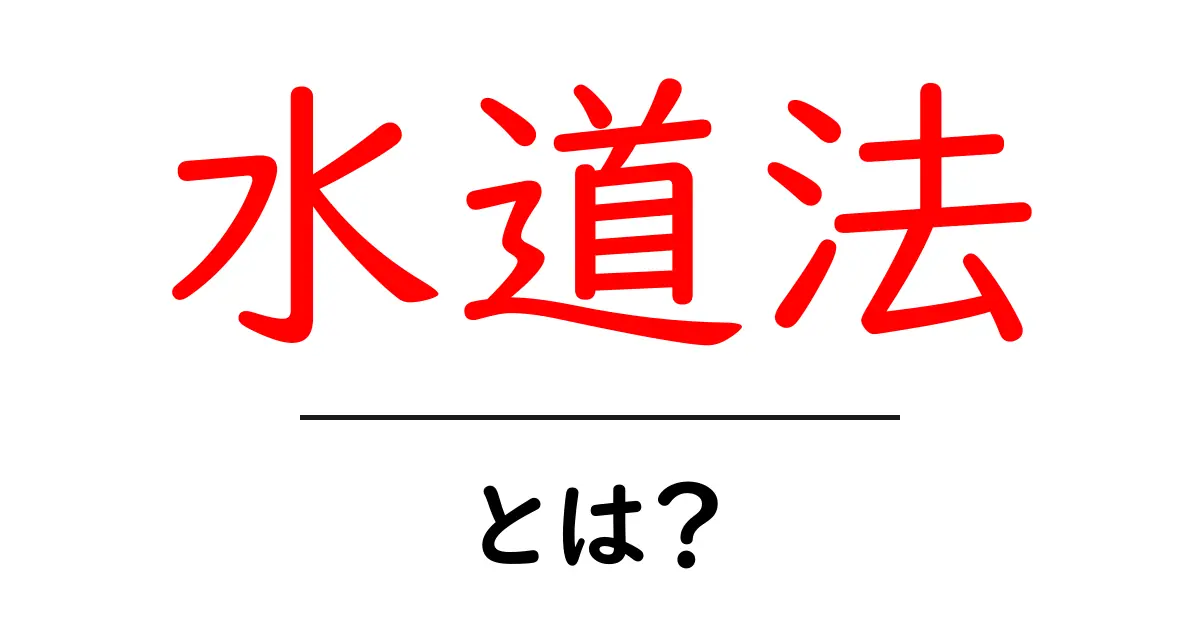
水道法とは?
水道法(すいどうほう)とは、日本における水道の管理や運営について定めた法律のことです。この法律は、私たちが日々使用する飲料水や生活用水を安全に、そして安定的に供給するために作られました。
水道法の目的
水道法の主な目的は以下の3つです。
- 1. 安全な水の供給
- 2. 水資源の管理
- 3. 生活環境の保全
これらの目的を達成するためには、国や地方自治体が適切に水道を運営し、必要な水質基準を守ることが必要です。
水道法の基本的な内容
1. 水道の設置と管理
水道法では、地方自治体が水道事業を運営しなければならないと定めています。また、水道の設置や設備の管理についても具体的な基準が設けられています。
2. 水質の基準
水道法では、水質基準を設けており、これをクリアする水が供給されることが求められています。具体的には、飲料水に対する細菌や化学物質の検査が定期的に行われます。
3. 水道料金
水道法では、水道料金の設定についても規定しています。利用者が公平に料金を支払うことができるように、料金体系が整備されています。
水道法が必要な理由
私たちの生活に欠かせない水ですが、自然災害や環境の変化などによって水源が減少したり、水質が悪化したりすることがあります。このような時、法律があることで、私たち一人ひとりが安全な水を利用できるようにするための措置が講じられます。
まとめ
水道法は、私たちの生活を支える重要な法律です。これからも安全で質の良い水を供給するために、この法律の重要性を理解し、適切に利用していきましょう。
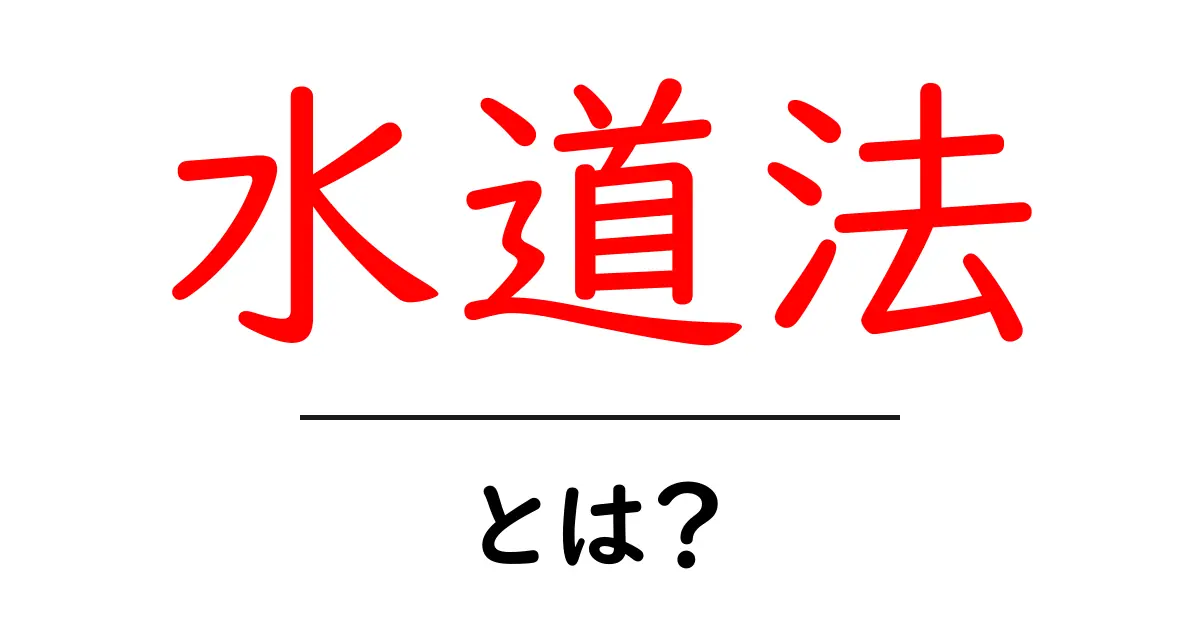
水道施設:水道法の下で設置・管理される水道に関連する施設のこと、配水管や浄水場などが含まれます。
給水:水道法に基づいて、住民や施設に水を供給することを指します。
浄水:水道水を安全に使えるようにするために、水を清潔に保つための処理プロセスです。
配水:浄水された水を家庭や企業に届けるための水道網を通じて行われる流通のことです。
水質基準:水道法で定められた飲用水の安全性を確保するための水質の基準です。
水道事業者:地域の水道サービスを提供する企業や自治体のこと。水道法に基づき、給水や水質管理に責任があります。
水道料金:水道サービスの利用料金で、使用量に応じて支払われます。水道法に基づき、公正に設定されています。
検査:水道法に基づき、水質や設備の安全性を定期的に確認するためのプロセスです。
水道管:水を供給するための管で、地中や建物内を通じて設置されます。
災害対策:水道法に基づいて、災害時にも安全に水を供給できるように計画される対策のことです。
水道条例:各自治体が水道に関する具体的な取り決めを定める法律。地域ごとの水道の管理や利用に関するルールが含まれています。
水道規則:水道法や水道条例の具体的な運用を定めるための細かいルール。水道の使用や料金、品質管理について明確に規定されています。
上下水道法:上下水道の管理や整備について規定した法律。水道法はこれに関連し、上下水道の事業運営をスムーズにするための基本的な指針を提供します。
水道制度:水道に関する一連の法律や規則、方針などの総称。水供給の仕組みや管理体制を指すことが多いです。
給水法:水道からの給水に関する法律、特に給水契約や水質基準について定めた法律。この法律によって、安全で衛生的な水の供給が確保されます。
水道設備:水道法に基づいて設置される、給水や排水のための機器や施設のこと。これには水道管、ポンプ、浄水器などが含まれます。
給水:水道法の指針に従って、水を供給すること。家庭や事業所に安全で清潔な水を届ける役割を担っています。
排水:家庭や事業所から水を流し出すこと。水道法では、排水が適切に行われ、環境に悪影響を及ぼさないように定められています。
浄水:水道法で求められる、飲用水として適した水にするための過程。水の浄化処理を通じて、微生物や有害物質を取り除きます。
水質基準:水道法に基づいて設定される、水の安全性を判断するための基準。飲用水はこの基準に適合しなければなりません。
地方自治体:水道法に基づく水道事業の運営を行う、地域を基盤とした行政機関。住民に水道サービスを提供します。
水道事業:水道の供給や管理を行う事業全般を指します。これは公共事業として、多くの場合、地方自治体が実施しています。
水道料金:水道の利用に対して徴収される料金。水の使用量に基づいて計算され、公共の水道事業の運営資金となります。
災害対策:水道法においては、地震や洪水などの災害時における水道の機能維持や復旧に関する計画や措置が定義されています。
水道法の対義語・反対語
該当なし





















