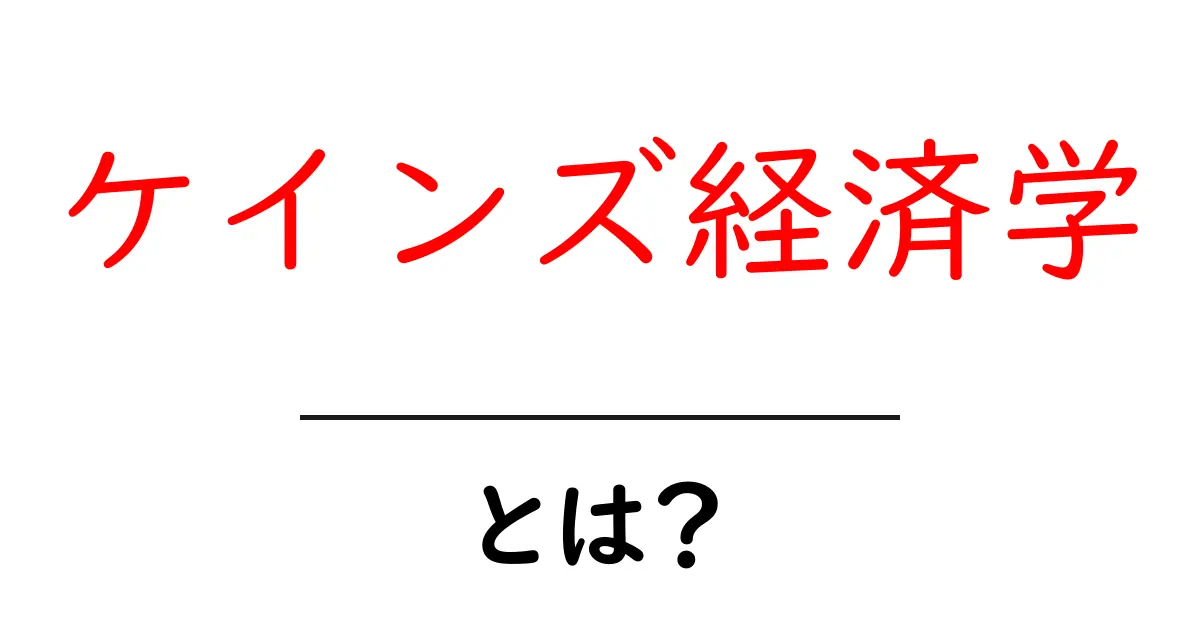
ケインズ経済学とは何か?
ケインズ経済学は、20世紀の初頭にイギリスの経済学者ジョン・メイナード・ケインズが提唱した経済理論です。この理論は、主に経済の景気循環や失業問題に対する対応策を考えます。
ケインズの考え方の基本
ケインズは、経済が自動的に安定するわけではないと考えました。つまり、需要が不足すると経済が停滞し、失業が増える可能性があるということです。彼は、特に「需要の重要性」を強調しました。
需要の重要性
需要とは、人々が商品やサービスを購入したいと思う量のことです。需要が高ければ、企業は商品をもっと作り、雇用を増やし、経済が活性化します。しかし、需要が低いと経済は衰退し、失業が増えるのです。
ケインズ経済学の政策提言
ケインズは、経済が不況に陥ったときには政府が積極的に介入すべきだと考えました。具体的には、政府が公共事業を行ったり、税金を減らしたりすることで、需要を刺激し、経済を活性化することを提案しました。
政府の役割
ケインズの理論では、政府が経済に介入することが、経済の安定に役立つとされています。例えば、失業が増えると、政府が雇用を生むためのプロジェクトを行い、働く場を提供することが重要です。
ケインズ経済学の影響
ケインズ経済学は、特に1930年代の大恐慌の際に多くの国で採用されました。経済学の考え方が変わり、政府の役割が重視されるようになったのです。これ以降、経済政策はケインズの理論に基づくものが多くなりました。
表: ケインズと古典派経済学の違い
| ポイント | ケインズ経済学 | 古典派経済学 |
|---|---|---|
| 政府の介入 | 必要とする | 不要とする |
| 需要の役割 | 重視 | 無視 |
| 景気循環の扱い | 重要視 | 自動的に回復 |
この表からもわかるように、ケインズ経済学は企業と政府の関係性を見直すものであり、経済の安定に対する考え方が大きく異なります。
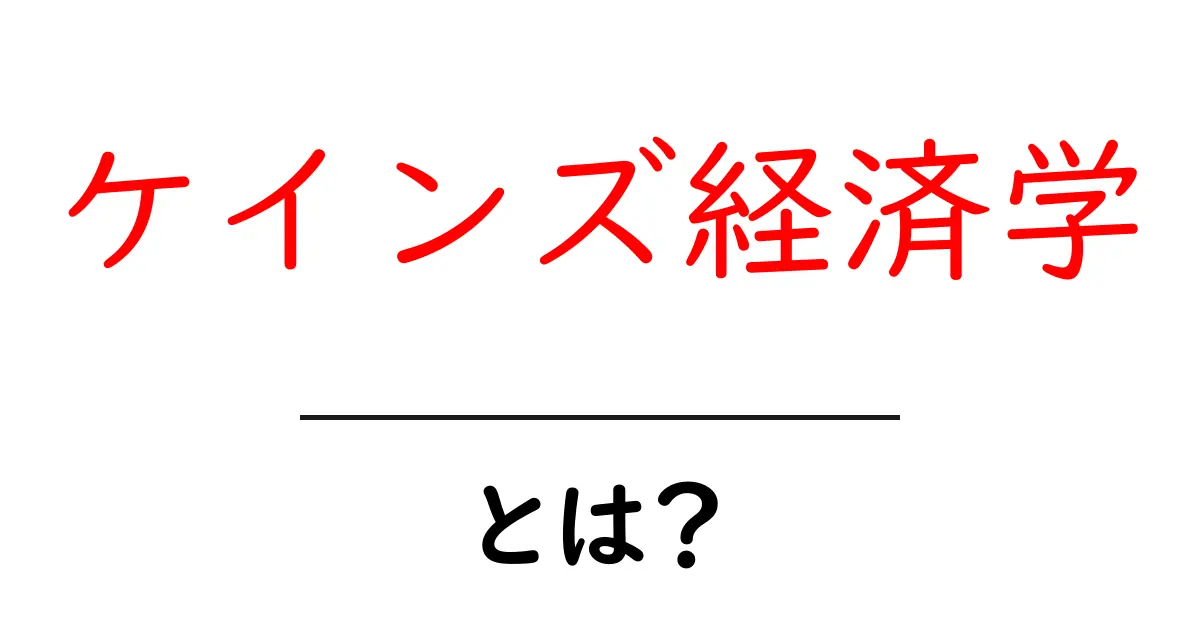
マクロ経済学:経済全体の動きを分析する学問で、総生産や失業率、物価などを取り扱います。ケインズ経済学はマクロ経済学の一分野です。
需給:商品やサービスの需要(買いたい人の数)と供給(売りたい人の数)を指します。需給のバランスが市場の価格を決定します。
総需要:特定の期間において、国内で消費される財やサービスの総量を指します。ケインズは総需要が経済の重要な動因であると考えました。
政府支出:政府が公共事業や社会サービスの提供に使うお金です。ケインズ経済学では、政府支出が経済を刺激する重要な手段とされています。
乗数効果:政府支出や投資の増加が、経済全体の需要を増加させる効果を指します。少ない投資でも、大きな需要の変化を引き起こすことができます。
失業:働きたいのに仕事が見つからない状態を指します。ケインズは、特に景気後退時の失業の解決策を提唱しました。
消費者信頼感:消費者が経済の将来に対して抱く期待や信頼度を測る指標です。信頼感が高いと消費が増え、経済成長に繋がります。
インフレーション:物価が継続的に上昇する現象を指します。ケインズ経済学では適度なインフレが経済成長に必要だとされています。
投資:資本を使って将来の利益を得るために行う行動です。ケインズ経済学では、投資は総需要の重要な要素とされています。
需要喚起政策:政府が経済活動を活発にするために、需要を増やすための政策を指します。ケインズの理論に基づき、特に景気が悪いときに効果を発揮します。
マクロ経済学:経済全体の動きを研究する学問で、ケインズ経済学はその重要な理論の一つです。マクロ経済学は、全体の産業、消費、雇用、物価などを分析します。
財政政策:政府の支出や税制を通じて経済に影響を与える手段です。ケインズ経済学では、景気回復のために政府による支出が重要とされています。
総需要管理:全体の需要を調節することを目指す経済政策の一つで、ケインズ経済学の考え方に基づいています。
循環論:経済の動きを示す考え方で、需要と供給の関係を強調します。ケインズ経済学は、需要が不況時の経済活動を刺激すると考えています。
有効需要:実際に市場で消費される需要のことです。ケインズ経済学では、有効需要が経済成長や雇用に直結するとされています。
労働市場の流動性:労働者が新しい仕事を見つけることが容易である状態を指します。ケインズ経済学では、労働市場の流動性が景気回復に寄与することが強調されています。
需要:人々が商品やサービスを購入したいと思う量のこと。ケインズ経済学では需要が経済の動きを左右するとされている。
供給:市場に出回る商品やサービスの量のこと。供給が需要を上回ると、価格が下がる傾向がある。
マクロ経済学:全体の経済を扱う学問。個別の事業体ではなく、国全体の経済成長や失業率などを研究する。
総需要:国内で一定期間に消費、投資、政府支出、輸出から構成されるすべての需要の合計。
雇用:人々が労働市場で労働力を提供し、対価を得る関係のこと。ケインズは雇用の維持が経済安定に必要だとした。
失業:働きたいのに仕事がない状態。経済が不安定な時に増えることが多い。
政府支出:政府が公共サービスやインフラに費やすお金。ケインズは、経済が低迷している時に政府支出を増やすことで需要を刺激できると提唱した。
財政政策:政府の支出や税金の調整を通じて経済に影響を与える政策。ケインズ経済学は、特に景気を安定させるための財政政策を重視している。
貨幣供給:市場に流通するお金の量のこと。貨幣供給が増えると、経済が活性化する可能性がある。
ケインズ経済学の対義語・反対語
該当なし





















