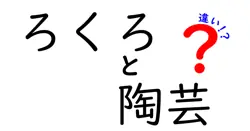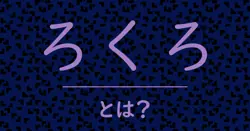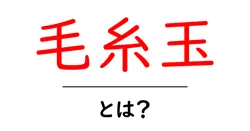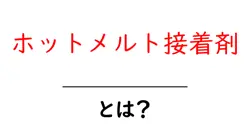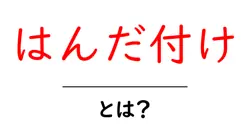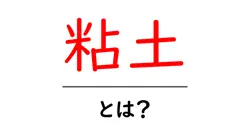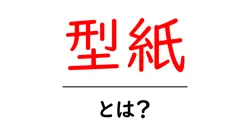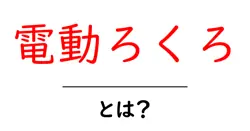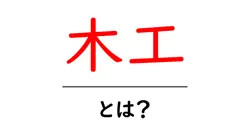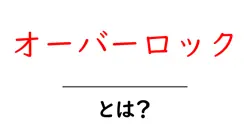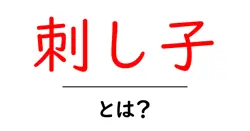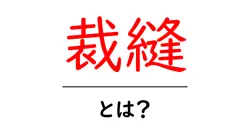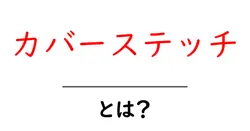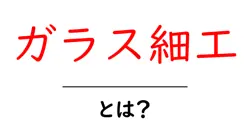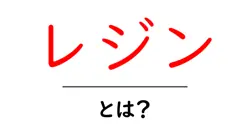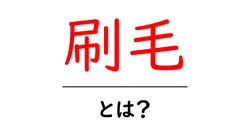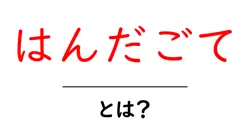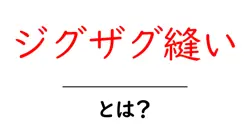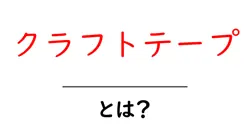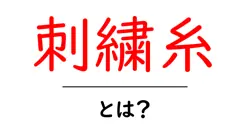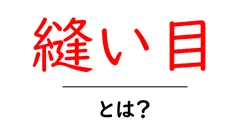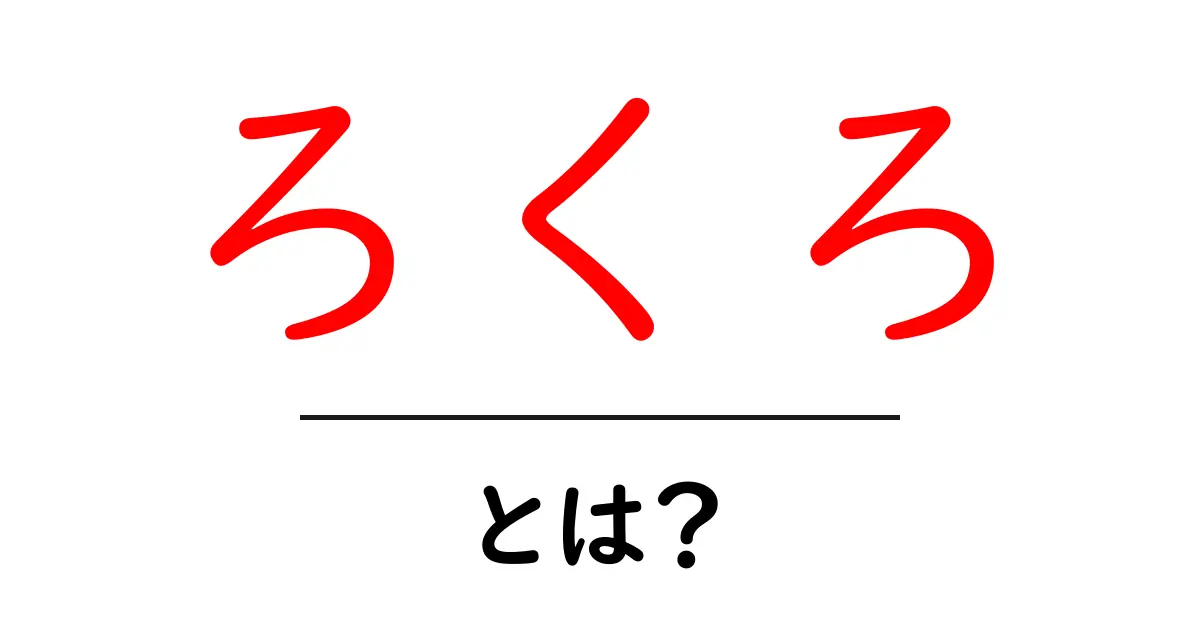
ろくろとは?
ろくろは、陶芸の作品を作る際に使う道具の一つで、主に粘土を成形するために使われます。ろくろを使うことで、円形の作品を簡単に作ることができ、陶器や焼き物の制作に欠かせないものです。
ろくろの種類
ろくろにはいくつかの種類があります。大きく分けると、手動のろくろと電動のろくろがあります。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 手動ろくろ | 古くから使われている方法で、手で回します。陶芸の基本を学ぶのに適しています。 |
| 電動ろくろ | 電動モーターで回転し、楽に成形ができます。初心者でも扱いやすいです。 |
ろくろの使い方
それでは、ろくろの使い方を説明します。
- 準備:まず、ろくろを設置し、粘土を用意します。
- 粘土の形成:粘土をろくろの中央に置き、手で均等に広げていきます。この作業を「センタリング」と呼びます。
- 成形:センタリングが終わったら、手のひらで粘土を押し上げたり引っ張ったりして、形を作ります。
- 削り・仕上げ:形ができたら、刃物やスポンジで滑らかに整えます。
- 乾燥・焼成:作った作品を乾燥させ、窯で焼成します。
陶芸の楽しさ
ろくろを使った陶芸は、ただ作品を作るだけでなく、心の安らぎを与える時間でもあります。自分の手で作る魅力を感じることで、日常のストレスから解放されることができます。陶芸教室も増えているので、興味がある方はぜひ参加してみてください。
まとめ
ろくろは、陶芸の世界では欠かせない道具です。手動でも電動でも、それぞれの魅力があります。ぜひ、自分でも挑戦してみてはどうでしょうか。
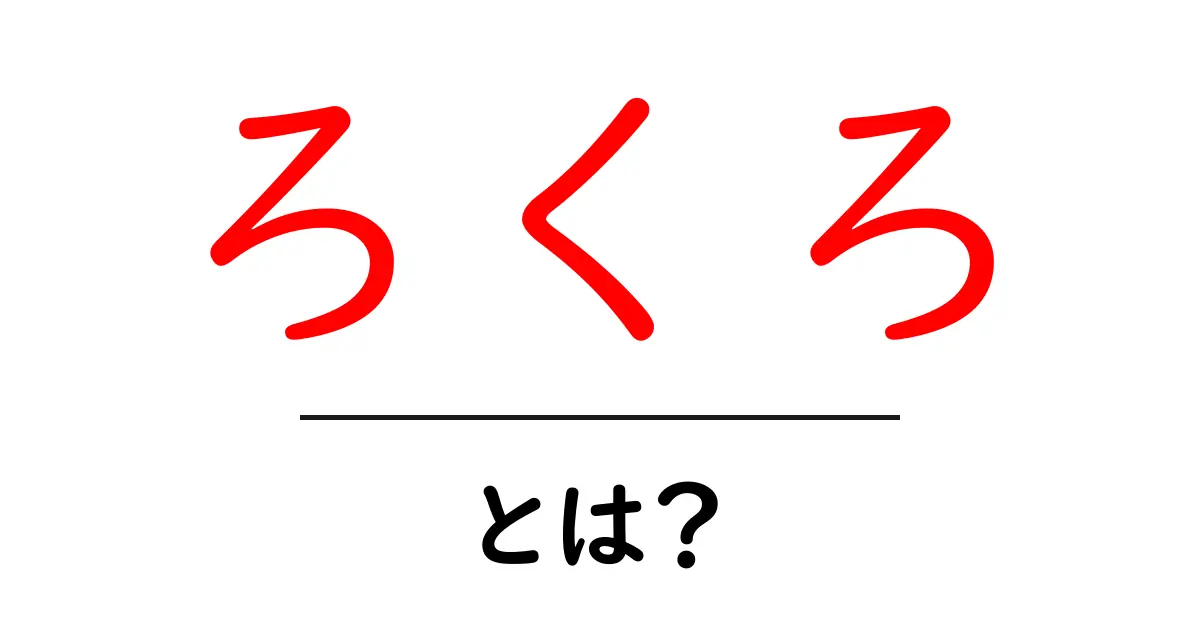
ロクロ とは:ロクロ(轆轤)とは、陶芸や陶器の制作に使う道具の一つです。主に回転する円盤の上に粘土を置き、手で形を整えながら、様々な形の器や器具を作ることができます。ロクロの仕組みは簡単で、中心に置いた粘土が回転することで、均一な形を作りやすくなるのです。最近では、陶芸教室やワークショップなどでロクロを使う体験ができますし、自分だけのオリジナルの作品を作る楽しさを味わうことができます。ロクロの使い方を覚えるには、知識だけでなく、手の感覚や経験も大切です。初心者でも少しずつコツをつかんでいくことで、自分なりのスタイルや技術を見つけることができるでしょう。陶芸に興味がある人は、ぜひロクロを使った作品作りに挑戦してみてください。楽しい体験ができること間違いなしです!
六ろ とは:「六ろ」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?これは、特に「6」という数字やその意味、あるいはそれにまつわる文化に関連することを指しています。たとえば、この「六ろ」は、数字の「6」に対する愛称や愛着から生まれた言葉の一つです。「6」という数字は、古代から様々な文化で特別な意味を持っていました。例えば、中国の文化では「6」は良い運を意味し、「六六大順」という言葉があるように、物事がうまく行くことを示します。また、数学では「6」は初の完全数とも言われ、自分自身以外の約数(1、2、3)を足すと自分に戻ってくることが特長です。このように、数字には単なる計算以上の深い意味があり、私たちの生活に多くの影響を与えています。「六ろ」という言葉を通じて、数字の世界に触れることができると楽しみながら学ぶことができます。友達と一緒に「6」について語ってみるのも面白いですね。数字の魔法を感じてみましょう!
轆轤 とは:「轆轤(ろくろ)」は、陶芸でよく使われる道具の一つです。この道具を使うことで、粘土を回転させながら成形し、器やオブジェを作ることができます。轆轤の基本的な構造は、中央に粘土を置き、周りの部分が回転することで、粘土を均一に形作ることができる仕組みになっています。陶芸の初心者でも、この轆轤を使うことで、簡単に自分だけのオリジナル作品を作ることができるんです。 轆轤には手動と電動の2種類があります。手動は自分の手を使ってペダルを踏み、回転させます。一方、電動轆轤はスイッチを入れるだけで回転が始まるので、初めての人でも使いやすいです。轆轤を使いこなすには、多少の練習が必要ですが、作品が形になっていく様子を見ると、とても楽しい気持ちになります。また、轆轤で作った器は、日常生活で使うことができるので、自分の作品を実際に使える喜びもあります。 陶芸の魅力は、手のひらで感じることができる粘土の質感や、完成した時の達成感にあります。轆轤を使った陶芸は、ほかの芸術とは違った楽しさを与えてくれる道具だと言えるでしょう。陶芸に挑戦するなら、ぜひこの轆轤の世界に入ってみてください!
陶芸 ろくろ とは:陶芸(とうげい)は、土を使ってさまざまな形を作り、その形を焼いて硬くする技術です。この中でも特に「ろくろ」と呼ばれる道具を使った陶芸が人気です。ろくろは、土を円盤のように回転させながら手で形を整えることができるので、非常にスピーディーかつ正確に作品を作ることができます。ろくろを使う陶芸は、特に食器や花瓶、芸術作品を作るのに適しています。まず、 clay(粘土)をろくろの中心に置き、回転させながら手の平や指で形を調整します。初心者でもこつさえつかめば、簡単にオリジナルの作品を作ることができるんですよ。また、完成した陶芸品は、焼成(ようせい)という工程を経て、強度を増し、磁器や陶器として使うことができるようになります。陶芸は、ものづくりの楽しさや土の温もりを感じることができる素晴らしい趣味です。ぜひ、ろくろを使った陶芸に挑戦して、自分だけの作品を作ってみてください!
陶芸:ろくろは陶芸の一部であり、土を円形に成形するための道具です。陶芸は、粘土を使って器や芸術作品を作る技術を指します。
輪:ろくろは主に円形の輪を作るための装置であり、土を回転させながら形を整えます。ここでの「輪」とは、ろくろ上の回転する部分を指します。
土:ろくろで使う基本的な素材は土です。陶芸用の土は、焼き上がりの色や質感を考えて選ばれます。
成形:ろくろの主な作業の一つが成形です。土をろくろにのせて回転させることで、さまざまな形の器を作り出します。
釉薬:ろくろで作った陶芸作品には、釉薬を使って表面に色や光沢を出します。この釉薬は焼成時にガラス質になり、作品の耐久性を高めます。
焼成:ろくろで作った作品は、窯で焼成されることで陶器になります。焼成は、土が硬化し、形が定まる重要な工程です。
手捻り:ろくろを使った技法の一つとして手捻りがあり、手で直接土を捻る技法と対比されることがあります。ろくろは機械的な操作が特徴です。
工具:ろくろ作業には様々な工具が使われます。たとえば、スポンジやカッターなどがあり、これらは形を整えたり、仕上げをしたりするのに役立ちます。
作品:ろくろを使って作成される最終的なものは作品です。陶器の皿や杯、装飾品などがあります。
伝統:ろくろを使った陶芸は、多くの文化において伝統的な技法として受け継がれてきました。各地の特色が反映された作品が見られます。
陶芸:粘土を使って器や彫刻を作る技術のこと。ろくろは陶芸の一部として、形を整える過程で使用される。
ろくろ挽き:ろくろを使って陶器や磁器を作る技術のこと。丸い形を生成するために粘土を回転させながら整える作業。
旋盤:工業的な機械で、回転する素材を切削して形を作る装置。ろくろと似た動作をするが、主に金属や木材で使用される。
陶器:高温で焼き固めた粘土製品のこと。ろくろを使って形成されたものも多く、日用品から美術品まで存在する。
成形:材料を特定の形に整える過程を指します。ろくろを使って粘土を成形することが一般的です。
陶芸:ろくろは、陶芸の道具の一つで、粘土を回転させながら成形するために使われます。陶芸自体は、粘土を使って器や彫刻を作る技術やアートを指します。
柳宗理:著名な陶芸家であり、ろくろを使った独自のスタイルで知られています。彼の作品はシンプルで機能的なデザインが特徴です。
陶器:ろくろで作られた器や土瓶などの焼き物を指します。陶器は、通常、粘土を成形し、その後に焼成することで完成します。
成形:ろくろを使って粘土を回転させ、求める形に整える作業のことです。成形の技術は、陶芸作品の品質に大きく影響します。
焼成:成形した陶器を高温の窯で焼くプロセスです。焼成により陶器は硬くなり、耐久性が増します。
釉薬:焼き上げた陶器の表面に塗布するコーティングの一種です。釉薬を使うことで、陶器に色や光沢を与え、さらに防水性を持たせることができます。
土練り:粘土をまとめてなめらかにする作業のことです。よい土練りがなされることで、ろくろでの成形がスムーズになります。
手びねり:ろくろを使用せず、手作業で粘土を成形する技法です。個性的な形を作りやすく、アート性の高い作品が生まれます。
器:陶芸作品として作られる受け皿や皿、カップなどを総称する言葉です。ろくろを使った器は、美しさと実用性を兼ね備えています。
ろくろの対義語・反対語
該当なし