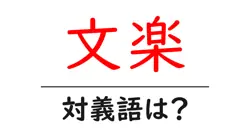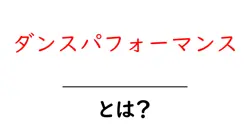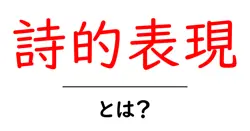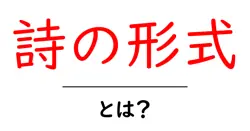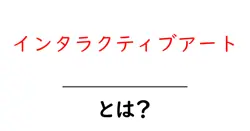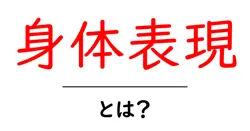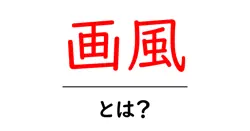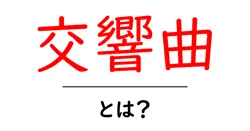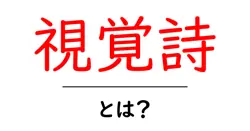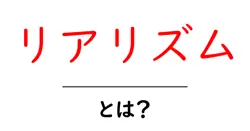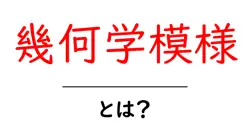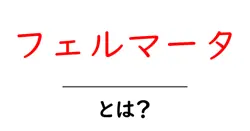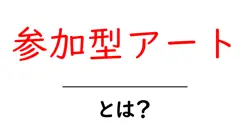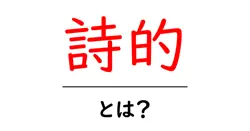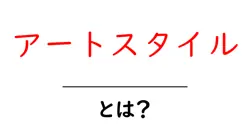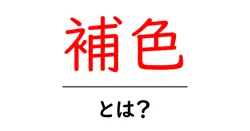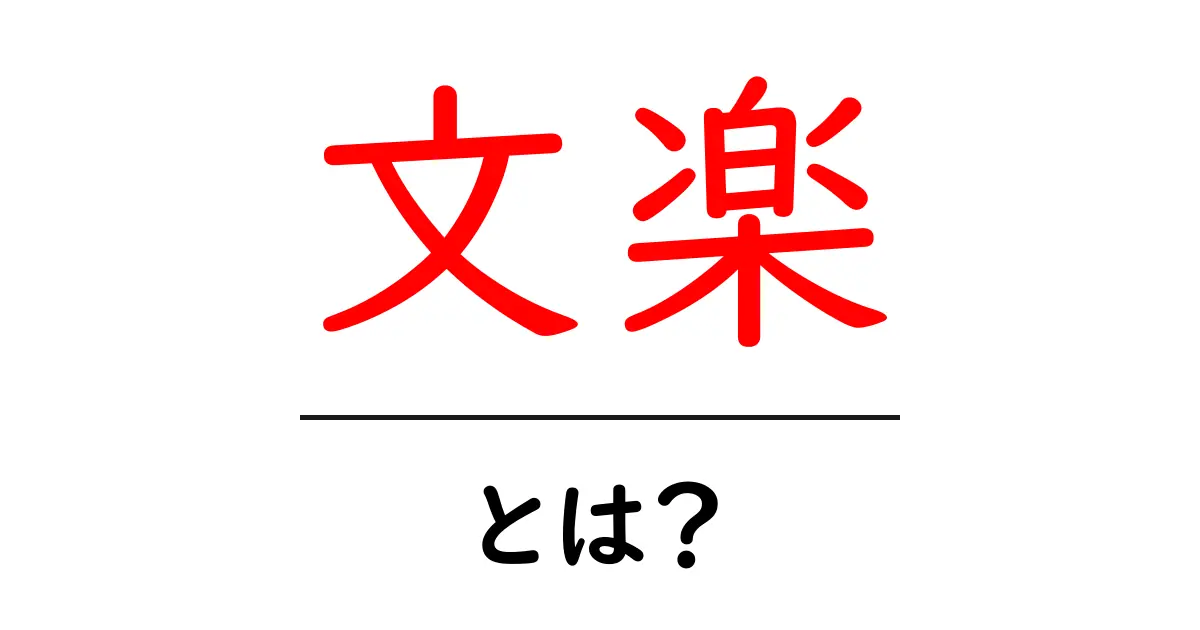
文楽とは?日本の伝統的な人形劇を知ろう!
文楽(ぶんらく)は、日本の伝統的な人形劇の一つで、非常に深い歴史と文化を持っています。文楽では、三人の人形遣いが一体の人形を操り、観客に物語を伝えます。その魅力は、豪華な人形や美しい語り、そして感情表現にあります。
文楽の歴史
文楽の起源は、江戸時代(17世紀から19世紀)に遡ります。当初は「浄瑠璃」と呼ばれる語り物と組み合わせて行われていました。浄瑠璃は、語り手が三味線(しゃみせん)という楽器を演奏しながら物語を語るスタイルです。この二つが結びついて、文楽が生まれました。
文楽の特徴
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 人形の大きさ | 文楽の人形は、一般的に約1メートルほどの大きさで、非常に精巧に作られています。 |
| 人形遣い | 一体の人形を三人が操ります。それぞれ、頭、右手、左手を担当します。 |
| 語り | 浄瑠璃の語り手が物語を進行させ、人形の動きに合わせて感情を込めて話します。 |
文楽の魅力
文楽の最大の魅力は、その独特な表現力にあります。人形たちは、まるで生きているかのように感情や思いを伝えます。特に、悲しい物語や恋愛や友情を描いた作品では、観客の心をつかんで離さない力があります。
文楽を楽しむ方法
文楽を観る方法はいくつかあります。まずは、専門の劇場で公演を観るのが一般的です。また、最近ではインターネットを通じて、文楽の演目を視聴できるサイトも増えてきています。興味のある人は、ぜひ一度は文楽の世界を体験してみてください。
まとめ
文楽は、日本の伝統文化の一部であり、長い歴史の中で人々に愛されてきました。その独特な魅力は、観る人々の心を深く打つことでしょう。日本の文化に興味がある人は、ぜひ文楽を観て、その美しさと奥深さを感じてみてください。
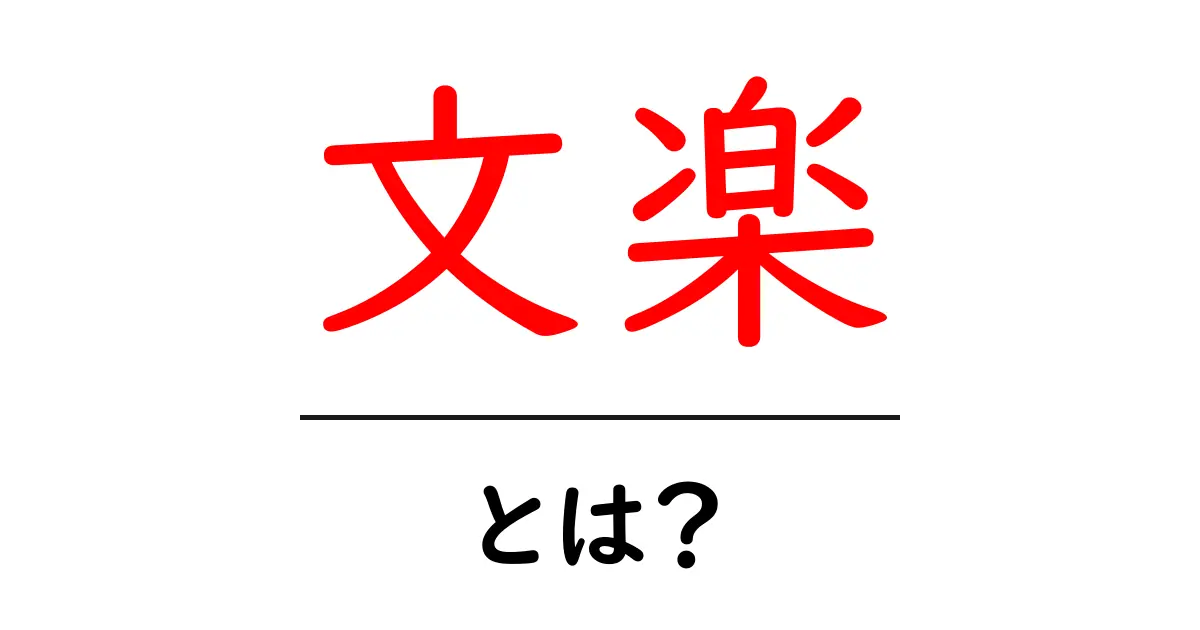
文楽 とは 簡単 に:文楽(ぶんらく)は、日本の伝統的な人形劇で、江戸時代から続いています。この劇は、特に三人の人形遣いが協力して一体の人形を動かすことで知られています。人形は木でできていて、手足や顔の表情を細かく作り込んでおり、本物の人間のように見えます。文楽の特徴は、ただ人形を動かすだけでなく、ストーリーを語るナレーターや、伴奏をする三味線の音楽があることです。これにより、観客は人形たちの感情や動きをより深く感じ取ることができます。文楽は、日本の伝統文化の一環として大切にされており、今でも多くの人に愛されています。学校の授業で学ぶこともあり、実際の公演を観ることもできます。文楽を観ることで、昔の人々の生活や思いを知ることができ、文化の大切さを感じられるでしょう。
文楽 義太夫 とは:文楽(ぶんらく)は、日本の伝統的な人形劇で、特に義太夫(ぎだゆう)という語りが重要な役割を果たしています。義太夫は、太夫(たゆう)と呼ばれる語り手が演じるもので、ストーリーに対して生き生きとした声で物語を語り、観客を引き込みます。この独特な語りは、さまざまな感情や状況を伝えることができ、文楽の魅力の一部でもあります。文楽の人形は非常に精巧に作られており、3人の人形遣いが協力して人形を操ります。このため、義太夫の声と見事な人形の動きが合わさり、観客はより深く物語に入ることができます。文楽は世界的にも評価されており、日本の文化を代表する芸術の一つです。このように、文楽義太夫はただの演技ではなく、日本の歴史や文化を深く理解できる素晴らしい体験を提供してくれます。
人形:文楽で使用される人形のこと。特に、複雑な動きと表現力を持つ人形が特徴です。
座組:文楽の公演を行うための演者やスタッフの集まり。各メンバーが役割を持ち、チームで作品を作り上げます。
浄瑠璃:文楽において、物語を語るための音楽や歌のスタイル。語り手が伴奏に合わせて演じられます。
演者:文楽において、人形を操作する人のこと。人形遣いと呼ばれ、特に高い技術を要します。
伝統:文楽が長年にわたって受け継がれてきた芸能文化。日本の伝統的な演劇形式の一つです。
舞台:文楽の公演が行われる場所。観客と演者が共に物語を楽しむ空間です。
作品:文楽で演じられるストーリーや演目のこと。歴史的なものから現代的なものまで様々です。
観客:文楽の公演を観る人々。彼らの反応が演者に影響を与える重要な存在です。
技術:文楽の演者が持つ人形遣いや語りの技能。特に高い完成度を求められます。
フィナーレ:文楽の公演の最後の部分。物語のクライマックスや大団円が描かれます。
人形浄瑠璃:文楽は、人形と語り手による浄瑠璃の融合芸術であり、特に人形を用いた日本の伝統演劇の形式です。
日本人形劇:日本の伝統的な人形を使った演劇全般を指し、文楽もその一つですが、特に文楽はその演技や演出が特徴的です。
浄瑠璃:浄瑠璃は、語り手が語るストーリーとともに人形が演じる形式を指し、文楽はこの浄瑠璃のスタイルを持つ代表的な形式です。
人形舞踏:人形舞踏は、人形を使って舞いを表現する芸術形態で、文楽でもこの技術が用いられています。
人形浄瑠璃:文楽は人形浄瑠璃の一種で、口調を使って演じられる人形劇です。浄瑠璃と呼ばれる語り手の素晴らしい物語とともに、人形が演じるストーリーが魅力です。
三味線:文楽の演奏では、三味線という楽器が使用されます。三味線は、日本の伝統的な弦楽器で、物語に合わせた音楽を奏でて、演技を彩ります。
人形:文楽で使用される人形は、通常は木製で、精緻な作りになっています。人間の動きを模した動きができるように設計されており、演者が見えない方法で操作されます。
役者:文楽では、役者は人形を操作する人々のことを指します。通常、三人一組で動かすことで、自然な動きを再現します。
浄瑠璃:浄瑠璃は、主に物語を語る音楽スタイルで、文楽においては物語を語りながら演技を進める大事な要素です。
舞台装置:文楽の舞台は、独特な舞台装置が用意されています。これにより、さまざまな場面や情景を表現することが可能です。
伝統芸能:文楽は、日本の伝統芸能の一つとして位置づけられています。古くから受け継がれてきた文化であり、その技術やスタイルは今も大切にされています。
大阪:文楽は大阪で発展した芸能で、そのルーツは大阪の古い劇場文化にさかのぼります。
音楽:文楽では、三味線による音楽が重要な役割を果たしています。この音楽は、ストーリーの感情や場面を引き立てる要素となっています。
観客:文楽の魅力は観客との一体感にもあります。観客は物語に感情移入し、登場人物の感情を共感することで、より深い体験を得ることができます。
文楽の対義語・反対語
芸術の人気記事
前の記事: « 尾羽とは?鳥の羽の不思議を探ろう!共起語・同意語も併せて解説!