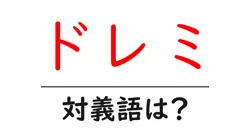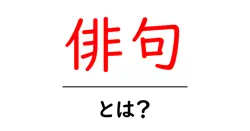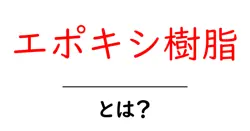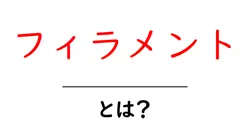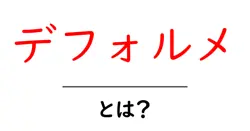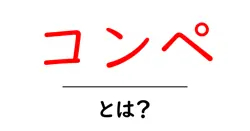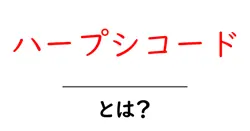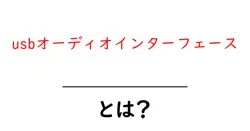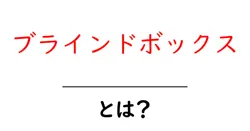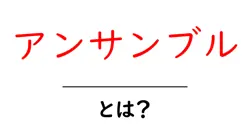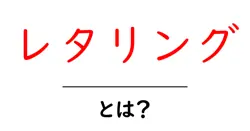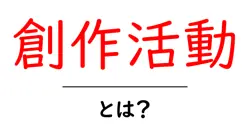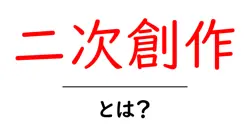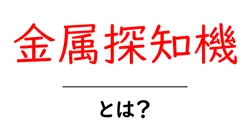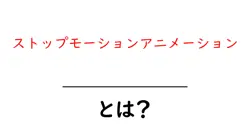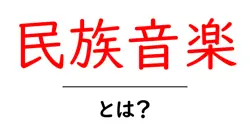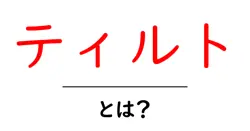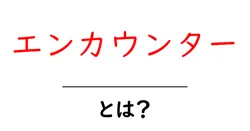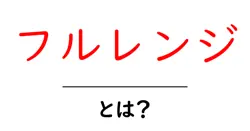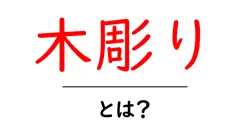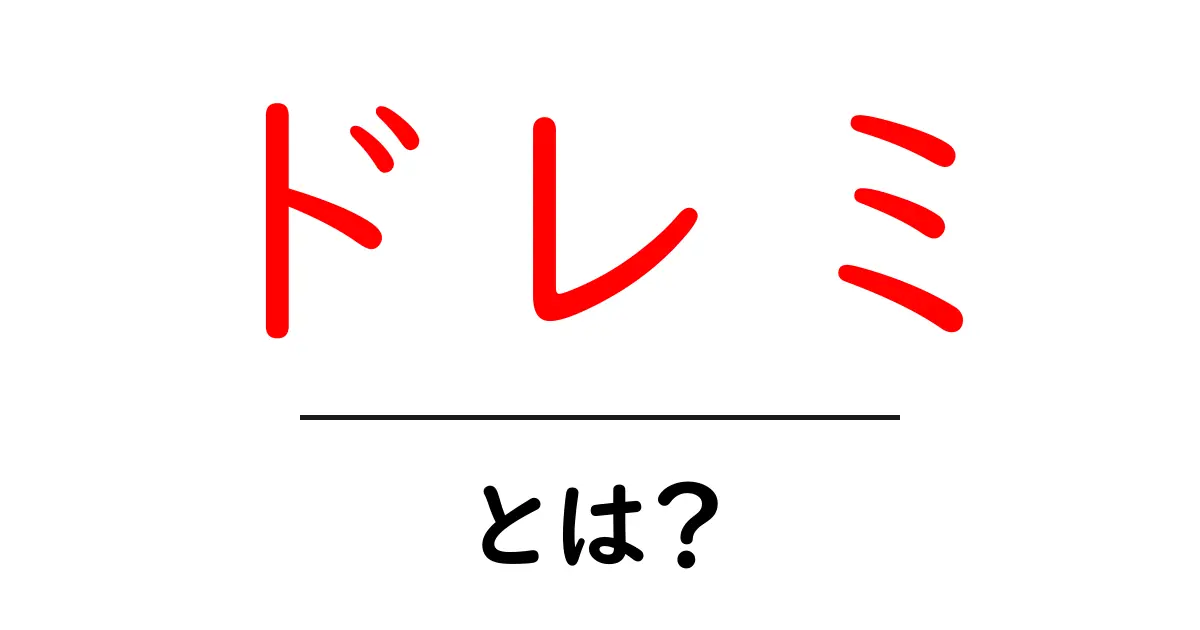
ドレミって何?音楽の基本から魅力を理解しよう!
音楽の世界に触れると「ドレミ」という言葉がよく出てきます。ドレミは、楽譜における音の高さを表す音階の名前です。具体的には、「ド」、「レ」、「ミ」、「ファ」、「ソ」、「ラ」、「シ」の7つの音から成り立っています。
ドレミの基本
音楽を学ぶ上で、ドレミは非常に重要です。これは、メロディーやハーモニーを作る際の基本的な音の配置でもあります。一般的に、ドレミはピアノやギターなど、様々な楽器で使われます。
音階の説明
| 音 | 音の名前 |
|---|---|
| ド | 第1音 |
| レ | 第2音 |
| ミ | 第3音 |
| ファ | 第4音 |
| ソ | 第5音 |
| ラ | 第6音 |
| シ | 第7音 |
ドレミの楽しい使い方
ドレミは単なる音の名前ではありません。物語や遊びの中でも使うことができます。例えば、小さな子供たちが歌を楽しむ時、「ドレミファソラシド」と歌うと、音楽がやさしく楽しく感じられます。
まとめ
音楽を始める際の第一歩は、ドレミを理解することです。この基本を知ることで、多くの楽器を演奏できるようになり、音楽をもっと楽しむことができます。音楽は人生を豊かにする素晴らしいものであり、ドレミはその始まりです。
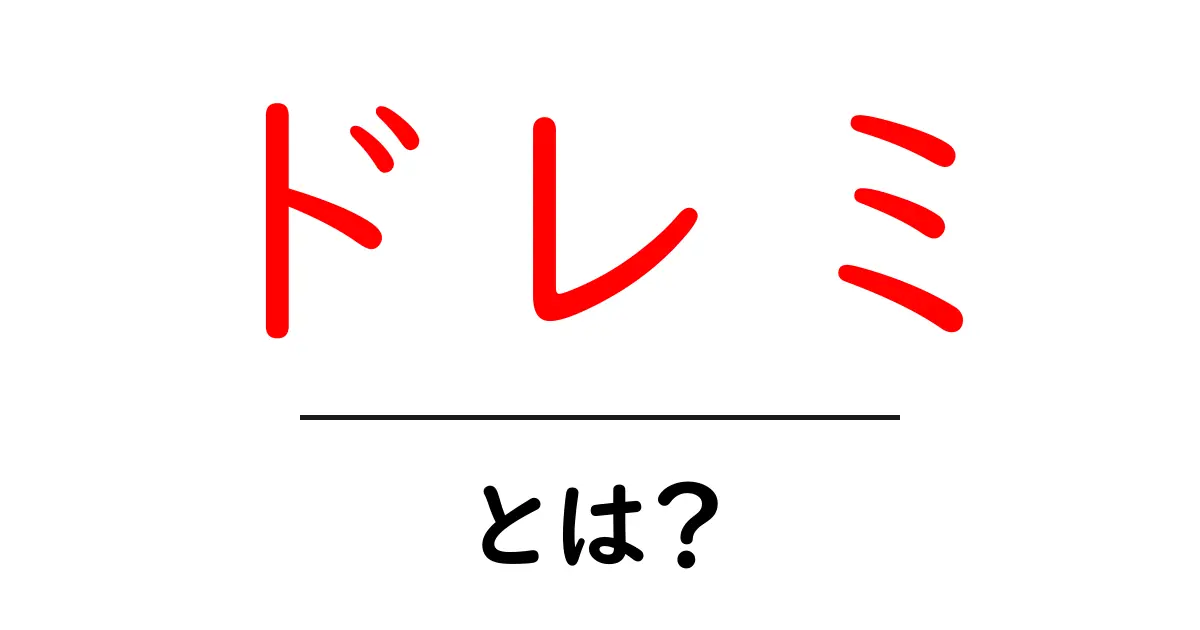
どれみ 1620 とは:「どれみ 1620」という言葉は、音楽や教育の分野で使われることが多いですが、具体的にどういう意味があるのでしょうか。まず、「どれみ」とは音階の基本を指す言葉で、音楽の基本を学ぶ際に重要な要素になります。そして、「1620」という数字は特定の意味を持つことが多いですが、例えば、ある楽器の種類やチューニング方法を示す際に使われたりします。特に音楽教育においては、子どもたちが楽しく音楽を学ぶための教材としても利用されることがあります。「どれみ 1620」は、基礎的な音楽教育を受ける際の指標や参考として、非常に重要なワードと言えるでしょう。音楽を学ぶ際には、このような基礎知識を持っていると、より深い理解につながります。これから音楽を始めようとする中学生にも、この言葉がどのように使われるかを知っておくと良いでしょう。
どれみ とは:「どれみ」は、音楽の基本的な音階の名前です。この音階は、ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソの7つの音から成り立っています。特に「どれみ」は、音楽の入り口として非常に重要で、楽器を学ぶときや歌を歌うときの基礎になります。どうしてこの音階が大切かというと、音楽のあらゆるジャンルに共通するルールだからです。たとえば、ピアノやギターを弾くとき、または歌を作るときにも「どれみ」の音階を使います。さらに、音楽を聴くときにもこの音がなにを表しているのかを理解する助けになります。「どれみ」を学ぶことで、音楽を感じる力も育てることができるんです。子どもから大人まで、みんなが楽しめる音楽の世界に、一緒に飛び込んでみましょう!
音階:音楽において、特定の音の高さを持つ音の系列のこと。ドレミはその基本的な音階を構成しています。
音楽:楽器や声を使ってメロディやリズムを表現するアートの一形態。ドレミは音楽の基本的な要素です。
楽器:音楽を演奏するための道具。ピアノ、ギター、バイオリンなどがあり、ドレミの音を出すために使います。
メロディ:音楽の中で、音の高低が組み合わさって形成される旋律のこと。ドレミの音を使って作られます。
和声:異なる音を同時に鳴らすことで生み出されるハーモニーのこと。ドレミを使った和声が、音楽の厚みを作ります。
リズム:音楽の中で、音の強弱や長短の繰り返しによって生まれる流れ。ドレミを使ってリズムを取ることができます。
ハーモニー:和声が組み合わさることで生じる、美しい音の響き。ドレミを使って和音を作ることで表現されます。
歌:人が声を使って音楽を表現する行為。ドレミは歌のメロディの基盤となります。
音符:音楽の楽譜で使われる記号で、ドレミを含む音の高さや長さを示します。
音楽理論:音楽の構造やメカニズムを理解するための学問。ドレミは音楽理論の基本的な要素の一つです。
音階:音の高さを順番に並べたもので、歌や音楽で基本となるメロディーの構成に使われます。
音楽ノート:音楽の基本的な単位で、音色やリズムを表現するために用いられる記号です。
ピアノの鍵盤:ドレミファソラシドの音を再現するための楽器の部品を指します。これにより音楽が演奏できるようになります。
メロディー:音の組み合わせによって作られる旋律で、感情やストーリーを表現するために重要な役割を果たします。
楽音:音楽で使われる音のことを指し、ドレミはその基本的な音の組み合わせを示します。
音階:音の高低を表すための基準で、ドレミファソラシのように音を順番に並べたもの。同じ音楽の調(トーン)を理解するためのベースとなります。
楽譜:音楽を視覚的に表現するための記号の集まりで、ドレミの音をどのように演奏するかを示すものです。
調性:音楽が特定の音階を基に構成されることを示す概念で、例えば、Cメジャーなど特定のスケールがその例となります。
メロディ:音楽の中で、ドレミの音を基にした主旋律のこと。一般的に歌詞やフレーズに合わせて歌われます。
和音:複数の音を同時に鳴らした場合の音の組み合わせで、ドレミを使ってさまざまなハーモニー(響き)を作ります。
音楽理論:音楽を理解するための原則やルールを学ぶための知識体系。ドレミを利用して、音楽の構造すべてを分析します。
音楽教育:音楽に関する知識やスキルを学んだり教えたりすること。ドレミなどの音符の読み方や演奏技術を学びます。
ソルフェージュ:音楽の音程やリズムを声で表現する練習法。ドレミを使用して音を正確に歌う技術を重視します。
演奏:楽器や歌を使って音楽を表現すること。ドレミを演奏することで、曲を楽しむことができます。
音楽ジャンル:特定のスタイルや特徴を持つ音楽の種類で、ポップ、クラシック、ジャズ、ロックなど、ドレミを基にした楽曲が多岐にわたります。