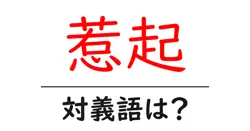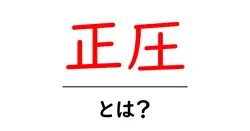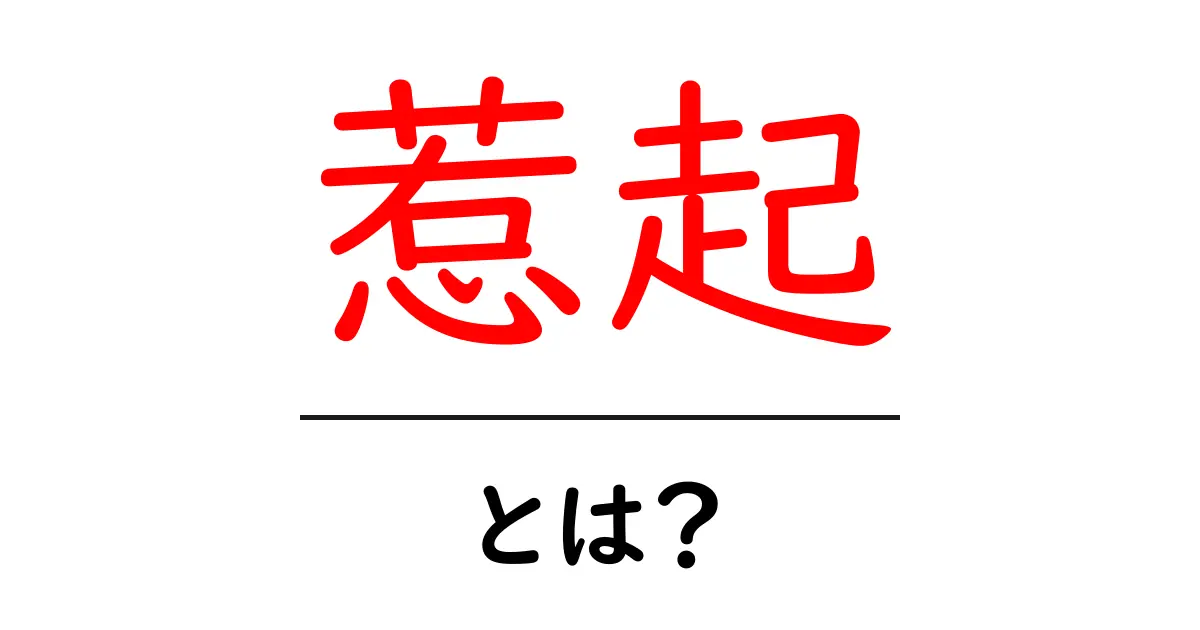
惹起とは?
「惹起」という言葉は、「引き起こす」や「引き立てる」という意味を持っています。日本語では、特定の状態や感情を呼び起こすことを指すことが多いです。この言葉は、主に心理学や文学などで使用されることが多く、何かを「惹起」することで、他の感情や反応が生まれるという文脈で使われます。
惹起の具体的な使い方
例えば、ある音楽を聴くと、昔の思い出が惹起されることがあります。この場合、音楽がきっかけとなって、過去の記憶や感情が呼び起こされるわけです。
また、文学作品でも「惹起」という言葉はよく使われます。作家が読者に特定の感情を惹起するために、描写や言葉の選び方に工夫を凝らすことがあります。
惹起の例を表にまとめてみました
| 状況 | 惹起される感情 |
|---|---|
| 古い写真を見る | 懐かしさ |
| 特別な場所を訪れる | 幸福感 |
| 友達との話し合い | 安心感 |
惹起の重要性
「惹起」という言葉は、日常の中で非常に重要な役割を果たします。例えば、教育現場では、教師が学生の興味を惹起するために、さまざまな教材やアクティビティを使用します。また、マーケティングの世界でも、商品の魅力を惹起することで、消費者の購買意欲を高めることができます。
まとめ
「惹起」は私たちの日常生活にも密接に関わっている言葉です。何かを惹起されることで、私たちの感情や行動が変わることがあります。archives/4394">そのため、この言葉を理解しておくことは、コミュニケーションや人間関係を深める上で非常に有益です。
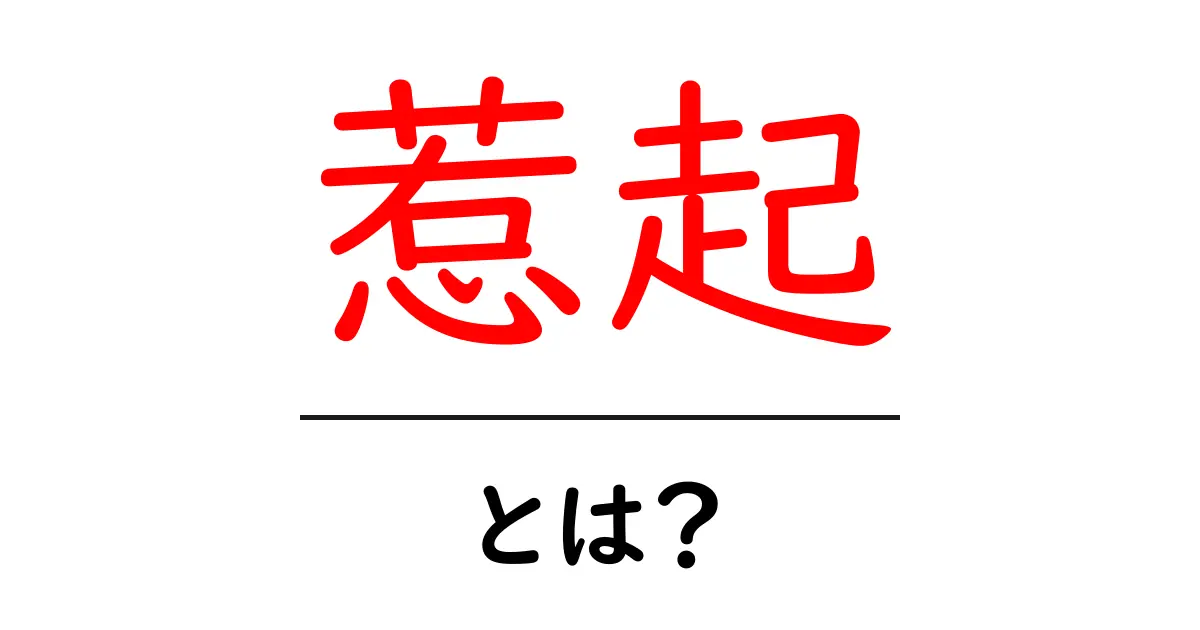 archives/9451">併せて解説!">
archives/9451">併せて解説!">感情:人の心の中で生じる状態や気持ちのこと。惹起は感情を引き起こすという意味合いがあるため、関連があります。
反応:何かに対しての応答や行動のこと。惹起は刺激によって反応を引き起こすことに関連するため、この言葉が共起します。
刺激:感覚や思考を引き起こすもの。惹起は外部からの刺激によって内面的な変化を引き起こす様子を示します。
記憶:過去の経験や知識を保持していること。惹起は特定の記憶を思い出させる作用にも使われることがあります。
行動:人がする動作や活動のこと。惹起は感情や反応をもとに、行動に結びつくことが多いため、共起します。
意識:自分の存在や周囲の状況を認識すること。惹起は意識に影響を与えることで、何かを感じさせることと関連しています。
思考:物事を考えたり判断したりする活動。惹起は思考プロセスを刺激することがあり、共起語となります。
欲求:何かを求める気持ち。惹起は特定の欲求を引き起こすことがあるため、関連性があります。
引き起こす:ある事象や状態を生じさせること。特定の出来事や反応を誘発することを指します。
誘発する:特定の行動や反応を他者に促すこと。何かを仕向けたり、影響を与えたりすることを意味します。
引き出す:ある応答や感情を引き出すこと。特定の状況や刺激によって、内面的な反応を生まれさせることを指します。
発生させる:何かを新たに生じさせること。状態や出来事が現れることを表します。
引き揚げる:高い位置に持ち上げること。他の物や状況から離れるようにすることも含まれます。
もたらす:何かを現実にすること。特定の結果や影響をもたらすことを指します。
促す:何かを進める、または奨励すること。行動を促進させる意味合いで使われます。
牽引:物事を引っ張って進めること。特に、他者を引きつけて前進させる影響を与えることを指します。
刺激:感覚や感情に影響を与えること。特に、興味を引き起こしたり、行動を促す要因となります。
誘引:特定の行動や反応を誘発すること。この言葉は、何かを引き寄せる力を表現しています。
感情喚起:特定の感情を呼び起こすこと。心理的な影響を与え、多様な反応を引き起こします。
反応:特定の刺激に対して示す動きや行動。感情的な反応から肉体的なものまで多岐に渡ります。
意識喚起:人々の注意を向けさせること。情報や感情をもとに、特定のテーマやアイデアについて考えさせます。
動機付け:行動を起こすための原動力を与えること。目標に向かって進むためのエネルギー源となります。
感覚:五感を通じて得られる情報や経験。人の反応に大きく影響を与える要素です。
惹起の対義語・反対語
惹起(じゃっき)とは? 意味・読み方・使い方をわかりやすく解説
惹起の読み方とは? 意味や言い換え・類義語、例文や英語表現を解説
未分類の人気記事
前の記事: « シマーとは?その意味と使い方を解説!共起語・同意語も併せて解説!