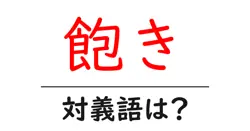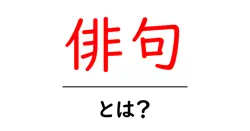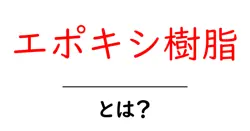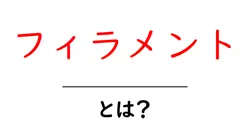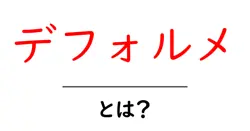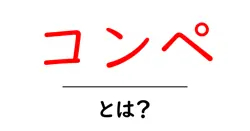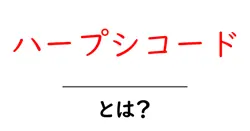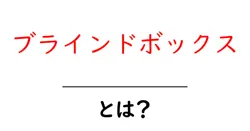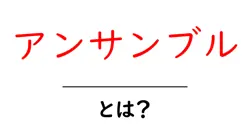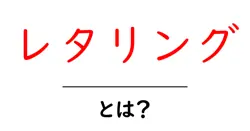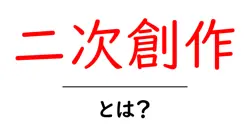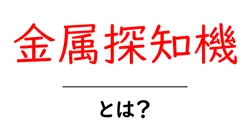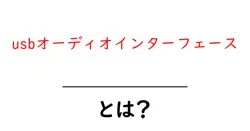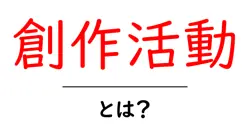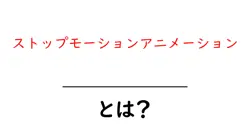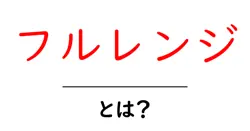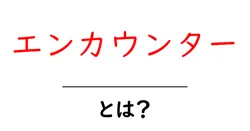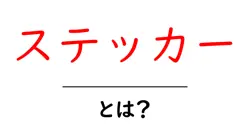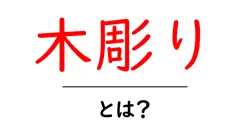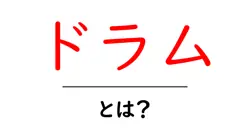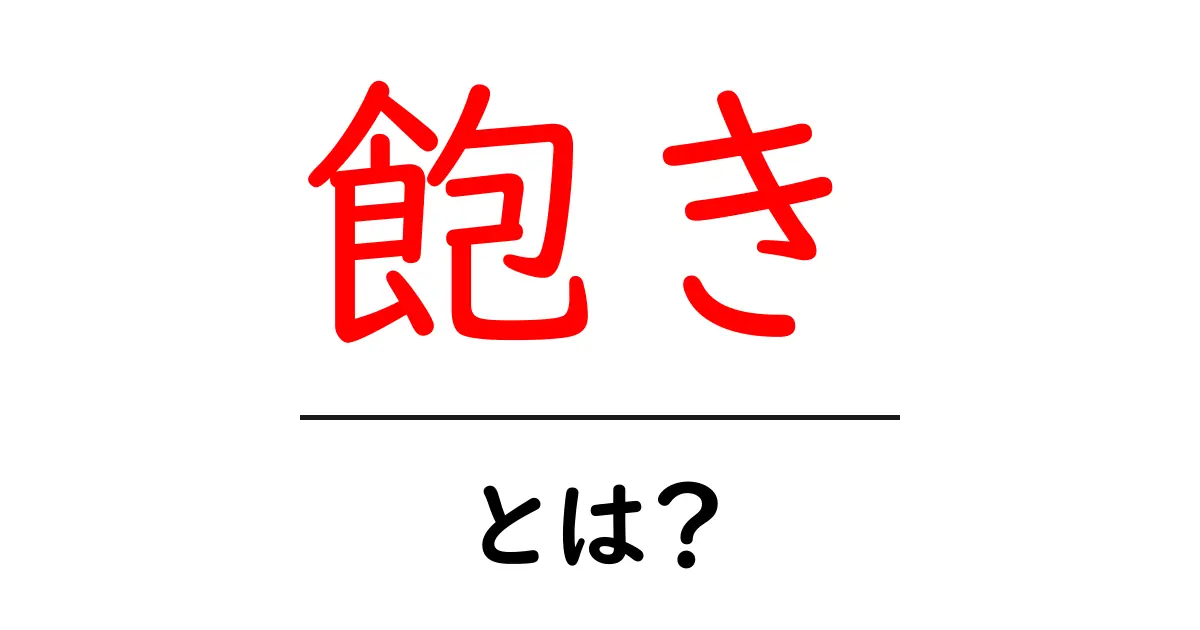
飽きとは何か?
「飽き」という言葉は、何かに対して興味を失ったり、続けていると感じるわずらわしさを示すものです。たとえば、毎日同じ食べ物を食べたり、同じ遊びを繰り返していると、だんだんそのことに飽きてしまいます。この状態は、気持ちが変わったり、新しい刺激を求める気持ちが強くなったりすることから起こります。
なぜ飽きを感じるのか?
飽きを感じる理由には、いくつかの要素があります。まず、人間の脳は新しい情報や刺激を求めるようになっています。新しい経験をすることで、脳はドーパミンという物質を分泌し、興奮や幸福感を与えます。しかし、同じことを繰り返すと、それほどの刺激が得られず、ドーパミンの分泌が減少し、飽きが生じるのです。
飽きがもたらす影響
飽きは時には悪いことではありません。新しいことに挑戦するきっかけともなり、自分を成長させるチャンスを与えてくれます。しかし、過度の飽きは注意が必要です。
主な影響:
| 影響 | 説明 |
|---|---|
| 集中力の低下 | 同じことを続けることで、注意が散漫になりやすくなる。 |
| やる気の喪失 | 興味を失うことで、物事に対する意欲が減少する。 |
| 新しい経験の減少 | 古い習慣から抜け出せず、新たな挑戦を避けるようになる。 |
飽きを克服する方法
飽きを感じたときは、いくつかの方法でその状態を克服することができます。
- 新しい趣味を始める:新しく興味を持てるものに挑戦してみましょう。
- 環境を変える:場所を変えて作業を行うことで新鮮な気持ちになります。
- 友達と一緒に活動する:周りの人と新しいことを楽しむことで、刺激を得やすくなります。
飽きは自然な感情ですが、それをどう扱うかが大切です。新しい挑戦を楽しみながら、自分自身を成長させていきましょう。
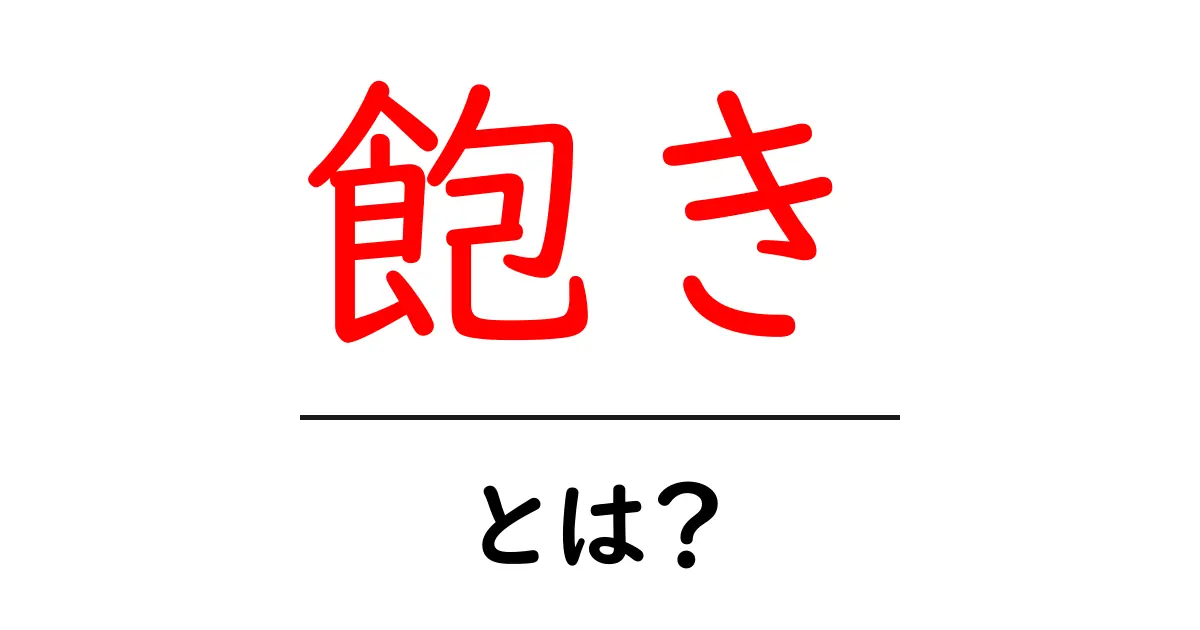
退屈:何かをしているのに心が満たされず、なにもする気が起きない状態。
興味喪失:もともと関心を持っていたことに対して、興味が完全になくなってしまった状態。
マンネリ:同じことを繰り返すことで新鮮さが失われ、飽きが生じる状態。
刺激:新しい経験や感覚。飽きから解放されるためには刺激的な要素が必要。
依存:特定のものに頼りすぎること。飽きは依存の結果として現れることがある。
変化:状況や環境が変わること。飽きが生じたときは、変化を取り入れることで解消されることが多い。
免疫:同じ刺激に対する抵抗力。飽きは免疫が関与する場合がある。
新鮮さ:新しい、または未経験の感覚。飽きを避けるためには新鮮な体験が必要。
退屈:何もすることがなくて、気が晴れない状態。興味が持てず、時間が長く感じられること。
嫌気:ある物事に対して持つうんざりした気持ち。繰り返し同じことを行い、もうそれに対して耐えられない状態。
倦怠:長い間同じことを続けてきたために生じる疲れや飽きの感覚。心や体にやる気を失った状態。
無関心:特定の物事に対して興味や関心を持たないこと。何に対しても心を動かされない状態。
飽き飽き:同じことが繰り返されることに対する強い飽きの感情。特に、好ましくない事柄に対して使われることが多い。
退屈さ:状況が刺激的でなく、楽しさや興味が欠けている感じ。飽きが生じることで心が退屈に感じる状態。
マンネリ:同じことの繰り返しになり、新鮮さが失われる状態のこと。飽きがくる原因の一つです。
退屈:興味や楽しみを感じず、何もしたくないと思う感情のこと。飽きが回ると退屈を感じやすくなります。
刺激:新しさや興奮をもたらすもの。飽き防止には刺激的な体験が重要です。
変化:状態や状況が変わること。変化を取り入れることで飽きを防ぐことができます。
新鮮さ:新しいことや感じたことから得られる刺激や感動のこと。飽きが来ると新鮮さが感じられなくなります。
関心:興味を持つこと。飽きが来て関心が薄れると、行動も減ってしまいます。
モチベーション:行動を起こそうとする意欲や動機のこと。飽きが来るとモチベーションも下がりがちです。
ルーチン:日常的に繰り返す行動や習慣のこと。ルーチンがマンネリ化すると、飽きを感じやすくなります。
気分転換:心をリフレッシュさせること。他の活動を行うことで飽きを解消する手段です。
体験:実際に行動して感じたこと。新しい体験を積むことで飽きを防ぐ効果があります。
飽きの対義語・反対語
飽き/厭き(あき) とは? 意味・読み方・使い方 - 国語辞書 - goo辞書
「飽きる」とは? 意味や類語表現、飽き性な人の特徴などを詳しく紹介
飽きとは何か|Dai Tamesue(為末大) - note
飽き飽き(あきあき) とは? 意味・読み方・使い方 - goo辞書
趣味・ホビーの人気記事
次の記事: シマーとは?その意味と使い方を解説!共起語・同意語も併せて解説! »