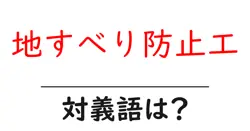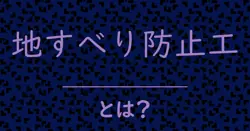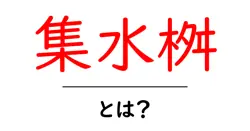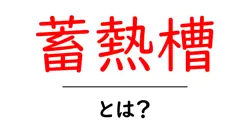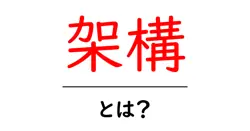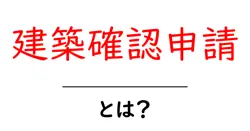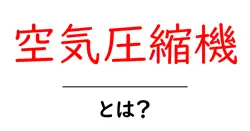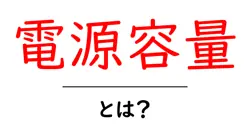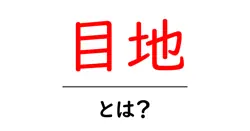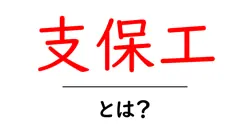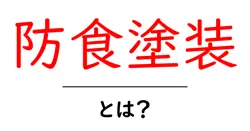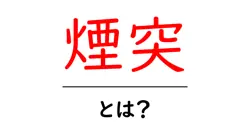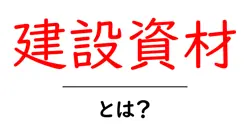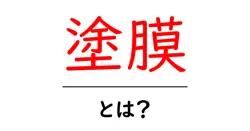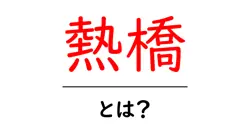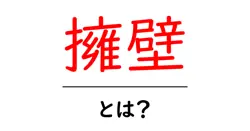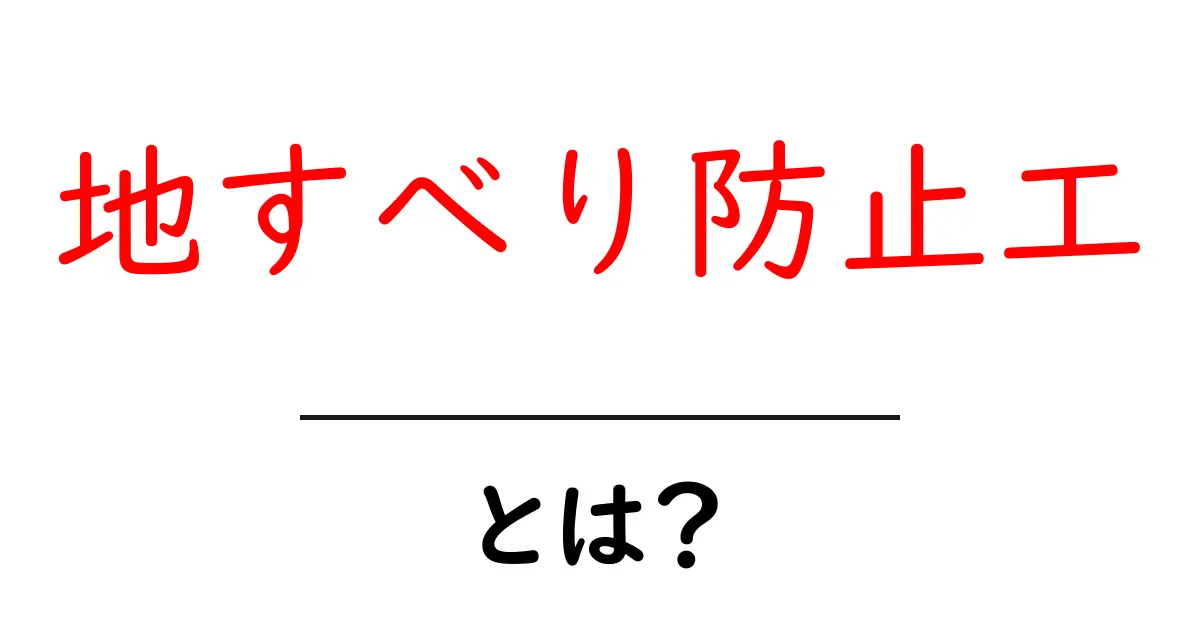
地すべり防止工とは?
地すべり防止工(じすべりぼうしかん)は、地すべりを防ぐための重要な工事です。地すべりとは、土や石が斜面から滑り落ちる現象のことで、これが起こると大きな危険が伴います。特に山や丘の近くに住んでいる人々にとっては、地すべりは非常に不安な問題です。この工法は、土地や建物を守るために開発されました。
地すべりの原因
地すべりが起こる原因はいくつかあります。主なものを以下に示します:
- 雨水や雪解け水:土の中に水分が多くなることで、土が柔らかくなり、滑りやすくなります。
- 地震:地震の揺れによって土が不安定になり、滑り落ちることがあります。
- 人間の活動:山を切り崩したり、建物を建てたりすることで、周りの土が不安定になることがあります。
地すべり防止工の方法
地すべり防止工には、いくつかの工法があります。代表的なものを以下にまとめました。
| 工法名 | 特徴 |
|---|---|
| 土留め工 | 土を支えるための壁を作る工法です。 |
| アンカー工法 | 地面にワイヤーを埋め込んで、土の動きを抑える方法です。 |
| 排水工 | 水を排出するための管を設置して、土を乾燥させる工法です。 |
地すべり防止工の重要性
地すべり防止工は、私たちの生活を守るために非常に重要です。特に、地すべりが発生した場合、人々や家や道路、鉄道などに大きな被害を与えることがあります。また、予防措置を取ることで、修理の費用や人命を守ることができます。地域全体の安全を考えると、地すべり防止工の実施は欠かせないと言えるでしょう。
最後に
地すべり防止工を知ることで、私たちの生活環境を守るためにどう行動すべきか考えるきっかけになります。地域の特性や地形を理解し、適切な対策を講じることで、より安全な社会を築いていけるでしょう。
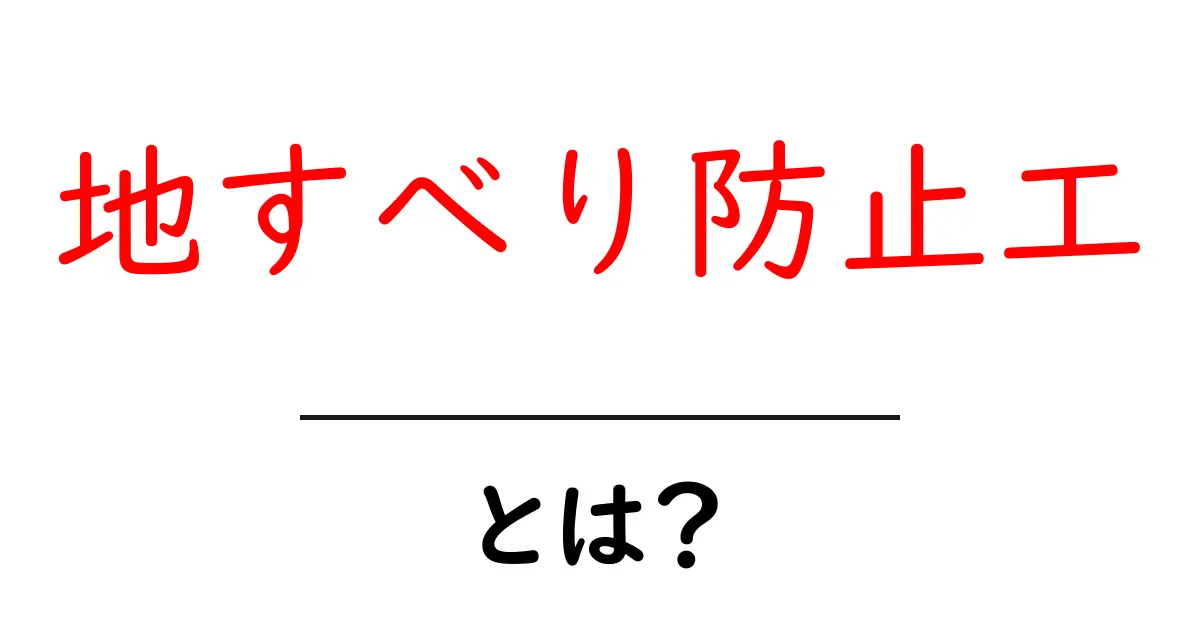 地すべり防止工とは?知って得られる安全のための工法共起語・同意語も併せて解説!">
地すべり防止工とは?知って得られる安全のための工法共起語・同意語も併せて解説!">土砂災害:土砂や岩が崩れ落ちる災害のこと。地すべりもその一種であり、特に地面が急な斜面で発生することがある。
護岸工:川や湖、海岸の岸辺を保護する工事。特に水の流れにより侵食されるのを防ぐために設計されており、地すべり防止工と併用されることがある。
地盤改良:地盤の強度や安定性を向上させる工事。地すべりのリスクを減らすために、地盤を固めたり、水を吸収しにくくする方法が用いられる。
排水:土壌や地盤から水を排出すること。余分な水分が地すべりを引き起こす原因となるため、適切な排水が重要。
斜面安定化:斜面の安定性を向上させるための工法。地すべりを防ぐために、斜面を強化したり、植生による保護を施したりする。
防災:自然災害から人命や財産を守る取り組み。地すべり防止工はその一環であり、住民の安全を確保するために重要な手段となる。
県土整備:県内の土地やインフラを整備し、地形や地質に合わせた安全な環境を確保する行政活動。地すべり防止工もその一つの施策として位置づけられる。
モニタリング:地すべりの発生を予測するために地盤や水の状態を定期的に観測すること。早期発見が地すべり防止工の効果を高める。
造成:土地を造成して利用可能な状態にすること。地すべりが懸念される地域では、造成時に十分な対策が必要。
土砂崩れ防止工:地面や山の斜面から土砂が崩れ落ちるのを防ぐための工事。具体的には、地すべりのリスクがある場所での対策を含む。
斜面安定工:山や丘の斜面を安定させるための工事で、地すべりや土砂崩れを防ぐ目的がある。
防災工事:自然災害から人や施設を守るための工事全般。地すべり防止工もこの防災工事の一部とされる。
土留め工:土の崩落を防ぐために行う工事で、斜面を支える構造物を設けることを指す。
地すべり:地面が急斜面で滑る現象で、土砂や岩が移動します。これが起こると、周囲に大きな危険が及ぶことがあります。
防止工:地すべりを防ぐための工事や技術のことです。土砂の移動を抑えるために、さまざまな方法が用いられます。
土留め:地盤を安定させるための構造物で、土や岩が崩れ落ちるのを防ぐ役割を持っています。
排水工:水分が地盤に影響を与えないように、地下水や雨水を排出するための工事です。これにより、土の流動性が低下します。
斜面安定:地すべりを防ぐために、斜面の安定性を確保する技術や工法のことです。
地質調査:地すべりが発生する可能性を評価するために行う、土壌や岩盤の調査です。これにより、適切な防止工の設計に役立ちます。
植生:植物を用いて地面を守る方法で、根が土を固定し地すべりのリスクを低減します。自然な方法による防止策と言えます。
支保工:工事や土木作業中に、地面が崩れないように支えるための構造物です。
コンクリート:防止工の一部として多く用いられる材料で、強度があるため地すべりの防止に効果的です。
監視システム:地すべりの兆候を早期に発見するために、センサーやカメラを用いて地盤の動きを監視するシステムです。
環境影響評価:防止工の計画に際して、環境への影響を調査し評価するプロセスです。