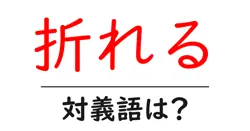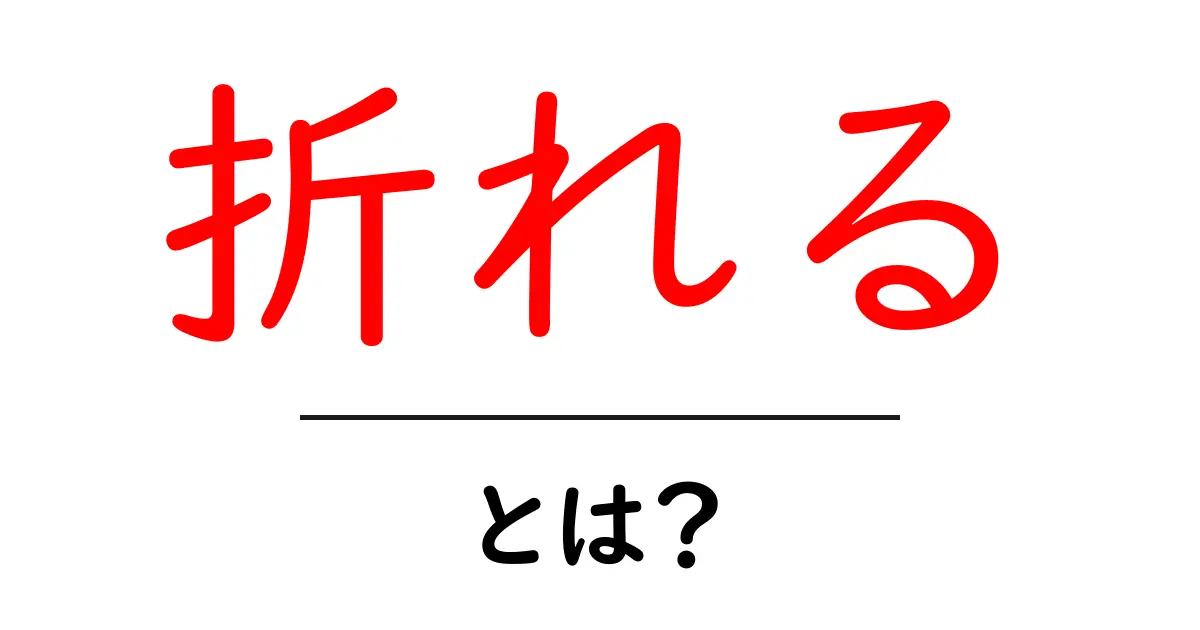
折れるとは?
「折れる」という言葉は、日本語でよく使われる動詞の一つです。日常生活においても頻繁に目にするこの言葉ですが、実際にどんな意味を持っているのでしょうか?今回は「折れる」という言葉の意味や使い方、そして具体的な例について詳しく解説していきます。
「折れる」の基本的な意味
「折れる」とは、物や形が曲がったり、壊れたりして、元の形に戻らなくなった状態を指します。例えば、木の枝やプラスチック製のものがある角度から力を加えられると、その部分が曲がって「折れ」てしまいます。この場合、「折れる」は物理的な現象を指しています。
日常生活での使い方
「折れる」という言葉は、物理的な意味だけではなく、比喩的な意味でも使われます。例えば、「心が折れる」という表現があります。これは、精神的に辛い状況やプレッシャーに耐えられず、気持ちが挫けてしまうことを意味します。
例文を見てみましょう
| 文例 | 意味 |
|---|---|
| 「彼は試験に落ちて心が折れた。」 | 彼は試験に合格できず、心が挫けてしまった。 |
| 「この竹は簡単に折れる。」 | この竹は力を加えると簡単に壊れる。 |
「折れる」の使い方を理解する
「折れる」という言葉の使い方は様々です。特に、日常会話の中では比喩的に使われることが多いです。たとえば、スポーツや試験などの場面で人々が「心が折れる」と語ることがあります。また、商品レビューや口コミなどでは、「この商品はすぐに折れた」と、物理的な意味で使われることもあります。
まとめ
「折れる」という言葉は、物理的な意味だけではなく、比喩的な表現としても幅広く使われています。日常生活の中で様々なシチュエーションで耳にすることが多いこの言葉を知ることで、よりコミュニケーションが深まるでしょう。
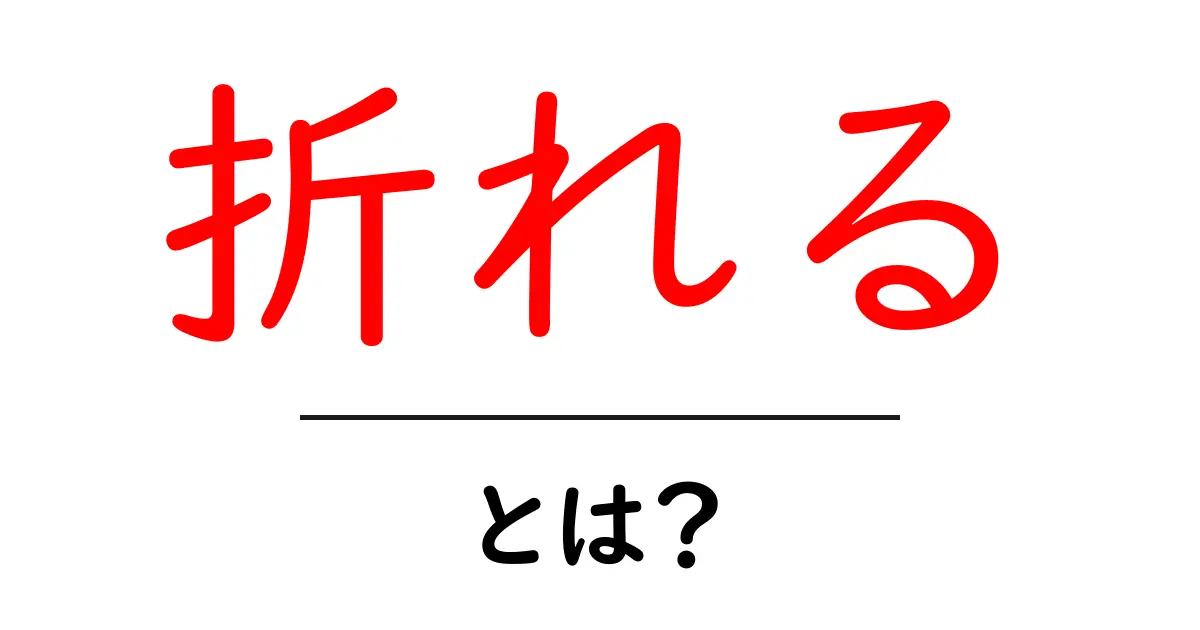 日常生活に潜む「折れる」の意味と使い方共起語・同意語も併せて解説!">
日常生活に潜む「折れる」の意味と使い方共起語・同意語も併せて解説!">折れる:物が力や圧力を受けて形が変わったり、壊れたりすること。
折る:ものを二つに分けたり、曲げたりすること。
曲がる:直線のものが曲がった状態になること。
耐久性:物が力や衝撃に耐える能力。
壊れる:物が完全に形を失ったり、機能しなくなること。
圧力:物体が受ける力の大きさ。
負荷:物にかかる力や重さのこと。
柔軟性:物が力を受けた際に変形しやすい特性。
強度:物の抵抗力や耐久性のこと。
破損:物が壊れたり、損傷を受けること。
材料:物体を構成する物質や素材のこと。
応力:材料にかかる力の集中具合。
破断:限界を超えた力が加わることで物が切れること。
可塑性:物質が変形した後に元に戻らない特性。
損傷:物が傷ついたり、破損した状態。
折り曲げる:物を中心にして折って形を変えること。例えば、紙を半分に折ることを指します。
破れる:物の繊維や構造が切れたりして、全体の形が崩れること。布や紙などが裂ける時によく使われます。
屈折する:物体が曲がったり、歪んだりすること。光や水の流れが曲がる場合によく使われます。
折損する:物が壊れてしまうこと。特に、本来の形を失ってしまうような状況を指します。
折れる:物の形が変わること。耐久性を超えた力が加わると、物体が折れてしまいます。
曲がる:直線的な形が、力が加わることで湾曲する様子。場所によっては、柔らかい物や弾力のある物が曲がることが多いです。
折返す:何かを折って元の位置に戻すこと。特に、マップや紙を折り返して再度見るような場合を指します。
折れる:物体が力を加えられて曲がったり割れたりすること。例えば、木の枝やプラスチック製品など。
折る:物体を曲げて形を変えること。紙を半分に折ると便箋などのように形が変わる。
折り紙:日本の伝統的な手工芸で、紙を折ることでさまざまな形を作る技術。折った紙を使って動物や花などを表現する。
折線:折れるポイントを示すために引かれた線。折りたたむ際の目安として使われる。
シャープペンシル:鉛筆の芯を自動的に出し入れできる文房具。折れた芯を交換する際に使われることがある。
折りたたみ式:使わないときにコンパクトに収納できるように設計された構造のこと。折りたたみ式の椅子や自転車などが該当する。
折れ線グラフ:データを視覚的に表現するためのグラフの一種。点を線で結び、変化を表す。
折れ角:物体が折れたときに形成される角度のこと。特に建築や製造業で重要な指標。
折り返す:物体を一度折り曲げて元に戻すこと。特に、手紙やメモなどを折り返して収納する際に使われる。