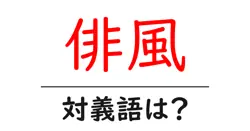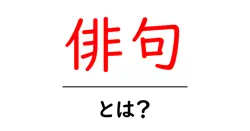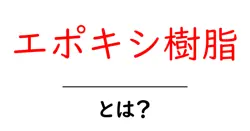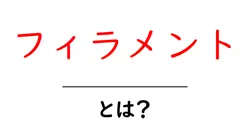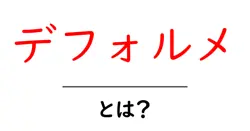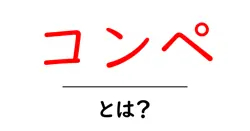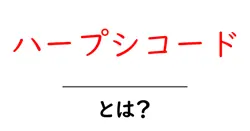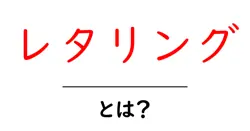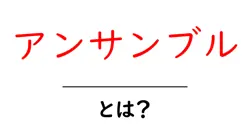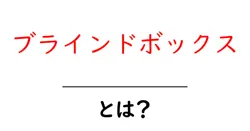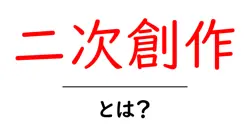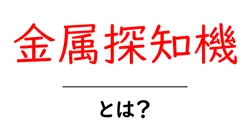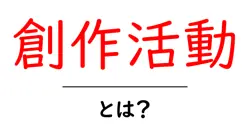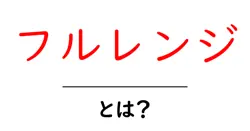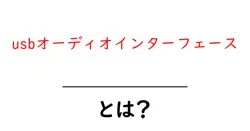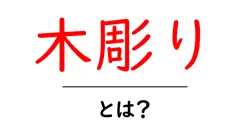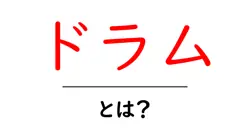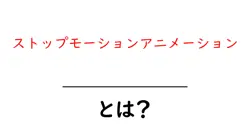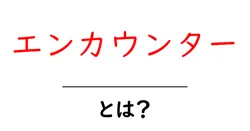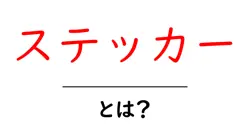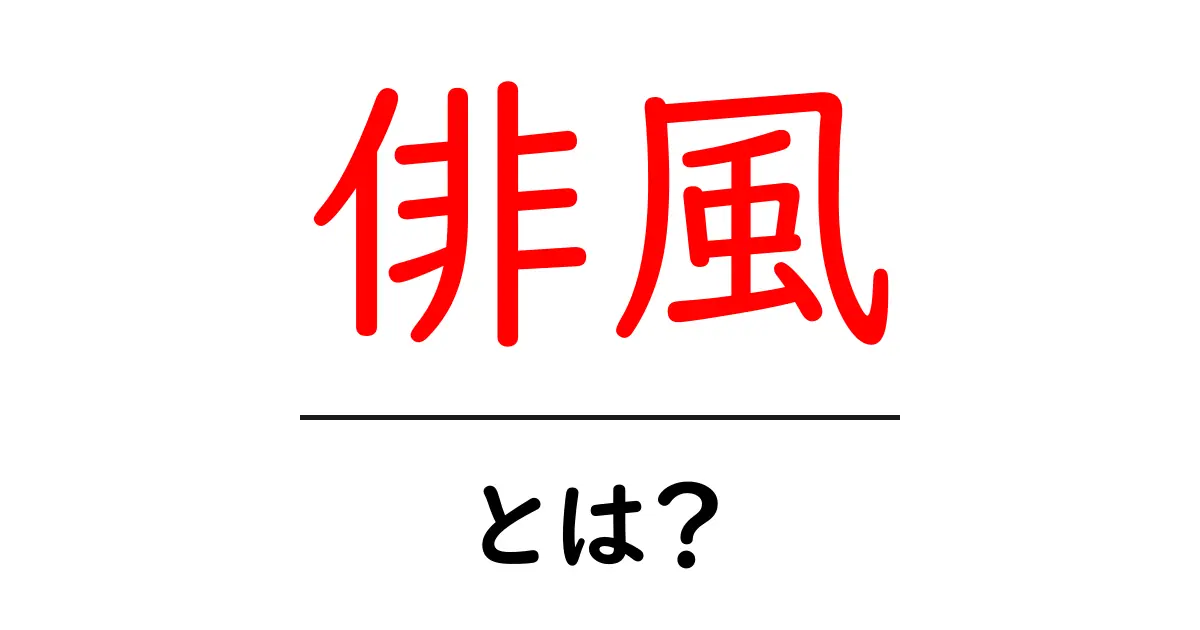
俳風とは?その意味について
「俳風」という言葉は、特に日本の詩や文学に関連しています。主に俳句や詩を作成する際のスタイルや表現方法を指します。ここでは、俳風の背景や楽しむ方法について具体的に解説していきます。
俳風の起源
俳風は、江戸時代に発展した俳句のスタイルから派生してきました。早い段階で、俳句は特定のリズムや言葉遣いを持ち、自然や感情を美しく表現するための手段として人気を集めました。
俳風の特徴
俳風の特徴は主に以下のような点にあります:
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 短い形式 | 通常の俳風は、17音から成る短い詩で構成されます。 |
| 季語の使用 | 自然や季節感を表現するために、特定の言葉(季語)が用いられます。 |
| 感情の表現 | シンプルながらも深い感情を表すことが多いです。 |
俳風を楽しむ方法
俳風を楽しむための方法はたくさんあります。まずは実際に自分で俳句を作ってみることが大切です。考えた言葉や自然の景色をイメージし、心からの言葉を紡いでみましょう。さらに、友達や家族と一緒に俳句を競い合ったり、俳句の教室に参加してみるのも良いでしょう。
まとめ
俳風はシンプルながらも人の心に響く表現方法であり、現代の生活の中でも多くの人に親しまれています。ぜひ、この機会に自分なりの俳風を見つけてみてはいかがでしょうか?
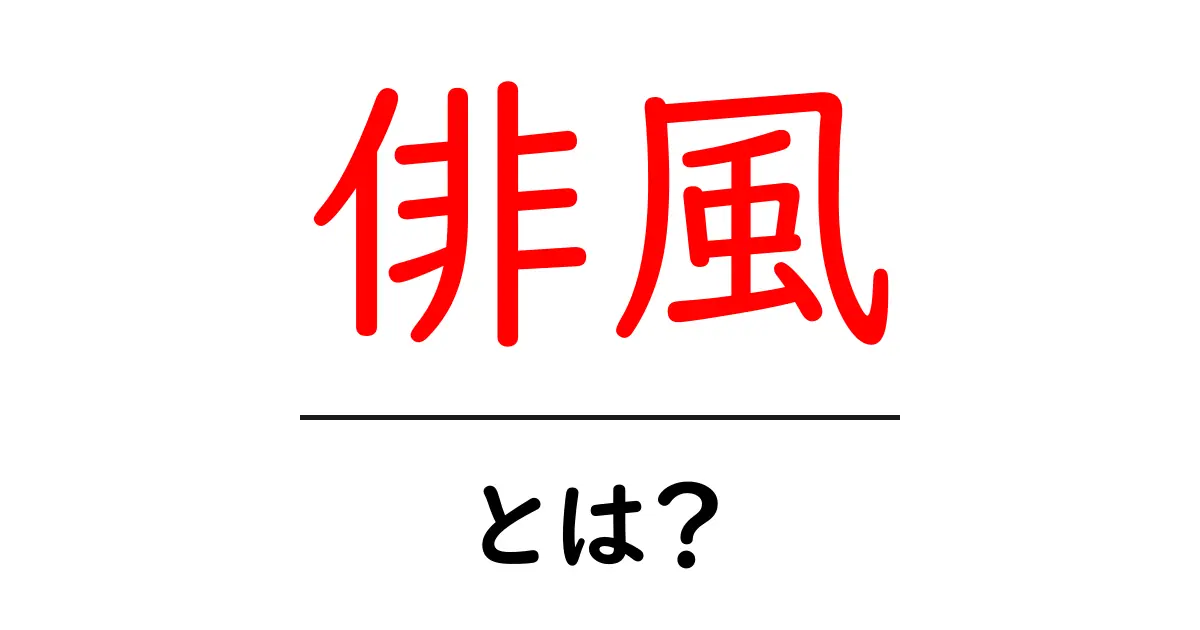 楽しみ方を徹底解説!共起語・同意語も併せて解説!">
楽しみ方を徹底解説!共起語・同意語も併せて解説!">俳句:5・7・5の17音からなる短詩で、自然や季節、人間の感情を表現します。
季語:俳句において季節を示すために使われる言葉で、春、夏、秋、冬それぞれの特性を持つものです。
表現:感情や思考を言葉や形にして伝える行為で、俳風の中では詩的な工夫が求められます。
抒情:詩や文学の中で、心情を率直に表現することを指します。俳風はしばしば抒情的な要素を含みます。
散文:定型にとらわれない自由な文体で、俳句は散文の中で使われることが多いです。
感性:物事を感じ取る能力で、俳風を詠む上で重要な要素です。
視点:物事を見る角度や立場で、俳句は独自の視点から表現されることが多いです。
構造:詩や文章の組み立て方で、俳風は特定の構造(音数ルール)を持っています。
美:物事の素晴らしさや魅力で、俳風では自然の美しさや日常の中の美を描くことがよくあります。
伝統:過去から引き継がれる文化や技法のことで、俳風は日本の伝統的な詩の形式です。
俳句:5・7・5の音数で構成される、短くても情景や感情を表現する日本の詩のひとつ。
詩:文学のひとつで、言葉を使って感情や情景を表現する形式。俳風もその一種として位置づけられる。
短歌:5・7・5・7・7の31音からなる日本の伝統的な詩形。俳風に比べて少し長いが、同じく感情や景色を表現することができる。
歌:感情や出来事を表現するために用いられる韻文。俳風と同様に、言葉のリズムや削ぎ落とされた表現が魅力。
風曲:自然や日常の風景を取り入れた音楽形式で、時に俳風のような感情を伝える。
川柳:5・7・5の形式で、ユーモアや風刺を利かせた詩。俳風とは異なるが、音数の規則性が共通している。
朔風:季節感を大切にした風情ある表現手法で、俳風に似たテーマを持つことがある。
俳句:俳風の基本的な形式で、575の17音からなる短い詩を指します。季節や日常の出来事を表現するため、豊かな言葉選びが求められます。
季語:俳句などの詩で、季節を表す言葉です。春の桜、夏の蝉、秋の紅葉、冬の雪などがあり、作品に季節感を与えます。
切れ字:俳句の中で用いられる言葉で、感情や情景を引き立てる役割を果たします。例えば「や」「かな」などがあり、詩のリズムや雰囲気を強調します。
俳人:俳句を作る人のことです。俳風を追求することで新たな視点や表現を提供し、詩の世界を広げます。
自由律:俳句の形式の一つで、音数やリズムに厳密な制限がないため、より自由に表現できるスタイルです。この形式は、伝統的な俳句とは異なるアプローチを提供します。
風景描写:俳風において、自然や日常の景色を具体的に描写することを指します。これにより、読者は情景を感じやすくなります。
心象風景:詩人の内面や感情に基づく風景を描くもので、俳風でよく用いられる手法です。具体的な場所ではなく、心の中のイメージを表現します。
即興性:俳風には、その場の感情や思いつきを基に即興で作る要素が含まれています。これにより、自然体の表現が生まれやすくなります。
俳風の対義語・反対語
俳風/誹風(はいふう) とは? 意味・読み方・使い方 - 国語辞書
しょうふうとは? 意味・読み方・使い方をわかりやすく解説 - goo辞書