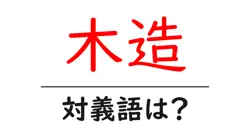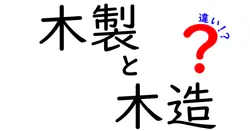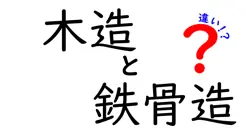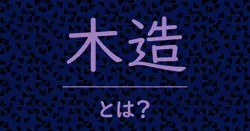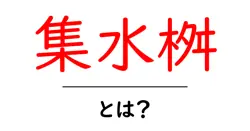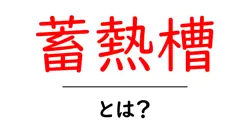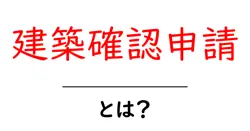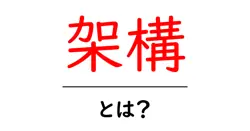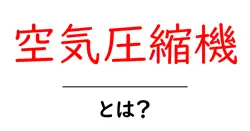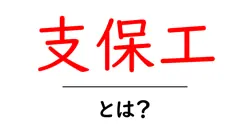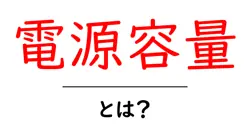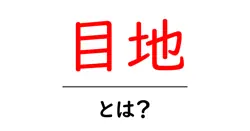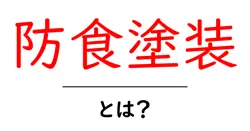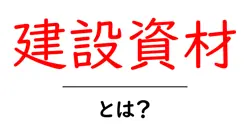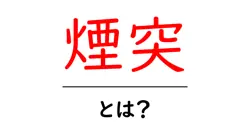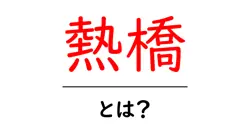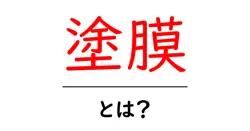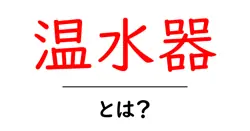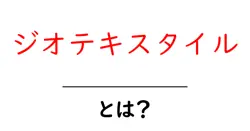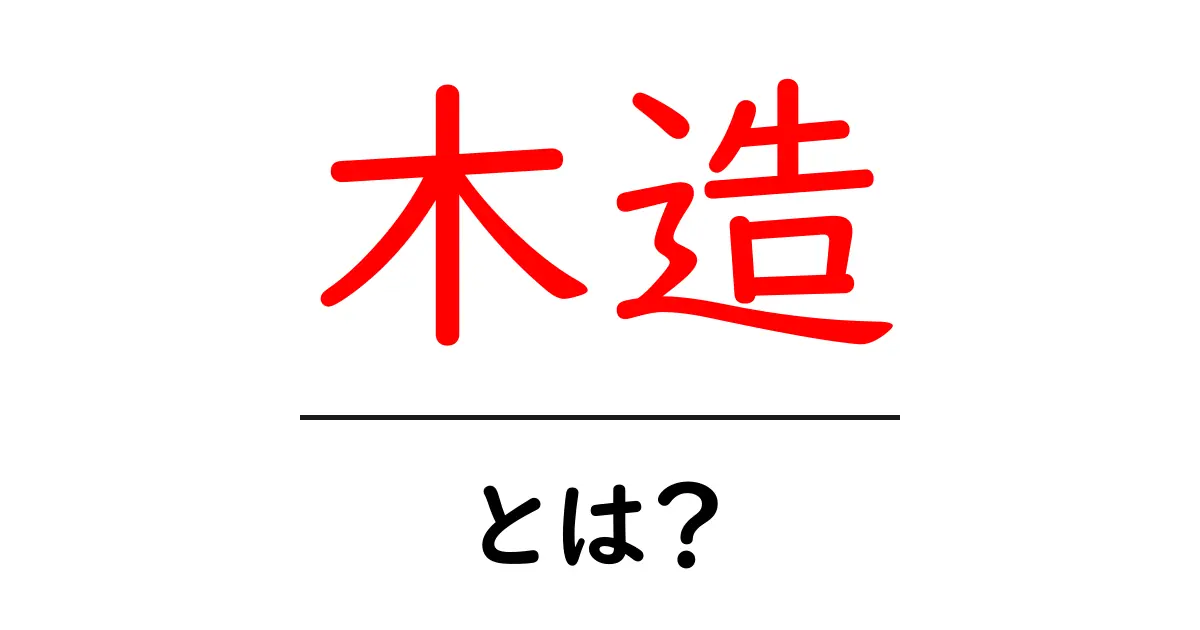
木造とは?その魅力とメリットを徹底解説!
木造という言葉は、建物が木材を主な素材として作られていることを指します。木材は自然素材であり、私たちの暮らしには古くから使われてきました。今回は木造の特徴、メリット、そしてデメリットについて詳しく見ていきましょう。
木造建築の特徴
木造建築にはいくつかの特徴があります。代表的なものを以下にまとめました。
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 自然素材 | 木は自然から得られる素材で、温かみがあります。 |
| 軽量 | 木造の建物は鉄筋コンクリートよりも軽いです。 |
| 加工しやすい | 木材は加工が簡単で、自由な形を作ることができます。 |
木造のメリット
木造の建物には以下のようなメリットがあります。
- 温かみがある: 木造の室内は、見た目にも暖かく、人に優しい環境を提供します。
- 耐震性: 木造建築は地震に対して柔軟性を持っており、衝撃を吸収する能力があります。
- 環境への配慮: 木材は再生可能な資源であり、適切に管理されれば環境に優しい素材です。
木造のデメリット
もちろん、木造建築にはデメリットも存在します。主なデメリットを見てみましょう。
- 耐久性: 木材は劣化しやすいため、定期的なメンテナンスが必要です。
- 火災のリスク: 木造は火に弱く、火災による危険性があります。
まとめ
木造は、その美しい見た目や温かみ、環境への配慮から、多くの人々に愛されています。ただし、木造建築を選ぶ際には、メリットだけでなくデメリットもしっかりと理解しておくことが重要です。正しくメンテナンスを行い、長く愛される住まいを作り上げていきましょう。
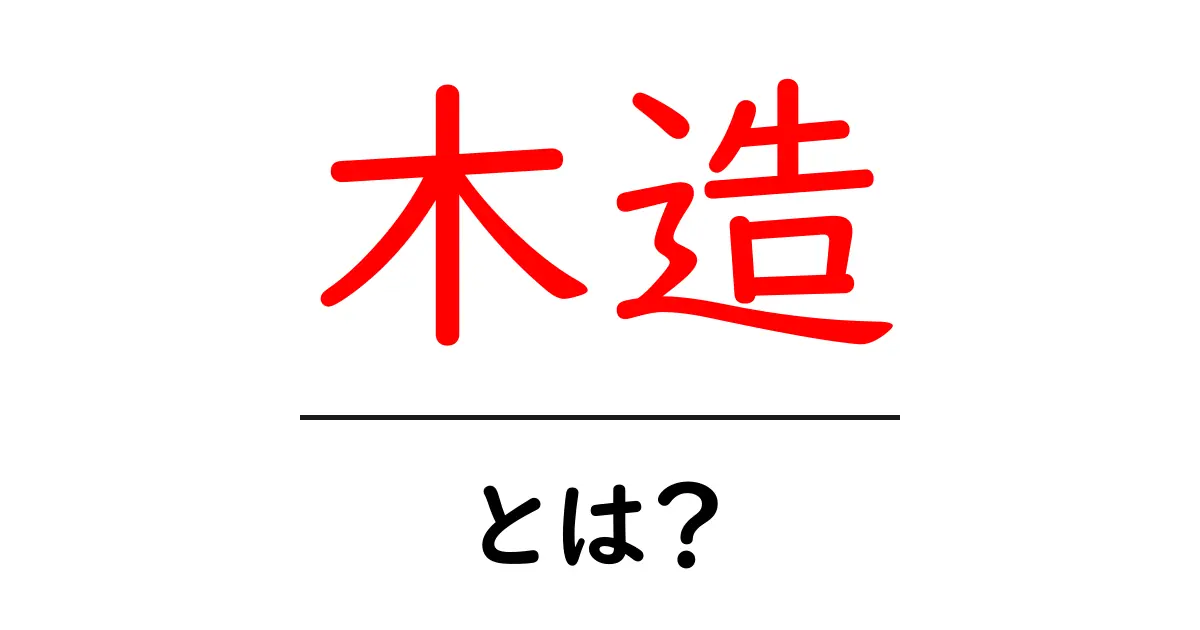
木造 ほぞ とは:木造ほぞとは、木材をつなげるために作られたくぼみのことです。この技術は、特に日本の伝統的な建築や家具作りにおいて重要な役割を果たしています。ほぞは、一つの木材がもう一つの木材にしっかりとはまるように設計されています。このようにすることで、全体の構造を強くし、安定性を高めることができます。たとえば、柱と梁をつなげたり、家具を組み立てたりする際に多く使われます。ほぞには、様々な形状や大きさがありますが、基本的にはどれも木材同士をしっかりと結び付けることが目的です。この技術は、工事が進むにつれてより進化し、近代的な建物にも応用されています。木材は湿気や温度の影響を受けやすいですが、ほぞの技術により、木材同士が長持ちするように工夫されています。木造ほぞの技術は、昔ながらの知恵や技術を今に受け継ぎ、私たちの生活に深く関わっています。木造の魅力を理解するためにも、ほぞについて知っておくことはとても大切です。
木造 亜鉛メッキ鋼板葺 とは:木造亜鉛メッキ鋼板葺(もくぞう あぜんめっきこうはんぶき)とは、木造の建物に使用される屋根の材質の一つで、亜鉛メッキ鋼板で作られています。この亜鉛メッキは、鋼板を亜鉛で覆うことで、さびにくく耐久性を高める役割を果たしています。つまり、雨や湿気に強いのです。木造の構造と相まって、軽量で施工がしやすいのが特徴です。また、見た目もスッキリしていて、色やデザインの選択肢も豊富です。太陽光を反射しやすいため、熱の蓄積が少なく、夏場でも涼しい室内を保つことができます。さらに、リサイクルがしやすい点も環境に優しいポイントです。木造亜鉛メッキ鋼板葺は、長持ちし、メンテナンスも簡単なため、最近では多くの新しい住宅やアパートで採用されています。
木造 在来工法 とは:木造在来工法とは、日本の伝統的な建築手法の一つで、木材を使って家を作る方法です。在来工法の特徴は、柱や梁を使って強い骨組みを作り、その間に壁や屋根をつけることです。この工法は、木材の持つ温かみや風合いを最大限に生かすことができます。木造在来工法は、地震や台風といった自然災害にも対応できるように設計されており、耐久性もあります。また、工期が比較的短く、地元の木材を使うことができるため、環境への配慮も意識されています。最近では、断熱性や耐火性を向上させるために新しい技術が取り入れられることが増えており、より快適な空間づくりが可能になっています。木造在来工法を選ぶことで、自然素材の魅力を感じられる家が手に入るでしょう。
木造 大引 とは:木造建築において「大引(おおびき)」はとても重要な役割を持っています。大引は床を支えるための木材で、主に基礎の上に設置されています。床を作るとき、その下にある大引が重さを支え、地面に伝える役割を果たします。大引は、家の強度を高めるためにも必要不可欠です。そのため、大引がしっかりと設置されていると、家が地震や風などの力に耐えられるようになります。また、木造建築では、湿気や虫の被害も考慮する必要があります。このため、大引は適切な材料や処理が施されていることが重要です。たとえば、防腐剤を使って、湿気による腐敗を防ぐことができます。さらに、地面からの湿気を防ぐために、大引の高さや設置位置も考慮されます。そうすることで、建物の寿命を長くすることができるのです。見えない部分ではありますが、家が丈夫で快適であるために、大引の存在はとても大切なのです。
木造 貫 とは:木造貫(もくぞうぬき)とは、主に木造建築に使われる部材の一種です。貫は、垂直または水平に配置されることで、建物の強度や安定性を保つ役割を果たします。特に、屋根や壁を支えるために重要です。木材は軽くて柔軟性があり、こうした特性を活かして、建物が地震や風などの力に耐えられるように工夫されています。 例えば、古い日本の伝統的な家屋でも木造貫が使われていることが多いです。これにより、建物が長持ちし、耐久性が高まります。また、木造貫にはデザイン的な役割もあります。木の温かみを感じられるため、居心地の良さをもたらします。 さらに、近代的な建築でも木造貫の考え方が取り入れられています。環境に優しい建材としてだけでなく、現代的なデザインと組み合わせて使用されることが増えています。そのため、木造貫は伝統と現代が融合した重要なパーツと言えるでしょう。木造建築においては、これらの知識を持っていると、より深く理解できるようになります。自分の家や建物を考える際にも、ぜひこの木造貫の役割を意識してみてください。
建材:建物の構造を作るための材料。木造建築では木材が主要な建材となる。
耐久性:建物や物の長持ちする性質。木造建築は適切に扱うことで耐久性が高まる。
断熱:熱の伝わりを防ぐこと。木材は断熱性が高く、冬は暖かく、夏は涼しい環境を作る。
施工:建物を建てるための作業。その過程で木材を使うことが多い。
構造:建物の形や支え方。木造は木材を使った独自の構造を持つ。
エコ:環境に優しいこと。木材は再生可能資源であり、エコな建材とされる。
伝統:昔から続く文化や習慣。木造建築は日本の伝統的な建築様式の一つ。
自然:人工的でないもの。木造建築は自然素材を使用し、周囲と調和することが多い。
デザイン:形や構造を考えること。木造建築では、柔らかい印象のデザインが可能。
施工主:建物を建てる依頼をする人。木造建築の施工主は、特に素材やデザインにこだわることが多い。
木製:木材で作られたものを指します。木造の家や家具などによく使われます。
ウッド:英語の「wood」をそのままカタカナ表記したもので、木材や木製品を指すことがあります。
木材建築:木材を使用して建築された構造物を指します。木造建築の一種で、特に伝統的な技法が使われる場合なども含まれます。
木造建築:木を使用して作られた建物の総称で、住宅や寺社、橋などさまざまな建物が含まれます。
天然木造:天然の木材を用いて作られた建物や構造物のことを指します。環境に優しい建築方法の一つです。
木構造:木材を使って構成された構造全般を指します。特に、梁や柱などの支える部分が木でできている場合を指します。
木材:木造建築に使用される木の素材のこと。様々な種類があり、強度や耐久性に違いがあります。
構造体:木造建築の骨格部分。柱や梁などで構成されており、建物の形を支えています。
耐震:地震による揺れに耐える性能のこと。木造建物も耐震設計が重要で、安全性を高めるために工夫されています。
断熱材:木造建築の中で使用される素材で、熱の伝わりを抑えるために用いられます。エネルギー効率を高める役割があります。
木造住宅:木材を中心に使って建てられた住宅のこと。自然素材のため、温かみがあり、居住性も考慮されています。
施工:建物を実際に建てるプロセスのこと。木造の場合、技術的な知識や経験が必要とされます。
安全基準:建物が安心して住めるために満たすべき法律や規則のこと。木造建築でも特定の基準が設けられています。
環境性能:木造建築が環境に与える影響やエネルギー効率のこと。木材の再生可能性などが評価されます。
仕上げ:木造建物の内部や外部に施される装飾や加工のこと。ペイントやコーティングなどが含まれます。
木造の対義語・反対語
木造建築の特徴やメリット・デメリットとは?施工事例と共に紹介
木造建築の特徴やメリット・デメリットとは?施工事例と共に紹介