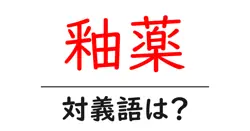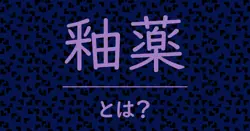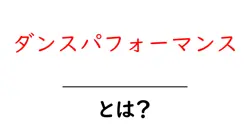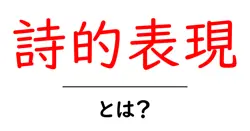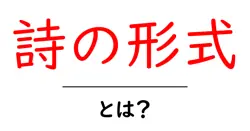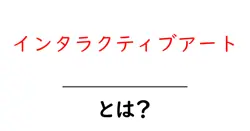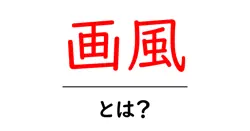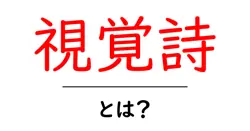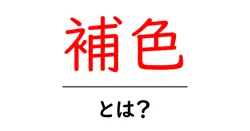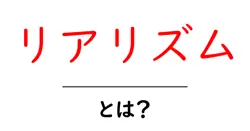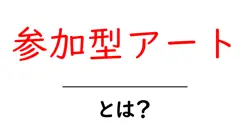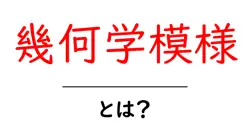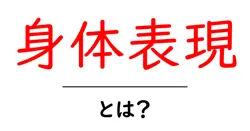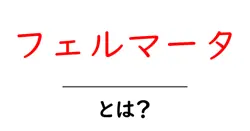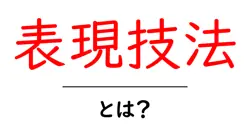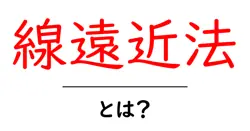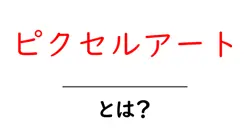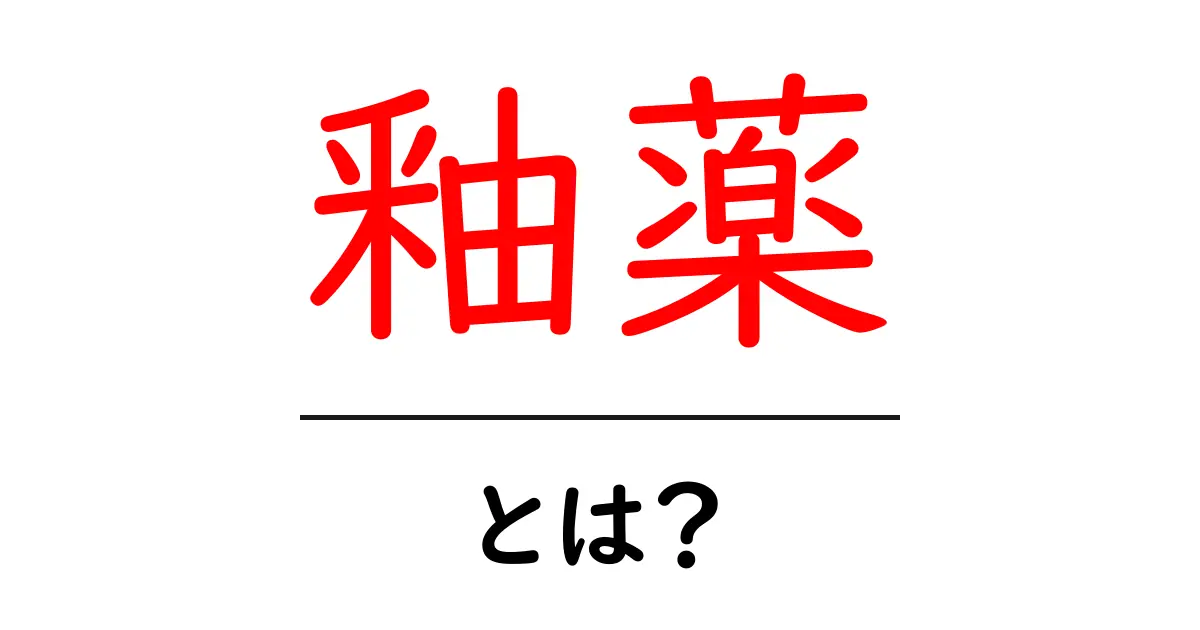
釉薬とは?
釉薬(ゆうやく)は、陶磁器や陶芸において用いられる重要な材料です。これは、焼成時に土の表面にかけられ、釉薬の特徴的な色や質感を与える役割を担っています。釉薬が施された作品は、見た目が美しいだけでなく、実用性も高まります。
釉薬の種類
釉薬にはさまざまな種類があり、色や質感が異なります。主な釉薬の種類には、以下のようなものがあります。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 透明釉 | 土の色をそのまま見せる |
| 透明釉 | 土の色を隠し、鮮やかな色を出す |
| matte釉 | 艶がないマットな質感を持つ |
| 青釉 | 青い色合いが特徴的な釉薬 |
釉薬の歴史
釉薬は、古代から使われてきました。中国の陶磁器が有名ですが、日本でも釉薬の技術は古くから存在し、時代とともに進化してきました。特に有名なものには、信楽焼や備前焼などがあります。
釉薬の使用方法
釉薬を使う際には、まず土を成型して焼成し、その後釉薬を施します。施釉を行った後、再度焼成を行うことで、釉薬が土に融合し、強度や美しさが増します。
釉薬の魅力
釉薬を使った作品は、色や質感に変化があり、その一つ一つが全く違った印象を与えます。釉薬を学ぶことは、奥深い陶芸の世界を理解するための第一歩でもあります。様々な釉薬を試しながら、自分だけのアート作品を作り上げることができるのです。
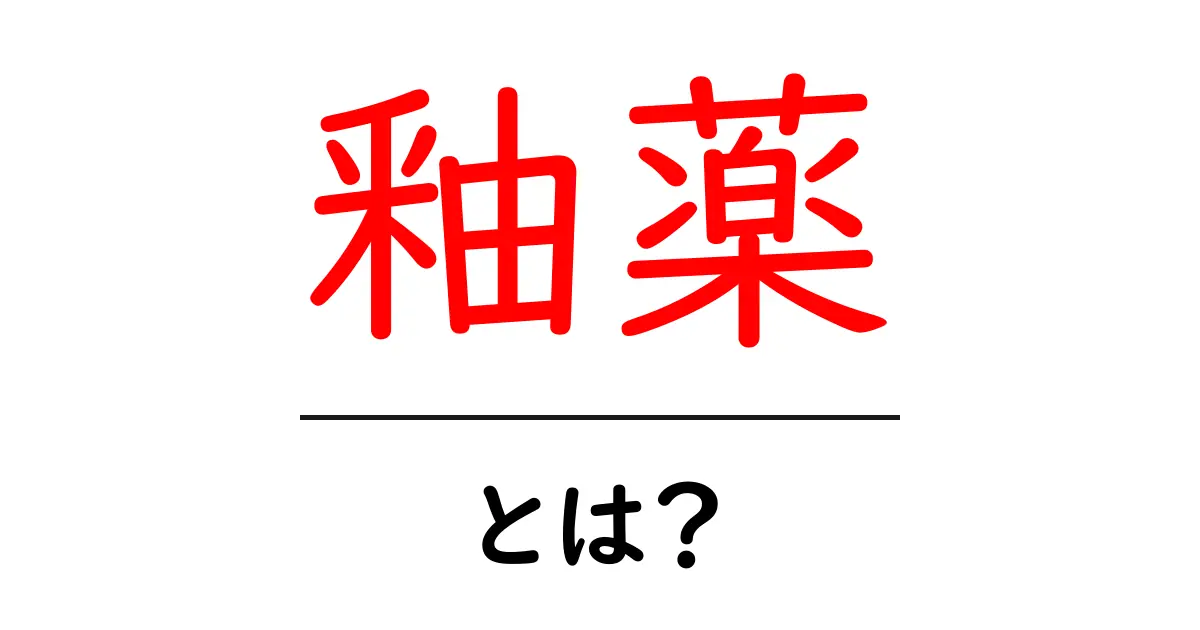
陶磁器:釉薬は陶磁器の表面に施されるガラス質の層で、主に美しさや水分の侵入を防ぐために使用されます。
焼成:釉薬を施した陶磁器を高温で焼成することで、釉薬が溶けて表面が滑らかになり、耐久性が向上します。
釉薬の種類:釉薬には様々な種類があり、透明釉、白釉、色釉などがあります。それぞれ異なる色や質感を持っています。
色彩:釉薬には多様な色彩があり、釉薬を使うことで陶磁器のデザインや美しさを引き立てることができます。
釉薬の調合:釉薬は様々な原料を混ぜて調合されます。成分によって色や質感が変わるため、調合は非常に重要です。
塗布:釉薬は陶磁器の表面に塗布し、均一な層を作ることが求められます。これにより、美しい仕上がりになります。
テクスチャー:釉薬には、艶やかなものやマットなものなど、テクスチャーの違いがあります。これによって見た目や触感が変化します。
酸化:釉薬の一部は酸化反応を利用して色合いが変化します。特定の金属酸化物が使われることが多いです。
後焼成:釉薬を施した後に再び焼成することで、釉薬の特性が際立ち、強固な層が形成されます。
装飾技法:釉薬を使った装飾技法には、刷毛目や掻き落としなどがあります。これにより、一層芸術的な表現が可能になります。
ガラス釉:ガラスのように光沢のある仕上がりを持つ釉薬のこと。陶器に用いると、耐水性を高める効果があります。
乳白釉:白っぽい色合いの釉薬で、柔らかい印象を与えます。陶器の表面に使うことで、温かみのあるデザインが楽しめます。
透明釉:透明な釉薬で、下地の色や模様をそのまま楽しむことができる特徴があります。色を重ねることができ、さまざまな表情を引き出します。
酸化釉:酸化状態で焼成された釉薬のこと。色合いや質感が多様で、独特の風合いが魅力です。
還元釉:還元焼成で使用される釉薬で、通常とは異なる色合いになりやすい特性があります。鉄分を含む場合に深い色味が出ることがあります。
装飾釉:装飾的な効果を持つ釉薬で、模様や色彩が豊富です。主に芸術的な陶芸作品に用いられます。
陶磁器:釉薬が使用されている陶器や磁器の総称で、美しい表面仕上げや色彩を持つ製品を指します。
釉薬の種類:釉薬には透明釉、半透明釉、opaque釉(不透明釉)、酸化釉、還元釉など多くの種類があり、それぞれが異なる見た目や効果を持っています。
焼成:釉薬を施した陶磁器を高温で焼くプロセス。焼成によって釉薬が溶融し、表面が平滑で美しい仕上がりになります。
化学成分:釉薬には様々な化学成分が含まれており、これにより色や質感が決まります。代表的な成分には石英、長石、酸化金属などがあります。
釉薬の効果:釉薬は陶磁器の表面を保護し、吸水性を減らす役割があります。また、色を加えることで視覚的な美しさを生み出します。
セラミックアート:釉薬を用いてアート作品を制作する技術。釉薬の特性を生かし、芸術的な表現が可能になります。
乳白釉:不透明で白っぽい釉薬の一種で、柔らかい印象を与えるため、特に食器やインテリアアイテムで多く使用されています。
クリア釉:透明な釉薬で、下地の色をそのまま引き立てる効果があります。色鮮やかなデザインや模様を表現する際に使われます。
グラデーション釉:異なる色合いを混ぜ合わせた釉薬の一種で、焼成後に自然なグラデーションをもたらすデザインが特徴です。
還元焼成:酸素を制限した環境で焼成することにより、釉薬や土の色合いが変化する技術。特に特有の深い色合いが得られることで知られています。
釉薬の対義語・反対語
釉薬の関連記事
芸術の人気記事
前の記事: « 親類とは?知っておきたい親族のこと共起語・同意語も併せて解説!