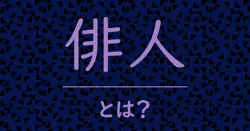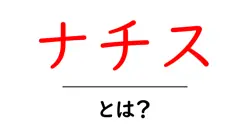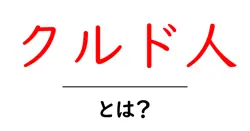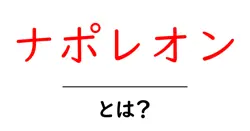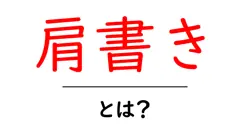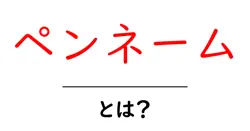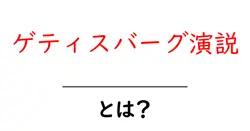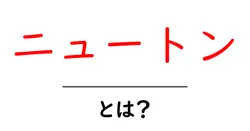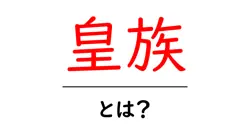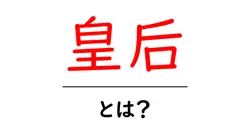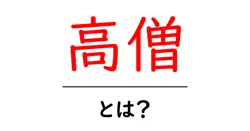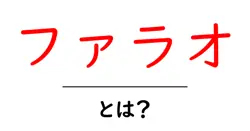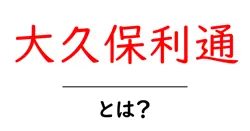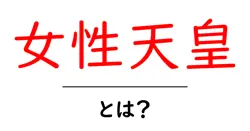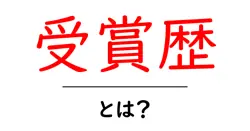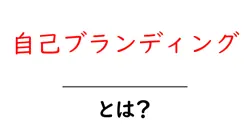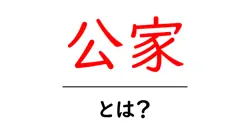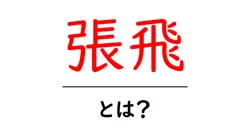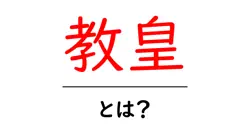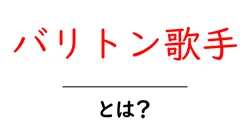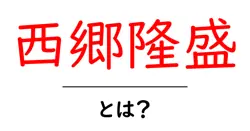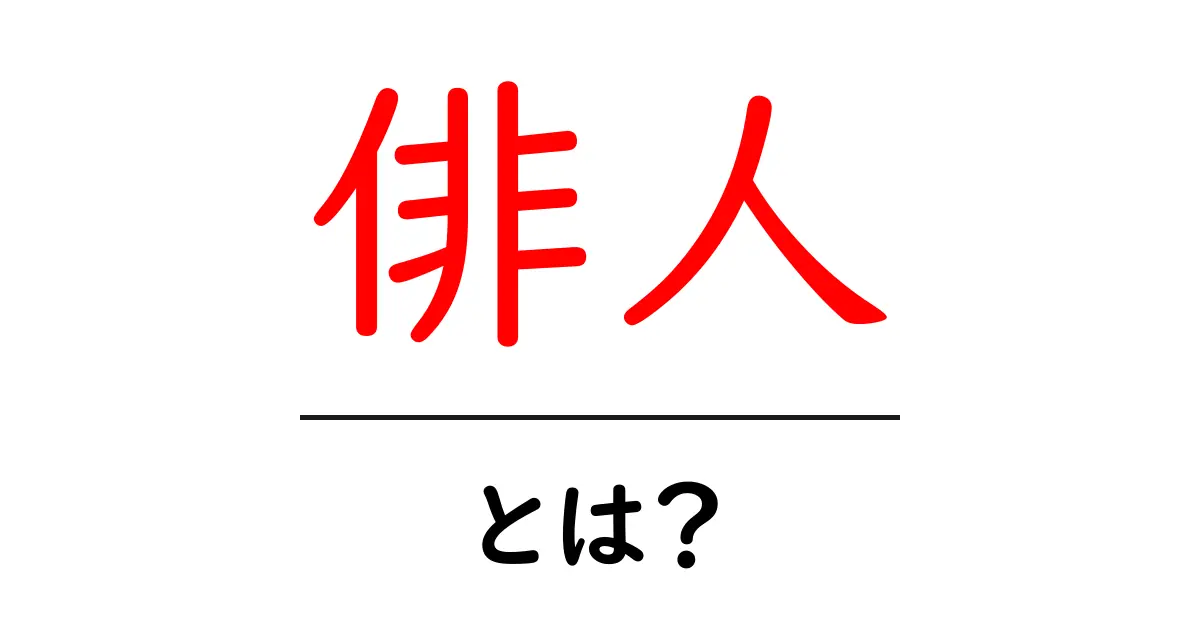
俳人について知ろう
皆さんは「俳人」という言葉を聞いたことがありますか?俳人は、俳句を詠む人のことを指します。俳句は、日本の伝統的な短い詩の形式で、5・7・5の音数から成り立っています。俳人たちは、この特別な形の詩を通じて、自分の感じることや思いを表現します。
俳人の歴史
俳人の活動は、江戸時代から盛んになりました。特に有名なのが松尾芭蕉です。彼は、旅行をしながら多くの俳句を残し、現在でも多くの人に愛されています。彼の俳句は、自然や人々の生活を感じさせるものが多く、多くの人に影響を与えました。
俳句の魅力
俳句の魅力は、短い言葉の中に豊かな意味が隠されているところです。たとえば、ある俳句が四季の移り変わりを表していたり、静かな風景を描写していたりします。たった17音の中に、深い感情や体験が込められているのです。このため、多くの人が俳句を通じて思いや感動を共有しています。
有名な俳人たち
| 名前 | 時代 | 特徴 |
|---|---|---|
| 松尾芭蕉 | 江戸時代 | 自然や旅をテーマにした作品 |
| 与謝蕪村 | 江戸時代 | 絵画的な表現と軽やかな言葉使い |
| 小林一茶 | 江戸時代 | 人情を大切にした俳句 |
現代の俳人たち
最近では、若い俳人たちも登場しています。SNSを利用して自分の俳句を発表する人も多く、俳句は新しい形で発展しています。例えば、インスタグラムやツイッターでは、俳句コンテストが開催され、若い世代が参加しています。これにより、伝統的な俳句がより広い層に親しまれるようになってきました。
俳句を始めてみよう
さて、もしあなたも俳句を詠んでみたいと思ったら、まずは身の回りの自然や出来事に目を向けてみてください。簡単な言葉で感じたことを表現し、5・7・5の形にしてみるだけで、あなたも立派な俳人の仲間入りです。
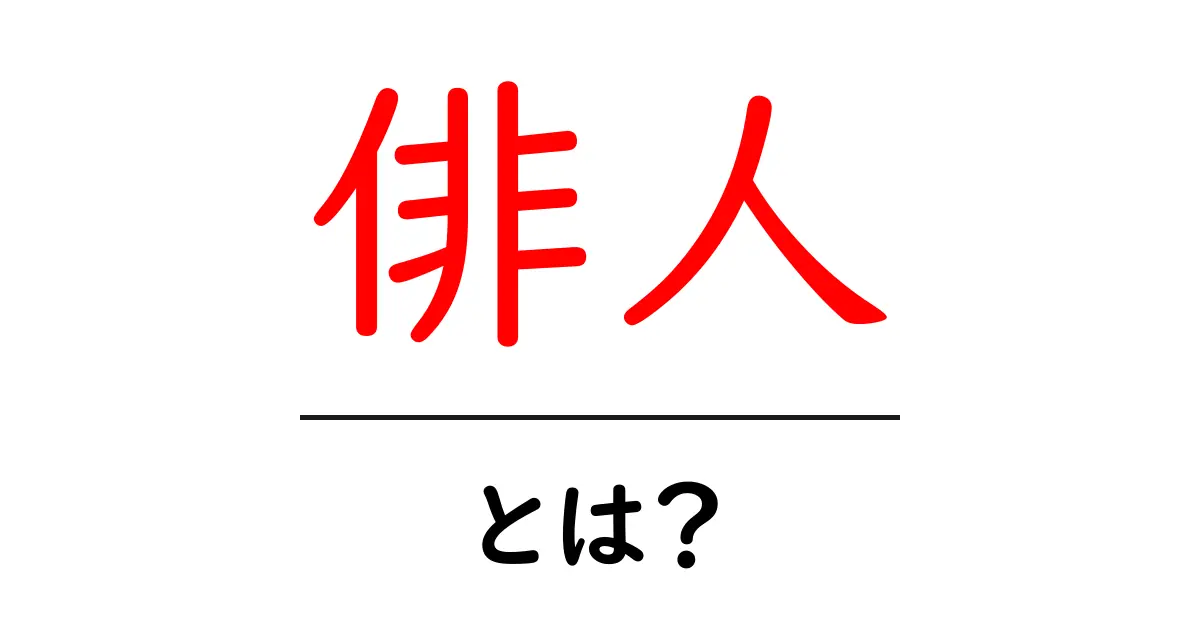
俳句:俳人が詠む短い詩で、通常は17音から成り、季語を含むことが特徴です。
季語:俳句において、季節を表す言葉で、作品に深みや情景を与えるために不可欠です。
詩:言葉をリズミカルに用いた表現で、感情や情景を美しく表現する文学の一形態です。
文学:言葉を用いて人間の経験や感情を表現する芸術の総称で、詩、散文、小説などが含まれます。
感性:物事を感じ取り、理解する能力で、特に芸術や文学の表現において重要な要素です。
自然:俳句の多くは自然をテーマにしており、四季折々の景色や生き物を描写することがよくあります。
表現:思いや感情、視覚的なイメージを言葉や音楽、アートなどで表す行為のことです。
風景:自然の景色や場面を指し、それを題材にした俳句も多く存在します。
習作:俳句や詩を書くための練習作品のことです。俳人が技術を磨く過程で作成します。
俳壇:俳人たちが集まる場所や団体のことを指し、交流や発表の場でもあります。
詩人:詩を創作する人。言葉の美しさやリズムを重視した作品を作ります。
俳句作家:俳句を主に制作する人。短い詩形の中で深い感情や自然の美しさを表現します。
短詩人:短い詩を作る人。俳句や川柳など、短文の中で表現を試みるスタイルです。
川柳作者:川柳を創作する人。ユーモラスな内容が特色で、日常の出来事や社会問題を風刺します。
吟遊詩人:旅をしながら詩を詠む人。音楽的な要素も含む詩作が特徴で、主に公共の場で詩を披露することが多いです。
俳句:俳人が詠む短い詩。通常は5・7・5の17音から成り、季語を含むことが多い。
季語:俳句や詩の中で使われる、季節を表す語。例えば、桜や雪など、その季節を感じさせる言葉。
スランプ:俳人が創作に行き詰まり、うまく詩が詠めない状態を指す。クリエイティブな活動においてよくある現象。
俳壇:俳句の世界やコミュニティを指す言葉。俳人たちが集まり、作品や技術について議論や交流を行う場。
名句:特に優れた俳句のこと。その伝統や作品が後世に残るような、印象深いものを指す。
俳風:ある種の俳句のスタイルや作風を示す言葉。例えば、「写実的な俳風」や「抽象的な俳風」などがある。
投句:俳句を発表すること。俳人が自らの作品を俳壇やコンテストに出す行為を指す。
結社:俳人たちが集まって構成する団体やグループ。定期的に会合を開いたり、作品を発表したりする。
講座:俳句を学ぶための授業やコース。初心者向けから上級者向けまで、様々な内容が提供される。
正岡子規:明治時代の俳人で、現代俳句の礎を築いた人物。彼の考え方やスタイルは多くの俳人に影響を与えた。
俳人の対義語・反対語
俳人(はいじん)とは? 意味・読み方・使い方をわかりやすく解説
俳人(はいじん)とは? 意味・読み方・使い方をわかりやすく解説
はいじんとは? 意味・読み方・使い方をわかりやすく解説 - goo辞書